受遺者(じゅいしゃ)とは?
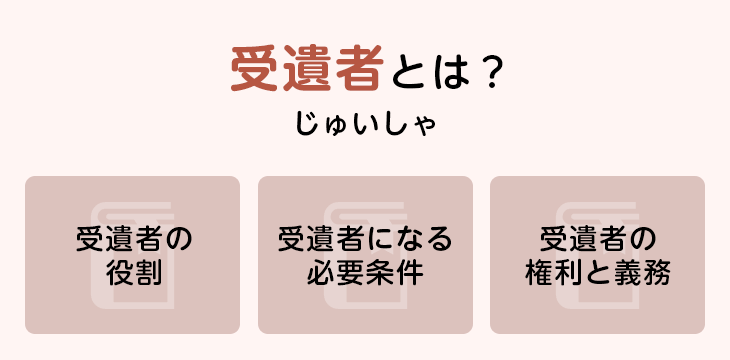
受遺者とは、遺言によって遺贈(財産の贈与)を受ける人のことです。
遺言者が亡くなった際に、遺言に基づいて特定の財産や権利を取得する立場にある人を指します。相続人ではなくても受遺者になることができるため、遺言による財産分配の重要な役割を担っています。
受遺者の基本的な意味と役割
受遺者は、民法上「遺贈を受ける者」と定義されています。遺言者が自分の財産の一部または全部を特定の人や団体に贈与する意思を遺言に記した場合、その財産を受け取る権利を持つのが受遺者です。
受遺者の役割は主に遺言に記載された特定の財産を受け取ることにあります。遺言執行者から財産の引き渡しを受け、必要な場合は登記や名義変更などの手続きを行います。
遺贈の種類による受遺者の立場
| 包括遺贈の受遺者 | 遺産全体またはその割合(例:遺産の3分の1)を受け取る立場。相続人と同様の権利義務を持ちます。 |
|---|---|
| 特定遺贈の受遺者 | 特定の財産(例:〇〇市〇〇町の土地、預金口座の資金など)を受け取る立場。その特定の財産についてのみ権利を持ちます。 |
上記の表は遺贈の種類によって受遺者の立場や権利が異なることを示しています。包括遺贈では相続人に近い立場となり、特定遺贈ではより限定的な権利を持つことになります。
受遺者と相続人の違い
受遺者と相続人は、どちらも故人の財産を受け取る立場にありますが、その根拠や権利内容には明確な違いがあります。受遺者は遺言による指定が必要であるのに対し、相続人は法律上当然に定められた権利を持ちます。
- 受遺者は遺言がなければ財産を取得できないが、相続人は法定相続分に基づき当然に相続権を持つ
- 受遺者は原則として遺産分割協議に参加できないが、相続人は遺産分割協議の当事者となる
- 受遺者は遺言に記載された特定の財産だけを請求できるが、相続人は遺産全体に対して権利を持つ
- 受遺者になれるのは誰でも(法人も含む)可能だが、相続人は民法で定められた範囲の親族に限られる
上記のリストは受遺者と相続人の主な違いを示しています。遺言者の意思によって財産を得る受遺者と、法律に基づいて自動的に相続権を得る相続人では、その法的地位に大きな違いがあることがわかります。
受遺者になれる人の条件
受遺者になるための条件は比較的緩やかで、遺言者が自由に指定できる範囲が広いのが特徴です。相続人に限らず、遺言者が財産を残したいと考える人や団体は広く受遺者になることができます。
受遺者になれる対象
| 個人 |
|
|---|---|
| 法人・団体 |
|
この表は受遺者になれる人や団体の例を示しています。個人だけでなく法人も受遺者になれるため、遺言者は幅広い選択肢の中から財産を遺贈する相手を選ぶことができます。
受遺者になれない場合
一方で、以下のような場合には受遺者になることができません。
- 遺言者の死亡時に既に死亡している人(同時死亡の場合も含む)
- 遺言者から相続欠格事由に該当する行為をした人
- 遺言者から廃除された相続人(ただし特別に指定された場合を除く)
- 法律上存在が認められない団体
上記のリストは受遺者になれない主な条件を示しています。特に注意すべきは、受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合、その遺贈は効力を失うことが多いという点です。
受遺者の権利と義務
受遺者は遺贈によって財産を取得する権利を持つ一方で、いくつかの義務や制限も課せられています。受遺者としての立場を理解するためには、これらの権利と義務のバランスを正しく把握することが重要です。
受遺者の主な権利
- 遺贈された財産の取得権:遺言に記載された財産を受け取る権利
- 遺贈の承認・放棄の選択権:遺贈を受け入れるか断るかを選択できる権利
- 遺贈目的物の引渡し請求権:遺言執行者や相続人に対して遺贈された財産の引き渡しを求める権利
- 登記請求権:不動産などの遺贈を受けた場合に、相続人に対して登記手続きを求める権利
この一覧は受遺者が持つ主な権利を示しています。特に遺贈の承認・放棄の選択権は重要で、負債が多い財産などの場合には放棄することも検討できます。
受遺者の主な義務
| 遺贈の負担付義務 | 遺言で「○○を条件に遺贈する」という負担が付されている場合、その条件を履行する義務 |
|---|---|
| 遺言執行者への協力義務 | 遺言執行者がいる場合、その職務執行に協力する義務 |
| 遺留分侵害額の支払義務 | 遺贈が相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額を支払う義務 |
| 税金の支払義務 | 遺贈によって取得した財産に対する相続税または贈与税を支払う義務 |
上記の表は受遺者が負う主な義務を示しています。特に遺留分侵害額の支払義務は重要で、法定相続人の遺留分を侵害するような大きな遺贈を受けた場合には、後日遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
受遺者に関する法的手続き
受遺者が遺贈された財産を適切に取得するためには、いくつかの法的手続きが必要になります。これらの手続きを正しく行うことで、スムーズに遺贈の効果を実現することができます。
受遺者が行うべき手続きの流れ
- 遺言の開封・検認:家庭裁判所で遺言の検認手続きに立ち会う(公正証書遺言の場合は不要)
- 遺贈の承認または放棄:遺贈を受け入れるか断るかの意思表示を行う
- 遺贈目的物の引渡し請求:遺言執行者または相続人に対して遺贈財産の引き渡しを請求する
- 所有権移転登記など:不動産などの場合、必要な登記手続きを行う
- 税金の申告・納付:取得した財産に対する相続税または贈与税の申告と納付を行う
この流れは受遺者が遺贈によって財産を取得する際の一般的な手続きを示しています。実際の手続きは遺贈される財産の種類や状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
遺贈の承認・放棄の期限
受遺者は遺贈の承認または放棄を自由に選択できますが、その選択には期限があります。
| 承認・放棄の期限 | 遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内 |
|---|---|
| 期限経過後の扱い | 原則として承認したものとみなされる |
| 期限延長 | 正当な理由がある場合、家庭裁判所に申し立てて期限の延長が可能 |
この表は遺贈の承認または放棄に関する期限について説明しています。期限内に判断することが難しい場合は、早めに専門家に相談することが大切です。
よくある質問
Q1. 受遺者と受贈者の違いは何ですか?
受遺者は遺言による遺贈で財産を受け取る人であるのに対し、受贈者は生前贈与によって財産を受け取る人を指します。受遺者は遺言者の死後に財産を取得しますが、受贈者は贈与者の生存中に財産を取得します。
Q2. 法人も受遺者になれますか?
はい、法人も受遺者になることができます。営利法人(会社など)、非営利法人(公益財団法人、NPO法人など)、宗教法人、学校法人など、様々な法人が受遺者となることが可能です。将来設立される予定の法人を受遺者に指定することもできます。
Q3. 受遺者は遺留分を請求できますか?
受遺者は原則として遺留分を請求することはできません。遺留分は法定相続人の一部(配偶者、子、直系尊属)にのみ認められる権利です。受遺者は遺言による指定がなければ財産を取得できないため、遺留分という最低限保障される権利は持ちません。
Q4. 受遺者が遺言者より先に亡くなった場合はどうなりますか?
受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、原則としてその遺贈は効力を失います(失効します)。ただし、遺言の中で受遺者が死亡した場合の代替受遺者が指定されている場合は、その指定に従います。
Q5. 受遺者は遺産分割協議に参加できますか?
特定遺贈の受遺者は原則として遺産分割協議に参加する権利はありません。しかし、包括遺贈の受遺者は相続人と同様の権利を持つため、遺産分割協議に参加することができます。また、特定遺贈の対象財産が遺産分割協議に影響する場合は、利害関係人として協議に関与できることもあります。
まとめ
受遺者とは、遺言によって遺贈を受ける立場にある人や団体のことです。相続人だけでなく、親族、友人、法人など幅広い対象が受遺者になることができ、遺言者の意思に基づいて財産を取得する権利を持ちます。
受遺者は遺贈の種類(包括遺贈か特定遺贈か)によって権利内容が異なり、包括遺贈の受遺者は相続人に近い立場を持ちますが、特定遺贈の受遺者は指定された特定の財産についてのみ権利を持ちます。
受遺者になるためには遺言による指定が必要であり、遺言者の死亡時に生存していることが条件となります。受遺者は遺贈を承認するか放棄するかを選択できますが、その期限は遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内と定められています。
遺贈によって財産を取得する際には、遺言執行者または相続人に対する引渡し請求、必要な登記手続き、税金の申告・納付など、いくつかの法的手続きが必要になります。また、遺贈が相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額の支払いが求められることもあります。
遺言による財産承継を考える際には、受遺者の立場や権利義務を正しく理解し、円滑な遺産承継のために専門家に相談することをおすすめします。






