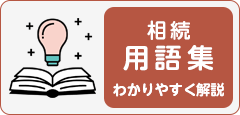現金を相続する際の注意点や税金・手続き・トラブル防止のポイント

相続財産の中でも最も扱いやすいのが現金です。評価額が明確で、分配しやすいという点で相続人にとっては便利な財産です。しかし、その一方で現金特有のリスクやトラブルが存在します。
現金の相続には、相続税の課税対象としての注意点や、相続人間での分配時の不平等感から生じる争い、さらには税務署による調査リスクもあります。現金を適切に相続し、損をしないためには正しい知識と対策が欠かせません。
この記事では、司法書士の視点から現金の相続について法律・手続き・税金・リスク回避まで詳しく解説します。安心して相続を進めるために、ぜひ最後までお読みください。
■もくじ
現金と預貯金の違い|相続での扱い方
現金は「物」、預貯金は「権利」として扱われる
相続の場面では、現金と預貯金は似たように扱われがちですが、法律上は異なる性質を持っています。現金は民法上「物」として扱われ、財布や家具と同じく、形ある財産として分類されます。
一方、預貯金は銀行に対する「債権」、つまり銀行からお金を引き出す権利です。私たちは銀行に現金を預けることで、銀行に対してその金額を請求する権利を持つことになります。この法的性質の違いが、相続時の取り扱いにも影響を与えます。
時効の違いにも注意
現金には時効の概念はありませんが、預貯金には時効があります。銀行に預けた預金は、民法上「商事債権」として扱われ、5年で消滅する可能性があります。ただし、実際には休眠預金として扱われ、金融機関から預金保険機構へと管理が移されます。
相続時の取り扱いの違い
かつては、預貯金は法定相続分に従い、相続人が個別に引き出すことができました。しかし、平成28年12月の最高裁判決により、預貯金も遺産分割協議の対象とされるようになりました。
これにより、現金も預貯金も相続人全員の合意が必要になり、勝手に引き出すことはできなくなりました。公平な分配のための重要なルールとして理解しておくことが必要です。
現金は物理的管理が必要
現金は目に見える形で管理されるため、相続財産に含まれている現金については、隠蔽や未申告が問題になりやすいです。相続人間で信頼関係を保つためにも、現金はしっかりと遺産分割協議に含めることが求められます。
現金と預貯金は性質が異なるものの、相続時には共に遺産分割の対象となり、相続人全員の合意が必要です。法的な違いを理解し、適切に対処することが重要です。
現金を相続する際の基本的な手続きの流れ
現金相続はシンプルだが手続きは必要
現金には預貯金のような口座管理がないため、「特別な手続きは不要」と思われがちですが、相続財産としての手続きはしっかり行う必要があります。現金であっても遺産分割協議や相続税の申告は必要です。
ここでは、現金を相続する際の手続きをわかりやすく解説します。以下の流れに沿って進めることで、トラブルを防ぎ、スムーズな相続が実現できます。
現金相続の基本的な流れ
- 遺言書の確認と相続人の確定:まずは遺言書の有無を確認し、相続人を戸籍謄本などから調査します。
- 相続財産の調査:現金を含め、すべての財産を把握する必要があります。隠し財産がないよう注意します。
- 遺産分割協議の実施:相続人全員で現金を含む財産の分配方法を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
- 相続税の申告と納付:課税対象額に応じて、相続税を申告・納付します。現金はそのまま課税対象となります。
現金は名義変更不要だが慎重な管理を
現金は不動産や有価証券のような名義変更手続きが不要なため、相続手続きが比較的簡便です。ただし、現金の所在や金額については相続人間で透明性を保つ必要があります。
また、タンス預金などの見落としやすい現金も忘れずに調査し、相続財産に含めましょう。申告漏れは重加算税などのペナルティの対象になります。
遺言書がある場合の優先度
被相続人が遺言書を残している場合、その内容が遺産分割協議よりも優先されます。ただし、遺言書に記載されていない財産があれば、その部分については遺産分割協議が必要です。
現金の相続も他の財産と同様、法的手続きを踏んで適切に管理することが求められます。相続人全員の協力がスムーズな相続の鍵です。
現金を相続するメリット・デメリット
現金相続のメリット
現金を相続する最大のメリットは、分配のしやすさです。不動産や株式と違い、評価額に差がないため、相続人全員が公平に分けることが可能です。
1. 分配が容易でトラブルが少ない
現金は相続財産の中でも即時に価値が確定しているため、相続人間での評価の違いによる争いが起こりにくいです。均等に分けやすいという特徴から、遺産分割協議もスムーズに進みやすくなります。
2. すぐに使用できる
不動産などは売却しないと現金化できませんが、現金は手続き完了後すぐに使用可能です。相続税の納税資金としてもそのまま使える点が大きなメリットです。
現金相続のデメリット
一方で、現金相続には節税面での不利や、細かい差による争いのリスクもあります。現金の特徴を理解し、対策を講じることが重要です。
1. 節税ができない
不動産や株式は、相続税評価額を下げることで節税効果を得ることが可能ですが、現金はそのままの金額で課税対象になります。節税対策ができないため、高額の現金相続は税負担が大きくなりがちです。
2. 少額の差がトラブルに発展することも
現金は分配しやすい反面、1円単位まで明確であるため、少しの差でも不公平感を生み、相続人間でトラブルに発展することがあります。不動産のように「目に見えない評価差」がない分、注意が必要です。
このように、現金相続は手続きが簡単な一方、税金やトラブルのリスクも存在します。メリット・デメリットを理解し、事前に対策を立てましょう。
現金にかかる相続税の計算方法
現金の評価はそのまま額面通り
現金は他の相続財産と異なり、時価評価を行う必要がありません。そのままの額面が相続税評価額となるため、計算が非常にシンプルです。
ただし、現金が多いほど相続税の負担は増加します。そのため、現金のみを多く相続する場合は、税額の確認と対策が重要になります。
相続税計算の基本手順
現金を含む相続税の計算は、以下の5つのステップで行います。現金だけ特別な計算方法はありませんが、正確に進めることが大切です。
- 相続財産の総額を算出(現金+他の財産-債務)
- 基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求める
- 法定相続分に基づいて各人の取得額を算出
- 取得額に税率を適用して相続税総額を計算
- 各人の実際の取得額に応じて税額を按分
基礎控除の計算式
基礎控除は、相続人の人数によって変動します。計算式は以下の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、基礎控除は4,200万円となります。
相続税率と控除額の一覧
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
現金を相続する際は、この表を用いて正確に税額を計算する必要があります。高額な現金相続の場合は特に注意が必要です。
他の資産と現金の節税効果の違い
現金は評価額が減らせない
現金は評価額を引き下げることができないため、相続税対策がしにくい資産です。相続税は財産の評価額に基づいて課税されるため、評価額を下げられない現金は、そのまま高額な課税対象になります。
そのため、相続税対策を考える場合には、現金だけに依存するのはリスクが高いといえるでしょう。
不動産は評価を下げて節税できる
一方、不動産には評価額を圧縮できる制度が存在します。たとえば、以下のような方法があります。
- 小規模宅地等の特例:一定条件のもと、土地の評価額を最大80%減額可能
- 建物の評価:固定資産税評価額を用いるため、購入価格より3割程度低くなる
現金と不動産の節税効果の比較
| 資産の種類 | 評価方法 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 現金 | 額面通り100% | 節税不可 |
| 土地 | 路線価評価+特例適用 | 最大80%評価減 |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 実勢価格より30%減 |
バランスの良い資産構成が大切
現金だけでなく、不動産や有価証券など、多様な資産構成を意識することで、相続税の負担を抑えることが可能です。生前のうちから、資産をどのように分けるのが最適か、専門家と相談しながら検討しておきましょう。
節税だけを考えて資産を偏らせるのではなく、相続人にとって負担の少ない形で資産を残す工夫が必要です。
現金を隠した場合のリスクとペナルティ
現金は隠しやすいが発覚しやすい
現金は、預貯金や不動産と異なり、目に見える形で管理されるため、相続人の中にはこれを申告せずに自分だけで管理しようとするケースがあります。しかし、現金を相続財産として申告しないことは重大な違法行為です。
税務署は、相続時に国税総合管理システム(KSKシステム)などを活用して、故人の財産状況を詳細に把握しています。特に、預貯金の出金履歴や、不自然な現金移動があった場合は、調査対象となります。
現金隠蔽が発覚した場合のペナルティ
現金を隠していたことが発覚すると、相続税の追徴課税だけでなく、重加算税や延滞税といったペナルティが科せられます。以下はその代表的な例です。
- 過少申告加算税:10%(または15%)
- 重加算税:35%~40%
- 延滞税:年利7.3%(直近の利率による変動あり)
税務調査が入るリスク
現金を多額に保有していた場合や、出所不明な現金がある場合には、税務署による税務調査が入る可能性が高まります。相続開始から数年後に発覚し、想定以上の税負担を強いられるケースもあります。
正しい申告が最善のリスク回避
現金を正しく申告し、適切に納税することが、結果的にトラブルを防ぎ、家族の信頼関係を守ることに繋がります。現金の隠蔽は必ず発覚すると考え、正直な相続を心がけましょう。
税務署はプロの目で相続財産を精査しています。相続人が不安な場合は、専門家に相談し、適切な申告を行うことが賢明です。
現金相続で失敗しないために専門家を活用する
専門家に依頼するメリット
現金相続は一見簡単に思われがちですが、税務リスクや相続人間のトラブルを避けるためには、専門家のサポートが有効です。
特に高額の現金を相続する場合や、相続人が複数いる場合は、司法書士や税理士の力を借りることで円滑に進めることができます。
司法書士の役割
司法書士は、遺産分割協議書の作成や、他の相続財産(不動産など)の名義変更手続きをサポートします。
現金相続においても、法的リスクの確認や、公正証書遺言の作成支援など、相続全体をトータルでサポートできます。
税理士の役割
税理士は、相続税の計算や節税対策についての専門家です。
現金相続においては、正確な相続税の申告と、税務署への対応をサポートします。特に、生前贈与の活用や、他の資産との組み合わせによる節税戦略を提案してもらえます。
専門家への依頼が安心・確実な相続のカギ
相続は、一生に何度も経験するものではありません。自分だけで対応しようとすると、法律や税務の落とし穴に気づかないことがあります。専門家に相談することで、適切な手続きを踏み、スムーズで安心な相続を実現できます。
日本リーガル司法書士事務所では、相続に特化した司法書士が無料相談を実施しております。現金の相続に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。