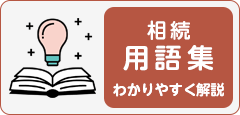相続に強い日本リーガル司法書士事務所の無料相談
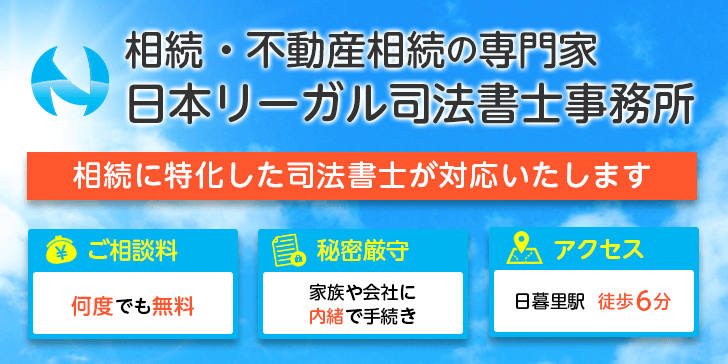
日本リーガル司法書士事務所が選ばれる5つの理由
-
1.ご相談は何度でも無料
お客様が安心して依頼できるように、当事務所では相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。
-
2.親切・丁寧な対応
親切・丁寧な対応を心掛け、お客様に最適な解決案をご提案いたします。
-
3.相続に精通している司法書士が在籍
相続に詳しい司法書士が何でもお応えいたします。初めて司法書士に相談する方にも分かりやすく説明することを心がけていますのでご安心ください。
-
4.徹底した秘密厳守
秘密厳守を徹底し、会社や家族に内緒にしたいなどお客様のご都合に合わせて対応いたします。
-
5.相続手続きのワンストップサービスが可能
相続のご相談から手続き完了までをワンストップで行います。
私たち日本リーガル司法書士事務所は、相続に関するご質問やご相談には、いつでもお答えできますのでお気軽にお問い合わせください。
何度でも無料の相談を承っております。お客様が安心して依頼いただけるよう、最適な解決策をご提案いたします。
■もくじ
相続とは
相続とは、被相続人(亡くなった人)が所有している財産、及び権利義務を受け継ぐことを言います。
被相続人の子供や配偶者など身分関係がある人が受け継ぐこととなり、人が亡くなったときに相続は開始され、その日が相続開始日となります。
相続財産は、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことをいい、相続開始日を遡り法定相続人に所有権が引き継がれることになります。
相続財産には様々なものがあり、建物や土地などの不動産、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金などの負債、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されることになります。
相続の義務化
2024年までに相続登記の申請義務化が始まります
今後、高齢化が進み相続された不動産が放置され、そのまま空き家になってしまう可能性がある相続登記は、日本でも大きな課題となっています。
現在、相続で不動産を譲り受けた場合、不動産登記をすることなく他の者に所有権を主張することができ、相続時に所有権登録をしなくても問題はありません。
このことから、相続登記を怠るケースが増えそのまま所有者が誰か分からないままの土地が増え続けています。
しかし、政府は相続した不動産の所有権の移転について、2024年をめどに不動産登記を義務化する予定です。
相続登記しないデメリット
相続登記しなかった場合のデメリットはいくつかあります。
登記していない場合、売却できない
民法によって登記をしていない不動産は第三者に対して主張できません。
不動産を相続した場合、所有者が相続人自らであることを証明する必要があり、登記上の名義人でなければなりません。
また、不動産の登記は実際に行われている必要があり、被相続人からそのまま買主に対して所有権の移転登記をすることは不可能です。
すぐに売却を考えているのであれば、他の手続きと一緒に不動産登記をしてしまう方が無難です。
権利関係が複雑になってしまう
不動産の相続登記をするには遺産分割協議書が必要となってきます。
また、相続した土地を売却する場合にも、相続登記が必要です。
被相続人が亡くなってから、相続登記を早急に行わず長い間放置してしまうと、他の相続人と連絡が取れなくなってしまったり、相続人が増えてしまって関係が複雑になり、遺産分割協議で全員の合意をもらうことが難しくなってきます。
自分の子供や孫のことを考えて、複雑な不動産登記を残さないためにも、早めに相続登記をおこなうことが大切です。
差し押さえされる可能性がある
相続人の中に債務者がおり、支払いが滞っている場合、債権者によって不動産の相続持ち分を差し押さえられてしまうケースもあります。
債権者は法律に基づき、借金がある相続人の法定相続分を差し押さえることが可能です。
もし、遺産分割協議がまとまっている場合でも、相続登記を完了させていないと、不動産を差し押さえた債権者に対して、それが自分のものと主張できません。
専門家に依頼した時のメリット
相続を専門家に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
専門的な知識と経験を持っている
相続には法的な知識や手続きが必要となります。専門家は相続に関する法律や手続きについて深い知識を持っており、適切なアドバイスや支援を提供することができます。
コスト削減
専門家は相続に関する手続きや書類作成などを行うことで、時間とコストを節約することができます。また、相続に関する税金や手数料の支払いについても適切なアドバイスを提供することができます。
嫌疑や不和を避ける
相続には遺産分割や相続人の関係によって不和が生じることがあります。専門家は公正な立場から遺産分割を行い、家族の紛争を避けることができます。
タイムリーな対応
相続には期限があります。専門家は期限を把握し、必要な手続きや書類作成などをタイムリーに行うことができます。
納得のいく相続プランの策定
専門家は相続人の状況に応じて最適な相続プランを策定することができます。遺産分割や相続税の節税などについてもアドバイスを提供することができます。
日本リーガル司法書士事務所では、相談者様の現状やご要望に合わせて最適なプランをご提案しますので、まずはご相談ください。
こんなお悩みがある方は相談
下記に記載されてあるお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください
相続登記を放置している方
相続登記を放置してしまう方もいらっしゃいますが、そのような場合は早急に手続きを進めることが重要です。相続登記を放置してしまうと、不動産や預貯金などの財産が相続人間で分割されず、法定相続人による分割が強制されてしまう場合があります。また、相続税の支払い期限もあるため、放置することで税金の滞納や遅延損害金の発生などの問題が生じることもあります。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記の手続きをスピーディーに行い、相続人間での分割が円滑に行われるようサポートしています。また、相続税申告書の作成や相続税の節税などについてもアドバイスを行っています。放置している方は一度、当事務所にご相談いただき、解決策を見つけることをおすすめいたします。
相続登記を全て任したい方
相続登記には、法務局での手続きや書類作成など複雑な手続きが必要です。そのため、相続登記を全て任せたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記に関する一連の手続きを代行することができます。相続人の方が必要な書類を用意する手間を省き、スムーズかつ迅速に手続きを進めることができます。また、相続税の申告や納税についても代行することができますので、安心して任せていただけます。
相続登記を全て任せる場合、弊所との契約を結ぶことになります。手続き内容や料金などについて詳しく説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めるようにしています。お気軽にご相談ください。
相続の費用
相続おまかせパック
| 相続おまかせパック | 100,000円+登録免許税・実費 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 実費 | 戸籍 1通 450円 除籍・原戸籍 1通 750円 住民票 1通 300円 登記事項証明書 1通 500円 |
相続おまかせパックが使えるケースと加算が発生するケース
| 使えるケース | 加算が発生するケース | |
|---|---|---|
| 被相続人 | 被相続人が1人 | 被相続人が2人以上 2人目から1人につき5万円加算 |
| 相続人について | 相続人が配偶者や子供 | 相続人が兄弟やおい、めい 2万円加算 |
| 相続人が5人以内 | 相続人が6人以上 6人目から1人につき1万円加算 |
|
| 同じ人がすべての不動産を相続 | 不動産ごとに相続人が別 2人目から1人につき3万円加算 |
|
| 不動産について | 相続登記を申請する法務局が1ヶ所 | 相続登記を申請する法務局が複数 2ヶ所目から1ヶ所につき3万円加算 |
| 不動産の個数が5個以内 | 不動産の個数が6個以上 6個目から1個につき3,000円加算 |
相続の流れ
相続の発生・開始
相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により始まります。
遺言書の有無を確認
遺言書の有無により、相続人や相続分が変わます。遺言書がある場合は指定相続、ない場合は法定相続になります。
相続人の確定
相続人の確定は、故人の遺産を引き継ぐ人たちが誰なのかを決定することです。通常、配偶者、子供、親族などが相続人となります。
遺産の確認
遺産の確認は、故人が所有していた財産や債務を調べ、遺産総額を算出することです。遺産の中には、不動産、預貯金、有価証券、保険金、車両、家財道具などが含まれます。また、故人が借金をしていた場合には、遺産からその借金を返済する必要があります。
相続するか、放棄するかを決める。
相続するか、放棄するかを決める。
準確定申告
準確定申告は、法定の確定申告期限前に、確定している項目については申告し、未確定の項目については後日確定し再提出する方法です。例えば、源泉徴収票や領収書が揃っていなかったり、帳簿類が未完成の場合に利用されます。準確定申告を行うことで、確定申告書を期限内に提出でき、また税務署からの指摘や追加調査のリスクを減らすことができます。
相続財産の評価
相続財産の評価は、相続人が引き継ぐ財産の価値を算定することです。不動産や株式など、財産の種類に応じて適切な評価方法を選択し、その価値を算出します。遺産分割協議書や相続税申告書に必要なため、正確に評価することが重要です。評価を依頼する場合には、専門家の鑑定士に依頼することが一般的です。
遺産分割
遺産分割とは、相続財産を相続人間で分割することです。遺産分割には、相続人間の合意による自主分割と、裁判所による強制執行分割があります。自主分割の場合は、相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。強制執行分割の場合は、裁判所が遺産分割調停を行い、分割方法を決定します。遺産分割には税金や手数料がかかることがあるため、適切な手続きを行うことが重要です。
相続税の申告と納税
相続税の申告と納税には、相続財産を評価し、相続税申告書を作成して税務署に提出し、税務署から納税通知書を受け取って納税する、という手続きが必要です。相続税申告書を作成する際には、相続人や相続財産の詳細などを記載する必要があります。
相続財産の名義変更
相続財産の名義変更には、相続人が相続財産の所有権を取得し、登記簿上で名義変更の手続きを行うことが必要です。具体的には、相続人が登記簿謄本などの書類を提出し、登記官が所有権移転登記を行うことで名義変更が完了します。
相続税の還付
相続税の還付は、相続税納付時に評価額が過少だった場合や確定していなかった場合に行われます。還付を受けるためには、税務署に申請を行い、還付額が確定したら銀行口座に振り込まれます。
相続には期限がある
相続の手続きには期限があるので注意が必要です。この期限を過ぎてしまうと手続きを進められず不利益を被る可能性もあるので気を付けてください。
相続開始を知ってから3ヶ月以内
「限定承認」や「相続放棄」は相続を知ってから3カ月以内におこなわなければいけません。
どのような遺産があるか調査するのにも時間がかかってしまったり、3カ月以内に手続きが間に合わない場合は、家庭裁判所で「熟慮機関の延長」を申し立て一定期間、期限を延ばしてもらうことができます。
相続開始を知ってから4ヶ月以内
相続開始を知ってから4カ月以内に、被相続人の生前における所得の確定申告(純確定申告)をおこなわなければいけません。
【純確定申告する可能性があるケース】
- 被相続人の給与が2000万円以上である場合
- 被相続人が事業を行っていた場合
- 被相続人が副業で収入を得ており、申告義務がある場合
相続開始を知ってから10ヶ月以内
相続税や納税は相続開始を知ってから10カ月以内におこなわなければいけません。納税、申告をしなかった場合無申告課税や延滞料を支払うことになります。
相続税の申告は税務署でおこなえますが、個人では知識がないと難しい手続きなので専門家に依頼したほうが無難です。
弊社では相続について知識を持った司法書士が在籍しているので、まずはお気軽にご相談してください。
遺産相続の対象になる財産とは
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続人が引き継ぐことを指します。
不動産や預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになる財産のことを「相続財産」と呼びます。
遺産相続の対象になる財産
遺産相続では被相続人が残したすべての財産が該当しますが、どのようなものが相続財産の対象になるのかを理解しておくと相続手続きも円滑に進めることができます。
プラスの財産
| 現金・有価証券 | 現金・預貯金・株式・貸付金・売掛金・小切手など |
|---|---|
| 不動産や権利 | 宅地・農地・建物・居宅・店舗・借家権など |
| 動産 | 自動車・船舶・家財・骨董品・宝石・貴金属・美術品など |
| その他 | 著作権・ゴルフ加入権・電話加入権・慰謝料請求権など |
マイナスの財産
| 負債 | 借金・ローン・買掛金・未払の税金(住民税、所得税など)・未払の家賃・未払の地代・未払いの医療費など |
|---|
遺産相続の対象にならない財産
被相続人が有している「一審専属権(その者のみが行使できる権利」「保険金・年金・退職金」「祭祀財産」の3種類は相続の対象になりません。
一身専属権
一身専属権とは、遺産相続の対象にならない財産の下、その者のみが行使できる権利のことをいいます。
| 一身専属権の種類 | 親権・代理権・生活保護受給権・不要請求権・雇用契約上の地位 |
|---|
これらの権利は相続財産に含まれない一身専属権となります。
遺族年金・生命保険金
遺族年金や生命保険金などは、受取人の権利と考えられているため、相続財産には含まれません。
しかし、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」というもので、相続税の課税の対象となっています。これらを受け取った場合は相続税を支払わなければならない可能性もあるので注意が必要です。
遺族年金は、受け取るために申請をしなければならないため、忘れずに申請しましょう。
祭祀財産
祭祀財産とは、家系図、仏壇、墓地などのことで、これらを引き継ぐ場合は相続財産には含まれません。
遺産相続の相続順位と受け取れる遺産の割合
遺産相続ができる権利は誰がもっているのか、どういった割合で分配されるかは民法によって定められています。
受け取れる遺産の割合のことを「法定相続分」といい、遺産を受け取れる権利がある人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者、そして一定の親族のみに権利が与えられます。
遺産分割では、基本的に法定相続分通りに分割されますが、相続できる権利を持っている人が全員納得しているのであれば、受け取る割合を変更することができます。
法定相続分や法定相続人について理解をして遺産相続を進めた方がスムーズに手続きが終わります。
法定相続人の相続順位と割合
| 第1順位 | 配偶者 子供(孫) |
1/2 |
|---|---|---|
| 第2順位 | 配偶者 | 2/3 |
| 父母(祖父母) | 1/3 | |
| 第3順位 | 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹 | 1/4 |
配偶者は常に相続人となり、子供がいる場合は子供も相続人となります。
被相続人の介護などをしていた場合
被相続人の介護を一人の相続人が担っていた場合は、該当相続人が「寄与分」を主張して相続分を修正することが可能です。
胎児が法定相続人になるときの相続割合
民法866条第1項に、「胎児は相続に関して、すでに生まれたものとみなす」と規定されています。よって、胎児であっても法定相続人となり、遺産を受け取れます。
前配偶者との子や養子の相続順位と遺産割合
養子の相続順位と遺産割合
養子の相続順位や遺産割合は、実子と違いがありません。そのため、第一順位の法定相続人となります。
前の配偶者との子の相続順位と割合
前配偶者との子にも相続権はあり、相続順位は第一順位で法定相続分も同じとなります。しかし、前妻や前夫は相続人ではないので注意してください。
法定相続人が死亡している場合(代襲相続)は相続順位と割合はどうなるのか
被相続人に子供や孫がいて、被相続人が亡くなる前に子供が亡くなっていた場合、本来子供が受け取るはずだった遺産を、孫が受け取れるようになります。このことを「代襲相続」と呼びます。
法定相続人を確定させるために必要な書類
| 書類の種類 | 戸籍謄本、住民票、除籍謄本、戸籍の附表、改製原戸籍謄本など |
|---|
これらの書類は家族であっても本人の委任状が必要になってきます。
相続の登記は日本リーガル司法書士事務所にお任せください
相続はとても繊細な手続きで、相続人同士でトラブルに発展してしまう場合もあります。
相続が発生したら、早い段階で専門家に依頼した方が無難です。日本リーガル司法書士事務所には相続登記に精通した司法書士が在任しているので、まずはお気軽にご相談ください。