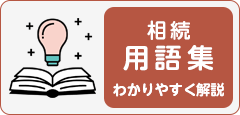相続時の銀行預金手続きについて|口座の調査から注意点まで徹底解説

家族が亡くなった後、銀行口座が凍結されてしまい、預金を引き出せず困ってしまう方が少なくありません。
特に、どの金融機関に口座があるのかわからない場合や、相続人同士で意見が食い違った場合、手続きがスムーズに進まないこともあります。
本記事では、預金の相続手続きの流れや注意点について詳しく解説し、安心して相続手続きを進めるためのポイントをご紹介します。
■もくじ
被相続人の銀行預金口座の調査のやり方
通帳やキャッシュカード、郵便物からの確認
被相続人の銀行預金口座を調査する際、まずは遺品の中にある通帳やキャッシュカードを確認しましょう。
最近は紙の通帳を発行しない金融機関もありますが、キャッシュカードや口座に関する郵便物があれば、口座の所在を特定する手がかりとなります。
また、預金の利息通知書や振込通知などの郵便物も確認してみてください。
生活圏内の金融機関に照会する
被相続人が生前に利用していた可能性のある、自宅周辺の金融機関に照会をかけるのも有効です。
地域密着型の金融機関(地銀、信用金庫、信用組合など)は特に利用されやすいため、都市銀行だけでなく地元の金融機関も必ず確認しましょう。
金融機関への口座照会に必要な書類
金融機関に口座の有無を確認するためには、次の書類が必要です。
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本
- 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
これらの書類を持参し、各金融機関の窓口で照会を行いましょう。
ネット銀行・通帳のない口座の確認方法
近年増えているネット銀行や通帳を発行しない口座についても注意が必要です。
これらは郵便物がない場合、口座の存在を把握しにくいですが、パソコンやスマートフォンの履歴、メールアカウントなどから利用状況を確認することができます。
また、被相続人のスマートフォン内の銀行アプリや、オンラインバンキングの履歴も重要な手がかりとなります。
全国銀行協会の「預金等照会制度」の活用
どうしても口座の所在が特定できない場合は、全国銀行協会が提供する「預金等照会制度」を活用する方法もあります。
この制度では、全国の銀行に対して一括で照会が可能となり、特定の条件を満たせば利用することができます。
制度の利用には、死亡の事実と相続人の関係が確認できる公的書類の提出が必要です。
預金の相続手続きは早めにする
相続手続きを放置すると手続きが複雑化する
被相続人の預金は、相続が発生すると相続人全員の共有財産となります。
この段階で、遺言書により受取人が指定されていれば、その指定された相続人が手続きを行うことで、預金を引き出すことができます。
一方で、遺言書が存在しない場合は、相続人全員での遺産分割協議を行い、誰が預金を取得するかを決めなければなりません。
手続きに期限はないが、早めの対応が重要
預金の相続手続きには法的な期限は設けられていませんが、できるだけ早めに進めることが望ましいです。
その理由として、手続きを放置することで以下のようなリスクが生じます。
- 相続人の一人が亡くなり、さらに二次相続が発生してしまう
- 相続人の数が増加し、遺産分割協議が困難になる
- 預金口座が凍結されたままになり、公共料金の引き落としなどに支障をきたす
特に、電気・ガス・水道などの公共料金や、ローンの引き落とし口座が凍結されると、生活に直結するトラブルとなります。
これらの理由から、早めに金融機関へ死亡の届出を行い、必要な手続きを速やかに始めることが大切です。
早期対応が相続税の申告にも影響
また、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
預金の相続手続きを後回しにすると、資産の全体像がつかめず、適正な相続税申告ができないリスクもあります。
そのため、預金の調査と手続きは、相続税申告の観点からも重要な作業となります。
預金を相続する手続き
口座凍結と手続きの開始
被相続人が亡くなった場合、まず金融機関に死亡の事実を連絡する必要があります。
この連絡を受けた金融機関は、被相続人の預金口座を凍結します。
口座が凍結されると、入出金や引き落としができなくなり、公共料金の自動引き落としも停止されるため注意が必要です。
凍結解除と預金相続の流れ
口座凍結後、預金を相続するためには、金融機関ごとに所定の手続きを行う必要があります。
以下は一般的な手続きの流れです。
- 金融機関の窓口に死亡の届出を行う
- 必要書類を提出する
- 金融機関での書類確認後、預金の払い戻し手続き
金融機関ごとに異なる必要書類
必要書類は金融機関や相続の状況によって異なるため、事前に確認することが重要です。
一般的には、以下の書類が求められます。
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
- 金融機関所定の届出書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)
法定相続情報証明制度の活用
戸籍一式を揃えるのが難しい場合、法定相続情報証明制度を活用することで、手続きが簡略化されます。
この制度では、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を金融機関に提出することで、戸籍謄本の代用として利用できます。
複数の金融機関で手続きを行う場合にも有効で、無料で複数枚発行できるのがメリットです。
分割協議前に仮払い制度を利用する
仮払い制度とは
相続手続きには時間がかかることが多く、特に遺産分割協議がまとまらないと、被相続人の預金をすぐに使うことができません。
そのような場合に利用できるのが、「相続預金の仮払い制度」です。
この制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前でも、一定額まで預金の払い戻しを受けることができます。
仮払い制度の利用条件
仮払い制度は、相続人の一人が単独で申請できますが、利用には条件があります。
- 預金口座が凍結されていること
- 相続人の1人が申請すること
- 他の相続人の同意は不要
ただし、仮払いを受けた金額は最終的な遺産分割の対象となり、仮払いを受けた相続人がそのまま全額を取得するわけではありません。
払い戻せる金額の上限について
仮払い制度で払い戻せる金額には上限があり、以下のように計算されます。
| 上限金額 | 1金融機関あたり最高150万円 |
|---|---|
| 計算式 |
|
| 具体例 |
|
仮払い制度利用時の必要書類
仮払い制度を利用するには、以下の書類を金融機関に提出します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 仮払いを請求する相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の仮払い申請書
金融機関によっては追加書類が必要な場合もあるため、事前に問い合わせて確認しましょう。
仮払い利用時の注意点
仮払い制度を利用した後は、正式な遺産分割協議の際に仮払い分を考慮する必要があります。
また、仮払いを利用したことで他の相続人との間に誤解やトラブルが生じる可能性もあるため、事後報告をしておくことが望ましいです。
放置してしまうと休眠預金となってしまう
休眠預金とは
被相続人の預金を長期間手続きせずに放置してしまうと、休眠預金として扱われることがあります。
休眠預金とは、最後の取引日から10年以上入出金のない預金口座のことをいいます。具体的には、2009年1月1日以降の預金で、10年以上放置されたものが対象となります。
休眠預金の流れとその後
休眠預金になると、金融機関から預金者宛てに通知が送られますが、住所変更や引越しなどで通知が届かない場合もあります。
通知が届かず、金融機関で確認が取れない場合は、その預金は預金保険機構へ移管され、民間の公益活動に活用される仕組みとなっています。
休眠預金でも払い戻しは可能
休眠預金となってしまった場合でも、相続人が金融機関で手続きを行えば引き出すことは可能です。
手続きの方法は、通常の預金相続の手続きと大きく変わりませんが、移管された場合は預金保険機構を通じての手続きが必要になることもあります。
そのため、休眠預金になる前に、できるだけ早く金融機関に連絡をし、相続手続きを開始することが望ましいです。
休眠預金の確認方法
被相続人の口座が休眠預金になっているか確認するには、以下の方法があります。
- 金融機関の窓口で直接確認
- 全国銀行協会の窓口や公式サイトを通じた確認
- 預金保険機構への問い合わせ
これらの方法を使って、被相続人の預金が休眠預金になっていないか、早めに確認しておきましょう。
遺産分割前の預金引き出しはトラブルに発展してしまう可能性がある
口座はすぐには凍結されない
被相続人が亡くなった場合、金融機関が死亡の事実を知るまでは預金口座は凍結されません。
そのため、キャッシュカードを利用すれば、ATMから預金を引き出すことが可能な状況が一時的に続きます。
しかし、この状況での引き出しは厳禁です。正規の手続きを経ずに預金を引き出すと、大きなトラブルに発展する可能性があります。
相続放棄や限定承認ができなくなるリスク
相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認を選択することが可能です。
しかし、被相続人の預金を引き出して使用してしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄や限定承認の権利を失ってしまいます。
結果として、多額の負債を背負うリスクもあるため、正式な手続き前に預金を使用するのは避けましょう。
他の相続人とのトラブルを防ぐために
遺産は相続人全員の共有財産であり、遺産分割協議が成立するまでは、誰か一人が勝手に預金を引き出すことは許されません。
仮に、葬儀費用や緊急の支出が必要で預金を使った場合でも、領収書や明細を保管し、他の相続人に説明責任を果たす必要があります。
こうした対応を怠ると、他の相続人との間で信頼関係が崩れ、遺産分割協議が長期化する原因になってしまいます。
事前の合意と手続きが円満相続の鍵
相続人全員の同意を得てから、仮払い制度を活用する、または正式に手続きを経て引き出すことが、トラブルを未然に防ぐ最善策です。
相続は感情的な問題にも発展しやすいため、誠実な対応を心がけましょう。
預金相続の手続に必要な書類
状況に応じて必要書類が異なる
預金を相続する際に必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無などによって異なります。
また、金融機関ごとに細かな要件が異なるため、事前の確認が重要です。
遺言書がある場合に必要な書類
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 遺言書(検認済証明書付きの場合あり)
- 相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の届出書
遺言書がない場合
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 金融機関所定の届出書
遺産分割協議書がない場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 家庭裁判所の調停調書または審判書
家庭裁判所の関与がある場合
遺産分割について家庭裁判所の調停や審判を受けた場合には、以下の書類が必要です。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
- 預金を相続する相続人の印鑑証明書
法定相続情報証明制度の利用で簡略化
多くの戸籍謄本の提出が必要な場合、法定相続情報証明制度を利用することで、手続きが簡略化されます。
法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸籍一式の代用となり、複数の金融機関でも利用可能です。
法定相続情報証明制度の活用方法とメリット
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、相続手続きの簡素化を目的として平成29年から始まった制度です。
この制度では、法務局に戸籍を提出して「法定相続情報一覧図」を作成してもらい、一覧図の写しを相続手続きで使用できます。
この一覧図は、戸籍謄本の束の代わりとして利用できるため、手続きが大幅に簡略化されます。
制度利用の流れ
- 被相続人の戸籍一式を揃える
- 法務局に申請し、法定相続情報一覧図を作成
- 法定相続情報一覧図の写しを無料で取得
- 各金融機関や不動産登記、税務申告で使用
一覧図の写しは、何枚でも無料で交付されますので、複数の金融機関で手続きを進める場合にも便利です。
制度利用のメリット
- 手続きの迅速化:戸籍の提出が1枚で済む
- コスト削減:戸籍の大量取得が不要になる
- 全国の金融機関で利用可能:一部を除き、ほとんどの機関が対応
- 不動産登記、税務署にも対応:各種相続手続きに利用可能
注意点
法定相続情報証明制度を利用するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要です。
また、一覧図は最新の相続情報が反映される必要があるため、相続人が新たに判明した場合などは再度申請が必要になります。
ネット銀行・通帳なし口座の調査方法
ネット銀行の普及と通帳のない口座の増加
近年では、ネット銀行や、通帳を発行しないタイプの口座が増加しています。
これにより、遺品整理で通帳が見つからず、口座の存在に気づかないケースが多くなっています。
ネット銀行の口座確認のポイント
ネット銀行の口座を調査するには、以下のような方法があります。
- スマートフォンやパソコンの中のネットバンキングアプリ、ログイン履歴を確認
- 遺品に残されたメールを確認し、口座取引に関する情報を探す
- クレジットカードの引き落とし銀行がネット銀行であるか確認
- スマートフォンのパスワード管理アプリに口座情報が登録されていないか確認
通帳のない口座の調査方法
最近は通帳を発行せず、WEB明細のみで管理される口座も増えています。
このような口座は、郵便物や通帳がないため発見が難しいですが、以下の情報を手がかりにできます。
- 公共料金やクレジットカードの引き落とし先の確認
- 生活圏内の金融機関に照会
- 被相続人が使っていたパソコンやスマホの履歴調査
- 全国銀行協会の預金等照会制度の利用
全国銀行協会の預金等照会制度
口座の所在がわからない場合、全国銀行協会の「預金等照会制度」を活用することで、全国の銀行を対象に口座の有無を確認することが可能です。
利用には、戸籍謄本や本人確認書類が必要となりますが、広範囲な調査ができるため、ネット銀行を含む不明口座の発見に役立ちます。
預金口座情報を家族で共有する重要性とその方法
口座情報を共有することの重要性
被相続人の口座情報が不明なまま相続が発生すると、調査に多大な時間と労力がかかってしまいます。
口座情報を生前から家族で共有しておくことで、スムーズな相続手続きが可能になります。
また、休眠預金になるリスクも回避でき、財産の把握が容易になるため、相続税申告にも有利です。
情報共有の方法
預金口座情報を家族で共有するには、以下の方法が効果的です。
- 口座情報を一覧表にまとめ、信頼できる家族に託す
- エンディングノートを活用し、金融資産情報を記載
- パスワード管理アプリを利用し、アクセス情報を共有
- 定期的に家族会議を行い、資産状況を確認
エンディングノートの活用
エンディングノートは、相続人に対して自身の希望や資産情報を伝えるための便利なツールです。
預金口座やネット銀行、投資口座なども記載しておくことで、家族が迅速に手続きを進められるようになります。
口座情報共有時の注意点
預金口座情報を共有する際は、セキュリティに十分注意してください。
紙で管理する場合は、金庫や鍵付きの引き出しに保管し、アプリの場合もパスワード設定を強化しましょう。
共有する相手は信頼できる家族に限り、不用意な情報漏洩を防ぐことが重要です。
まとめ
相続時の預金手続きは、迅速かつ正確な対応が求められます。
口座の調査から手続きに必要な書類、仮払い制度の活用や休眠預金のリスク回避など、事前に知っておくことで安心して相続を進めることができます。
また、法定相続情報証明制度や家族間での口座情報の共有も、円滑な相続のカギとなります。
不安や疑問がある場合は、専門家に相談することでトラブルを未然に防ぐことができ、確実な手続きを実現できます。
日本リーガル司法書士事務所では、相続に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。