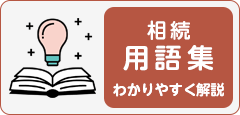遺留分とは?相続で知っておくべき権利と計算方法・請求手続きの完全ガイド

相続において「遺留分」という言葉を耳にしたことはありますか?遺言書によって相続財産の全てが特定の相続人に与えられたとしても、他の相続人には最低限の財産を受け取る権利が法律で保障されています。この権利こそが「遺留分」です。
遺留分は相続トラブルを防ぐ重要な制度ですが、誰に認められるのか、どのくらいの割合なのか、どのように請求するのかなど、知っておくべき点が多くあります。相続で後悔しないためにも、遺留分に関する正しい知識を身につけておきましょう。
この記事では、司法書士の視点から遺留分の基本から計算方法、請求手続きまで詳しく解説します。相続で権利を守るための情報として、ぜひ最後までお読みください。
■もくじ
遺留分とは?相続で保障される最低限の取り分
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の一定の相続人に対して法律で保障された最低限の相続分のことです。
たとえば、被相続人が遺言書で「全財産を長男に相続させる」と指定したとしても、配偶者や他の子どもたちには、一定割合の財産を相続する権利が法律で守られています。これが「遺留分」という制度です。
民法第1042条では「兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分として、第三章(相続の効力)の規定による相続分の2分の1の割合(直系尊属のみが相続人である場合にあっては、その相続分の3分の1の割合)に相当する財産を受ける」と定められています。
つまり、遺留分とは相続においてどのような遺言があっても奪うことができない最低限度の相続分であり、兄弟姉妹以外の相続人を保護するための重要な権利なのです。
遺留分が必要とされる理由
なぜ遺留分という制度が設けられているのでしょうか。その理由は主に以下の3つにあります。
1つ目は近親者の生活保障です。配偶者や子どもなど、被相続人と近い関係にあった方の生活を保障するために、最低限の財産を取得できる権利が必要とされています。
2つ目は財産形成への貢献の考慮です。特に配偶者は、被相続人の財産形成に協力してきた場合が多く、その貢献に対する報いとして遺留分が保障されています。
3つ目は不公平な遺言からの保護です。被相続人の一時的な感情や第三者の影響による不公平な遺言から、本来相続を受けるべき近親者を守る役割も果たしています。
このように遺留分制度は、相続における公平性を担保し、相続人の権利を守るために重要な役割を果たしているのです。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分と混同されやすい概念に「法定相続分」があります。両者の違いを明確にしておきましょう。
| 法定相続分 | 民法で定められた、遺言がない場合の相続財産の分け方の割合。相続人の組み合わせによって決まる。 |
|---|---|
| 遺留分 | 遺言があっても奪われない、法律で保障された最低限の相続分。基本的に法定相続分の半分(直系尊属のみの場合は3分の1)。 |
法定相続分は、遺言がない場合のデフォルトの分け方であり、遺言があればその内容が優先されます。一方、遺留分は遺言があっても保障される最低限の取り分であり、遺言によってこれを下回る場合は請求することができます。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1です。しかし、遺言で「全財産を配偶者に」とされていた場合、子どもたちは最低限の遺留分として、それぞれ遺産の8分の1を請求できる権利があります。
遺留分は単なる目安ではなく、民法で認められた法的権利です。そのため、遺留分を侵害されている相続人は、法的手続きを経てその権利を主張することができます。ただし、遺留分はあくまで権利であって義務ではありませんので、請求するかどうかは相続人の判断に委ねられています。
遺留分が認められる相続人と認められない相続人
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分は全ての相続人に認められているわけではありません。民法では、遺留分が認められる相続人を明確に定めています。遺留分を請求できるのは以下の相続人です。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に遺留分が認められる相続人となります。婚姻関係にある夫または妻は、どのような相続の場面でも遺留分請求権を持ちます。ただし、事実婚(内縁関係)の場合は法律上の配偶者ではないため、遺留分は認められません。
子どもや孫などの直系卑属
被相続人の子どもは遺留分が認められます。子どもが既に亡くなっている場合は、代襲相続により孫が相続人となり、その孫にも遺留分が認められます。養子も実子と同様に遺留分が認められます。
直系卑属とは、被相続人から見て直接の血縁関係にある子孫のことを指します。子、孫、ひ孫などが該当し、これらの相続人には遺留分が保障されています。
親や祖父母などの直系尊属
被相続人に子どもがいない場合、次の順位の相続人として親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。これらの直系尊属にも遺留分が認められます。
直系尊属とは、被相続人から見て直接の血縁関係にある先祖のことを指します。父母、祖父母、曾祖父母などが該当します。ただし、子どもがいる場合は、直系尊属は相続人とならないため、遺留分も問題となりません。
遺留分が認められない相続人
兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。相続人として相続権は持っていますが、遺留分は保障されていないのです。したがって、遺言によって兄弟姉妹の相続分がゼロとされても、遺留分侵害を理由に請求することはできません。
甥・姪
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、代襲相続により甥や姪が相続人となることがありますが、この場合も遺留分は認められません。兄弟姉妹に遺留分が認められていないため、その代襲者である甥や姪にも遺留分は認められないのです。
相続放棄・相続欠格・相続廃除と遺留分の関係
通常は遺留分が認められる相続人であっても、以下のような場合には遺留分請求権を失うことがあります。
相続放棄した場合
相続放棄とは、相続人が一切の相続財産を受け取らないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため、遺留分請求権も失います。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続欠格となった場合
相続欠格とは、一定の非行を行った相続人が、法律の規定により当然に相続権を失うことをいいます。例えば、被相続人や他の相続人を殺害した場合や、詐欺・脅迫によって遺言の作成を妨げた場合などに該当します。相続欠格者となった場合、遺留分請求権も失われます。
相続廃除された場合
相続廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所の審判を経て特定の相続人の相続権を奪うことができる制度です。著しい非行があった場合などに認められます。相続廃除された相続人は、相続権と共に遺留分請求権も失います。
なお、相続欠格と相続廃除は似ていますが、相続欠格は法律の規定により自動的に相続権を失うのに対し、相続廃除は被相続人の意思表示と家庭裁判所の審判によって相続権を失う点が異なります。
遺留分は重要な権利ですが、上記のような事情がある場合には認められないことがあります。相続に関して不安や疑問がある場合は、早めに専門家である司法書士に相談することをおすすめします。日本リーガル司法書士事務所では無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
遺留分の割合と計算方法
遺留分の基本的な計算方法
遺留分は単に法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)と理解するのが基本ですが、実際の計算はもう少し複雑です。遺留分の正確な算出のためには、まず「総体的遺留分」を確定し、そこから個々の相続人の「個別的遺留分」を導き出します。
遺留分を計算する際の基本的な考え方は以下の通りです。
- 総体的遺留分の確定:誰が相続人になるかによって、遺産全体の中で遺留分として保障される割合(1/2または1/3)を決定する
- 個別的遺留分の計算:総体的遺留分に各相続人の法定相続分の割合をかけて、個々の相続人の遺留分を算出する
この2段階の計算方法を押さえておくことで、複雑な遺留分の計算も理解しやすくなります。
総体的遺留分と個別的遺留分
総体的遺留分
総体的遺留分とは、遺産全体の中で遺留分として保障される部分の割合のことです。これは相続人の組み合わせによって異なります。
| 直系尊属のみが相続人の場合 | 遺産全体の3分の1 |
|---|---|
| それ以外の場合 | 遺産全体の2分の1 |
「直系尊属のみが相続人の場合」とは、被相続人に配偶者も子どももおらず、親や祖父母だけが相続人となる場合を指します。この場合、総体的遺留分は遺産全体の3分の1になります。
「それ以外の場合」とは、配偶者や子どもが相続人に含まれる場合などを指します。この場合、総体的遺留分は遺産全体の2分の1になります。
個別的遺留分
個別的遺留分とは、各相続人が実際に請求できる遺留分のことです。これは「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分の割合」をかけて計算します。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続分の割合は以下のようになります。
- 配偶者:2分の1
- 子ども:各4分の1(2分の1を2人で分ける)
この場合の総体的遺留分は2分の1なので、各相続人の個別的遺留分は次のように計算されます。
- 配偶者の遺留分:1/2(総体的遺留分)× 1/2(法定相続分)= 1/4(遺産全体の4分の1)
- 子どもの遺留分:1/2(総体的遺留分)× 1/4(法定相続分)= 1/8(遺産全体の8分の1)
このように、相続人それぞれの遺留分は、総体的遺留分と法定相続分の掛け算で求められます。
相続人の組み合わせ別の遺留分割合一覧
様々な相続人の組み合わせにおける遺留分の割合を一覧表にまとめました。
| 相続人の組み合わせ | 各相続人の遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
| 子のみ(1人) | 子:1/2 |
| 子のみ(複数) | 各子:1/2 ÷ 子の人数 |
| 配偶者と子(1人) | 配偶者:1/4 子:1/4 |
| 配偶者と子(複数) | 配偶者:1/4 各子:1/4 ÷ 子の人数 |
| 直系尊属のみ(1人) | 直系尊属:1/3 |
| 直系尊属のみ(複数) | 各直系尊属:1/3 ÷ 人数 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:1/3 直系尊属:1/6 |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
この表を参考にすれば、どのような相続人の組み合わせでも、各相続人の遺留分がどのくらいになるのかを把握することができます。
遺留分計算の具体例
具体的な例を通して、遺留分の計算方法をさらに理解しましょう。
例1:配偶者と子ども2人の場合
被相続人の遺産総額が3,000万円で、配偶者と子ども2人が相続人の場合を考えます。被相続人の遺言で「全財産を長男に相続させる」と指定されていた場合、配偶者と次男は遺留分を請求できます。
- 配偶者の遺留分:3,000万円 × 1/4 = 750万円
- 次男の遺留分:3,000万円 × 1/8 = 375万円
つまり、配偶者は長男に対して750万円、次男は長男に対して375万円の遺留分侵害額を請求できます。
例2:配偶者と親の場合
被相続人の遺産総額が2,000万円で、配偶者と父親が相続人の場合を考えます。被相続人の遺言で「全財産を配偶者に相続させる」と指定されていた場合、父親は遺留分を請求できます。
- 父親の遺留分:2,000万円 × 1/6 = 約333万円
つまり、父親は配偶者に対して約333万円の遺留分侵害額を請求できます。
不動産がある場合の遺留分の計算
遺産に不動産が含まれる場合、遺留分の計算はより複雑になります。不動産の評価方法によって遺留分の金額が大きく変わることもあります。
不動産の評価方法としては主に以下の方法があります。
- 相続税評価額(路線価方式や倍率方式)
- 固定資産税評価額
- 不動産鑑定評価額
- 実勢価格(市場価格)
遺留分侵害額請求においては、相続開始時の不動産の客観的な交換価値が基準となります。一般的には不動産鑑定評価額や実勢価格に近い金額が採用されることが多いですが、当事者間の協議によって決めることもできます。
不動産がある場合の遺留分計算は専門的な知識が必要なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。日本リーガル司法書士事務所では、不動産を含む遺産の遺留分計算についても無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺留分の放棄について
遺留分は権利であること
遺留分は法律によって認められた権利ですが、義務ではありません。つまり、相続人は遺留分を請求するかどうかを自由に選択できるのです。被相続人の遺言内容に納得できる場合や、家族の平和を優先したい場合など、遺留分を請求しないという選択も可能です。
例えば、配偶者に全財産を相続させるという遺言があっても、子どもたちがその内容に同意していれば、あえて遺留分を請求する必要はありません。このように、遺留分はあくまでも「請求できる権利」であり、必ず請求しなければならないものではないのです。
また、遺留分を放棄することもできます。遺留分の放棄には「相続開始後の放棄」と「生前の放棄」の2種類があります。
相続開始後の遺留分放棄
相続開始後の遺留分放棄とは、被相続人が亡くなった後に、遺留分を請求する権利を放棄することです。これは特別な手続きを必要とせず、単に遺留分を請求しないという消極的な方法でも実現できます。
ただし、明確に遺留分を放棄する意思を示したい場合は、書面で「遺留分を放棄する」という意思表示をすることもできます。これにより、後日のトラブルを防止することができるでしょう。
なお、相続放棄とは異なり、遺留分の放棄は家庭裁判所での手続きは不要です。また、相続自体は受けつつ、遺留分だけを放棄することも可能です。
生前の遺留分放棄の方法と条件
被相続人の生前に遺留分を放棄することも可能です。これを「遺留分の事前放棄」といいます。しかし、生前の遺留分放棄は厳格な手続きが必要とされており、以下の条件を満たす必要があります。
- 家庭裁判所の許可を得ること
- 公正証書などの書面で行うこと
- 放棄する本人が成年であること
家庭裁判所の許可を得るには、遺留分を放棄することが相続人にとって不利益ではないことを証明する必要があります。例えば、被相続人から生前に十分な贈与を受けている場合や、他の形で財産的な保障がある場合などが該当します。
また、公正証書などの書面による手続きが必要です。単なる念書や同意書では、法的効力は認められません。生前の遺留分放棄は厳格な条件があるため、必ず専門家に相談した上で手続きを進めることをおすすめします。
放棄後の撤回可能性
遺留分の放棄を一度行うと、原則として撤回することはできません。特に家庭裁判所の許可を得て行った生前の遺留分放棄は、よほどの事情変更がない限り撤回は認められないと考えられています。
ただし、以下のような例外的な場合には、撤回が認められる可能性があります。
- 放棄の意思表示に詐欺や脅迫があった場合
- 放棄後に被相続人の財産状況が大きく変わった場合
- 放棄の前提となった条件が満たされなかった場合
例えば、「被相続人から生前に十分な援助を受ける」という条件で遺留分を放棄したにもかかわらず、その条件が履行されなかった場合には、撤回が認められる可能性があります。
ただし、このような撤回が認められるケースは非常にまれであり、基本的には一度放棄した遺留分の権利を取り戻すことは困難です。そのため、遺留分の放棄を検討する際には、将来の状況変化も考慮に入れて慎重に判断することが重要です。
遺留分放棄の効果
遺留分を放棄すると、その相続人は遺留分に関する権利を完全に失います。つまり、被相続人の遺言や生前贈与によって遺留分を侵害されても、異議を申し立てることができなくなります。
ただし、遺留分のみを放棄した場合、相続自体の権利は残ります。例えば、遺言がない場合の法定相続分に基づく相続権は保持されます。一方、相続放棄をした場合は、遺留分を含むすべての相続権を失うことになります。
遺留分の放棄は、被相続人の意思を尊重したい場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合など、さまざまな理由で検討されることがあります。
しかし、その影響は大きいため、十分な検討と専門家のアドバイスを受けることが重要です。日本リーガル司法書士事務所では、遺留分放棄に関する相談も承っておりますので、不安や疑問がある方はぜひご相談ください。
遺留分侵害額請求とは
遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への変更点
遺留分を侵害された場合の請求方法は、2019年7月1日に施行された改正相続法によって大きく変わりました。それまでの「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと変更されたのです。この変更には重要な意味があります。
改正前の遺留分減殺請求では、遺留分を侵害された相続人は、遺産そのものの返還を請求することができました。例えば、ある不動産が遺言によって長男に相続された場合、次男が遺留分減殺請求をすると、その不動産は長男と次男の共有財産となっていました。
これに対し、改正後の遺留分侵害額請求では、原則として金銭での支払いが求められるようになりました。上記の例でいえば、長男は不動産を単独で所有したまま、次男に対して遺留分相当額のお金を支払うことになります。
| 改正前(遺留分減殺請求) | 遺産そのものの返還を請求(物的請求権) |
|---|---|
| 改正後(遺留分侵害額請求) | 遺留分相当額の金銭の支払いを請求(金銭債権) |
この改正により、遺産分割のプロセスがシンプルになり、相続トラブルの解決がスムーズになることが期待されています。
遺留分侵害額請求のメリット
遺留分侵害額請求の制度には、以下のようなメリットがあります。
共有状態の回避
改正前の制度では、遺留分減殺請求によって不動産などの財産が共有状態になることがよくありました。共有状態になると、財産の売却や活用に全員の同意が必要となり、意見が対立すると財産が塩漬け状態になることがありました。
遺留分侵害額請求では、財産は受遺者や受贈者がそのまま保有し、金銭で清算するため、共有状態による問題を避けることができます。
遺言の意思の尊重
金銭での清算により、被相続人の遺言の意思をより尊重できるようになりました。特定の財産を特定の相続人に相続させたいという遺言者の意思が、遺留分の権利を保障しながらも実現しやすくなったのです。
紛争解決の促進
共有状態を避けることで、その後の共有物分割などの二次的な紛争を防止できます。また、金銭での清算は分かりやすく、当事者間の交渉もスムーズに進みやすいという利点があります。
請求できる相手と金額
請求できる相手
遺留分侵害額請求ができる相手は、遺留分を侵害する利益を受けた者です。具体的には以下のような人が対象となります。
- 遺言によって遺産を取得した相続人や第三者(受遺者)
- 死因贈与によって財産を取得した者(受贈者)
- 生前贈与によって財産を取得した者(被相続人死亡前1年以内の贈与、または「遺留分を侵害する意思」を持って行われた贈与の場合)
複数の受遺者や受贈者がいる場合、遺留分侵害額請求は一定の順序で行われます。この順序については後ほど詳しく説明します。
請求できる金額
- 遺留分侵害額 = 遺留分の割合 × 遺留分算定の基礎となる財産額 – 相続人が既に取得している財産額
「遺留分算定の基礎となる財産額」とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた純資産(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたもの)に、一定の生前贈与や死因贈与の価額を加えたものです。
「相続人が既に取得している財産額」とは、遺言や法定相続、特別受益(生前贈与など)によって既に取得している財産の額です。
例えば、遺産総額1億円で、配偶者と子ども1人が相続人の場合、子どもの遺留分は1億円の4分の1である2,500万円です。遺言で子どもが1,000万円しか相続できない場合、子どもは遺留分侵害額として2,500万円から1,000万円を引いた1,500万円を請求できることになります。
遺留分侵害額の計算は複雑になることが多いため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。日本リーガル司法書士事務所では、遺留分侵害額の計算から請求手続きまで丁寧にサポートしておりますので、ご相談ください。
遺留分を請求できるケース
不公平な遺言書がある場合
遺留分侵害額請求が最も一般的に行われるのは、被相続人の遺言書によって遺留分が侵害された場合です。例えば、以下のようなケースが該当します。
特定の相続人に財産を集中させる遺言
「全財産を長男に相続させる」「全財産を配偶者に相続させる」などの遺言は、他の法定相続人の遺留分を侵害する可能性があります。例えば、配偶者と子ども2人がいる場合に、全財産を配偶者に相続させる遺言があると、子どもたちの遺留分(それぞれ8分の1)が侵害されることになります。
第三者に財産を遺贈する遺言
被相続人が法定相続人以外の第三者(友人や内縁の配偶者など)に財産を遺贈する遺言を残した場合も、法定相続人の遺留分を侵害する可能性があります。相続人の遺留分を超える部分について第三者に遺贈がなされた場合、相続人は遺留分侵害額を請求できます。
相続人の一部を廃除する遺言
遺言で特定の相続人を廃除する場合、家庭裁判所の審判が必要です。正当な廃除の場合、その相続人は遺留分請求権を失いますが、廃除の理由が不十分だったり、手続きに問題があったりする場合は、廃除された相続人も遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
死因贈与がある場合
死因贈与とは、贈与者(被相続人)の死亡を条件として効力が生じる贈与契約のことです。死因贈与は遺贈と類似した効果を持ちますが、契約であるため、受贈者の承諾が必要です。
死因贈与の特徴
死因贈与は被相続人の死亡時に効力が生じるため、相続財産と同様に遺留分侵害額請求の対象となります。死因贈与によって相続人の遺留分が侵害された場合、相続人は受贈者に対して遺留分侵害額を請求することができます。
死因贈与の例
例えば、被相続人が「自分が死亡したら、愛人に自宅不動産を贈与する」という契約を締結していた場合、その自宅不動産の価値によっては相続人の遺留分を侵害する可能性があります。このような場合、相続人は受贈者(愛人)に対して遺留分侵害額を請求できます。
生前贈与がある場合
被相続人の生前贈与も、一定の条件を満たす場合には遺留分侵害額請求の対象となります。ただし、すべての生前贈与が対象となるわけではなく、以下の条件を満たす贈与に限られます。
相続開始前1年以内の贈与
被相続人の死亡前1年以内に行われた贈与は、原則として遺留分算定の基礎財産に含まれます。これは、相続直前に財産を第三者に贈与することで遺留分制度を潜脱するのを防ぐためです。例えば、被相続人が死亡の半年前に多額の現金を友人に贈与していた場合、相続人はその友人に対して遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
遺留分侵害の意思をもってなされた贈与
相続開始1年より前の贈与であっても、被相続人と受贈者の双方が「遺留分を侵害する意思」をもって行った贈与は、遺留分侵害額請求の対象となります。ただし、この「遺留分侵害の意思」を証明するのは難しいため、実際に認められるケースは限定的です。
特別受益となる贈与
相続人に対する生前贈与で、特別受益(持ち戻し)の対象となるものは、相続開始前10年以内のものであれば遺留分算定の基礎財産に含まれます。例えば、被相続人が長男に高額な不動産を贈与していた場合、次男や三男は長男に対して遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
ただし、被相続人が「持ち戻し免除」の意思表示をしていた場合は、その贈与は原則として特別受益とはならず、遺留分算定の基礎財産にも含まれません。しかし、その贈与が他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
遺留分侵害額請求の対象となるケースは複雑で、個々の事情によって判断が異なる場合があります。遺留分に関する問題でお悩みの方は、日本リーガル司法書士事務所の無料相談をご利用ください。専門家が丁寧にご説明し、適切な解決策をご提案いたします。
遺留分侵害額請求の方法と流れ
話し合いによる解決
遺留分侵害額請求の第一歩は、当事者間での話し合いです。裁判所での手続きを経る前に、まずは遺留分を侵害した相手に対して請求の意思を伝え、交渉を試みることが一般的です。
請求の意思表示
遺留分侵害額請求は、請求者が相手方に対して「遺留分を侵害しているので支払いを求める」という意思表示をすることで効力が生じます。この意思表示は口頭でも有効ですが、後のトラブルを避けるためにも、書面で行うことをお勧めします。
内容証明郵便の活用
特に相手方との関係が良好でない場合は、内容証明郵便を利用して請求書を送付する方法が有効です。内容証明郵便には以下のメリットがあります。
- 請求の日付と内容が証明される
- 相手方が「知らなかった」と主張することを防止できる
- 遺留分侵害額請求権の時効を中断できる
内容証明郵便には、遺留分を侵害されている旨と請求額、支払い期限などを明記します。専門的な知識が必要なため、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
合意書の作成
話し合いがまとまり、合意に達した場合は、その内容を「遺留分侵害額についての合意書」などの形で書面にまとめておきましょう。合意書には以下の内容を含めるとよいでしょう。
- 当事者の氏名・住所
- 遺留分侵害額の金額
- 支払い方法と期限
- 分割払いの場合は各回の支払金額と期日
- 合意に至った日付
合意書は当事者全員が署名・押印し、各自が保管します。この合意書があれば、後日のトラブルを防ぐことができます。
調停の申立てと進め方
当事者間の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てることができます。調停は裁判よりも手続きが簡単で費用も安く、和解による解決を目指す手続きです。
調停の申立て
調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立てには以下の書類が必要です。
- 調停申立書
- 戸籍謄本(被相続人と当事者全員分)
- 遺産目録
- 遺言書のコピー(ある場合)
- その他関係資料
調停申立ての費用は、申立手数料(収入印紙)と郵便切手代などが必要ですが、訴訟に比べると低額です。
調停の進行
調停では、裁判官1名と調停委員2名が間に入り、当事者の主張を聞きながら解決策を探ります。一般的な流れは以下の通りです。
- 第1回調停期日:当事者の主張を聞く
- 財産調査:遺産の範囲や価額を調査
- 遺留分の計算:調停委員会が遺留分侵害額を計算
- 解決案の提示:調停委員会が解決案を提示
- 合意形成:当事者が合意に至れば調停成立
調停は原則として非公開で行われ、和やかな雰囲気の中で話し合いが進められます。調停が成立すると、調停調書が作成され、これは裁判の確定判決と同じ効力を持ちます。
訴訟による解決
調停でも合意に至らない場合は、「遺留分侵害額請求訴訟」を提起することになります。訴訟は裁判官の判断によって解決を図る手続きです。
訴訟の提起
訴訟は、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に提起します。訴状には請求の根拠や金額を明確に記載し、必要な証拠を添付します。訴訟提起には一定の手数料(訴額に応じた印紙代)が必要です。
遺留分侵害額請求訴訟は専門的な法律知識が必要なため、弁護士や司法書士に依頼することを強く推奨します。専門家に依頼することで、勝訴の可能性が高まります。
訴訟の進行
訴訟の一般的な流れは以下の通りです。
- 訴状の提出:請求内容と根拠を記載した訴状を裁判所に提出
- 答弁書の提出:被告が反論や主張を記載した答弁書を提出
- 口頭弁論:当事者が裁判所で主張を行う
- 証拠調べ:財産評価や遺留分計算のための証拠調査
- 判決:裁判官が判断を下す
訴訟は公開の法廷で行われ、原則として複数回の期日を経て判決に至ります。判決が確定すると、被告は判決内容に従って支払いを行う義務が生じます。被告が支払わない場合は、強制執行の手続きを取ることができます。
遺留分侵害額請求の順序
複数の受遺者や受贈者がいる場合、遺留分侵害額請求には法律で定められた順序があります。この順序に従って請求していくことが重要です。
遺贈と死因贈与
まず最初に遺贈や死因贈与を受けた人に対して遺留分侵害額請求を行います。遺贈と死因贈与が複数ある場合、基本的に価額に応じて按分して請求します。
生前贈与
遺贈や死因贈与からの回収では遺留分侵害額を満たせない場合に限り、生前贈与を受けた人に対して請求することができます。その際、新しい贈与から順に請求していくことになります。例えば、3年前の贈与と1年前の贈与がある場合、まず1年前の贈与を受けた人に請求します。
同時期の贈与
同時期に複数の贈与が行われていた場合は、各贈与の価額に応じて按分して請求します。例えば、同じ日に2人が異なる価値の贈与を受けていた場合、その価値の割合に応じて請求額を按分します。
遺留分侵害額請求は複雑な手続きであり、請求の順序や方法を誤ると権利を失う可能性もあります。不安な点がある方は、日本リーガル司法書士事務所の無料相談をご利用ください。専門家が適切なアドバイスを提供し、円満な解決に向けてサポートいたします。
遺留分侵害額請求権の時効と注意点
時効の期間
遺留分侵害額請求権には時効があります。民法第1048条では、遺留分侵害額請求権は「相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」行使しないと時効によって消滅すると定められています。
この「知った時」とは、被相続人が亡くなったこと(相続開始)と、遺言や贈与によって自分の遺留分が侵害されていることの両方を知った時点を指します。例えば、被相続人の死亡時には遺言書の存在を知らなかったが、半年後に遺言書が見つかった場合、その半年後から1年間の時効期間が始まります。
1年という期間は比較的短いため、遺留分侵害を知った場合は速やかに行動することが重要です。時効を過ぎてしまうと、正当な権利があっても請求できなくなってしまいます。
除斥期間について
遺留分侵害額請求権には時効だけでなく、「除斥期間」も設けられています。除斥期間とは、権利の存続期間を画一的に定めたもので、時効と異なり中断や停止がありません。
民法第1048条では、遺留分侵害額請求権は「相続開始の時から10年を経過したとき」にも消滅すると規定されています。これは、相続人が相続開始や遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すれば、もはや遺留分侵害額請求はできなくなるということです。
例えば、被相続人が亡くなってから8年後に遺言書が発見された場合、その時点から1年以内に請求する必要がありますが、相続開始から10年が経過する前に請求手続きを完了させなければなりません。
時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の時効を止めるには、以下の方法があります。
請求
相手方に対して遺留分侵害額の支払いを請求することで、時効は中断されます。請求の方法に特別な形式はありませんが、後日の証拠として残るように書面で行うことが望ましいです。特に内容証明郵便を用いると、いつ請求したかを証明できるため有効です。
調停・訴訟の提起
家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てたり、地方裁判所に訴訟を提起したりすることも、時効を中断する効果があります。調停や訴訟が不調に終わっても、その手続き中は時効が進行しません。
差押え・仮差押え・仮処分
相手方の財産を差し押さえたり、仮差押えや仮処分を行ったりすることも時効を中断します。ただし、これらの手続きには裁判所の決定が必要で、一定の担保金も必要となるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
承認
相手方が遺留分侵害額請求権の存在を認めること(承認)も時効を中断します。例えば、相手方が「遺留分侵害額を支払います」と書面で約束した場合、その時点で時効は中断されます。
ただし、口頭での承認は後に「言っていない」と否定される可能性があるため、書面で残すことが重要です。
内容証明郵便の活用
遺留分侵害額請求において、内容証明郵便を活用することは非常に有効です。内容証明郵便とは、郵便局が差出人の依頼により、いつ、誰から、誰に、どのような内容の文書を送ったかを証明する特殊な郵便サービスです。
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便には以下のようなメリットがあります。
- 請求の日時と内容を公的に証明できる
- 相手方が「請求を受けていない」と主張するのを防げる
- 時効の中断効果を確実に証明できる
- 裁判になった場合の有力な証拠となる
内容証明郵便の書き方
遺留分侵害額請求の内容証明郵便には、以下の内容を明記するとよいでしょう。
- 被相続人の氏名と死亡日
- 請求者が遺留分権利者であること
- 遺留分を侵害している事実(遺言や贈与の内容)
- 遺留分侵害額の計算根拠と金額
- 支払いを求める旨の明確な意思表示
- 回答期限(通常は1ヶ月程度)
内容証明郵便の作成は専門的な知識が必要なため、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。日本リーガル司法書士事務所では、遺留分侵害額請求の内容証明郵便作成から、その後の交渉、調停・訴訟まで一貫してサポートしております。
時効の完成を防ぐためのポイント
遺留分侵害額請求権の時効を完成させないために、以下のポイントに注意しましょう。
- 相続開始を知ったら早めに遺言書の有無を確認する
- 遺留分侵害を知ったら速やかに専門家に相談する
- 請求は書面(できれば内容証明郵便)で行う
- 話し合いが長引きそうな場合は、先に時効中断の手続きをしておく
- 相手方からの回答や承認の内容は必ず記録に残す
時効は一度完成してしまうと、権利回復が極めて困難です。「様子を見よう」と思っているうちに時効が完成してしまうケースも少なくありません。遺留分侵害の可能性を感じたら、早めに専門家に相談することをお勧めします。
遺留分に関するよくある質問
遺留分の対象となる財産の範囲
遺留分の計算の基礎となる財産(遺留分算定の基礎財産)について、よく質問があります。遺留分算定の基礎財産には以下のものが含まれます。
相続開始時に被相続人が有していた財産
被相続人が亡くなった時点で所有していた全ての財産(預貯金、不動産、有価証券、車両、貴金属、美術品など)が対象となります。また、借金などの債務も考慮され、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた「純資産」が基礎となります。
みなし相続財産
被相続人が生前に行った一定の贈与も、「みなし相続財産」として遺留分算定の基礎財産に加えられます。具体的には以下のものが該当します。
- 相続開始前1年以内にされた贈与
- 相続人に対する特別受益となる贈与(相続開始前10年以内のもの)
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
遺留分の対象とならない財産
一方、以下のような財産は遺留分算定の基礎財産に含まれません。
- 生命保険の死亡保険金(受取人が指定されている場合)
- 死亡退職金(受取人が指定されている場合)
- 祭祀財産(墓地や仏壇など)
- 相続開始1年より前の贈与(特別な事情がない場合)
これらの財産は原則として遺留分の計算に含まれないため、遺言でこれらの財産の取得者を指定しても、他の相続人の遺留分を侵害することにはなりません。
遺留分を請求するタイミング
遺留分侵害額請求をするタイミングについても、多くの方が疑問を持っています。
最適な請求タイミング
遺留分侵害額請求は、相続開始(被相続人の死亡)後であればいつでも可能です。ただし、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に請求する必要があります。
最適なタイミングとしては、以下の点を考慮するとよいでしょう。
- 遺産の全体像が把握できた段階
- 遺言書の検認手続きが終わった後
- 遺産分割協議が行き詰まった場合
- 時効が迫っている場合は早急に
遺産分割協議との関係
遺留分侵害額請求と遺産分割協議は別個の手続きですが、同時並行で進めることも可能です。ただし、遺産分割協議が成立すると、その内容に同意したものとみなされ、後から遺留分侵害額請求をすることが難しくなる場合があります。
そのため、遺言があり遺留分侵害の可能性がある場合は、遺産分割協議書に「遺留分侵害額請求権を留保する」という文言を入れておくか、遺産分割協議の前に遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことが賢明です。
遺留分を請求したときの家族関係への影響
遺留分侵害額請求は法律上の権利ですが、実際に請求することで家族関係に亀裂が生じることを心配される方も多くいらっしゃいます。
請求による影響の可能性
遺留分侵害額請求は、特定の相続人に対して金銭の支払いを求める行為であるため、その相手方との関係が悪化する可能性は否定できません。特に、以下のような場合は注意が必要です。
- 相手方が請求の理由を理解していない場合
- 相手方の資金繰りが厳しい場合
- もともと家族関係が良好でない場合
円満な解決に向けた工夫
家族関係を維持しながら遺留分の問題を解決するために、以下のような工夫が考えられます。
- 請求前に丁寧に説明し、理解を求める
- 一括払いが難しい場合は分割払いを提案する
- 中立的な第三者(司法書士や弁護士)を介して交渉する
- 家庭裁判所の調停を利用する
遺留分侵害額請求は法的権利ですが、家族関係も大切な財産です。両者のバランスを考慮した対応を心がけることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、円満な解決を目指しましょう。
遺留分の計算や請求は自分でもできるか
遺留分の計算や請求を自分で行うことは理論上は可能ですが、実際には多くの困難が伴います。
自分で行う場合の課題
遺留分侵害額請求を自分で行う場合、以下のような課題があります。
- 財産評価の難しさ(特に不動産や事業用資産)
- 「みなし相続財産」の範囲の判断
- 適切な請求書類の作成
- 相手方との交渉技術
- 法的な主張の組み立て
専門家に依頼するメリット
司法書士や弁護士などの専門家に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
- 正確な遺留分の計算が可能
- 法的に有効な請求手続きが確保される
- 感情的対立を避け、中立的立場から交渉できる
- 裁判になった場合の対応力
- 時効管理の確実性
遺留分侵害額請求は、一生に何度も経験するものではありません。適切な解決のためにも、専門家のサポートを受けることをお勧めします。日本リーガル司法書士事務所では、遺留分に関する無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。
最後に10つ目の項目を作成します。
まとめ:遺留分で相続トラブルを防ぐために
遺留分制度は、相続人の権利を保護する重要な制度です。ここまで解説してきた内容を踏まえ、遺留分に関する重要なポイントをまとめます。
遺留分の基本を押さえる
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分です。配偶者、子ども、親などの直系尊属には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。遺留分の割合は、基本的に法定相続分の半分(直系尊属のみの場合は3分の1)となります。
遺留分は単なる目安ではなく、法律で保障された権利です。たとえ被相続人が遺言で「全財産を特定の相続人に相続させる」と指定していても、他の法定相続人には遺留分を請求する権利があります。
遺留分侵害額請求の流れを理解する
遺留分を侵害された場合は、侵害した相手に対して「遺留分侵害額請求」を行います。具体的な流れは以下の通りです。
- 相続開始と遺留分侵害の事実を確認する
- 遺留分侵害額を計算する
- 相手方に請求の意思表示をする(できれば書面で)
- 話し合いで解決を試みる
- 話し合いがまとまらない場合は調停や訴訟へ
遺留分侵害額請求権には1年の時効と10年の除斥期間があります。権利を失わないためにも、遺留分侵害を知ったら速やかに行動することが重要です。
遺留分を考慮した遺言書作成のポイント
遺言書を作成する際は、相続人の遺留分を侵害しないように注意することも大切です。遺留分を考慮した遺言書作成のポイントは以下の通りです。
- 各相続人の遺留分を事前に計算しておく
- 遺留分を侵害する可能性がある場合は、その対応策を考えておく
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合は、生前に対策を講じる
- 遺言執行者を指定し、円滑な遺産分割を図る
もし遺留分を侵害する内容の遺言を残したい場合は、影響を受ける相続人からあらかじめ遺留分の放棄を得ておくなどの対策も検討するとよいでしょう。ただし、遺留分の生前放棄には家庭裁判所の許可が必要です。
専門家のサポートを活用する
遺留分に関する問題は複雑で、専門的な知識が必要です。以下のような場面では、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
- 遺留分が侵害されているかどうか判断したい場合
- 遺留分侵害額の正確な計算が必要な場合
- 遺留分侵害額請求の手続きを進めたい場合
- 遺留分を考慮した遺言書を作成したい場合
- 遺留分の放棄手続きを検討している場合
専門家のサポートを受けることで、法的に正確な手続きを進めることができ、後々のトラブルを防ぐことができます。
円満な相続を実現するために
遺留分は法的権利ですが、その行使が家族間の対立を招くこともあります。相続は単なる財産分与ではなく、故人の意思を継ぎ、遺された家族の将来にも関わる重要な問題です。
円満な相続を実現するためには、法的権利の主張だけでなく、家族間のコミュニケーションと相互理解も大切です。必要に応じて第三者の専門家を介することで、感情的対立を避け、客観的な解決を図ることができます。
相続の問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談することをお勧めします。日本リーガル司法書士事務所では、相続に関する無料相談を実施しております。遺留分をはじめとする相続のお悩みに、経験豊富な司法書士が丁寧にお応えします。