遺産分割(いさんぶんかつ)とは?
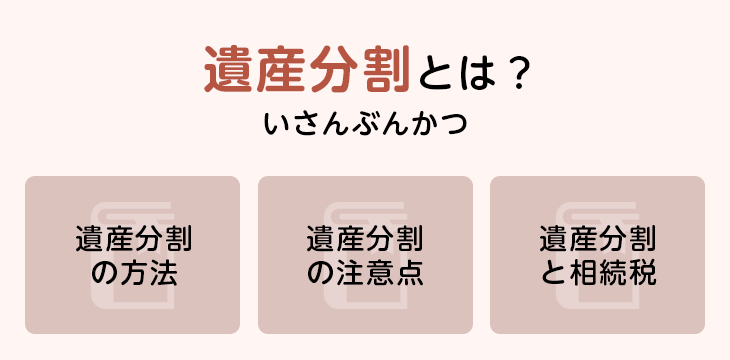
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人(法定相続人や遺言で指定された相続人)の間で分ける手続きのことです。相続が開始すると、相続人全員の共有財産となるため、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。
遺産分割の方法には、遺言による指定、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)、家庭裁判所による調停・審判などがあります。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人の間で分配する手続きです。相続が開始されると、相続財産は一時的に相続人全員の共有状態となります。
この共有状態を解消し、誰がどの財産を取得するかを確定させるのが遺産分割の目的です。遺産分割が完了するまでは、預貯金の引き出しや不動産の売却などには原則として相続人全員の同意が必要となります。
遺産分割の対象となる財産
| 対象となる財産 |
|
|---|---|
| 対象とならない財産 |
上記の表は遺産分割の対象となる財産とならない財産を示しています。生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合は遺産分割の対象外となりますが、受取人が「相続人」と指定されている場合は遺産分割の対象となることがあります。
遺産分割の方法
遺産分割には主に3つの方法があります。被相続人の意思が優先され、次いで相続人の合意、最後に法律の規定による分割となります。
- 遺言による分割:被相続人が遺言で財産の分け方を指定している場合
- 遺産分割協議:相続人全員の話し合いで決める方法
- 調停・審判:話し合いがつかない場合に家庭裁判所に申し立てる方法
遺言がある場合は原則としてその内容に従いますが、遺留分を侵害するような内容の場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。遺言がない場合や遺言で指定されていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。
法定相続分と指定相続分
遺産分割協議では、法定相続分を基準としつつも、相続人の合意があれば自由に分割割合を決めることができます。法定相続分とは民法で定められた相続分のことで、相続人の続柄によって異なります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者:1/2、子:1/2(子が複数の場合は均等分割) |
| 配偶者と親(子がいない場合) | 配偶者:2/3、親:1/3(親が双方いる場合は均等分割) |
| 配偶者と兄弟姉妹(子も親もいない場合) | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数の場合は均等分割) |
この表は主な法定相続分を示しています。ただし、実際の遺産分割では法定相続分通りに分ける必要はなく、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う話し合いです。相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任する必要があります。
- 相続人の確定:戸籍謄本等で相続人を確定させる
- 相続財産の調査:預貯金、不動産、負債などを調査する
- 遺産分割協議の実施:相続人全員で話し合いを行う
- 遺産分割協議書の作成:合意内容を書面にまとめる
- 名義変更等の手続き:各種財産の名義変更を行う
上記のリストは遺産分割協議の一般的な流れを示しています。遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産の名義変更など、各種手続きに必要となる重要な書類です。
遺産分割協議書の必要記載事項
- 作成日
- 被相続人の氏名・死亡日
- 相続人全員の氏名・住所・続柄
- 分割する財産の内容と帰属先
- 各相続人の署名・押印
遺産分割協議書には上記の事項を必ず記載します。特に不動産の記載については、所在地、地番、面積など登記事項証明書の記載に合わせることが重要です。また、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要となることが一般的です。
遺産分割における注意点
遺産分割を円滑に進めるためには、いくつかの注意点があります。これらを事前に理解しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
遺産分割の期限
遺産分割には原則として期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告する必要があります。遺産分割が間に合わない場合は「未分割」として申告し、後日「更正の請求」を行うことになります。
また、令和5年(2023年)4月からは相続開始から3年を経過すると、法定相続分で遺産分割がされたものとみなされる制度(配偶者居住権等に関する特例あり)が施行されています。
遺産分割と相続放棄
相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。
ただし、相続放棄の申述前に遺産を処分するなど「相続財産の処分」に当たる行為をした場合、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
特別受益と寄与分
| 特別受益 | 被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた場合、その価額を相続分から控除する制度 |
|---|---|
| 寄与分 | 被相続人の事業や介護などに特別に貢献した相続人が、法定相続分に加えて取得できる部分 |
特別受益と寄与分は、公平な遺産分割を実現するための制度です。特別受益は「持ち戻し」とも呼ばれ、生前贈与や遺贈を受けた相続人の相続分から、その価額を差し引いて計算します。寄与分は被相続人の財産維持や増加に特別に貢献した相続人に認められるものです。
遺産分割と相続税
遺産分割の結果は相続税の計算に影響します。遺産分割の方法によっては、相続税の総額や各相続人の納税額が変わることがあります。
相続税の申告と納付
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。申告期限までに遺産分割が完了していない場合は、法定相続分で仮に計算して申告し、後日遺産分割が確定したら「更正の請求」を行います。
相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。特に事業承継や不動産が多い場合は、各種特例措置の適用も検討する必要があります。
遺産分割の方法と税負担
| 現物分割 | 財産をそのまま分ける方法。財産の性質に応じた課税 |
|---|---|
| 換価分割 | 財産を売却して現金化し、その代金を分ける方法。売却時に譲渡所得税が発生する可能性あり |
| 代償分割 | 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭等で代償する方法。代償金の資金準備が必要 |
遺産分割の方法には主に上記の3種類があります。それぞれ税負担が異なるため、相続人の状況や財産の内容に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。特に不動産などの評価額が高い財産については、慎重な検討が必要です。
よくある質問
遺言がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
遺言で全ての財産について指定がされている場合は原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺言の内容が不明確だったり、遺留分を侵害していたりする場合は、相続人間で協議が必要になることがあります。また、遺言に記載されていない財産が見つかった場合も、その部分については遺産分割協議が必要となります。
相続人の一人と連絡が取れない場合、遺産分割はどうすればよいですか?
相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、連絡が取れない相続人がいる場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも解決しない場合は審判に移行します。また、行方不明などの理由で長期間連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることも検討できます。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのですか?
法律上、遺産分割協議書の作成は義務付けられていませんが、後々のトラブル防止や各種名義変更手続きのために作成することを強くおすすめします。特に不動産の相続登記や相続税の申告には遺産分割協議書が必要となることが一般的です。さらに、令和6年(2024年)4月から不動産の相続登記が義務化されたため、より一層重要性が高まっています。
預貯金の解約には遺産分割協議書が必要ですか?
金融機関によって対応は異なりますが、多くの場合、預貯金の解約には遺産分割協議書の提出が求められます。特に高額な預貯金の場合はほぼ必須です。一部の金融機関では少額の場合に限り、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書で対応してくれることもあります。遺産分割前に仮払いが認められるケースもありますので、各金融機関に確認することをおすすめします。
遺産分割で揉めないためにはどうすればよいですか?
遺産分割で揉めないためには、まず被相続人の生前から遺言を残しておくことが最も効果的です。遺言がない場合は、相続人間でオープンなコミュニケーションを心がけ、財産の全体像を共有することが大切です。また、感情的にならず、各相続人の事情や希望を尊重する姿勢が重要です。専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に仲介してもらうことで、中立的な立場から適切なアドバイスを受けられることもあります。
まとめ
遺産分割とは、被相続人の財産を相続人の間で分配する手続きです。相続開始後、相続財産は一時的に相続人全員の共有状態となり、この状態を解消するために遺産分割を行います。
遺産分割の方法には、遺言による分割、相続人全員による遺産分割協議、家庭裁判所による調停・審判があります。遺言がある場合は原則としてその内容に従いますが、遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求が可能です。
遺産分割協議では、法定相続分を基準としつつも、相続人全員の合意があれば自由に分割割合を決めることができます。協議の結果は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割を進める際は、特別受益(生前贈与など)や寄与分(被相続人への特別な貢献)も考慮する必要があります。また、令和5年(2023年)4月からは相続開始から3年経過すると法定相続分で分割されたとみなされる制度が施行されていることにも注意が必要です。
遺産分割の結果は相続税の計算にも影響するため、税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。円滑な相続のためには、生前からの準備や専門家への相談が重要です。






