物納可能資産(ぶつのうかのうしさん)とは?
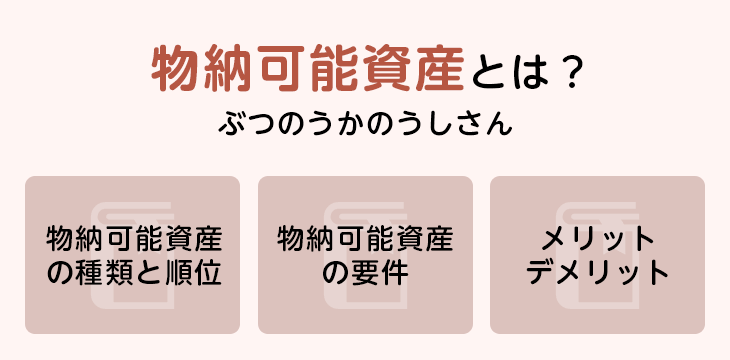
物納可能資産とは、相続税の支払いを現金ではなく、物(財産)で納税することができる資産のことです。相続税の納付が金銭では困難な場合に、一定の条件を満たした財産を国に納めることで納税義務を果たすことができます。
物納は「物納申請」という手続きを経て行われ、すべての資産が物納可能なわけではなく、法律で定められた特定の資産のみが対象となります。
物納可能資産の種類と順位
物納可能資産は法律で定められており、第1順位から第3順位までの順位が付けられています。物納を申請する場合は、原則として順位の高い資産から納付していくことになります。
| 第1順位 |
|
|---|---|
| 第2順位 |
|
| 第3順位 |
|
上記の表は物納可能資産の種類と順位を示しています。不動産が第1順位に含まれているため、相続した土地や建物は物納しやすい資産といえます。
物納可能資産の要件
すべての相続財産が物納できるわけではありません。物納するためには以下の要件を満たす必要があります。
- 金銭で納付することが困難であること
- 被相続人から相続または遺贈により取得した財産であること
- 管理処分が不適当でないこと(汚染土地や権利関係が複雑な不動産などは不可)
- 物納申請時に相続人が所有しており、物納許可時まで維持されていること
- 担保権等の付着がないこと(抵当権などが設定されていない)
上記のリストは物納するための主な要件です。特に「金銭で納付することが困難」という要件が重要で、単に現金での納付を避けたいという理由では物納は認められません。
管理処分不適当財産の例
国が管理・処分することが不適当と判断される財産は物納が認められません。以下はその例です。
- 土壌汚染や地盤沈下のある土地
- 境界が不明確な土地
- 権利関係が複雑で争いがある財産
- 違法建築物
- 管理に多額の費用がかかる財産
これらの財産は国が管理・処分することが困難であるため、物納が認められない可能性が高いです。事前に専門家に相談することをおすすめします。
物納の流れと手続き
物納を行うためには、以下の流れで手続きを進める必要があります。
- 相続税の申告期限内に延納申請書と物納申請書を提出:相続開始から10か月以内に税務署へ提出
- 審査:税務署が物納の要件を満たしているか審査(数か月〜1年程度)
- 物納許可通知書の受領:許可された場合は通知書が届く
- 物納財産の引き渡し:不動産の場合は所有権移転登記など
- 物納手続完了:相続税の納付義務が消滅
物納の手続きは複雑で時間がかかるため、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
必要書類
物納申請には以下の書類が必要となります。
| 基本書類 |
|
|---|---|
| 不動産の場合の追加書類 |
|
| 有価証券の場合の追加書類 |
|
上記の表は物納申請に必要な主な書類です。財産の種類によって必要書類が異なるため、事前に税務署に確認することをおすすめします。
物納のメリットとデメリット
物納には以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
物納を検討する際は、上記のメリットとデメリットを十分に考慮し、他の納税方法(延納など)と比較検討することをおすすめします。
物納と延納の違い
相続税の納付が困難な場合の選択肢として、物納と延納があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 物納 | 延納 |
|---|---|---|
| 納付方法 | 財産で納付 | 分割して金銭で納付 |
| 対象財産 | 法定の物納可能資産のみ | 関係なし(金銭納付) |
| 期間 | 一度の手続きで完了 | 最長20年(不動産の場合) |
| 利子 | 物納許可までの利子税 | 延納期間中の利子税 |
| 担保 | 不要 | 原則として必要 |
| 手続きの複雑さ | 非常に複雑 | 比較的簡単 |
上記の表は物納と延納の主な違いを示しています。一般的に、まず延納を検討し、それでも納付が困難な場合に物納を検討するという順序になります。
よくある質問
Q1. 物納と現金納付を併用することはできますか?
はい、可能です。例えば、相続税1,000万円のうち、600万円を現金で納付し、残りの400万円分を物納するといった併用が認められています。
ただし、金銭で納付できる部分は金銭で納付しなければならず、一部だけを物納することが困難な場合は、その理由を明確にする必要があります。
Q2. 物納申請中に利子税はかかりますか?
はい、物納申請中も利子税はかかります。物納申請が許可されるまでの期間(審査期間)についても、相続税の法定納期限の翌日から物納許可の日までの期間について利子税が課されます。
このため、物納申請が長期化すると利子税の負担が大きくなる可能性があります。
Q3. 共有財産を物納することはできますか?
共有持分の物納は原則として認められていません。ただし、共有者全員が同意して共有財産全体を物納する場合や、共有関係を解消して単独所有にした上で物納する場合は可能です。
共有財産の物納を検討する場合は、事前に税務署や専門家に相談することをおすすめします。
Q4. 物納した不動産を買い戻すことはできますか?
原則として、一度物納した財産を買い戻す制度はありません。物納によって財産の所有権は国に移転し、国有財産として管理・処分されます。
ただし、国が一般競争入札などで売却する際に入札に参加することは可能です。
Q5. 物納が認められなかった場合はどうなりますか?
物納申請が却下された場合、相続税を現金で納付するか、延納の申請を行う必要があります。延納についても要件を満たさない場合は、現金での一括納付を求められます。
また、物納申請から却下までの期間について利子税がかかるため、早めに対応策を検討することが重要です。
まとめ
物納可能資産とは、相続税の納付を現金ではなく、国に財産を納めることで納税義務を果たす制度において、納付に使える財産のことです。物納可能資産には国債・地方債、不動産、有価証券など法律で定められた種類があり、第1順位から第3順位まで優先順位が付けられています。
物納を行うためには「金銭納付が困難であること」「相続・遺贈により取得した財産であること」「管理処分に適していること」などの要件を満たす必要があります。手続きは相続税の申告期限内に物納申請書を提出するところから始まり、審査を経て許可された後に財産を国に引き渡します。
物納のメリットは現金がなくても相続税を納付できることや財産を売却する必要がないことですが、手続きが複雑で時間がかかること、審査が厳しいことなどのデメリットもあります。相続税の納付方法としては、まず延納(分割納付)を検討し、それでも納付が困難な場合に物納を検討するという順序が一般的です。
物納を検討する際は、税理士や司法書士などの専門家に相談し、自分の状況に最適な納税方法を選ぶことをおすすめします。






