公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは?
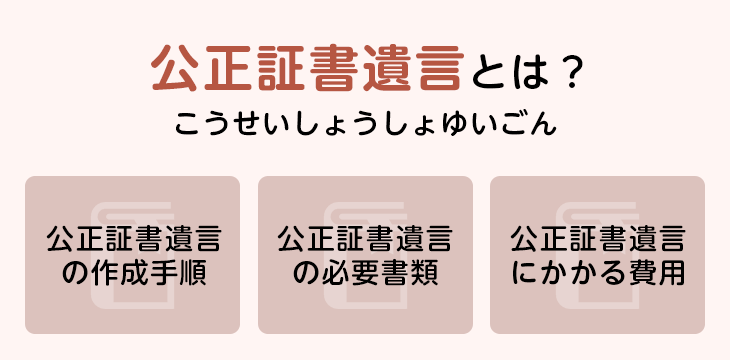
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を筆記し、作成する遺言の形式です。
民法で定められた遺言の中で最も確実性が高く、紛失や偽造のリスクが少ないため、相続争いを防ぐ効果があります。公証役場で作成され、原本は公証役場で保管されるため安全性が高いことが特徴です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言の一種で、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する正式な文書です。民法第969条に規定されており、遺言者と証人2名以上の立会いのもとで作成されます。
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本や謄本が交付されます。遺言者が亡くなった後、相続人は公証役場で遺言書を確認することができます。
公正証書遺言は、法的な専門家である公証人が関与するため、内容の不備や無効となるリスクが低く、家庭裁判所での検認手続きも不要という大きな特徴があります。
| 公正証書遺言の特徴 | 公証人が作成し、原本は公証役場で保管される法的効力の高い遺言です |
|---|---|
| 根拠法 | 民法第969条 |
| 必要な人員 |
|
この表は公正証書遺言の基本情報をまとめたものです。公正証書遺言は法的な効力が高く、後々のトラブル防止に役立ちます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、他の遺言形式と比較して多くのメリットがあります。以下にその主なメリットをご紹介します。
- 形式不備による無効リスクが低い
- 原本が公証役場で保管されるため紛失の心配がない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 偽造や変造のリスクがない
- 公証人のアドバイスを受けながら作成できる
- 相続人が遺言の存在を知らなくても、法務局の遺言書情報証明制度で確認可能
公正証書遺言は、専門家である公証人の関与により法的に確実な効力を持つため、相続トラブルを未然に防ぐ効果があります。特に財産が多い場合や、相続人間で争いが予想される場合におすすめです。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成は、以下の手順で進められます。計画的に準備を進めることで、スムーズに遺言を残すことができます。
- 公証役場への事前相談:内容や必要書類について確認します
- 遺言内容の検討:相続財産の内容や相続人への分配方法を決めます
- 証人の手配:利害関係のない2名以上の証人を用意します
- 必要書類の準備:遺言者の本人確認書類や相続財産の証明書類を揃えます
- 公証役場での作成:遺言者が口述し、公証人が筆記して文書を作成します
- 遺言書の確認と署名押印:内容確認後、遺言者、証人、公証人が署名押印します
- 正本・謄本の受け取り:遺言者は正本や謄本を受け取ります
この手順は公正証書遺言作成の一般的な流れです。実際の手続きは公証役場によって若干異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
証人について
公正証書遺言を作成する際には、証人2名以上が必要です。ただし、証人には一定の制限があります。
| 証人になれない人 | |
|---|---|
| 証人の役割 | 遺言者本人の意思確認、遺言内容の証明、署名押印による証明 |
この表は公正証書遺言における証人についての注意点をまとめたものです。証人は利害関係のない第三者が望ましく、多くの場合、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要となります。事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
| 遺言者の本人確認書類 |
|
|---|---|
| 相続財産に関する書類 |
|
| 相続人に関する書類 |
|
この表は公正証書遺言作成時に必要な主な書類をまとめたものです。実際に必要な書類は遺言の内容によって異なるため、事前に公証役場に確認することをおすすめします。
公正証書遺言にかかる費用
公正証書遺言の作成には、以下のような費用がかかります。遺言の内容や財産の価額によって変動するため、事前に確認しておくことが大切です。
| 公証人手数料 | 遺言書に記載される財産の価額に応じて決まります(5,000円〜) |
|---|---|
| 正本・謄本の交付手数料 | 1枚あたり250円+用紙代 |
| 証人費用 | 公証役場で紹介してもらう場合は1名あたり5,000〜10,000円程度 |
| その他 | 出張手数料(公証人が出張する場合)、相談料など |
この表は公正証書遺言作成時にかかる主な費用をまとめたものです。公証人手数料は法務省令で定められており、財産価額1,000万円の場合は約2万円程度です。
よくある質問
Q1. 公正証書遺言は自筆証書遺言とどう違いますか?
公正証書遺言は公証人が作成し、原本が公証役場で保管される遺言です。一方、自筆証書遺言は遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名押印する遺言です。
公正証書遺言は法的な専門家である公証人が関与するため、形式不備による無効リスクが低く、検認手続きも不要です。また、原本が公証役場で保管されるため、紛失・偽造のリスクもありません。
Q2. 公正証書遺言を作成するのに年齢制限はありますか?
公正証書遺言を作成するには、満15歳以上で遺言能力(遺言の内容を理解し、自分の意思で決定する能力)があることが条件です。高齢者でも意思能力があれば作成可能です。
ただし、認知症など判断能力に不安がある場合は、医師の診断書を事前に用意するなど、遺言能力を証明する対策を講じておくことが望ましいでしょう。
Q3. 公正証書遺言は後から内容を変更できますか?
公正証書遺言は、遺言者の生存中であれば変更や撤回が可能です。変更方法としては、新たに公正証書遺言を作成して前の遺言を撤回する方法が一般的です。
部分的な変更の場合も、変更内容を含めた新たな公正証書遺言を作成します。その際、前の遺言の一部または全部を撤回する旨を明記します。
Q4. 証人は親族や友人でもいいですか?
証人には一定の制限があり、推定相続人や受遺者、またその配偶者や直系血族は証人になれません。つまり、遺言によって財産を受け取る人やその近親者は証人になれないことになります。
親族や友人でも、上記の制限に該当しなければ証人になることは可能ですが、後のトラブル防止のため、利害関係のない第三者を選ぶことが望ましいでしょう。
Q5. 公正証書遺言は必ず公証役場に行かなければ作成できませんか?
基本的には公証役場で作成しますが、遺言者が病気や高齢などの理由で公証役場に行くことが困難な場合、公証人に出張を依頼することも可能です。病院や自宅などでも作成できます。
出張の場合は別途出張費用がかかりますが、遺言者の状況に合わせて柔軟に対応してもらえるのも公正証書遺言のメリットの一つです。
まとめ
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与して作成される遺言であり、民法で定められた遺言の中で最も確実性が高い形式です。遺言者の意思を正確に反映し、後の相続トラブルを防ぐ効果があります。
公正証書遺言の最大のメリットは、形式不備による無効リスクが低く、原本が公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配がないことです。また、家庭裁判所での検認手続きも不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。
作成には公証人手数料などの費用がかかりますが、相続トラブルを防ぐことによる精神的・経済的なメリットを考えれば、決して高いものではありません。特に財産が多い場合や相続人間でトラブルが予想される場合には、公正証書遺言の作成をおすすめします。
遺言は「終活」の重要な一部です。自分の意思を明確に伝え、残された家族の負担を軽減するためにも、早めに公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。






