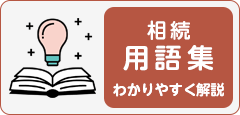相続人になるの誰?相続の範囲・順位・割合を徹底解説

ご家族が亡くなったとき、「誰が遺産を相続できるのか」「どのような割合で分けるのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
相続において、法定相続人の範囲や順位、相続できる割合は民法で明確に定められています。しかし、実際の家族関係は複雑で、誰が相続人になるのか、どのような割合で遺産を分けるのかを正確に把握することが難しい場合も多いでしょう。
この記事では、相続の基本から特殊なケースまで、法定相続人の範囲や優先する順位、相続権を失うケースなどを詳しく解説します。また、相続人調査の方法や相続人がいない場合の手続きも解説します。
法定相続人とは
相続が発生したとき、まず重要となるのは「誰が遺産を引き継ぐ権利を持つのか」を理解することです。法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」を指します。
この「法定相続人」という概念をしっかりと理解することが、円滑な相続手続きの第一歩となります。
法定相続人と受遺者の違い
相続において、財産を受け取る立場には主に二種類あります。一つは法律で定められた「法定相続人」、もう一つは遺言書で指定された「受遺者」です。
「法定相続人」は民法によって定められた権利を持ちますが、「受遺者」は被相続人の遺言によって財産を受け取る人を指します。
例えば、被相続人が遺言書で「友人に自宅を遺贈する」と記していた場合、その友人は法定相続人ではなくても「受遺者」として指定された財産を受け取ることができます。
しかし、遺言書の内容であっても、法定相続人に保障された「遺留分」を侵害するような内容は、後に法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。相続では、遺言の内容と法定相続人の権利のバランスが重要なポイントとなります。
遺言の有無による相続人の違い
誰が遺産を相続するかは、被相続人が遺言を残したかどうかで大きく変わります。民法では「遺言は相続よりも優先される」と定められています(民法964条)。
遺言書がある場合、その内容に従って財産が分配されます。例えば「長男に自宅を相続させる」「次男に預金の70%を相続させる」といった具体的な指示があれば、原則としてそれに従います。
ただし、遺言書は民法で定められた形式に従っていなければ無効となるため注意が必要です。また、遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合、法定相続人は遺留分侵害額請求ができます。
遺言書がない場合や、遺言書に指定のない財産については、民法の規定に従って法定相続人が相続することになります。法定相続人の範囲や順位、相続分は明確に定められているため、これに基づいて遺産分割協議を行うことになります。
このように、遺言の有無によって相続の進め方は大きく異なります。そのため、相続が発生したらまず遺言書の有無を確認することが重要です。
法定相続人の範囲と相続順位
法定相続人には明確な範囲があり、被相続人との関係性によって相続の順位が定められています。ここでは、具体的に誰が法定相続人となり得るのか、またその優先順位について解説します。
配偶者は常に相続人になる
配偶者は常に相続人となります。他の相続人が誰であっても、被相続人の配偶者は必ず相続権を持ちます。
ただし、ここでいう配偶者とは「法律上の婚姻関係にある人」を指します。内縁関係の場合は、たとえ長年一緒に暮らしていても法定相続人にはなりません。
また、被相続人が亡くなった時点で離婚していた元配偶者も相続権はありません。離婚届が提出されていない別居中の配偶者は、法律上は婚姻関係が継続しているため相続人となります。
血族相続人と相続順位
配偶者以外の相続人は、被相続人との血縁関係に基づき、以下の順位で定められています。
- 第1順位:直系卑属(子、孫、ひ孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(および甥・姪)
この順位は被相続人に近い関係にある人から優先される形になっています。上位の順位に相続人がいる場合、下位の順位の人は原則として相続権を持ちません。
たとえば、被相続人に子どもがいる場合、両親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。子どもや孫がいない場合に初めて、両親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
親族でも相続権がない人
被相続人の親族であっても、法定相続人に該当しない人は遺産を相続できません。具体的には、以下のような人が該当します。
- 内縁の配偶者
- 離婚した元配偶者
- 養子縁組していない連れ子
- 姻族(配偶者の親や兄弟姉妹)
- いとこ
- 伯父伯母、叔父叔母
- 上位の順位がいる場合の下位順位の親族
これらの人々は、被相続人と親しい関係にあったとしても、民法上の相続権はありません。ただし、被相続人が遺言を残していれば、受遺者として財産を受け取ることは可能です。
また、近年の民法改正(2019年7月施行)により、被相続人の生前に介護や看護に貢献した特別な親族には「特別寄与料」を請求できる制度が創設されました。これにより相続人ではなくても、一定の要件を満たせば被相続人への貢献に応じた対価を受け取れる可能性があります。
相続割合の具体例
相続人が誰になるかによって、法定相続分(遺産の分配割合)は変わります。ここでは、相続人の組み合わせごとの具体的な相続割合について解説します。
配偶者と子がいる場合
被相続人の配偶者と子が相続人となる場合、配偶者が2分の1(50%)、子が2分の1(50%)の割合で相続します。
子が複数いる場合は、子どもたちで等分することになります。例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。
| 相続人の構成 | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者と子1人 |
|
| 配偶者と子2人 |
|
| 配偶者と子3人 |
|
配偶者がいない場合(先に亡くなっている場合や相続放棄した場合など)は、子どもたちで等分します。例えば、子が3人いる場合は、それぞれ3分の1ずつ相続します。
配偶者と直系尊属がいる場合
被相続人に子どもがおらず、配偶者と直系尊属(両親や祖父母)が相続人となる場合、配偶者が3分の2(約66.7%)、直系尊属が3分の1(約33.3%)の割合で相続します。
直系尊属が複数いる場合は、その人数で等分します。例えば、配偶者と両親がいる場合、配偶者が3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつとなります。
| 相続人の構成 | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者と両親 |
|
| 配偶者と父のみ |
|
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
被相続人に子どもも両親もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が4分の3(75%)、兄弟姉妹が4分の1(25%)の割合で相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で等分します。例えば、配偶者と兄弟が2人いる場合、配偶者が4分の3、兄弟はそれぞれ8分の1ずつとなります。
| 相続人の構成 | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者と兄弟1人 |
|
| 配偶者と兄弟2人 |
|
このように、相続人の組み合わせによって法定相続分は変動します。また、相続順位が下がるほど配偶者の相続割合が大きくなることがわかります。
なお、これらの法定相続分はあくまで民法で定められた原則であり、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。ただし、その場合でも全相続人の合意が必要となります。
相続権を失うケース
法定相続人であっても、一定の事由により相続権を失うことがあります。ここでは、相続権を失う主な3つのケース「相続欠格」「相続廃除」「相続放棄」について解説します。
相続欠格とは
相続欠格とは、一定の事由に該当する場合に自動的に相続権が剥奪される制度です。民法では以下の事由に該当する場合、たとえ法定相続人であっても相続権を失うと定めています。
- 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させたとき
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかったとき
- 詐欺や強迫により、被相続人に遺言の作成・変更・撤回をさせたり、妨げたりしたとき
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したとき
相続欠格は、裁判所の判断を経ずに法律上当然に適用されるため、該当する事由があれば自動的に相続権を失います。
なお、相続欠格で相続権を失った人に子どもがいる場合、その子どもは代襲相続により被相続人の遺産を相続することができます。相続欠格は個人の行為に対する制裁であり、その子どもまで相続権を奪うものではないためです。
相続廃除とは
相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて相続人の相続権を奪う制度です。以下の事由がある場合、被相続人は家庭裁判所に廃除の申立てをすることができます。
- 相続人が被相続人に対して虐待をしたとき
- 相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
- 相続人に著しい非行があったとき
相続廃除の対象となるのは、配偶者と第1順位・第2順位の相続人(子や父母など)に限られ、兄弟姉妹など第3順位の相続人は対象外です。
相続廃除は被相続人の生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言で廃除する旨を記載することで行われます。ただし、遺言による廃除は被相続人の死後、家庭裁判所による確認の審判を受ける必要があります。
相続廃除された人の子どもは、相続欠格の場合と同様に代襲相続することができます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が自らの意思で相続権を放棄することです。借金や負債が多い場合など、相続することでかえって不利益を被る可能性がある場合に選択されることが多い方法です。
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といい、原則として延長はできませんが、やむを得ない事情がある場合は家庭裁判所に伸長の申立てをすることも可能です。
相続放棄が認められると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。そのため、遺産のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継ぎません。
相続放棄をした人の子どもは代襲相続できません。また、相続放棄により次順位の相続人(例:子が全員相続放棄した場合の親)が繰り上がって相続権を得ることになります。
なお、相続放棄は個々の相続財産についてではなく、相続財産全体について行うものです。「この不動産だけ相続放棄する」といった部分的な放棄はできません。
特殊な相続のケース
相続には通常のケース以外にも、特殊な事例があります。ここでは代襲相続や養子、胎児、未成年者、行方不明者が関わる相続について詳しく解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人より先に死亡している場合などに、その子(被相続人からみれば孫など)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
例えば、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続権を得ます。
代襲相続が認められるケースは以下の通りです。
- 相続人となるべき人が、被相続人より先に死亡している場合
- 相続人となるべき人が、相続欠格により相続権を失った場合
- 相続人となるべき人が、相続廃除により相続権を失った場合
相続放棄をした場合は、「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、代襲相続は発生しません。
代襲相続の対象となるのは第1順位の直系卑属(子や孫など)と第3順位の兄弟姉妹(およびその子である甥姪)です。第2順位の直系尊属(父母や祖父母など)には代襲相続は認められていません。
養子・胎児・未成年者の相続
養子の相続権
養子は実子と同様に法定相続人となります。ただし、養子の種類によって相続関係が異なります。
普通養子の場合、養親との間に新たな親子関係が発生する一方、実親との親子関係も存続します。そのため、養親と実親の両方の法定相続人となります。
これに対し特別養子の場合は、養親との間に親子関係が発生すると同時に実親との親子関係が終了します。そのため、特別養子は養親の法定相続人になりますが、実親の法定相続人にはなりません。
胎児の相続権
相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児であった場合、民法上は「既に生まれたものとみなす」とされており、相続権が認められています。
ただし、この規定は胎児が無事に生まれた場合に限られます。流産や死産、人工中絶の場合には、最初から存在しなかったものとして扱われます。
胎児がいる場合の遺産分割は、胎児が生まれるまで待つか、胎児の取り分を留保して暫定的に行うことになります。
未成年者の相続
未成年者も相続人になることができますが、民法上、単独で契約などの法律行為を行う能力が制限されているため、法定代理人が必要になります。
通常、未成年者の法定代理人は親ですが、親が同じ相続人として関わる場合には利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
行方不明者がいる場合
法定相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続きが進められなくなります。
まずは戸籍の附票や住民票などから最後の住所地を調べ、手紙を送るなどして連絡を試みます。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
不在者財産管理人は行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。家庭裁判所から選任された不在者財産管理人は、行方不明者の利益のために行動する義務があります。
また、行方不明者の生死が長期間にわたって不明な場合は、「失踪宣告」の申立てをすることも可能です。失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。失踪宣告は、普通失踪(7年間の生死不明)と特別失踪(危難に遭遇してから1年経過)の2種類があります。
相続人調査の方法
相続手続きを進める上で、まず重要となるのが「誰が法定相続人なのか」を正確に把握することです。ここでは、法定相続人を調査するための具体的な方法について解説します。
遺言書の調査・検認
まず最初に行うべきは、被相続人が遺言書を残していないかどうかの確認です。遺言書があれば、その内容に従って相続が進められるからです。
自宅を探すだけでなく、以下の可能性も検討しましょう。
- 銀行の貸金庫に保管されていないか
- 弁護士・司法書士・税理士などの専門家に預けていないか
- 公正証書遺言として公証役場で作成していないか
- 法務局で自筆証書遺言を保管していないか(2020年7月施行の制度)
公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の有無を照会することができます。また、法務局で保管されている自筆証書遺言については、法務局で確認できます。
遺言書が見つかった場合の対応は種類によって異なります。
- 公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言:検認不要
- それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言:開封せずに家庭裁判所での検認が必要
検認とは、遺言書の内容を確認して相続人に通知するとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認を受けずに勝手に開封すると過料の対象となる可能性があるため注意しましょう。
戸籍謄本による相続人調査
遺言書の有無にかかわらず、法定相続人を特定するための戸籍調査は必ず行う必要があります。戸籍調査では以下のような戸籍謄本を収集します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の配偶者の戸籍謄本
- 被相続人の子どもたちの戸籍謄本
- 必要に応じて、その他の相続人(両親、兄弟姉妹など)の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本を取得するには、市区町村役場の戸籍課などに請求します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めることで、結婚歴や子どもの有無などが確認できます。
相続人調査は、思わぬところに別の相続人がいる可能性も考慮して、丁寧に行う必要があります。例えば、被相続人に前婚の配偶者との間に生まれた子どもがいるケースや、戸籍に記載のない非嫡出子がいるケースもあります。
また、相続人が既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫など)が代襲相続することになるため、さらにその戸籍謄本も取得する必要があります。
相続人の所在調査
戸籍で相続人を特定した後は、その相続人の現在の住所を調べる必要があります。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要だからです。
相続人の現住所を調べるには、戸籍の附票を取得します。戸籍の附票とは、その戸籍に記載されている人の住所の履歴を記録した公文書です。最後の住所地から、現在の住所を追跡することができます。
それでも連絡が取れない相続人がいる場合は、前述の「不在者財産管理人」の選任など、専門的な対応が必要になります。
法定相続情報証明制度の活用
2017年5月から始まった「法定相続情報証明制度」を利用すると、戸籍謄本等の束を何度も用意する手間を省くことができます。
この制度では、戸籍謄本等を法務局に提出すると、法定相続人が誰であるかを証明する書面(法定相続情報一覧図)が無料で発行されます。この一覧図を使えば、各種相続手続きで戸籍謄本の原本を何度も提出する必要がなくなります。
相続手続きは金融機関や不動産登記など複数の機関で行うことが多いため、この制度を活用することで手続きが効率化されます。法務局に一度申請しておけば、必要な枚数の証明書を無料で発行してもらえるため、ぜひ活用しましょう。
相続人がいない場合の手続き
遺言書も残されておらず、法定相続人も存在しない場合、遺産はどのように扱われるのでしょうか。ここでは、相続人不在の場合の手続きについて解説します。
相続財産管理人と国庫帰属
相続人がいない、またはすべての相続人が相続放棄した場合、その遺産は「相続人不存在の財産」となります。このような場合、家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」を行う必要があります。
申立ては、被相続人の債権者や、特別縁故者になり得る人、検察官などが行います。また、利害関係がなくても、被相続人の最後の住所地の市区町村長も申立てが可能です。
家庭裁判所が相続財産管理人を選任すると、相続財産管理人は以下のような職務を行います。
- 相続財産の調査・管理:被相続人の財産目録を作成し、遺産を適切に管理します
- 相続債権者等への公告:官報に掲載し、債権者や受遺者に請求の申出を促します
- 債権者等への弁済:債権者や受遺者に対して弁済を行います
- 特別縁故者への分与:特別縁故者がいれば、財産の分与を行います
- 残余財産の国庫帰属:上記すべての手続き後に残った財産は国庫に帰属します
相続財産管理人による手続きは、選任から国庫帰属まで約1~2年程度かかるのが一般的です。この間の相続財産管理人の報酬や諸経費は相続財産から支払われます。
特別縁故者による分与請求
特別縁故者とは、被相続人と特別な縁故関係にあった人のことで、民法では次のような人が該当するとされています。
- 内縁の配偶者
- 事実上の養子(養子縁組の届出をしていない養子)
- 長年にわたり被相続人の療養看護に努めた人
- 被相続人と生計を同じくしていた人
- 被相続人の財産の維持や増加に貢献した人
特別縁故者は法定相続人ではないため通常は相続権を持ちませんが、相続人がいない場合には例外的に財産分与を受けることができます。
特別縁故者として財産分与を受けるには、相続財産管理人による相続債権者等への弁済が終わった後、3ヶ月以内に家庭裁判所に請求する必要があります。家庭裁判所は、被相続人との縁故の程度、被相続人の財産の額、その他の事情を考慮して分与の可否と範囲を決定します。
分与が認められれば、その範囲内で相続財産を取得できますが、他に特別縁故者がいる場合は複数人で分け合うことになります。特別縁故者への分与は家庭裁判所の裁量に委ねられるため、分与を受けられない可能性もあります。
2019年民法改正:特別寄与制度
2019年7月に施行された民法改正により、「特別寄与制度」が新設されました。これは法定相続人ではない親族が、被相続人の療養看護などを無償で行い、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した場合に、相続人に対して金銭的請求ができる制度です。
例えば、長男の妻が義父(夫の父)の介護を長年にわたって行った場合、従来は法定相続人ではないため何の対価も受け取れませんでしたが、この制度により相続人に対して「特別寄与料」を請求できるようになりました。
特別寄与料の請求は、相続の開始を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります。金額については当事者間の協議で決定し、協議が調わない場合は家庭裁判所に請求することになります。
この制度は相続制度を補完するものとして重要な役割を果たしており、法定相続人ではなくても被相続人への貢献に応じた対価を受け取れる可能性が広がりました。
よくある質問
相続に関する疑問や質問は多岐にわたります。ここでは、相続人に関してよく寄せられる質問にお答えします。
養子は相続人になれますか?
はい、養子は実子と同様に法定相続人となります。ただし、養子の種類によって相続関係が異なります。
「普通養子」の場合は、養親との親子関係が新たに発生する一方で、実親との親子関係も継続します。そのため、養親と実親の両方の相続人となります。
一方、「特別養子」の場合は、養親との親子関係が発生すると同時に実親との親子関係が終了します。そのため、養親の相続人になりますが、実親の相続人にはなりません。
内縁の配偶者は相続権がありますか?
いいえ、内縁の配偶者には原則として法定相続権はありません。法律上の婚姻関係にある配偶者のみが法定相続人となります。
ただし、被相続人が遺言書で内縁の配偶者を受遺者に指定していれば、遺言に基づいて財産を取得することができます。
また、相続人がいない場合は「特別縁故者」として財産分与を請求することも可能です。さらに、共有名義の財産や、内縁の配偶者が支払いに貢献した財産がある場合は、その持分を主張できる可能性もあります。
相続人が未成年者の場合はどうすればよいですか?
未成年者も相続人になることができますが、単独で相続に関する法律行為を行うことはできません。親権者(通常は親)が法定代理人として手続きを行います。
ただし、「親も同じ相続に関わっている場合」には利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。例えば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となる場合が該当します。
特別代理人は、未成年者の利益を守る立場から遺産分割協議に参加し、未成年者にとって不利にならないよう配慮します。この手続きは、未成年者の法的権利を守るために必要不可欠です。
胎児は相続人になれますか?
はい、相続開始時に胎児だった子どもは、生きて生まれた場合に限り相続人となります。民法上、胎児は「既に生まれたものとみなして」取り扱われます。
ただし、この規定は胎児が無事に生まれた場合に限られ、流産や死産、人工中絶の場合には相続権は発生しません。
相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議は胎児の出生を待って行うか、胎児の取り分を留保した上で暫定的に行うことになります。出生前に胎児のために特別代理人を選任する必要があります。
行方不明の相続人がいる場合はどうすればよいですか?
相続人の中に行方不明者がいる場合、まずは戸籍の附票や住民票から最後の住所を調べ、手紙を送るなど連絡を試みることが大切です。
それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
また、行方不明者の生死が長期間不明な場合は「失踪宣告」の申立てを行うことも検討できます。失踪宣告が認められると、その行方不明者は法律上死亡したとみなされ、相続が開始します。普通失踪(7年間の生死不明)と特別失踪(危難に遭遇してから1年経過)の2種類があります。
相続放棄の期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
相続放棄は原則として「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります。この期間を過ぎても、正当な理由があれば家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
「正当な理由」として認められやすいのは、以下のようなケースです。
- 相続財産に多額の借金があることを知ったのが3ヶ月経過後だった
- 相続人であることを知ったのが3ヶ月経過後だった
- 災害や入院など、やむを得ない事情があった
ただし、伸長が認められるかどうかは裁判所の判断によります。期限を過ぎた相続放棄については、早急に司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
養子縁組していない配偶者の連れ子は相続人になれますか?
いいえ、養子縁組をしていない配偶者の連れ子(継子)は法定相続人にはなれません。法定相続人は血縁関係または法律上の親子関係(養子縁組)がある場合に限られます。
継子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言書で財産を遺贈するなどの対応が必要です。養子縁組をすれば、法律上の親子関係が発生するため法定相続人となります。
なお、被相続人の生前に継子が特別な貢献をしていた場合、2019年の民法改正で創設された「特別寄与制度」を利用できる可能性もあります。
まとめ
相続は、法律に基づいて進める必要がある複雑な手続きです。本記事では、法定相続人の範囲や相続順位、相続権を失うケース、特殊な相続のケースなど、相続に関する重要事項を解説してきました。
法定相続人になるのは、配偶者と一定の血族(子ども、親、兄弟姉妹など)に限られており、その範囲や相続順位は民法で明確に定められています。また、相続割合も相続人の組み合わせによって法律で規定されています。
相続権は相続欠格や相続廃除、相続放棄によって失われることがあります。また、代襲相続や養子・胎児・未成年者の相続、行方不明者が関わる相続など、特殊なケースについても理解しておくことが重要です。
相続手続きを進めるためには、まず遺言書の有無を確認し、戸籍謄本等による相続人調査を丁寧に行うことが必要です。相続人がいない場合は、相続財産管理人の選任や特別縁故者への分与、最終的には国庫帰属という流れになります。
相続は家族関係や財産状況によって一つひとつのケースが異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。特に、遺言書の解釈や相続人の特定、遺産分割協議など、法律的な判断が必要な場面では司法書士などの専門家のサポートが役立ちます。
相続に関する疑問や不安は、早い段階で解消しておくことが重要です。相続トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現するためにも、法定相続人の範囲や権利について正しく理解しておきましょう。
日本リーガル司法書士事務所では、相続に関する無料相談を承っております。遺言書の作成や相続手続き、遺産分割協議など、相続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。経験豊富な司法書士が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。