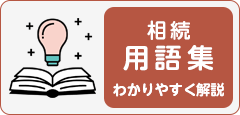相続財産調査とは?調査手順・注意点・専門家の選び方を解説
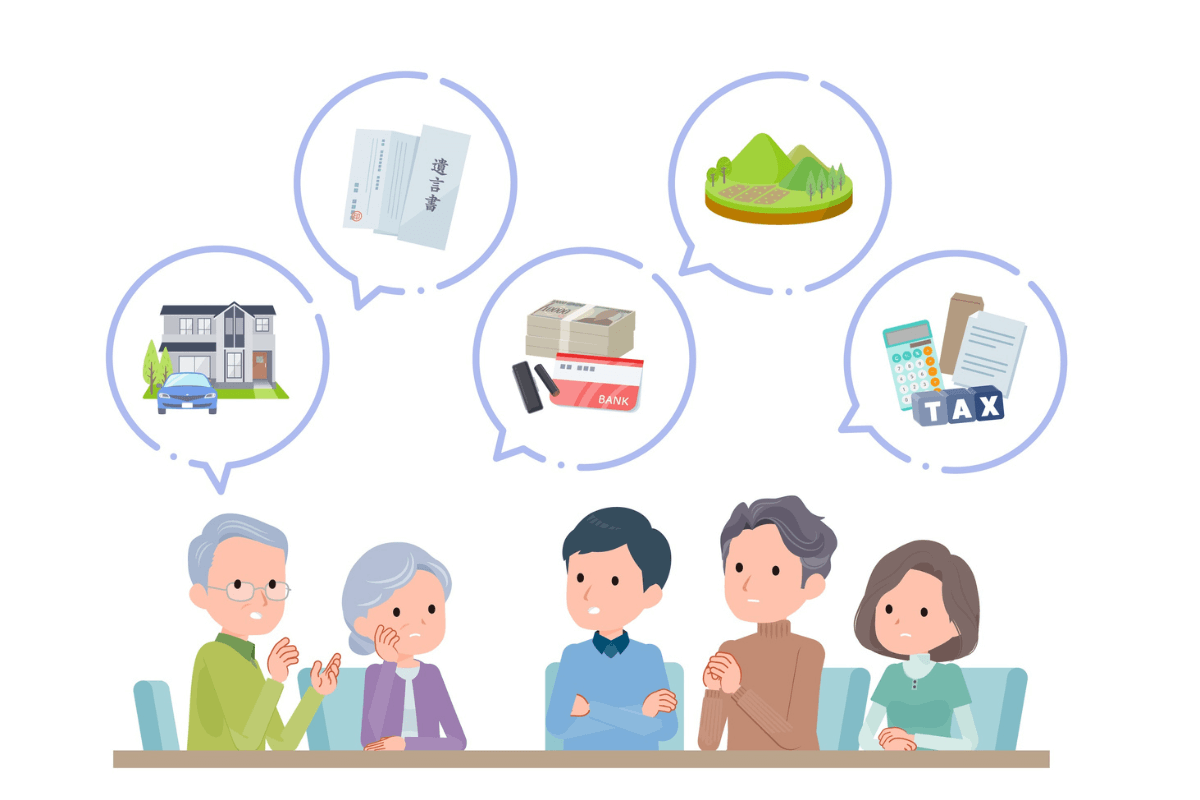
親族が亡くなったとき、相続の手続きに直面することになりますが、相続財産の調査を怠ると、大きな損失を招くことがあります。
例えば、借金などのマイナス財産が後から判明したり、相続税の申告漏れでペナルティを受けたりするリスクがあるためです。
本記事では、相続財産調査の具体的な手順や注意点、そして負担を減らすための専門家の選び方について詳しく解説します。
■もくじ
相続財産調査とは?必要な理由と基本知識
相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)が残したすべての財産を調べる手続きです。財産には、現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い税金などのマイナスの財産も含まれます。
相続人は、これらの財産の内容を把握したうえで、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択する必要があります。正確に調査を行わないと、借金を相続してしまうリスクや、相続税の申告漏れにより税務署からのペナルティを受ける危険があります。
なぜ相続財産調査が必要なのか
相続財産を正しく把握することは、以下の理由から非常に重要です。
- 相続放棄や限定承認の判断材料になる
- 遺産分割協議を円滑に進めることができる
- 調査不足による相続人間のトラブル防止
- 相続税の正確な申告を行うため
特に遺言がない場合や、相続人が複数いる場合は、相続財産を正確に把握しなければ、協議後に新たな財産が判明して遺産分割協議をやり直す事態に陥ることもあります。
相続財産調査の期限
相続財産の調査には期限があります。相続放棄や限定承認を選ぶ場合は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。これを「熟慮期間」と呼びます。
また、相続税の申告が必要な場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税を行う必要があります。この期限内に正確な財産調査を完了させることが重要です。
期限を過ぎると、単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
相続財産調査の具体的な手順
相続財産の調査は、漠然と始めると時間と手間がかかりすぎてしまうことがあります。スムーズに進めるためには、効率的な手順を知っておくことが大切です。
1. 被相続人の遺品を確認する
まずは、被相続人の自宅や貸金庫にある重要書類を探しましょう。具体的には、以下のような書類が財産調査に役立ちます。
- 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
- 固定資産税の納付書、不動産の登記済証・登記事項証明書
- 株式や証券の取引報告書、保険証券
- 借入金の契約書、ローンの請求書
これらの情報から、どの機関に問い合わせるべきかの目安を立てることができます。
2. 金融機関や役所などへの問い合わせ
次に、判明した金融機関や不動産の所在自治体などに、具体的な財産の内容を確認していきます。主に以下のような問い合わせを行います。
- 金融機関への残高証明書の取得
- 不動産所在地の役所から固定資産評価証明書を取得
- 証券会社から株式や国債の保有状況を確認
- 保険会社から保険金受取の確認
これらの手続きには、被相続人の戸籍謄本や死亡届、相続人の身分証明書が必要です。事前に問い合わせ先に必要書類を確認しておきましょう。
3. 負債・債務の確認
財産調査では、プラスの財産だけでなく、借金などの負債も調査する必要があります。借入先の情報は、自宅に残された請求書やローン契約書から確認します。
また、信用情報機関に照会することで、金融機関との取引履歴が把握できます。代表的な信用情報機関は次の通りです。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
それぞれの機関に郵送で開示請求することで、被相続人の借入状況を確認することが可能です。
4. 調査結果の整理と評価
集めた情報をもとに、相続財産を一覧にまとめます。評価額を確定し、相続税申告の要否を判断します。
この段階で、単純承認・相続放棄・限定承認の選択を最終決定します。疑問点があれば、専門家に相談することをおすすめします。
財産の種類ごとの調査ポイント
相続財産には多くの種類があり、それぞれ調査方法が異なります。抜け漏れなく調査を行うために、財産の種類ごとのポイントを理解しておくことが大切です。
金融機関の預貯金
被相続人が利用していた金融機関を特定するには、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物を確認します。
利用先がわかったら、残高証明書を金融機関に依頼します。依頼には、被相続人の戸籍謄本、相続人の身分証明書などが必要です。
また、通帳がある場合は記帳を行い、引き落とし記録から貸金庫の有無や他の財産の手掛かりを探ります。
有価証券・ネット証券
証券会社からの取引報告書や株主総会通知を確認します。最近では、ネット証券も多く、書類が郵送されていない場合もあります。被相続人のメールやPC履歴を確認するのも一つの手段です。
仮想通貨やゴルフ会員権、保険積立金なども相続対象になるため、幅広く調査が必要です。
不動産
不動産の調査は、固定資産税の納付書や課税明細書から所有状況を確認します。納付書が無い場合は、市町村役場で固定資産評価証明書を取得します。
被相続人名義の登記事項証明書を法務局で確認することも重要です。これにより、共有不動産の把握も可能になります。
貴金属・自動車・美術品
貴金属は、現物や貸金庫にある可能性があります。自動車は車検証を、不動産の登記簿謄本と同様に確認が必要です。
また、美術品や骨董品はリスト化し、専門業者による鑑定評価を依頼すると良いでしょう。
借金・保証債務
借金については、ローン契約書や請求書を確認します。不明な場合は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)への開示請求を行います。
保証債務は地道な調査が必要です。被相続人の交友関係やビジネス関係を調べ、保証人となっていたか確認しましょう。
信用情報の調査方法と注意点
被相続人に借金があったかどうかを確実に確認するためには、信用情報機関への照会が有効です。金融機関との取引履歴を把握することで、思わぬ負債を見落とすリスクを避けることができます。
信用情報機関とは?
信用情報機関は、個人の借入やクレジットカードの利用履歴などを管理する団体です。日本には以下の3つの主要な信用情報機関があります。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
これらの機関に開示請求を行うことで、被相続人がどの金融機関で借入をしていたか、またはクレジットカードを利用していたかが分かります。
信用情報の開示請求の方法
信用情報の開示請求は郵送で手続きが可能です。それぞれの機関の公式ウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、被相続人の戸籍謄本、死亡の事実を証明する書類、申請者の身分証明書を添付して送付します。
開示には数百円程度の手数料がかかり、開示結果はおおむね1~2週間で届きます。
注意点:個人間の借金は調査できない
信用情報機関には、個人間の貸し借りや、非金融機関からの借入についての情報は登録されていません。これらは、被相続人の書類や関係者への聞き取りで確認するしか方法がありません。
そのため、被相続人の自宅にある書類は、不用意に廃棄せず、一通り目を通してから判断することが大切です。
また、被相続人が保証人となっていた可能性がある場合も、契約書や関係先への問い合わせが必要となります。
相続財産調査は専門家に依頼するべきか?
相続財産の調査は、時間と労力を要する複雑な作業です。相続人自身で進めることも可能ですが、不備や漏れがあると、後々大きなトラブルに発展する恐れがあります。そのため、専門家への依頼も検討するべきです。
専門家に依頼するメリット
- 調査の漏れやミスを防げる
- 手続きがスムーズに進む
- 法律や税金の専門的なアドバイスが受けられる
- 相続税申告や登記も一括対応が可能
特に相続財産が多い場合や、相続人間で紛争が予想される場合は、専門家に依頼することで精神的負担も軽減できます。
専門家の種類と選び方
相続財産調査に対応できる専門家は複数いますが、それぞれ得意分野が異なります。
| 司法書士 |
|
|---|---|
| 弁護士 |
|
| 税理士 |
|
状況に応じて、適切な専門家を選びましょう。例えば、不動産の名義変更が必要な場合は司法書士に、税金の対応が必要なら税理士に、トラブルが起こりそうな場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。
専門家に依頼した場合の費用相場
専門家への依頼費用は、業務内容や地域によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
- 司法書士:20万円~50万円程度
- 弁護士:30万円~100万円以上(内容による)
- 税理士:20万円~100万円(財産の規模による)
複数の専門家に依頼する場合でも、提携関係があることが多く、スムーズに紹介してもらえるケースもあります。まずは、お気軽に日本リーガル司法書士事務所の無料相談をご利用ください。
まとめ|相続財産調査を正確に進めるために
相続財産調査は、相続手続きを進めるうえで最も重要な第一歩です。調査を怠ると、借金の相続や申告漏れといった大きなリスクを背負うことになります。
被相続人が残した財産を漏れなく確認し、正確に評価することで、相続人間のトラブルを防ぎ、円満な遺産分割を実現することができます。
相続財産の調査は、期限内に進めなければならず、非常に煩雑です。専門家の力を借りることで、時間と労力を大幅に節約し、安心して相続を進めることができます。
相続でお悩みの方は、ぜひ日本リーガル司法書士事務所の無料相談をご利用ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。