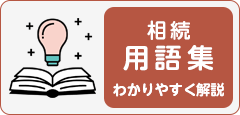親が住んでいたマンションの相続手続きは?名義変更・評価額・注意点まで徹底解説

親からマンションを相続したけれど、何から手を付ければ良いのか分からないとお悩みではありませんか?
マンション相続は、名義変更や税金の申告など、複雑な手続きを適切に進める必要があります。さらに2024年4月からは、相続登記の義務化が始まり、放置していると罰則の対象になるリスクもあります。
本記事では、相続したマンションに関する手続きの流れや必要書類、費用、そして注意点まで詳しく解説します。正しい知識を持って、スムーズな相続を進めるための参考にしてください。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記やマンションのご相談を無料で承っております。お困りの際はぜひご相談ください。
■もくじ
マンションを相続したら最初にすべきこと
マンションを相続した場合、すぐに手続きを開始する必要があります。まずは相続人としてどのような行動を取るべきかを明確にしておくことが重要です。
1. 遺言書の有無を確認する
相続の第一歩は、被相続人が遺言書を残していないか確認することです。遺言書がある場合、そこに記載された内容が優先され、誰がマンションを相続するかが決まります。
遺言書には以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言:本人が自筆で作成し、自宅などで保管。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が関与して作成。
- 法務局保管遺言:自筆証書を法務局で保管。
遺言書を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを行いましょう(公正証書遺言は検認不要)。
2. 相続人の確認と相続財産の調査
次に、相続人が誰であるかを確認し、相続財産の内容を調査します。相続人の特定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。
相続財産の調査には、以下のような資料を確認します。
- 固定資産税の納税通知書
- 名寄帳(市区町村役場で取得可能)
- 登記事項証明書(法務局で取得)
マンションだけでなく、預貯金やその他の財産についても確認が必要です。
3. 放置せず早めに専門家へ相談を
マンションの相続は、名義変更や税金の申告が伴い、複雑な手続きになることがあります。手続きを放置すると、固定資産税や管理費の支払い義務が生じたり、罰則の対象になる可能性もあります。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記や財産調査の無料相談を承っています。お早めにご相談いただくことで、安心して相続手続きを進めることができます。
マンションを相続したら、まずは遺言書の確認と財産の調査を行い、手続きを円滑に進めるために専門家の力を借りましょう。
マンション相続の手続きの流れと相続登記の義務化
マンションを相続した場合、法律で定められた手順に従って、名義変更などの手続きを進める必要があります。
2024年4月からは、相続登記が義務化され、手続きを怠ると罰則が科されるようになりました。
1. マンション相続の基本的な手続きの流れ
マンションの相続手続きは、以下のような流れで進めます。
- 遺言書の確認
- 相続人の特定と相続財産の調査
- 遺産分割協議の実施と協議書の作成
- 相続税の申告・納付
- 相続登記(名義変更)の申請
それぞれのステップで、必要な書類や注意点がありますので、慎重に進めましょう。
2. 相続登記の義務化とは?
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
これにより、相続人は次の条件のいずれかを満たした場合、3年以内に相続登記を行う必要があります。
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内
- 遺産分割協議が成立した日から3年以内
期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
3. 義務化の背景と注意点
これまで相続登記は任意でしたが、放置されたままの不動産が増加し、所有者不明土地問題が深刻化していました。
そのため、相続登記の義務化によって、不動産の適正な管理と流通の促進が目指されています。
相続したマンションを放置せず、速やかに相続登記を行いましょう。登記を済ませることで、売却や賃貸などの活用もスムーズに行えます。
4. 相続人申告登記の活用
相続登記義務化に伴い、新たに「相続人申告登記」という制度も開始されました。
この制度を活用すると、相続人である旨を登記簿に記載するだけで、罰則を一時的に回避することができます。
相続人申告登記は、登記の準備に時間がかかる場合や、遺産分割が未確定な場合に便利です。
注意点として、相続人申告登記だけでは、マンションを売却したり担保にしたりすることはできません。正式な相続登記を必ず行う必要があります。
相続登記に必要な書類とその取得方法
マンションの名義変更(相続登記)を行うためには、多くの書類が必要になります。書類の準備には時間がかかるため、早めに対応することが大切です。
1. 市区町村役場で取得する書類
相続登記に必要な書類のうち、市区町村役場で取得するものは以下の通りです。
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、相続人を特定します。 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印した実印の証明書。相続人全員分が必要です。 |
| 住民票の除票・戸籍の附票 | 被相続人の最終住所を確認するために必要です。 |
| 固定資産評価証明書 | 登記申請時に必要な登録免許税の計算に使用します。 |
2. 自分で作成する書類
次に、自分で作成する書類は以下の通りです。
- 登記申請書:法務局に提出する名義変更申請のための書類。
- 遺産分割協議書:相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を記載した書面。
- 相続関係説明図:相続人の関係性を図にまとめたもの。簡易な家系図です。
これらの書類は、記載ミスがあると再提出を求められることがあります。正確に作成することが大切です。
3. 遺言書の種類により異なる書類
相続登記の際に必要な書類は、相続の方法によって異なります。
| 遺言書による相続登記 |
|
|---|---|
| 遺産分割協議による相続登記 |
|
| 法定相続による登記 |
|
4. 書類の取得期限と注意点
一部の書類には、有効期限があります。特に印鑑証明書は、発行から3カ月以内のものが必要となりますので、取得時期に注意しましょう。
また、書類の綴じ方や提出方法についても、法務局ごとに指定がある場合があります。事前に確認し、不備がないようにしましょう。
不安がある場合は、日本リーガル司法書士事務所の無料相談をご利用ください。
マンション相続にかかる費用と税金
マンションを相続する際には、登記手続きや税金など、さまざまな費用が発生します。事前にどのような費用がかかるのかを把握しておくことで、スムーズに準備を進めることができます。
1. 登記手続きにかかる費用
相続登記には主に以下の費用がかかります。
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1通数百円で、全て揃えても5,000円~10,000円程度が目安です。 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4%(1000分の4) 土地が100万円以下の場合、土地部分は非課税。 |
| 司法書士報酬 | 依頼内容によって異なりますが、5万円~10万円前後が相場です。 |
登録免許税は、マンションの建物部分と敷地権部分の合計評価額に基づいて計算します。敷地権割合に注意して、正確に算出しましょう。
2. 相続税の概要と計算方法
相続税は、基礎控除額を超える財産を相続した場合に発生します。
基礎控除額の計算式は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
相続財産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の申告期限
被相続人が亡くなった日から10カ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。
申告期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生するため注意が必要です。
3. 小規模宅地等の特例で相続税を軽減
被相続人が住んでいたマンションを相続した場合、小規模宅地等の特例を適用することで、相続税評価額を最大80%軽減することが可能です。
この特例を適用するためには、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細は専門家にご相談ください。
4. 延納・物納の活用
相続税の支払いが困難な場合、延納や物納を利用することも可能です。
- 延納:相続税を分割して支払う方法。
- 物納:現金での納付が難しい場合、不動産などで納付。
いずれも条件がありますので、事前に申請が必要です。
相続したマンションの活用方法を徹底比較
マンションを相続した後、「住む」「貸す」「売る」という3つの選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況に最適な活用方法を選びましょう。
1. 相続したマンションに「住む」選択肢
相続したマンションに自分自身や家族が住む選択は、故人の思い出が詰まった住まいを継続して利用できる方法です。特に、被相続人と同居していた場合や、立地条件が良い場合に検討する価値があります。
メリット
マンションに住むことには、以下のようなメリットがあります。
- 引っ越し費用や住み替えのための新たな住宅購入費が不要
- 住宅ローンがない場合、住居費の負担が軽減される
- 思い出の詰まった住まいで生活を続けられる
- 小規模宅地等の特例を活用すれば相続税の負担を軽減できる可能性がある
デメリット
一方で、マンションに住むことに伴うデメリットも考慮する必要があります。
- 自分がすでに別の住居を持っている場合、二重の住居費負担が生じる
- 立地や間取りが自分のライフスタイルに合わない可能性がある
- 築年数が古い場合、修繕や設備更新の費用がかかる
- 管理費や修繕積立金の負担が継続的に発生する
マンションに住む選択肢は、現在の住まいに不満がある場合や、相続したマンションの立地が良い場合に特に有効です。ただし、すでに自分の住まいを持っている場合は、住み替えに伴う様々な費用や手間も考慮しましょう。
2. 相続したマンションを「貸す」選択肢
相続したマンションを賃貸物件として活用すれば、資産を保持しながら家賃収入を得られるという大きなメリットがあります。特に将来的に自分や家族が住む可能性がある場合に検討する価値があります。
メリット
マンションを賃貸に出すことには、以下のようなメリットがあります。
- 定期的な家賃収入が得られる
- 資産としてマンションを保有し続けられる
- 人が住むことで空き家にならず、建物の劣化を防げる
- 将来的に自分が住むという選択肢も残せる
デメリット
一方で、賃貸経営には様々な手間やリスクも伴います。
- 賃貸に出すためのリフォーム費用が必要になる場合が多い
- 入居者とのトラブル対応や賃貸管理の手間がかかる
- 空室リスクがある(家賃収入が得られない期間が生じる可能性)
- 管理費・修繕積立金は自己負担となる
- 賃貸所得に対する確定申告や税金の納付が必要
賃貸に向いているマンションは、築年数が比較的浅いものや駅近などの人気エリアにある物件です。検討する場合は、近隣の賃貸相場や需要を調査し、リフォーム費用と家賃収入のバランスを考慮して判断しましょう。
| 賃貸管理の方法 | 賃貸管理会社に委託する場合、家賃の5~10%程度の管理手数料がかかりますが、入居者募集や家賃回収、トラブル対応などを任せられます。自主管理の場合、手数料は不要ですが、すべての対応を自分で行う必要があります。 |
|---|---|
| 定期借家契約の活用 | 将来的に自分が住む可能性がある場合は、契約期間を定めた「定期借家契約」を検討しましょう。期間満了で契約が自動的に終了するため、計画的に活用できます。 |
3. 相続したマンションを「売る」選択肢
相続したマンションを売却すれば、まとまった現金を得られるだけでなく、維持管理の手間や費用から解放されます。特に複数の相続人がいる場合や、マンションを活用する予定がない場合に適した選択肢です。
メリット
マンションを売却することには、以下のようなメリットがあります。
- まとまった現金化ができ、相続税の納付資金に充てられる
- 複数の相続人がいる場合、現金分割で平等に分けられる
- 管理費・修繕積立金などの維持費の負担がなくなる
- 将来的な建物の老朽化リスクを回避できる
デメリット
一方で、売却にもいくつかのデメリットがあります。
- 不動産という資産を手放すことになる
- 思い出の詰まった住まいを手放す心理的な負担がある
- 売却益に対して譲渡所得税が課される可能性がある
- 不動産市況によっては希望価格で売却できないこともある
売却を検討する場合は、築年数や立地条件によって市場価値が大きく変わることを理解しておきましょう。また、「3,000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」など、相続不動産の売却時に利用できる税制優遇措置も確認することが重要です。
4. 各選択肢の判断基準
マンションの活用方法を決める際は、以下のポイントを総合的に考慮して判断しましょう。
| マンションの状態 | 築年数、間取り、立地条件、設備の状態などが活用方法に大きく影響します。築浅で立地が良ければ賃貸や売却に適していますが、築古のマンションは売却を優先的に検討した方が良い場合もあります。 |
|---|---|
| 相続人の状況 | 複数の相続人がいる場合、公平性を考慮して売却して現金分割するケースが多いです。単独相続の場合は、自分のライフプランに合わせて選択できます。 |
| 将来の見通し | 将来的に自分や家族が住む可能性がある場合は、一時的に賃貸にするという選択肢も検討価値があります。その見込みがない場合は売却を検討しましょう。 |
| 資金ニーズ | 相続税の納付資金が必要な場合や、まとまった資金が欲しい場合は売却が適しています。安定収入を望む場合は賃貸が検討できます。 |
どの選択肢を選ぶにしても、まずは相続登記を完了させることが前提となります。相続登記が完了していなければ、売却も賃貸もできないため、必ず先に手続きを進めておきましょう。
また、複数の不動産会社に相談して、マンションの価値や市場動向について専門家の意見を聞くことも大切です。日本リーガル司法書士事務所では、相続したマンションの活用方法についてもアドバイスを行っていますので、お気軽にご相談ください。
相続したマンションの維持管理と発生する費用
マンションを相続して保有し続ける場合、様々な維持管理費用が発生します。賃貸に出す場合も自分が住む場合も、これらの費用を理解して適切に管理することが大切です。
1. マンション所有に伴う定期的な費用
マンションを所有していると、以下のような定期的な費用が発生します。これらは売却しない限り、継続的に負担しなければなりません。
| 管理費 | 共用部分の清掃や照明、エレベーターなどの設備維持費用として、毎月支払う必要があります。マンションの規模や築年数によって異なりますが、一般的に3LDKで月額1万円前後が相場です。 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 大規模修繕のための積立金として、毎月徴収されます。築年数が経過するほど金額が上がる傾向があり、築20年以上のマンションでは月額1~2万円程度かかることもあります。 |
| 固定資産税・都市計画税 | マンションの評価額に基づいて毎年課税される税金です。マンションの資産価値にもよりますが、年間10~30万円程度が目安となります。 |
| 火災保険料 | 建物の火災保険は、管理組合で一括加入している場合もありますが、専有部分については個別に加入する必要があります。年間1~3万円程度が相場です。 |
これらの費用は、マンションを所有している限り継続的に発生します。賃貸に出している場合でも、管理費や修繕積立金、固定資産税などはオーナー負担となりますので注意が必要です。
2. 突発的に発生する修繕・更新費用
マンションの所有期間中には、突発的な修繕費用や設備の更新費用も発生する可能性があります。特に築年数が古いマンションほど、これらの費用が高額になる傾向があります。
- 専有部分の水回り設備の修理・交換費用
- エアコンや給湯器などの設備更新費用
- 内装のリフォーム費用(賃貸に出す場合や自分が住む場合)
- 特別修繕積立金(大規模修繕時に一時的に徴収されることがある)
例えば、築20年以上のマンションでは、水回りの全面リフォームに100~200万円程度、内装のリフォームに100万円前後の費用がかかることもあります。これらの費用は、マンションの状態や築年数によって大きく異なります。
3. 賃貸に出す場合の追加費用
相続したマンションを賃貸に出す場合は、さらに以下のような費用が発生します。
| 初期リフォーム費用 | 賃貸に出すためには、クリーニングや壁紙の張替え、水回りの修繕などが必要になることが多く、50~100万円程度の初期投資が必要になるケースがあります。 |
|---|---|
| 賃貸管理手数料 | 賃貸管理会社に委託する場合、家賃の5~10%程度の管理手数料がかかります。入居者募集時には、家賃の0.5~1ヶ月分の仲介手数料も発生します。 |
| 空室リスクに伴う費用 | 入居者が見つからない期間は収入がなくても、管理費や修繕積立金などの固定費は支払い続ける必要があります。 |
賃貸経営を検討する際は、これらの費用も含めた収支計画を立てることが重要です。家賃収入だけを見るのではなく、諸経費を差し引いた実質的な収益を計算しましょう。
4. 老朽化マンションの維持管理リスク
築30年以上の古いマンションを相続した場合、維持管理に関する様々なリスクが高まります。
- 大規模修繕費用の増加(30年以上経過すると躯体の補修も必要になることがある)
- 設備の老朽化による突発的な修繕費用の増加
- 空室率の上昇(古いマンションほど入居者が見つかりにくくなる)
- 管理組合の機能低下(高齢化や空き家増加による)
このような老朽化マンションの場合、将来的な資産価値の低下も考慮して、早めに売却するという選択肢も検討する価値があります。
5. 経済的負担を軽減するための対策
マンション維持の経済的負担を軽減するためには、以下のような対策が考えられます。
- 賃貸に出して家賃収入を得る(維持費を家賃でカバー)
- 固定資産税の軽減措置の確認(自分が住む場合、住宅用地の特例が適用される)
- リフォーム時の省エネ設備導入で光熱費を抑制(自分が住む場合)
- 修繕積立金の値上げ予定などを管理組合に確認し、将来の負担増に備える
特に複数のマンションを相続した場合や、自宅とは別にマンションを相続した場合は、維持コストの総額を考慮して、一部を売却するという選択肢も検討しましょう。
マンションの維持管理には様々な費用がかかりますが、適切に管理すれば資産価値を保ちながら活用することができます。日本リーガル司法書士事務所では、相続したマンションの維持管理や活用方法についても無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
マンション相続で陥りやすいトラブルと解決法
マンション相続に関するトラブルは少なくありません。事前に知識を持っておくことで、多くのトラブルを回避することが可能です。ここでは、よくあるトラブル事例とその解決方法について解説します。
1. 相続人間でのマンションの共有名義問題
相続人が複数いる場合、マンションを共有名義のままにすることがありますが、これは将来的に様々なトラブルを引き起こす原因になります。
発生するトラブル
- 売却や賃貸に出す際に、全員の同意が必要となり、一人でも反対すると実行できない
- 管理費の支払いや修繕の判断について、相続人間で意見が分かれる
- 住宅ローンを組むなど担保に入れることが難しくなる
- さらに次の相続が発生すると、権利関係がより複雑になる
解決方法
共有名義によるトラブルを避けるためには、以下の方法が効果的です。
- 遺産分割協議で誰か一人が単独所有する方法を選ぶ(代償分割)
- マンションを売却して現金化し分配する(換価分割)
- 共有持分を買い取りして単独所有に移行する
- 共有者間で管理や費用負担に関する取り決めを書面で作成しておく
特に複数の相続人でマンションを共有する場合は、将来的な売却や管理についての合意書を作成しておくことが重要です。専門家のサポートを受けながら、具体的な取り決めを行いましょう。
2. 相続登記を放置するリスク
2024年4月からの義務化により、相続登記を放置することのリスクが一層高まっています。
発生するトラブル
- 10万円以下の過料が科される可能性がある(相続登記義務化に伴う罰則)
- マンションの売却や賃貸ができなくなる
- ローンの組み直しや住宅ローン控除の申請ができなくなる
- 相続人が増えるごとに手続きが複雑化し、費用も増加する
解決方法
相続登記の問題を解決するには、次の対応が重要です。
- 相続を知った日から3年以内に必ず相続登記を行う
- すぐに遺産分割協議が整わない場合は、相続人申告登記を活用する
- 複雑なケースでは、司法書士に依頼して確実に手続きを進める
相続登記義務化は2024年4月から始まったばかりの制度ですが、今後は厳格に運用されることが予想されます。早めの対応を心がけましょう。
3. 相続したマンションのローン問題
相続したマンションに住宅ローンが残っている場合、その扱いが問題になることがあります。
発生するトラブル
- ローンの返済義務も相続することになり、経済的負担が生じる
- 返済が困難な場合に相続放棄するかの判断を迫られる
- 団体信用生命保険に加入していたか不明で、手続きが進まない
解決方法
マンションのローン問題に対しては、以下の対応が有効です。
- まず団体信用生命保険の有無を確認する(加入していれば、ローンは保険で完済される)
- ローンが残っている場合は、借り換えや売却による完済を検討
- 返済が難しく、他に相続したい財産がない場合は、相続放棄も選択肢に
- 金融機関と早めに相談し、返済計画の見直しを行う
なお、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなるため、注意が必要です。
4. 管理組合との関係のトラブル
マンションを相続した後、管理組合との関係でトラブルが生じることもあります。
発生するトラブル
- 管理費や修繕積立金の滞納が発生している場合の清算問題
- 相続の連絡を怠ったことによる管理組合とのコミュニケーション不足
- 総会議決権の行使者が不明確になる問題
- 管理規約の内容を知らないことによる違反
解決方法
管理組合との関係を良好に保つためには、次のような対応が重要です。
- 相続後、速やかに管理組合への届出を行う
- 滞納がある場合は、早めに清算計画を相談する
- 管理規約や細則を入手して確認し、理解しておく
- 共有名義の場合は、議決権行使者を明確に届け出る
管理組合とのトラブルは、マンションの住環境や資産価値にも影響します。特に、滞納金があると売却時にも問題になるため、早期に解決することが大切です。
5. 相続したマンションの状態に関するトラブル
特に遠方に住んでいた親のマンションを相続した場合、物件の状態に関するトラブルが発生することがあります。
発生するトラブル
- 想定以上の設備の老朽化や不具合の発見
- 被相続人の生前の使用による室内の汚損や破損
- 想定外の修繕費用の発生
- 近隣とのトラブルの存在
解決方法
マンションの状態に関するトラブルを解決するには、以下の対応が効果的です。
- 相続後、早めに現地確認と状態調査を行う
- 必要に応じてホームインスペクション(住宅診断)を依頼する
- 管理会社や管理組合に修繕履歴やトラブル履歴を確認する
- 売却や賃貸に出す前に、必要な修繕やリフォームの検討を行う
特に築年数が古いマンションでは、想定外の不具合が見つかることも少なくありません。早めに状態を把握し、必要な対策を講じることが重要です。
マンション相続に関するトラブルは、事前の知識と適切な専門家への相談で多くが回避できます。日本リーガル司法書士事務所では、マンション相続に関する様々なトラブルについても無料相談を承っていますので、お困りの際はぜひご相談ください。
マンション相続に関するよくある質問
マンションを相続する際には、手続きの進め方や費用について疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。ここでは、特に多く寄せられる質問にお答えします。
Q. 相続したマンションの名義変更は自分でできますか?
相続登記は、自分で必要書類を揃え、法務局に申請すれば自力で行うことが可能です。しかし、書類に不備があると受理されないため、注意が必要です。
以下のような場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
- 急いで売却したい
- 相続人間での関係が良くない
- 書類作成に不安がある
司法書士に依頼すれば、確実かつスムーズに手続きを進めることができます。
Q. マンションだけを相続放棄することはできますか?
相続放棄は、すべての財産を放棄する手続きであり、マンションだけを選んで放棄することはできません。
マンションを相続したくない場合は、遺産分割協議で他の相続人に引き取ってもらい、その代わりに他の財産を相続する方法を取ります。
どうしても相続全体を放棄したい場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。
Q. 共有名義のマンションはどうすれば良いですか?
相続人が複数いて、マンションを共有名義で相続するケースもあります。共有名義のままでは、売却や賃貸などを行う際に、全員の同意が必要になります。
トラブルを避けるためにも、できる限り単独名義に変更するか、売却して現金化し、分配する方法を検討しましょう。
Q. マンション相続の手続きに期限はありますか?
相続登記は、2024年4月から義務化され、3年以内に手続きを行わないと過料が科される可能性があります。また、相続税の申告期限は10カ月以内です。
期限を過ぎると、延滞税やペナルティが発生するため、早めの対応が必要です。
日本リーガル司法書士事務所では、期限内に確実に手続きを進めるためのご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
まとめ
マンションの相続には、名義変更や税金の申告など、複雑で重要な手続きが伴います。2024年4月からは相続登記が義務化され、放置すれば罰則の対象になるリスクもあります。
また、マンションの維持管理費や税金の負担、共有名義によるトラブルなど、相続後の課題も多く存在します。
相続したマンションを有効に活用し、スムーズに手続きを進めるためには、専門家のサポートが重要です。
日本リーガル司法書士事務所では、相続登記に精通した司法書士が、あなたの相続を安心して進められるよう丁寧にサポートいたします。
相続でお悩みの方は、日本リーガル司法書士事務所の無料相談をぜひご利用ください。正確で迅速な対応で、あなたの相続問題を解決へ導きます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。