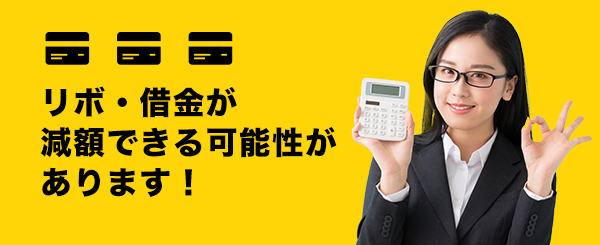借金の取り立てにお悩みの方へ!債務整理で即日ストップする方法と流れを解説
本記事はプロモーションを含みます
「毎日の借金の取り立て電話に精神的に追い詰められている」「家族や職場に取り立てが来ないか不安で夜も眠れない」といった悩みを抱えていませんか?
借金の取り立ては、債務整理を弁護士や司法書士に依頼することで最短即日〜2週間程度でストップさせることができます。これは、専門家が発行する「受任通知」が債権者に届くと、法律によって取り立てが禁止されるためです。
しかし、ただ債務整理をすれば良いというわけではなく、債務整理の種類や依頼の仕方によって取り立てが止まるタイミングは異なります。また、受任通知を送ったにもかかわらず取り立てが止まらないケースもあるのです。
本記事では、債務整理による取り立てストップの仕組み、取り立てが止まるタイミング、取り立てへの正しい対処法など、借金問題でお悩みの方に役立つ情報を詳しく解説します。借金の取り立てから解放されて新しい生活を始めるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
■もくじ
債務整理すると借金の取り立ては本当に止まる?
「債務整理をすれば本当に取り立てが止まるの?」と不安に思っている方は多いでしょう。結論から言うと、債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、最短即日〜2週間程度で借金の取り立ては法的に止まります。
これは、弁護士や司法書士などの専門家が債権者(お金を貸した側)に「受任通知」を送ることで、法律上、債権者からの取り立て行為が禁止されるためです。専門家に依頼後、通常は数日以内に受任通知が発送され、債権者に届くと取り立ては止まります。
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が受任通知を無視して取り立てを続けることは「貸金業法」違反となり、罰則の対象になります。また、銀行や信用金庫は法律上の強制力はありませんが、実務上は受任通知を尊重して取り立てを止めるのが一般的です。
ただし、債務整理の方法や依頼先によって取り立てが止まるまでの期間や効果には違いがあります。また、すべてのケースで取り立てが必ず止まるわけではないことにも注意が必要です。
債務整理による取り立てストップの効果
債務整理による取り立てストップには、以下のような効果があります。
- 自宅や職場への電話による督促がなくなる
- 郵送やFAXによる督促状が届かなくなる
- 自宅や勤務先への訪問による取り立てがなくなる
- 返済も一時的に止めることができる
- 精神的な負担から解放される
特に大きな効果は「返済も一時的に止められる」ことです。取り立てが止まっている間、それまで返済に充てていたお金を生活再建のために使ったり、債務整理の費用に回したりすることができます。
しかし、ここで注意すべきは「一時的」という点です。債務整理の最終的な目的は借金問題を解決することであり、取り立てを永久に逃れるものではありません。債務整理の種類によっては、手続き後も返済を続ける必要があるケースもあります。
取り立てが止まらないケース
一方で、以下のようなケースでは債務整理をしても取り立てが止まらないことがあります。
- 個人間の借金の場合
- 闇金業者からの借金の場合
- 税金や公共料金などの公的債務の場合
- 自分で債務整理を行い、専門家に依頼していない場合
特に注意すべきは、税金の滞納による督促は債務整理では止められないという点です。税金は債務整理の対象外となる「非免責債権」であり、自己破産しても免除されません。税金の支払いが難しい場合は、各自治体の税務課や国税局に相談して分割払いなどの対応を検討する必要があります。
また、専門家に依頼せずに自分で債務整理を進める場合は、受任通知が送られないため、手続きが完了するまで取り立ては続きます。その間の精神的負担や追加の返済負担を考えると、専門家への依頼をおすすめします。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
債務整理による取り立てストップの仕組み
債務整理による取り立てストップの中心となるのが「受任通知」です。ここでは、受任通知とは何か、どのように取り立てを止める効力があるのか、その法的根拠について詳しく解説します。
受任通知とは何か
受任通知(じゅにんつうち)とは、債務整理を依頼された弁護士や司法書士が、金融機関や貸金業者などの債権者に対して「債務整理を代理人として進める」ことを知らせる通知書のことです。介入通知とも呼ばれます。
受任通知には主に以下のような内容が記載されています。
- 弁護士や司法書士が債務整理を受任した事実
- 債務整理の方法(任意整理、個人再生、自己破産など)
- 債務者への直接の取り立て停止要請
- 取引履歴の開示請求
- この通知が債務の承認に当たらない旨の記載
受任通知が債権者に届くと、それ以降は債務者(お金を借りた側)ではなく、依頼を受けた弁護士や司法書士を通じてやり取りすることになります。つまり、債権者は債務者に対して直接連絡することができなくなるのです。
受任通知による取り立てストップの法的根拠
受任通知による取り立てストップには、しっかりとした法的根拠があります。主に以下の法律によって規定されています。
貸金業法による規制
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は、「貸金業法第21条」によって規制されています。この法律では、債務者が弁護士や司法書士に債務の処理を委託し、その旨の通知(受任通知)があった場合、正当な理由なく債務者に対して電話、電報、FAX、訪問などの方法で債務の弁済を要求することを禁止しています。
つまり、受任通知到着後の取り立ては違法行為となり、行政処分や罰則の対象となる可能性があるのです。
サービサー法による規制
借金などの回収を専門に行う債権回収業者(サービサー)に対しても、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)第18条」で同様の規制が定められています。この法律でも、弁護士等からの通知があった場合、正当な理由なく債務者に対して訪問や電話での取り立てを禁止しています。
銀行や信用金庫などの金融機関の場合
銀行や信用金庫などの金融機関は、上記の法律による直接的な規制対象ではありません。しかし、実務上は受任通知を尊重して取り立てを停止するのが一般的です。
これは、債務整理を行うような状況の債務者からは、取り立てを続けても回収が見込めないことが多いためです。また、金融機関としての社会的信用や評判を考慮して、過度な取り立てを避ける傾向があります。
受任通知発送から取り立てストップまでの流れ
債務整理の依頼から取り立てがストップするまでの一般的な流れは以下のとおりです。
- 債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼する
- 弁護士や司法書士が債権者に受任通知を発送する(依頼当日〜数日以内)
- 債権者が受任通知を受け取る(発送から1〜3日程度)
- 受任通知到着後、債権者からの取り立てが法的に停止される
受任通知の発送から、最短即日〜2週間程度で取り立ては止まります。例えば、午前中に受任通知が発送され、債権者が午後に受け取った場合、その日のうちに取り立てが止まることもあります。
ただし、債権者内での確認作業に時間がかかる場合など、依頼から取り立てが止まるまで2週間程度かかることもあります。依頼から2週間以上たっても取り立てが止まらない場合は、依頼した弁護士や司法書士に相談しましょう。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
債務整理のタイプ別:取り立てが止まるタイミング
債務整理には大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。それぞれの手続きにおいて、取り立てが止まるタイミングが異なりますので、詳しく解説します。
また、弁護士や司法書士に依頼するか、自分で手続きを行うかによっても取り立てが止まる時期は大きく変わってきます。
専門家に依頼した場合と自分で行う場合の違い
まず、専門家に依頼するか自分で手続きを行うかによる違いを理解しておきましょう。
| 専門家に依頼した場合 | 受任通知の効力により、最短即日〜2週間程度で取り立てが止まる。依頼方法や専門家によって差がある。 |
|---|---|
| 自分で手続きを行う場合 | 受任通知が発送されないため、債務整理の手続きが開始または完了するまで取り立ては継続する。手続き完了までに数ヶ月〜1年以上かかる場合もある。 |
自分で債務整理を進める場合、受任通知が送られないため、債務整理手続きの完了まで取り立ては続きます。その間の精神的負担や追加の返済負担を考えると、専門家への依頼が推奨されます。
では、それぞれの債務整理方法について詳しく見ていきましょう。
任意整理の場合
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行い、将来利息のカットや元金の分割返済などの条件で和解する方法です。
専門家に依頼した場合
弁護士や司法書士に依頼した場合、受任通知が債権者に届いた時点(最短即日〜2週間程度)で取り立てが止まります。その後、和解が成立するまでの期間(通常3〜6ヶ月程度)は、原則として返済も止めることができます。
ただし、任意整理は債権者ごとに個別に行う手続きであるため、手続きをしていない債権者からの取り立ては止まりません。すべての債権者に対して取り立てを止めたい場合は、すべての債権者に対して受任通知を送る必要があります。
自分で行う場合
自分で任意整理を行う場合、債権者に返済計画の変更を申し出た時点で取り立てが止まることもありますが、これは債権者の対応次第です。法的強制力はなく、和解が成立するまで(3〜6ヶ月程度)取り立てが続く可能性が高いです。
また、自分で交渉を行う場合、債権者が交渉に応じない、または厳しい条件を提示してくるケースも少なくありません。
個人再生の場合
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りを3〜5年かけて返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま債務を整理できます。
専門家に依頼した場合
弁護士や司法書士に依頼した場合、受任通知により最短即日〜2週間程度で取り立てが止まります。その後、個人再生手続きの開始決定が出れば、法的に債権者からの取り立てが禁止されます。
また、個人再生の場合は全ての債権者に対して同時に効力が発生するため、一部の債権者だけに取り立てが続くということはありません。
自分で行う場合
自分で個人再生を申し立てる場合、裁判所が「再生手続開始決定」を出した時点で取り立てがストップします。申立てから開始決定までは通常3〜4ヶ月程度かかりますが、専門的な知識がない場合はそれ以上の時間を要する可能性があります。
個人再生は非常に複雑な手続きであり、専門的な法律知識が必要です。失敗すると再度申立てが必要になるため、自分で行うのはリスクが高いと言えるでしょう。
自己破産の場合
自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。資産がある場合は処分されますが、生活に必要最低限の財産は残すことができます。
専門家に依頼した場合
弁護士に依頼した場合、受任通知により最短即日〜2週間程度で取り立てが止まります。その後、破産手続開始決定が出れば、法的に債権者からの取り立てが禁止されます。
自己破産も個人再生と同様に、すべての債権者に対して同時に効力が発生するため、一部の債権者だけに取り立てが続くことはありません。
自分で行う場合
自分で自己破産を申し立てる場合、裁判所が「破産手続開始決定」を出した時点で取り立てがストップします。申立てから開始決定までは同時廃止事件で1〜2ヶ月程度、管財事件では3〜4ヶ月程度かかります。
ただし、自己破産も専門的な知識が必要な手続きです。自分で申し立てた場合、書類不備などで手続きが遅れたり、管財事件になる可能性が高くなったりするリスクがあります。
取り立てストップに関する3つの注意点
債務整理による取り立てストップについて、以下の3点に注意が必要です。
- 受任通知が届く前に債権者から連絡があった場合は、「弁護士(司法書士)に依頼したので、そちらにお問い合わせください」と伝えましょう。
- 取り立てが止まっても、債務そのものがなくなるわけではありません。債務整理の手続きを確実に進める必要があります。
- 債務整理に失敗すると、再び取り立てが始まる可能性があります。専門家のアドバイスに従い、計画的に手続きを進めましょう。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
受任通知到着後も取り立てが止まらないケース
受任通知は多くの場合、借金の取り立てを止める効果がありますが、すべてのケースで取り立てが必ず止まるわけではありません。ここでは、受任通知を送付しても取り立てが止まらない可能性があるケースと、その対処法について解説します。
個人間の借金の場合
友人、知人、親族などの個人から借りたお金については、受任通知の法的強制力が及びません。受任通知による取り立て禁止の法的効力は、貸金業法やサービサー法によって規制されている業者に対するものだからです。
個人間の借金の場合、債権者は法人ではなく個人であるため、以下のような理由から取り立てが続くことがあります。
- 感情的な要素が絡みやすい(「お金を返してもらえないのは納得できない」等)
- 法律の知識が不足している(受任通知の意味を理解していない)
- 貸金業法などの規制対象外であることを認識している
個人間の借金で取り立てが執拗に続く場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 依頼した弁護士・司法書士から直接、貸主に説明してもらう
- 取り立てが悪質な場合は、裁判所に「接近禁止命令」を申し立てる
- 警察に相談する(悪質な場合)
個人間の借金も債務整理の対象にはなりますが、取り立てへの対応は通常の金融機関などとは異なることを理解しておきましょう。
闇金業者からの借り入れの場合
闇金業者とは、貸金業者として登録せず、出資法の上限金利を超える金利で貸付けを行う違法な業者です。こうした業者は、そもそも法律を無視した営業を行っているため、受任通知を送付しても無視して取り立てを続けるケースが少なくありません。
闇金業者の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 法外な金利(年率20%を超える)で貸し付ける
- 貸金業登録番号を持っていない
- 契約書を交付しない、または不十分な契約書しか交付しない
- 違法な取り立て手段を用いる(脅迫、深夜の電話、職場への連絡など)
闇金業者からの借り入れがある場合、債務整理を依頼する弁護士や司法書士に必ず伝えておくことが重要です。専門家は適切な対応方法をアドバイスしてくれますし、必要に応じて警察と連携して対応することもあります。
具体的な対処法としては、以下のような方法があります。
- 弁護士・司法書士から闇金業者に対して「引き直し計算」の結果を通知する
- 返済義務がないことを通知する(出資法違反の場合、契約自体が無効になることがある)
- 警察に被害届を提出する
- 嫌がらせ行為があれば証拠(録音など)を残しておく
闇金業者との関わりは非常に危険です。借入れてしまった場合は、一人で解決しようとせず、必ず専門家に相談しましょう。
なお、貸金業者が正規の業者かどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。借入れ前に必ず確認することをおすすめします。
税金や公共料金などの公的債務の場合
税金や国民健康保険料、年金などの公的債務は、債務整理の対象外となります。そのため、受任通知を送付しても取り立てや督促は止まりません。
これらの公的債務は「非免責債権」と呼ばれ、自己破産をしても免除されない債務です。公的債務の滞納がある場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 各自治体の税務課や国税局の相談窓口に相談する
- 分割払いや納付猶予の申請を行う
- 生活困窮者自立支援制度などの公的支援を利用する
特に税金の滞納は、民間の借金よりも早いペースで差し押さえなどの強制執行に進む可能性があります。滞納が長期化する前に、早めに相談するようにしましょう。
受任通知が届く前の取り立てについて
受任通知が発送されても、債権者に届くまでの間(通常1〜3日程度)は取り立てが続くことがあります。この期間に債権者から連絡があった場合は、以下のように対応するとよいでしょう。
- 「弁護士(または司法書士)に債務整理を依頼した」と伝える
- 「詳しくは依頼した弁護士(または司法書士)に問い合わせてほしい」と伝える
- 弁護士(または司法書士)の名前と連絡先を伝える
- 返済に関する約束はしない
また、受任通知が届いているはずなのに取り立てが続く場合は、依頼した弁護士や司法書士に相談しましょう。専門家から債権者に対して再度連絡を取るなどの対応をしてもらえます。
最も重要なのは、取り立てに対して一人で対応しようとしないことです。債務整理を依頼した専門家に状況を報告し、指示に従って対応することが解決への近道となります。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
債務整理前の取り立てへの正しい対処法
債務整理を決意しても、実際に専門家に依頼するまでの間、取り立ては続きます。この期間の対応を誤ると、その後の債務整理に悪影響を及ぼす可能性もあるため、債務整理前の取り立てには慎重に対応する必要があります。ここでは、債務整理前の取り立てへの正しい対処法を解説します。
取り立て電話への対応
債権者からの電話による取り立ては、精神的に非常に負担になります。以下のポイントを意識して対応しましょう。
返済の約束はしない
返済できない状況にもかかわらず、督促の電話で焦って「来週には必ず払います」などと約束してしまうことは避けてください。実行できない返済の約束をすると、信頼関係が損なわれ、その後の債務整理の交渉が難しくなることがあります。
また、返済の約束をすることで、時効が成立する可能性のあった債務でも「債務の承認」となり、時効の中断事由になってしまう場合があります。
冷静かつ誠実に対応する
取り立ての電話を受けた際は、感情的にならず、冷静かつ誠実に対応することが重要です。「事情があって今は支払えない」「債務整理を検討している」など、状況を簡潔に伝えましょう。
相手の言葉に感情的に反応すると、話が拗れる原因になります。また、無視を続けると督促がエスカレートする可能性もあるため、一度は応対することが望ましいでしょう。
債務整理を検討中であることを伝える
「債務整理を検討しており、弁護士(または司法書士)に相談する予定です」と伝えることで、取り立ての頻度が減ることもあります。多くの債権者は、債務整理の可能性を知ると、その後の対応を検討するために一時的に取り立てを控える傾向にあります。
督促状への対応
郵送やFAXによる督促状については、以下のように対応しましょう。
- 内容を確認し、保管しておく
- 債務整理の際に必要な情報(債権者名、債務額など)を記録しておく
- 特に催告書や訴状が届いた場合は無視せず、早急に専門家に相談する
督促状の中には、「訴状」や「支払督促」など、法的手続きが始まったことを示す重要な書類が含まれている場合があります。これらを無視すると、自分の知らないところで裁判が進み、給与や預金の差し押さえにつながる可能性があるため、注意が必要です。
訪問による取り立てへの対応
自宅や職場への訪問による取り立ては、法律で厳しく規制されていますが、実際に行われるケースもあります。その場合は以下のように対応しましょう。
自宅への訪問
- 無理に家に入れる必要はない
- 冷静に対応し、感情的にならない
- 「債務整理を検討している」と伝える
- 相手の名前、所属、連絡先を確認する
- 悪質な取り立ての場合は、録音や録画で証拠を残す
職場への訪問
職場への訪問は、債務者の社会的信用を著しく損なう行為であり、多くの場合違法です。以下のように対応しましょう。
- 勤務中であれば「勤務中なので後ほど連絡する」と伝える
- 個人的な話は職場の外でするよう依頼する
- 借金の話は周囲に聞こえないよう注意する
- 悪質な場合は上司や会社に相談し、対応してもらう
職場への取り立ては「貸金業法」で禁止されており、特に悪質な場合は弁護士や司法書士に相談し、対応を依頼することも検討しましょう。
違法な取り立て行為への対応
以下のような取り立て行為は違法であり、断固として拒否すべきです。
- 深夜(午後9時〜午前8時)の電話や訪問
- 脅迫めいた言動や暴力的な言動
- 家族や職場の同僚など第三者への取り立て
- 社会的信用を傷つける行為(近隣への噂の流布など)
- 執拗な取り立て(1日に何度も電話するなど)
違法な取り立てを受けた場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 取り立ての内容を録音・記録する
- 弁護士や司法書士に相談する
- 警察に相談する
- 金融庁や財務局などに通報する
違法な取り立ては、我慢せずに専門家や関係機関に相談することが重要です。一人で抱え込まず、適切な支援を求めましょう。
差し押さえが始まりそうな場合の対応
取り立てが長期間続き、差し押さえの予告通知などが届いた場合は、早急に対応する必要があります。
差し押さえとは、債権者が裁判所を通じて債務者の財産(給与、預金、不動産など)を強制的に換金・処分して、債権を回収する法的手続きです。差し押さえが始まると、生活に大きな支障をきたす可能性があります。
差し押さえが予告されている場合や、すでに裁判所からの通知が届いている場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。特に以下のような書類が届いた場合は要注意です。
- 訴状
- 支払督促
- 差押命令
- 執行文付きの判決謄本
差し押さえを止めるためには、個人再生や自己破産などの法的手続きが必要になることが多いため、専門家の適切なアドバイスを受けることが重要です。
債務整理の決断と専門家への相談
取り立てが続いている状況で最も重要なのは、早期に債務整理を決断し、専門家に相談することです。取り立てに対応しているうちに時間が経ってしまうと、状況が悪化する可能性があります。
弁護士や司法書士への相談は、多くの場合無料で受け付けています。借金問題は一人で抱え込まず、専門家の力を借りて解決の道を探りましょう。
また、専門家に相談する際は、以下の情報を整理しておくとスムーズです。
- 借入先(債権者)の一覧
- 各債権者への借入額
- 取り立ての状況(頻度、内容など)
- 収入や生活状況
杉山事務所などのおすすめ事務所では無料相談を実施していますので、取り立てにお悩みの方はぜひご利用ください。経験豊富な専門家が、あなたの状況に合った解決策を提案します。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
債務整理と取り立てに関する注意点
債務整理による取り立てストップは大きなメリットですが、いくつか注意すべき点があります。ここでは債務整理と取り立てに関する重要な注意点を解説します。特に把握しておくべき3つの重要事項について詳しく見ていきましょう。
取り立てが長期におよんでいる場合は差し押さえに注意
借金の返済をすでに長期間滞納し、数ヶ月間取り立てを受けている場合は、差し押さえに発展するリスクが高いため注意が必要です。
差し押さえは裁判所を介した「強制執行手続」の一つで、債務者の給与や預金、不動産などの財産を債権者が強制的に回収する法的手段です。一度差し押さえが始まると、生活に大きな支障をきたす可能性があります。
差し押さえのプロセス
通常、差し押さえに至るまでには以下のようなプロセスがあります。
- 債権者が裁判所に訴えを提起する
- 裁判所から訴状や支払督促が債務者に送付される
- 債務者が応訴せず、または支払いに応じない場合、判決や債務名義が確定する
- 債権者が強制執行の申立てを行う
- 裁判所が差押命令を発令する
このプロセスの途中で債務整理を開始すれば、差し押さえを回避できる可能性がありますが、差し押さえ命令が出た後では対応が難しくなります。
債務整理方法による差し押さえ対応の違い
すでに差し押さえが始まっている場合や、差し押さえの危険性が高い場合は、債務整理の方法を慎重に選ぶ必要があります。
| 個人再生 | 裁判所が個人再生の手続開始を決定した時点で、差し押さえは中止される(民事再生法第39条)。すでに始まっている差し押さえも止めることが可能。 |
|---|---|
| 自己破産 | 申立て後、裁判所が破産手続開始を決定した段階で、差し押さえは中止される(破産法第249条1項)。すでに始まっている差し押さえも止めることが可能。 |
| 任意整理 | 裁判所を介さない手続きのため、差し押さえを法的に止める効力はない。債権者との交渉で差し押さえを取り下げてもらえる可能性はあるが、確実ではない。 |
差し押さえのリスクが高い場合や、すでに差し押さえが始まっている場合は、自己破産や個人再生といった裁判所を介した手続きを選択する方が安全と言えるでしょう。
税金の督促は債務整理では止められない
税金や社会保険料などの公的債務に関する督促は、債務整理による受任通知では止められません。これらは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産をしても免除されない債務です。
税金は法律上、他の債権よりも優先して弁済される「優先債権」にあたります。そのため、税金の滞納による督促や差し押さえは、債務整理とは別に対応する必要があります。
税金滞納への対応方法
税金の支払いが難しい場合は、以下の窓口に相談することで対応策を探ることができます。
- 所得税、相続税、贈与税など(国税):最寄りの税務署または国税局電話相談センター
- 住民税、固定資産税など(地方税):各自治体の税務課窓口
税金の滞納に対しては、以下のような対応策があります。
- 分割納付:収入状況に応じて分割で支払う
- 納税猶予:一定期間支払いを猶予してもらう
- 換価の猶予:差し押さえた財産の換価(売却)を猶予してもらう
税金の滞納は民間の借金よりも早いペースで差し押さえなどの強制執行に進む傾向があります。支払いが難しくなった時点で、早めに相談するようにしましょう。
債務整理せずに受任通知のみを出してもらうことはできない
「実際には債務整理をするつもりはないが、当面の取り立てを避けるために受任通知だけ出してもらえないか」と考える方もいるかもしれませんが、債務整理をしないのに受任通知だけを出すことはできません。
弁護士や司法書士には、依頼を受けた内容に対して誠実に業務を行う義務があります。実態のない受任通知を作成することは、弁護士法や司法書士法に違反する可能性があります。
また、受任通知による取り立ての禁止は、債務者の生活再建を目的とした法的制度です。生活再建の意思がない債務者を保護する必要はないという考え方から、単に取り立てを逃れるだけの目的では利用できません。
さらに、受任通知を送ったにもかかわらず実際の債務整理手続きを進めない場合、弁護士や司法書士が辞任することになり、債権者に「辞任通知」が送られます。その結果、再び取り立てが始まるだけでなく、今後の債務整理がより難しくなる可能性もあります。
受任通知発送のタイミングに注意が必要なケース
通常、債務整理を依頼すると即日〜数日以内に受任通知が発送されますが、以下のようなケースでは受任通知の発送タイミングに注意が必要です。
住宅ローンや自動車ローンがある場合
住宅ローンや自動車ローンなど、担保付きの借入がある場合、受任通知を送ると担保物(住宅や自動車)が引き上げられてしまう可能性があります。こうした財産をすぐに失うと生活に大きな支障をきたすこともあるでしょう。
このような場合、依頼した専門家と相談の上、以下のような対応を検討することがあります。
- 住宅を残したい場合は、個人再生の住宅ローン特則の利用を検討する
- 自動車を残したい場合は、親族による買取りや代替手段の確保を先に行う
- 担保物の処分や代替手段の確保が終わるまで、受任通知の発送を遅らせる
受任通知の発送タイミングは、債務者の生活状況や今後の計画に合わせて調整することが重要です。依頼する専門家とよく相談して決めるようにしましょう。
給与や賞与の入金直前の場合
給与や賞与の入金直前に受任通知を送ると、その入金を債務整理の費用に充てることができなくなる可能性があります。受任通知による取り立てストップの効果は、返済の停止も含むためです。
特に賞与など、まとまった金額の入金が見込める場合は、入金後に受任通知を送った方が、債務整理の費用を確保しやすくなることもあります。このようなケースでも、専門家と相談の上で最適なタイミングを決めることが大切です。
受任通知後の債権者とのコミュニケーション
受任通知が送られた後は、原則として債権者からの連絡はなくなります。しかし、もし債権者から直接連絡があった場合は、以下のように対応しましょう。
- 「弁護士(司法書士)に依頼しているので、そちらにお問い合わせください」と伝える
- 依頼した専門家の名前と連絡先を伝える
- 自分から返済の約束や交渉はしない
- 連絡があった事実を依頼した専門家に報告する
受任通知後の債権者との直接のやり取りは、せっかくの受任通知の効果を弱める可能性があります。債権者とのコミュニケーションは、すべて依頼した専門家を通じて行うようにしましょう。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
取り立てが止まっている間にすべきこと
債務整理を依頼して受任通知が送られると、取り立ては止まり、一時的に返済も停止できます。しかし、この期間は単に「何もしなくていい期間」ではありません。取り立てが止まっている間こそ、債務問題の解決と将来の生活再建に向けて積極的に行動すべき重要な時期です。
ここでは、取り立てが止まっている間に取り組むべき具体的な行動について解説します。
債務整理の手続きに必要な準備をする
取り立てが止まっている間は、依頼した債務整理の手続きを進めるための準備を確実に行うことが最優先です。債務整理の方法によって準備すべき内容は異なります。
必要書類の収集
債務整理に必要な書類を集めましょう。主な必要書類は以下の通りです。
| 債務関係の書類 |
|
|---|---|
| 収入・資産関係の書類 |
|
| 身分関係の書類 |
|
特に自己破産や個人再生など裁判所を介する手続きでは、多くの書類が必要になります。依頼した専門家の指示に従って、必要な書類を漏れなく準備しましょう。
財産目録の作成
自己所有の財産をリストアップした財産目録を作成します。これは特に自己破産や個人再生で重要です。以下のような財産を漏れなく記載する必要があります。
- 現金、預貯金
- 不動産(土地、建物)
- 自動車、バイク
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 生命保険、損害保険
- 貴金属、美術品
- 退職金請求権
- 他者への貸付金、債権
財産を隠したり虚偽の申告をしたりすると、債務整理が認められなくなる可能性があるため、正直に申告することが重要です。
家計簿・収支表の作成
毎月の収入と支出を記録した家計簿や収支表を作成します。これは任意整理や個人再生では特に重要で、返済計画の基礎となります。
- 月々の収入(給与、年金、児童手当など)
- 固定費(家賃、水道光熱費、保険料、通信費など)
- 生活費(食費、日用品費、交通費、医療費など)
- その他の支出(教育費、娯楽費など)
正確な家計簿を作成することで、今後の返済計画の実現可能性や生活の見通しが明確になります。
債務整理の費用を確保する
債務整理には、弁護士・司法書士への依頼費用や裁判所への申立て費用などが必要です。取り立てが止まっている間に、これらの費用を確保することも重要なタスクです。
専門家への報酬
債務整理の依頼費用は、手続きの種類や債権者数、債務額などによって異なります。目安としては以下のようになります。
| 任意整理 | 1社あたり2〜5万円程度、着手金や減額報酬などが別途必要な場合もある |
|---|---|
| 個人再生 | 30〜50万円程度 |
| 自己破産 | 同時廃止事件で20〜30万円程度、管財事件で40〜60万円程度 |
これらの費用は一括払いが原則ですが、分割払いに対応している事務所も多いです。依頼した専門家と相談し、無理のない支払い計画を立てましょう。
裁判所への費用
個人再生や自己破産など裁判所を介する手続きでは、裁判所への費用も必要です。
- 個人再生:予納金、印紙代など合計で約15〜20万円程度
- 自己破産:予納金、印紙代など合計で約5〜40万円程度(管財事件ではさらに高額)
これらの費用も含めて、債務整理の総費用を計画的に準備する必要があります。
費用確保の方法
取り立てが止まっている間は、それまで返済に充てていたお金を債務整理の費用に回すことができます。その他にも以下のような方法で費用を確保することが考えられます。
- 親族や知人からの借入れ(返済計画を明確にして)
- 不要な資産の売却(自己破産を予定している場合は注意が必要)
- 副業やアルバイトで収入を増やす
- 生活費を見直して支出を削減する
ただし、債務整理直前の財産処分や特定の人への返済は、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として問題になる可能性があるため、必ず専門家に相談した上で行動しましょう。
生活の立て直しと再建計画を立てる
債務整理は単に借金を減らすだけでなく、その後の生活を立て直すことが本来の目的です。取り立てが止まっている間に、今後の生活再建に向けた計画を立てることも重要です。
収入を安定・増加させる方法を検討する
債務整理後も安定した生活を送るためには、収入の確保が欠かせません。以下のような方法を検討しましょう。
- 現在の仕事でのキャリアアップ、昇給の可能性
- より条件の良い転職の検討
- 資格取得などによるスキルアップ
- 副業の可能性
特に任意整理や個人再生を選択する場合は、今後3〜5年間の返済を続けていく必要があるため、安定した収入源の確保は非常に重要です。
家計の見直しと支出削減
収入だけでなく、支出の見直しも重要です。無駄な支出を削減し、効率的な家計管理を心がけましょう。
- 固定費(通信費、保険料など)の見直し
- 食費の効率化(まとめ買い、自炊の増加など)
- 光熱費の節約
- 不要なサブスクリプションサービスの解約
家計簿をつけることで、どこに無駄な支出があるかが明確になります。債務整理中だけでなく、その後も継続して家計管理を行うことが重要です。
再借金を防ぐための対策
債務整理後に再び借金問題に陥らないためには、以下のような対策が有効です。
- クレジットカードの利用を控える
- 緊急時のための貯蓄を少しずつでも始める
- 衝動買いを避けるための工夫(クーリングオフの活用など)
- 公的支援制度(生活福祉資金貸付制度など)の情報を知っておく
債務整理後は信用情報機関に事故情報が登録され、数年間(5〜10年程度)は新たな借入れが難しくなります。この期間を「借金に頼らない生活習慣を身につける機会」と前向きに捉えて、健全な家計管理を実践しましょう。
メンタルケアも大切に
借金問題に悩んでいた時期の精神的ストレスは大きなものです。取り立てが止まった安心感からホッとする一方で、債務整理への不安や迷いも感じることがあるでしょう。
この時期こそ、心身の健康を整えることも大切です。十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動を心がけ、必要に応じて専門家(医師やカウンセラーなど)に相談することも検討しましょう。
また、債務整理の過程で不安なことがあれば、依頼した弁護士や司法書士に遠慮なく相談してください。専門家は法律面だけでなく、精神的なサポートも含めたトータルな支援を行ってくれます。
取り立てが止まった安心感に浸るだけでなく、この期間を積極的に活用して債務問題の完全解決と将来の生活再建に向けた準備を進めましょう。杉山事務所などのおすすめ事務所では、債務整理後の生活再建までサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
まとめ:債務整理で取り立てを止めるための5つのポイント
ここまで、債務整理による借金取り立てストップの仕組みや流れ、注意点などを詳しく解説してきました。最後に、債務整理で取り立てを効果的に止めるための5つの重要ポイントをまとめます。
1. 早期に専門家への相談を決断する
借金の取り立てに悩んでいる場合、できるだけ早く弁護士や司法書士への相談を決断することが重要です。取り立てが長期化すると、差し押さえのリスクが高まるだけでなく、精神的な負担も増大します。
「もう少し様子を見よう」「なんとか自分で解決しよう」と思って先延ばしにすると、状況が悪化する可能性が高いです。借金の返済が難しくなり始めた段階で、専門家への相談を検討しましょう。
杉山事務所などのおすすめ事務所では無料相談を実施していますので、まずは気軽に相談することから始めてみてください。専門家からのアドバイスを受けることで、今後の見通しが立ちやすくなります。
2. 自分の状況に合った債務整理方法を選ぶ
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、それぞれ取り立てが止まるタイミングや効果に違いがあります。自分の状況に合った最適な債務整理方法を選ぶことが、取り立てを効果的に止めるポイントです。
例えば、差し押さえのリスクが高い場合は裁判所を介した個人再生や自己破産が有効です。一方、住宅ローンがあり自宅を残したい場合は個人再生が適しています。
専門家に相談する際は、以下のような情報を整理しておくと、適切な方法を提案してもらいやすくなります。
- 借入先と借入額
- 収入や資産の状況
- 取り立ての状況(頻度や方法)
- 今後も維持したい資産(住宅、自動車など)
3. 受任通知の発送タイミングを専門家と相談する
受任通知は最短即日で取り立てを止める効果がありますが、発送のタイミングは慎重に検討する必要があります。住宅ローンや自動車ローンがある場合、受任通知を送ると担保物件が引き上げられるリスクがあるためです。
また、給与や賞与の入金直前に受任通知を送ると、その入金を債務整理の費用に充てることができなくなる可能性もあります。
受任通知の発送タイミングは、依頼した専門家とよく相談した上で決めるのが賢明です。あなたの生活状況や今後の計画に合わせた最適なタイミングを見極めましょう。
4. 取り立てが止まらない場合の対応策を知っておく
受任通知を送付しても、以下のようなケースでは取り立てが止まらないことがあります。
- 個人間の借金の場合
- 闇金業者からの借り入れの場合
- 税金や公共料金などの公的債務の場合
これらのケースでは、それぞれ適切な対応策を理解しておくことが重要です。個人間の借金では接近禁止命令の検討、闇金業者の場合は警察への相談、税金の滞納では役所の窓口での分納相談など、状況に応じた対策を講じる必要があります。
受任通知を送った後も取り立てが続く場合は、すぐに依頼した専門家に報告し、対応方法について相談しましょう。一人で対応しようとせず、専門家の力を借りることが解決への近道です。
5. 取り立てが止まっている間を有効活用する
取り立てが止まっている間は、単に安心するだけでなく、債務整理の手続き準備や将来の生活再建に向けた計画を立てる大切な期間です。この期間を有効活用しましょう。
具体的には、以下のような取り組みが重要です。
- 債務整理に必要な書類の収集と準備
- 債務整理の費用の確保
- 家計の見直しと支出削減策の実施
- 収入増加のための方策(転職、スキルアップなど)の検討
- 再び借金に頼らない生活習慣の構築
これらの取り組みは、債務整理の成功だけでなく、その後の生活の安定にも大きく影響します。取り立てがストップしたという一時的な安心に浸るのではなく、借金問題の根本的な解決と将来の生活再建に向けた行動を積極的に進めましょう。
最後に:借金問題は必ず解決できます
借金の取り立てに悩み、精神的に追い詰められている方は少なくありません。しかし、適切な専門家のサポートを受ければ、どんな借金問題も必ず解決の道が開けます。
債務整理は「借金からの解放」と「新たな生活の始まり」への第一歩です。取り立ての電話や督促状に怯える日々から解放され、前向きな気持ちで生活を再建していくためにも、まずは専門家への相談を検討してみてください。
杉山事務所などのおすすめ事務所では、豊富な経験と実績を持つ専門家が、あなたの状況に合った最適な解決策を提案します。無料相談も実施していますので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断