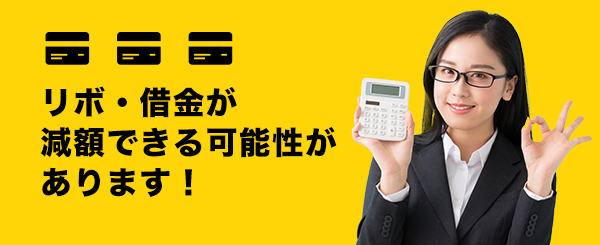債務整理にかかる期間は?手続き完了から返済終了・ブラックリスト解除までを解説
本記事はプロモーションを含みます
「債務整理を考えているけど、どれくらいの期間がかかるのだろう?」「いつから借金の取り立てが止まるのか知りたい」「手続き完了までの流れを詳しく知りたい」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などの種類があり、選択する手続きによって期間が大きく異なります。また、手続き完了後の返済期間やブラックリストに載る期間についても知っておくことが重要です。
本記事では、債務整理にかかる期間について徹底解説します。手続き別の所要期間や、返済開始までの流れ、ブラックリスト期間について詳しく説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
債務整理の相談は早ければ早いほど選択肢が広がります。返済に苦しんでいる方は、ぜひこの記事を参考にして適切な債務整理の方法を検討してみてください。
■もくじ
債務整理の各手続きにかかる期間
債務整理とは、返済が難しくなった借金問題を解決するための法的手続きです。借金の状況や返済能力によって最適な方法が異なり、それぞれ手続きにかかる期間も変わってきます。
債務整理の手続きにかかる期間は、おおむね3ヶ月~1年程度です。債務整理の種類別にかかる期間を簡単にまとめると次のようになります。
| 債務整理の種類 | 手続きにかかる期間 |
|---|---|
| 任意整理 | 3~6ヶ月程度 |
| 個人再生 | 6ヶ月~1年程度 |
| 自己破産 | 5ヶ月~1年程度 |
| 特定調停 | 3~5ヶ月程度 |
債務整理の中でも、裁判所を通さない任意整理が最も短期間で完了することが多いです。一方、裁判所を通す個人再生や自己破産は書類準備や審査に時間がかかるため、完了までに時間を要します。
それでは、各債務整理の手続きにかかる期間について詳しく見ていきましょう。
債務整理の種類による期間の違い
債務整理は大きく分けて「裁判所を通さない手続き」と「裁判所を通す手続き」の2種類に分類できます。それぞれの特徴と期間の違いを理解しておくことが重要です。
裁判所を通さない手続きである任意整理は、債権者との直接交渉で解決を図るため、比較的短期間で手続きが完了します。しかし、債権者の協力が得られない場合は交渉が長引くこともあります。
裁判所を通す手続きである個人再生や自己破産は、法的な保護を受けられる一方で、裁判所への申立てや審査など複雑な手続きがあるため時間がかかります。ただし、確実に借金問題を解決できるメリットがあります。
特定調停は簡易裁判所を通す手続きですが、任意整理と似た性質を持ち、比較的短期間で進められます。
適切な債務整理の選び方
債務整理の方法選びで「期間」は重要な要素ですが、それだけで判断すべきではありません。以下のポイントも考慮して最適な方法を選びましょう。
- 借金の総額と返済能力のバランス
- 持ち家や車などの財産を残せるかどうか
- 保証人への影響
- 将来的な信用情報への影響
- 職業制限の有無
返済能力に応じた適切な債務整理方法を選ぶことが、最終的には手続き期間の短縮にもつながります。状況が複雑な場合は、専門家に相談して最適な方法を見つけることをおすすめします。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
任意整理にかかる期間と流れ
任意整理は、裁判所を介さずに弁護士や司法書士が債権者と直接交渉する債務整理の方法です。将来の利息をカットし、元金を3~5年程度の分割払いにする内容で和解することが一般的です。
任意整理にかかる期間は通常3~6ヶ月程度です。債権者の数や交渉の難航度によって期間が変わることがありますが、債務整理の中では比較的短期間で完了する方法といえます。
任意整理の手続きの流れと期間
任意整理の手続きは、専門家への依頼から和解成立まで、以下のような流れで進みます。
| 手続きの内容 | かかる期間 |
|---|---|
| 弁護士・司法書士への依頼 | 即日 |
| 受任通知の送付 | 即日~3日程度 |
| 取引履歴の開示請求と債務額の調査 | 1~2ヶ月程度 |
| 利息制限法に基づく引き直し計算 | 1~2週間程度 |
| 和解案の作成と債権者との交渉 | 2~3ヶ月程度 |
| 和解成立・書面の交換 | 2週間程度 |
| 返済開始 | 和解成立後 |
それでは、各ステップの詳細を見ていきましょう。
①弁護士・司法書士への依頼と受任通知の送付(即日~3日)
債務整理を専門家に依頼すると、弁護士や司法書士は早ければ当日、遅くとも3日以内に債権者へ「受任通知」を送付します。受任通知は、債務者の代理人として専門家が交渉にあたることを債権者に通知する書類です。
この受任通知が債権者に届くと、債権者からの取立てや督促が法的に禁止されます。また、受任通知の効力により返済も一時的にストップするため、毎月の返済負担から解放されます。
②取引履歴の開示請求と債務額の調査(1~2ヶ月程度)
専門家は各債権者に対して取引履歴の開示を請求します。取引履歴とは、いつ、いくら借入れ・返済したかという記録で、正確な債務額を確定するために必要です。
債権者によって対応の速さが異なるため、すべての取引履歴が揃うまでに1~2ヶ月程度かかることが一般的です。場合によっては、対応が遅い債権者があると、この段階だけで2ヶ月以上かかることもあります。
③利息制限法に基づく引き直し計算(1~2週間程度)
取引履歴が揃ったら、専門家は利息制限法に基づいて債務額を再計算します。これを「引き直し計算」といい、過去に払いすぎた利息があれば、それを元金から差し引いて正確な債務額を確定させます。
場合によっては、過払い金が発生していることもあります。引き直し計算には1~2週間程度かかります。
④和解案の作成と債権者との交渉(2~3ヶ月程度)
正確な債務額が確定したら、債務者の返済能力に応じた和解案を作成し、債権者との交渉を開始します。主な交渉内容は以下の通りです。
- 将来利息のカット
- 遅延損害金の減額または免除
- 分割返済回数の設定(通常36~60回)
- 毎月の返済額の決定
債権者との交渉は通常2~3ヶ月程度かかりますが、債権者の数が多いほど時間がかかります。また、債権者が和解案に合意しない場合は、再交渉が必要となり、さらに時間がかかることもあります。
⑤和解成立・書面の交換(2週間程度)
交渉がまとまると、債権者との間で和解書を取り交わします。和解書には返済条件や返済スケジュールなどが明記されています。和解書の取り交わしには約2週間程度かかります。
⑥返済開始
和解成立後は、和解内容に基づいて返済を開始します。任意整理後の返済期間は通常3~5年(36~60回払い)です。
任意整理が適している人
任意整理は次のような方に適している債務整理方法です。
- 定期的な収入があり、元金の分割返済が可能な人
- 借金総額が比較的少なく、将来利息カットで返済可能な人
- 保証人に迷惑をかけたくない人
- 住宅ローンや自動車ローンがあり、家や車を手放したくない人
任意整理は裁判所を通さないため比較的短期間で手続きが完了し、財産を手放す必要もありません。ただし、元金自体は減額されないため、返済能力に見合った借金額である必要があります。
個人再生にかかる期間と流れ
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残額を原則3年で返済する債務整理方法です。借金総額が5分の1から10分の1程度に圧縮されるため、任意整理では返済が難しい場合に検討される方法です。
個人再生にかかる期間は通常6ヶ月~1年程度です。裁判所での手続きが必要なため、任意整理よりも時間がかかります。また、提出書類も多く準備に時間を要します。
個人再生の手続きの流れと期間
個人再生の手続きは、依頼から再生計画認可決定まで、以下のような流れで進みます。
| 手続きの内容 | かかる期間 |
|---|---|
| 弁護士・司法書士への依頼 | 即日 |
| 受任通知の送付 | 即日~3日程度 |
| 債権者・財産・家計などの調査 | 数ヶ月程度 |
| 個人再生の申立て | 1ヶ月程度 |
| 個人再生委員の選任 | 申立てから1週間程度 |
| 再生手続の開始決定 | 申立てから1ヶ月程度 |
| 再生計画案の提出 | 2~3ヶ月程度 |
| 再生計画案の認可決定 | 2~3ヶ月程度 |
| 返済開始 | 認可決定後 |
それでは、各ステップの詳細を見ていきましょう。
①弁護士・司法書士への依頼と受任通知の送付(即日~3日)
個人再生も任意整理と同様に、まず専門家への依頼から始まります。依頼を受けた専門家は、即日~3日以内に債権者へ受任通知を送付します。受任通知が債権者に届くと、取立てや督促が法的に禁止され、返済も一時的にストップします。
②債権者・財産・家計などの調査(数ヶ月程度)
個人再生の申立てには、借金の詳細な状況だけでなく、財産状況や家計の収支に関する情報も必要です。専門家は債権者に取引履歴の開示を求めるとともに、債務者の財産や収入・支出の状況を詳しく調査します。
この調査には数ヶ月かかることが一般的です。特に、不動産など価値の評価が必要な財産がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
③個人再生の申立て(1ヶ月程度)
調査が完了したら、裁判所に個人再生の申立てを行います。申立てには多くの書類が必要で、その準備に1ヶ月程度かかります。主な必要書類は以下の通りです。
- 再生手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 収入・支出に関する資料
- 給与明細や確定申告書などの収入証明
- 住民票や戸籍謄本など
これらの書類を専門家の指示に従って準備し、裁判所に提出します。
④個人再生委員の選任(申立てから1週間程度)
個人再生の申立てが受理されると、裁判所によっては「個人再生委員」が選任されることがあります。個人再生委員は、債務者の財産状況を調査し、再生計画案の作成をサポートする役割を担います。
なお、個人再生委員は必ず選任されるわけではなく、裁判所が必要と判断した場合や、東京地方裁判所に申立てを行った場合などに選任されます。
⑤再生手続の開始決定(申立てから1ヶ月程度)
裁判所が申立内容を審査し、問題がなければ「再生手続開始決定」が下されます。これは個人再生の手続きを正式に開始する決定で、通常、申立てから1ヶ月程度で出されます。
この決定が出されると、一時的に債権者の権利行使が制限され、法的な保護の下で再生計画案の作成に進むことができます。
⑥再生計画案の提出(2~3ヶ月程度)
再生手続開始決定後、債務者は再生計画案を作成して裁判所に提出します。再生計画案とは、借金をどのように減額し、どのようなスケジュールで返済していくかを記載した計画書です。
再生計画案の作成には、債務者の収入や財産状況を考慮した「最低弁済額」の計算が必要です。また、個人再生委員がいる場合は、その意見も反映させる必要があります。これらの準備に2~3ヶ月程度かかります。
⑦再生計画案の認可決定(2~3ヶ月程度)
提出された再生計画案は、債権者の意見を聴取した上で裁判所が審査します。問題がなければ「再生計画認可決定」が下され、再生計画が確定します。この決定には提出から2~3ヶ月程度かかります。
再生計画が認可されると、借金は計画通りに減額され、残額を分割返済していくことになります。
⑧返済開始
再生計画認可決定後、計画に従って返済を開始します。個人再生後の返済期間は原則3年(36回払い)です。特別な事情がある場合は、最長5年(60回払い)まで延長できることもあります。
個人再生が適している人
個人再生は次のような方に適している債務整理方法です。
- 借金総額が高額で任意整理では返済が難しい人
- 安定した収入があり、減額後の借金なら返済可能な人
- 住宅ローンがあり、家を残したい人(住宅資金特別条項の利用)
- 自己破産では制限される職業に就いている人
個人再生は借金を大幅に減額できる一方で、手続きが複雑で時間もかかります。また、再生計画に従った返済を続ける必要があり、途中で返済できなくなると計画が失敗し、元の借金額に戻ってしまうリスクもあります。
すみません、タイプミスがありましたようですが、回答を承ったと理解します。
続いて「自己破産にかかる期間と流れ」のセクションを作成します。
自己破産にかかる期間と流れ
自己破産は、裁判所に返済能力がないことを認めてもらい、借金の支払い義務をほぼ全額免除してもらう債務整理方法です。返済の見込みがない状況で借金問題を抜本的に解決できる手段として利用されます。
自己破産にかかる期間は通常5ヶ月~1年程度です。個人再生と同様に裁判所での手続きが必要となるため、ある程度の時間を要します。なお、財産状況によって手続きが異なり、期間も変わってきます。
自己破産の手続きの種類と期間
自己破産の手続きは、債務者の財産状況によって次の3つに分類されます。それぞれ手続きの内容や期間が異なります。
| 手続きの種類 | 該当するケース | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 財産額が20万円を下回る場合など | 5~7ヶ月程度 |
| 管財事件 | 財産額が20万円を上回る(家や車を所有している)場合など | 8ヶ月~1年程度 |
| 少額管財事件 | 財産額が20万円を上回るが、財産の調査・換価処分の時間を短縮できる場合など | 6~8ヶ月程度 |
最も一般的な「同時廃止事件」の場合の手続きの流れを見ていきましょう。
自己破産(同時廃止事件)の手続きの流れと期間
| 手続きの内容 | かかる期間 |
|---|---|
| 弁護士・司法書士への依頼 | 即日 |
| 受任通知の送付 | 即日~3日程度 |
| 申立書類の作成・準備 | 2~3ヶ月程度 |
| 裁判所への申立て | 書類準備完了後 |
| 破産審尋 | 申立てから1ヶ月程度 |
| 破産手続開始決定 | 1週間程度 |
| 免責審尋・免責決定 | 1~2ヶ月程度 |
| 免責確定 | 1ヶ月程度 |
それでは、各ステップの詳細を見ていきましょう。
①弁護士・司法書士への依頼と受任通知の送付(即日~3日)
自己破産も他の債務整理方法と同様に、まず専門家への依頼から始まります。依頼後、専門家は即日~3日以内に債権者へ受任通知を送付します。受任通知が債権者に届くと、取立てや督促が法的に禁止され、返済も一時的にストップします。
②申立書類の作成・準備(2~3ヶ月程度)
自己破産の申立てには多くの書類が必要です。専門家の指示に従って、以下のような書類を準備します。
- 破産申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 収入・支出に関する資料
- 給与明細や確定申告書などの収入証明
- 破産に至った事情を説明する陳述書
- 住民票や戸籍謄本など
これらの書類を揃えるのに2~3ヶ月程度かかることが一般的です。特に、借入先が多い場合や長期間にわたる借入がある場合は、資料収集に時間がかかることがあります。
③裁判所への申立て
必要書類が揃ったら、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行います。申立ての際には、破産手続きの予納金(裁判所に支払う費用)も必要です。同時廃止事件の場合、予納金は数万円程度です。
④破産審尋(申立てから1ヶ月程度)
申立て後、裁判所で破産審尋が行われます。債務者は裁判官から借金の状況や破産に至った経緯、現在の生活状況などについて質問を受けます。この審尋は申立てから1ヶ月程度経過してから行われることが多いです。
⑤破産手続開始決定(1週間程度)
破産審尋で問題がなければ、裁判所から「破産手続開始決定」が下されます。同時廃止事件の場合、破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了します。
⑥免責審尋・免責決定(1~2ヶ月程度)
破産手続開始決定後、債務者は「免責審尋」を受けます。免責審尋では、免責不許可事由(免責が認められない理由)がないかが審査されます。問題がなければ、裁判所から「免責許可決定」が下されます。
免責許可決定が出るまでには、破産手続開始決定から1~2ヶ月程度かかります。
⑦免責確定(1ヶ月程度)
免責許可決定が出されてから2週間以内に債権者から異議申立てがなければ、免責が確定します。免責が確定すると、正式に借金の支払い義務がなくなります。
免責確定までは、免責許可決定から1ヶ月程度かかるのが一般的です。
管財事件の場合の追加手続き
財産額が20万円を超える「管財事件」の場合は、破産管財人が選任され、財産の調査・換価処分が行われるため、さらに時間がかかります。主な追加手続きは以下の通りです。
- 破産管財人の選任と管財人面接
- 財産の調査・換価処分
- 債権者集会(通常1~2回)
- 配当手続き
これらの手続きにより、管財事件の場合は自己破産完了までに8ヶ月~1年程度かかることが一般的です。
自己破産が適している人
自己破産は次のような方に適している債務整理方法です。
- 借金総額が高額で、任意整理や個人再生でも返済が難しい人
- 安定した収入がなく、継続的な返済が困難な人
- 財産をほとんど持っていない人
- 病気や失業などで収入が激減した人
自己破産は借金をほぼ全額免除できる強力な債務整理方法ですが、一定の財産は失うことになり、ブラックリストに載る期間も長くなります。また、免責が認められるまでは、一部の職業制限もあります。
特定調停にかかる期間と流れ
特定調停は、簡易裁判所を通じて債権者と和解する債務整理方法です。任意整理と似た特徴を持ちますが、裁判所の調停委員が間に入るため、債権者との交渉がスムーズに進むことがあります。
特定調停にかかる期間は通常3~5ヶ月程度です。債権者数や交渉の難航度によって期間が変わることがありますが、他の裁判所を通じた手続きと比べると、比較的短期間で完了します。
特定調停の手続きの流れと期間
特定調停の手続きは、申立てから調停成立まで、以下のような流れで進みます。
| 手続きの内容 | かかる期間 |
|---|---|
| 必要書類の作成・準備 | 1週間程度 |
| 特定調停の申立て | 書類準備完了後 |
| 調査期日 | 申立てから1ヶ月程度 |
| 調停期日(複数回) | 2~3ヶ月程度 |
| 調停成立・調停調書の作成 | 数日~1週間程度 |
| 返済開始 | 調停成立後 |
それでは、各ステップの詳細を見ていきましょう。
①必要書類の作成・準備(1週間程度)
特定調停の申立てには、以下のような書類が必要です。
- 特定調停申立書
- 債権者一覧表
- 収入・支出に関する資料
- 給与明細や確定申告書などの収入証明
- 返済計画案
必要書類は弁護士や司法書士のサポートを受けながら準備するとスムーズです。書類準備には通常1週間程度かかります。
②特定調停の申立て
必要書類が揃ったら、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に特定調停の申立てを行います。申立ての際には、1債権者につき収入印紙代(数千円)と郵便切手代が必要です。
申立てが受理されると、裁判所から調査期日の通知が届きます。
③調査期日(申立てから1ヶ月程度)
調査期日では、裁判所の調停委員が債務者から借金状況や収入・支出状況、返済能力などについて聴取します。この情報をもとに調停委員は、債権者との調停に向けた返済計画案を作成します。
調査期日は申立てから1ヶ月程度で設定されることが一般的です。
④調停期日(2~3ヶ月程度)
調査期日後、債権者も交えた調停期日が設定されます。ここでは、調停委員が作成した返済計画案をもとに、債権者と債務者の間で和解条件について話し合います。
調停期日は通常月1回程度のペースで行われ、債権者の数や交渉の難航度によって2~3回程度開催されることが一般的です。全ての債権者との調停が完了するまでに、2~3ヶ月程度かかります。
⑤調停成立・調停調書の作成(数日~1週間程度)
全ての債権者と合意に達すると、調停が成立します。調停の内容は「調停調書」として作成され、これは裁判所の判決と同等の効力を持ちます。調停調書の作成には数日~1週間程度かかります。
なお、債権者の一部または全部が合意しない場合は、調停不成立となることもあります。その場合は、別の債務整理方法を検討する必要があります。
⑥返済開始
調停が成立すると、調停調書に記載された内容に基づいて返済を開始します。特定調停後の返済期間は通常3~5年(36~60回払い)です。
特定調停のメリットとデメリット
特定調停のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 裁判所が間に入るため、債権者の協力を得やすい
- 申立てから和解までの期間が比較的短い
- 弁護士や司法書士を介さなくても自分で手続き可能
- 費用が比較的安い
デメリット
- 元金は減額されず、将来利息のカットのみ
- 全ての債権者が合意しないと成立しない
- 個人で進めると難しい場合がある
- 債権者が多いと手続きが煩雑になる
特定調停が適している人
特定調停は次のような方に適している債務整理方法です。
- 定期的な収入があり、元金の分割返済が可能な人
- 任意整理で債権者が交渉に応じなかった人
- 弁護士・司法書士費用をできるだけ抑えたい人
- 債権者数が比較的少ない人
特定調停は任意整理と似た性質を持つため、同様のケースで検討されることが多いです。ただし、実際には債権者にとって任意整理よりも不利な条件での和解を求めることは難しいため、まずは任意整理を検討し、債権者が交渉に応じない場合に特定調停を選ぶという流れが一般的です。
債務整理の手続き開始で取立てが止まる期間
債務整理を検討している方の多くは、返済の遅延により債権者からの督促や取立てに悩まされているケースが少なくありません。ここでは、債務整理の手続き開始によって取立てが止まる期間について解説します。
結論からいうと、債務整理を弁護士や司法書士に依頼した時点で、原則として債権者からの取立てはストップします。そして、手続きが完了するまでその状態が続きます。
受任通知で取立てが止まる仕組み
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、専門家は債権者に対して「受任通知」という書面を送付します。受任通知とは、債務者の代理人として債務整理手続きを進めることを債権者に通知する文書です。
貸金業者は、受任通知を受け取ると法律上、債務者に対して直接取立てをすることができなくなります。これは貸金業法第21条で規定されており、違反した場合は罰則の対象となります。
| 債務整理の種類 | 取立てが止まる期間 |
|---|---|
| 任意整理 | 受任通知送付から和解成立または手続き終了まで |
| 個人再生 | 受任通知送付から再生計画認可決定確定まで |
| 自己破産 | 受任通知送付から免責確定まで |
| 特定調停 | 申立て後から調停成立または不成立まで |
受任通知の送付タイミングと効果
弁護士や司法書士に依頼すると、通常即日~3日以内に受任通知が送付されます。優良な事務所であれば、依頼当日に受任通知を送付することが一般的です。
受任通知の主な効果は以下の通りです。
- 債権者からの電話や訪問による取立てが止まる
- 以後の連絡は全て代理人(弁護士・司法書士)を通じて行われる
- 返済も一時的にストップできる
- 債務者の精神的負担が軽減される
受任通知が債権者に届くまでの間は、まだ取立てが続く可能性があります。受任通知を送付したことを債権者に電話で伝え、取立てをストップしてもらうよう依頼することも可能です。
債権者別の対応の違い
受任通知を受け取った後の対応は、債権者の種類によって若干異なる場合があります。
| 債権者の種類 | 受任通知後の対応 |
|---|---|
| 貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社など) | 貸金業法により直接の取立てが禁止され、厳格に守られる |
| 銀行・信用金庫 | 貸金業法の適用はないが、実務上は取立てを停止することが多い |
| 債権回収会社(サービサー) | 債権管理回収業法により直接の取立てが禁止される |
| 個人間の借金 | 法律上の規制はないが、弁護士が介入することで取立てが抑制されることが多い |
取立てが止まらないケース
ほとんどの場合、受任通知によって取立ては止まりますが、以下のようなケースでは取立てが継続する可能性があります。
- 非免責債権(税金、養育費、罰金など)の場合
- 受任通知が債権者に届いていない場合
- 個人間の貸借で、貸主が法律を知らない場合
- 債務整理の対象から外している債権の場合
万が一、受任通知を送付したにもかかわらず取立てが続く場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。債権者に対して警告を行い、それでも止まらない場合は法的措置を取ることも可能です。
返済停止の期間と注意点
受任通知の効果により、債務整理の手続き中は返済が一時的に停止されます。返済停止期間は、債務整理の種類によって異なります。
- 任意整理:和解成立まで(3~6ヶ月程度)
- 個人再生:再生計画認可決定まで(6ヶ月~1年程度)
- 自己破産:免責確定まで(5ヶ月~1年程度)
- 特定調停:調停成立まで(3~5ヶ月程度)
ただし、返済停止中も利息は発生し続ける可能性があるため、手続きが長引くほど債務が増えることがあります。また、住宅ローンなど債務整理の対象外とする借金は、通常通り返済を継続する必要があります。
債務整理後の返済期間はどれくらい?
債務整理の手続きが完了した後も、自己破産を除いて返済を継続する必要があります。ここでは、各債務整理方法の手続き完了後の返済期間について解説します。
債務整理後の返済期間は、選んだ債務整理の方法によって大きく異なります。おおむね次のような期間が目安となります。
| 債務整理の種類 | 返済期間の目安 |
|---|---|
| 任意整理 | 3~5年程度(36~60回払い) |
| 個人再生 | 原則3年(最長5年) |
| 自己破産 | 返済義務免除(非免責債権を除く) |
| 特定調停 | 3~5年程度(36~60回払い) |
それでは、各債務整理方法ごとの返済期間の詳細を見ていきましょう。
任意整理後の返済期間(3~5年程度)
任意整理の場合、債権者との和解で決まった返済計画に基づいて返済を続けます。一般的に3~5年(36~60回払い)の分割返済となることが多いです。
任意整理で減額されるのは主に将来利息と遅延損害金で、元金はほとんど減額されません。そのため、元金を分割して返済する期間が必要となります。
返済期間は債権者との交渉で決まり、以下の要素によって変動します。
- 債務総額の大きさ
- 債務者の返済能力
- 債権者の方針
- これまでの返済状況
なお、任意整理後の返済中に2回以上の滞納が続くと、和解契約が破棄され、残債務の一括請求を受ける可能性があります。返済計画は無理のない範囲で設定し、確実に守ることが重要です。
臨時収入があれば繰り上げ返済も可能で、早期に完済すれば信用情報の回復も早まります。
個人再生後の返済期間(原則3年・最長5年)
個人再生の場合、再生計画に基づいて原則3年(36回払い)で返済します。特別な事情がある場合は、裁判所の許可を得て最長5年(60回払い)まで延長することも可能です。
個人再生では、借金総額が5分の1から10分の1程度に圧縮されるため、任意整理と比べて返済負担が大幅に軽減されます。ただし、最低弁済額(住宅資金特別条項を利用しない場合は100万円)の返済は必須となります。
返済期間を延長できる「特別な事情」の例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 子どもの教育費負担が大きい
- 病気や怪我の治療費がかかる
- 老親の介護費用がかかる
- 収入が一時的に減少している
個人再生後の返済は必ず守る必要があります。万が一、返済が困難になった場合は、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。再生計画の変更が認められることもあります。
ただし、再生計画に従った返済ができなくなると、再生計画が取り消され、減額前の債務額に戻ってしまうリスクがあります。
自己破産後の返済期間(返済義務免除)
自己破産の場合、免責許可決定が確定すると、原則として全ての借金の返済義務が免除されます。そのため、返済期間はありません。
ただし、以下の「非免責債権」については、自己破産後も返済義務が残ります。
- 税金(所得税、住民税など)
- 養育費や婚姻費用
- 罰金や科料
- 故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償
- 浪費や賭博などが原因で裁判所が免責を認めなかった債務
非免責債権については、自己破産後も支払い義務が継続するため、別途返済計画を立てる必要があります。
特定調停後の返済期間(3~5年程度)
特定調停の場合、調停調書に記載された内容に基づいて返済を続けます。任意整理と同様に3~5年(36~60回払い)の分割返済となることが一般的です。
特定調停でも減額されるのは主に将来利息と遅延損害金で、元金はほとんど減額されません。返済期間中は調停調書の内容に従った返済を続ける必要があります。
特定調停後の返済を怠ると、債権者は調停調書を基に強制執行の申立てができるため、給与や預金の差押えなどを受ける可能性があります。返済計画は無理のない範囲で設定することが重要です。
返済期間中の注意点
債務整理後の返済期間中は、以下の点に注意しましょう。
- 返済日と返済額を必ず守る
- 返済が難しくなりそうな場合は早めに相談する
- 新たな借入れをしない
- 返済状況を記録しておく
- 完済したら必ず完済証明書をもらう
完済後は信用情報の回復を待つことになりますが、その間も金銭管理をしっかり行い、再び借金問題に陥らないよう注意することが大切です。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
債務整理後のブラックリスト期間
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。ここでは、債務整理後のブラックリスト期間と影響について詳しく解説します。
ブラックリストに載る期間は、債務整理の方法や信用情報機関によって異なりますが、おおむね5~7年程度です。この期間中は、新たなクレジットカードの作成やローンの利用が制限されます。
信用情報機関とブラックリスト
日本には主に3つの信用情報機関があり、それぞれ異なる業態の情報を管理しています。債務整理の情報もこれらの機関に登録されます。
| 信用情報機関 | 加盟している主な業態 | 情報の特徴 |
|---|---|---|
| CIC(シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社 | クレジットカードの利用状況や携帯電話の分割払い情報 |
| JICC(日本信用情報機構) | 消費者金融、クレジットカード会社 | キャッシングやカードローンの利用状況 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫、信用保証協会 | 住宅ローンや銀行ローンの利用状況 |
債務整理方法別のブラックリスト期間
債務整理の方法と信用情報機関ごとのブラックリスト期間は以下の通りです。
| 信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 |
|---|---|---|---|---|
| CIC | 完済日から5年 | 完済日から5年 | 破産手続開始決定日から5年 | 完済日から5年 |
| JICC | 完済日から5年※ | 完済日から5年※ | 手続き終了日から5年 | 完済日から5年※ |
| KSC | 完済日から5年 | 完済日から5年または手続開始決定日から7年のいずれか遅い方 | 破産手続開始決定日から7年 | 完済日から5年 |
※2019年9月30日以前の契約・借入れでは、和解日または手続開始決定日から5年となる場合があります。
このように、完済してから5年経過すれば、多くの場合は信用情報が回復します。ただし、自己破産や個人再生など、裁判所を通した手続きの場合は、手続き開始日から一定期間が経過するまでブラックリストに載り続けることがあります。
ブラックリスト掲載による影響
ブラックリストに載っている間は、以下のような制限を受けることがあります。
- クレジットカードの作成や利用ができなくなる
- 住宅ローンや自動車ローンなどの審査に通らなくなる
- 携帯電話の分割払いができなくなる
- 奨学金などの保証人になれなくなる
- 賃貸契約の審査に影響が出ることがある
- 一部の就職活動に影響が出ることがある
ただし、現金払いでの生活に支障はありませんし、公共料金やインターネット契約など多くのサービスは利用できます。また、電子マネーやデビットカードなどは作成できる場合が多いです。
信用情報の回復までの対応策
ブラックリスト期間中は、以下のような対応策で日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
- デビットカードを活用する
- 電子マネー(チャージ式)を利用する
- プリペイドカードを利用する
- 現金での支払い習慣を身につける
- 家族名義のカードを利用する(家族カード作成は避ける)
また、ブラックリスト期間中は計画的な家計管理を心がけ、貯蓄習慣を身につけておくことが大切です。これにより、クレジットカードなしでも安定した生活を送ることができます。
信用情報の回復後にすべきこと
ブラックリスト期間が終了すると、信用情報が回復し、再びクレジットカードやローンの利用が可能になります。しかし、すぐに多くのカードを作ったり、借入れを行ったりするのは避けましょう。
信用情報回復後は、以下のポイントに注意して金融サービスを利用することをおすすめします。
- まずは審査が比較的通りやすいカードから作成する
- リボ払いなど借金体質につながる支払方法は避ける
- 支払いは必ず期日内に行う
- 無理のない範囲で利用枠を設定する
- 複数のカードを同時に作らない
債務整理後の信用情報回復は、新たな人生のスタートと考えましょう。再び借金問題に陥らないよう、計画的な資金管理を心がけることが大切です。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
債務整理の期間を短縮する方法
債務整理はできるだけ早く完了させたいと考える方も多いでしょう。ここでは、債務整理の手続き期間を短縮するための方法と、注意点について解説します。
債務整理の期間短縮は、事前の準備や専門家の選択、適切な対応によって可能になります。ただし、急ぎすぎると手続きに支障をきたすこともあるため、バランスを考えることが大切です。
債務整理の手続き期間を短縮する方法
債務整理の各段階で、期間を短縮するためにできることを見ていきましょう。
①事前準備を万全にする
債務整理を依頼する前に、以下の書類や情報を準備しておくことで、手続きの初期段階をスムーズに進めることができます。
- 借入先の一覧(会社名、支店名、契約番号、借入残高など)
- 直近の返済明細や請求書
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入証明書(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
- 家計の収支状況(収入と支出の内訳)
- 財産の状況(預貯金、不動産、車、有価証券など)
特に借入先の情報は正確に把握しておくことが重要です。不明な点がある場合は、事前に信用情報開示を行って確認しておくと良いでしょう。
②実績豊富な専門家に依頼する
債務整理の経験が豊富な弁護士や司法書士に依頼することで、手続きを効率的に進めることができます。専門家選びのポイントは以下の通りです。
- 債務整理の実績が豊富である
- 対応が迅速である(初回相談から受任通知送付まで速い)
- 債権者との交渉経験が豊富である
- 依頼者の状況に合わせた最適な債務整理方法を提案してくれる
無料相談を活用し、複数の事務所を比較検討することをおすすめします。また、オンライン対応可能な事務所を選ぶと、書類のやり取りもスムーズに進む場合があります。
③専門家からの依頼に迅速に対応する
債務整理の手続き中に、専門家から追加書類の提出や情報提供を求められることがあります。これらの依頼に素早く対応することで、手続きの停滞を防ぐことができます。
- 書類提出の依頼には速やかに応じる
- 質問や確認事項にはできるだけ早く回答する
- 連絡がとれる状態を維持する
- 重要な決断を迅速に行う
特に裁判所を通じた手続きでは、期日が定められているため、期限内の対応が非常に重要です。
④債権者数を絞る(任意整理の場合)
任意整理では、債権者の数が多いほど交渉に時間がかかります。すべての債権者を対象とするのではなく、返済が特に困難な借入先に絞って任意整理を行うことで、手続期間を短縮できる場合があります。
例えば、高金利の消費者金融やクレジットカードのキャッシングは任意整理の対象とし、低金利の銀行ローンは通常通り返済を続けるという選択も可能です。
⑤適切な債務整理方法を選択する
状況に応じた最適な債務整理方法を選ぶことも、全体の期間短縮につながります。
- 借金総額が少なく、返済能力がある場合は任意整理
- 財産がほとんどなく、返済能力もない場合は自己破産(同時廃止事件)
- 持ち家を残したい場合は個人再生
無理な方法を選ぶと、途中で手続きが行き詰まったり、やり直しが必要になったりして、かえって時間がかかることがあります。
債務整理方法別の期間短縮のポイント
各債務整理方法ごとの期間短縮のポイントを解説します。
任意整理の期間を短縮するポイント
- 過去の取引履歴や契約書類を事前に揃えておく
- 債権者との交渉実績が豊富な専門家に依頼する
- 交渉が難航しそうな債権者については、早めに妥協案を検討する
- 和解条件は現実的な範囲で設定する
個人再生の期間を短縮するポイント
- 財産や収支状況の資料を事前に整理しておく
- 個人再生の実績が豊富な弁護士に依頼する
- 最低弁済額や返済計画は現実的なものにする
- 裁判所からの質問には迅速かつ正確に回答する
自己破産の期間を短縮するポイント
- 借金に至った経緯を整理し、陳述書の作成準備をしておく
- 財産状況を正確に把握し、隠し事をしない
- 免責不許可事由に該当する行為がないか確認しておく
- 同時廃止が可能な条件を整える(財産を20万円以下にする等)
期間短縮で注意すべきこと
債務整理の期間短縮を急ぐあまり、以下のような点に注意が必要です。
- 情報や書類の虚偽申告は絶対に避ける(発覚すると手続きがやり直しになる)
- 極端に安い報酬の事務所は業務が雑になりがちなので注意
- 債権者に対して過度な要求は交渉を長引かせる原因になる
- 手続き期間より返済期間やブラックリスト期間の方が長いことを理解する
債務整理は手続きの正確性も重要です。短期間で終わらせることよりも、確実に債務問題を解決することを優先しましょう。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断
ありがとうございます。最後のセクション「債務整理の期間についてよくある質問」を作成します。
債務整理の期間についてよくある質問
ここでは、債務整理の期間に関してよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。債務整理を検討する際の参考にしてください。
Q1. 債務整理をすると、すぐに返済が止まりますか?
A1. 弁護士や司法書士に依頼すると、多くの場合即日~3日以内に債権者へ受任通知が送付されます。受任通知が債権者に届くと、法律上、取立てや督促が禁止され、返済も一時的にストップします。つまり、専門家に依頼した時点で、実質的に返済を止めることができます。
ただし、住宅ローンなど、債務整理の対象外とする借金は引き続き返済する必要があります。また、非免責債権(税金、養育費など)も同様です。
Q2. 任意整理と個人再生、自己破産はどれが早く完了しますか?
A2. 一般的に任意整理が最も早く完了します。裁判所を通さず債権者と直接交渉するため、手続きが比較的シンプルだからです。任意整理の場合、通常3~6ヶ月程度で完了します。
一方、個人再生と自己破産は裁判所を通す手続きのため、書類準備や審査に時間がかかり、完了までに6ヶ月~1年程度を要します。自己破産の中でも、同時廃止事件であれば比較的早く(5~7ヶ月程度)終わることが多いです。
Q3. 債務整理中に引っ越しや転職をしても大丈夫ですか?
A3. 基本的には問題ありませんが、必ず事前に担当の弁護士や司法書士に相談してください。住所や勤務先が変わると、裁判所への提出書類の変更が必要になる場合があります。
特に個人再生の場合は、収入状況が変わると再生計画に影響する可能性があるため、転職は慎重に検討する必要があります。また、自己破産の場合も、免責審尋などの期日に裁判所に出頭できる場所に住む必要があります。
Q4. 任意整理後の返済期間を短くすることはできますか?
A4. 可能です。任意整理後の返済期間は通常3~5年(36~60回払い)ですが、臨時収入があれば繰り上げ返済を行うことで、返済期間を短縮できます。
繰り上げ返済を希望する場合は、債権者に連絡して手続き方法を確認しましょう。なお、繰り上げ返済により早期に完済すると、信用情報の回復も早まるメリットがあります。
Q5. 個人再生の返済期間は必ず3年なのですか?
A5. 個人再生の返済期間は原則3年(36回払い)ですが、特別な事情がある場合は裁判所の許可を得て最長5年(60回払い)まで延長することができます。
特別な事情とは、子どもの教育費や医療費の負担が大きい場合、老親の介護費用がかかる場合などが該当します。一方、返済期間を3年より短くすることは原則として認められていません。
Q6. 自己破産の免責が確定するまでの間、何か制限はありますか?
A6. 自己破産の申立てから免責確定までの間は、以下のような制限を受けます。
- 一定の職業に就けない(弁護士、司法書士、公認会計士など)
- 破産管財人の許可なく財産の処分ができない
- 住所変更や氏名変更時に裁判所への届出が必要
- 裁判所から呼び出しがあれば応じなければならない
これらの制限は免責確定後に解除されます。通常、免責確定までには申立てから5~12ヶ月程度かかります。
Q7. 債務整理中に新たな借入れはできますか?
A7. 債務整理中の新たな借入れは原則として避けるべきです。債務整理は既存の借金問題を解決するための手続きであり、新たな借入れは手続きに悪影響を与える可能性があります。
特に個人再生や自己破産の場合、手続き中の借入れは裁判所に誠意がないと判断される恐れがあります。どうしても資金が必要な場合は、担当の弁護士や司法書士に相談してください。
Q8. ブラックリスト期間中でもクレジットカードは作れませんか?
A8. ブラックリスト期間中は、一般的なクレジットカードの審査には通らないことがほとんどです。ただし、以下のような代替手段があります。
- デビットカード(銀行口座と連動したカード)
- プリペイドカード(事前にチャージして使うカード)
- 保証金型クレジットカード(一部の会社で提供)
デビットカードやプリペイドカードは、信用情報に関係なく作成できるケースが多いので、ブラックリスト期間中の支払い手段として活用できます。
Q9. 債務整理後にマイホームを購入することはできますか?
A9. 債務整理後すぐにマイホームを購入するのは難しいですが、ブラックリスト期間(5~7年)が経過して信用情報が回復すれば、住宅ローンの審査に通る可能性があります。
ただし、債務整理の履歴自体は一定期間、金融機関の内部データとして残ることがあります。住宅ローンを組む際は、債務整理後の返済実績をしっかり積み重ね、頭金をできるだけ多く用意することをおすすめします。
Q10. 債務整理の手続き中に債権者から連絡があった場合はどうすればいいですか?
A10. 債務整理を弁護士や司法書士に依頼した後、債権者から直接連絡があった場合は、「○○法律事務所の△△先生に依頼しているので、そちらに連絡してください」と伝えるだけで大丈夫です。
受任通知が届いているにもかかわらず、しつこく連絡が続く場合は、担当の弁護士や司法書士に報告しましょう。貸金業者による直接の取立ては法律違反となる可能性があります。
まとめ
債務整理の期間は、選ぶ手続き方法や個々の状況によって異なりますが、おおむね手続き自体は3ヶ月~1年程度で完了します。ただし、返済期間やブラックリスト期間はさらに長期間続くことを理解しておく必要があります。
債務整理は借金問題を解決するための有効な手段ですが、手続きの流れや期間をよく理解した上で進めることが大切です。
複雑な手続きや判断に迷った場合は、杉山事務所などのおすすめ事務所の無料相談や無料診断をご利用ください。専門家のアドバイスを受けることで、最適な債務整理方法を選択できるでしょう。
最短30秒!まずは気軽にチェック!
杉山事務所の無料減額診断