相殺(そうさい)について詳しく解説
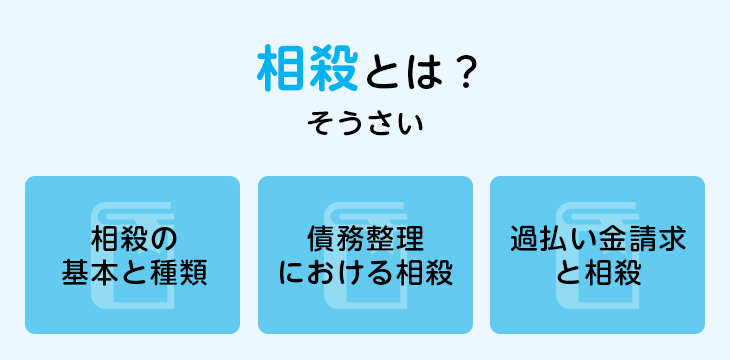
相殺とは、当事者間に互いに同種の債権・債務が存在する場合に、その債権と債務を対等額で消滅させる法律行為のことです。民法第505条に規定されている制度で、「AさんがBさんに対して持つ債権」と「BさんがAさんに対して持つ債権」を互いに打ち消し合うことができます。
債務整理や過払い金請求の場面では、金融機関が債務者の預金と貸付金を相殺したり、過払い金返還請求に対して残債務と相殺したりするケースがよくあります。この相殺の仕組みを理解することは、債務整理を進める上で非常に重要です。
相殺の基本と種類
相殺には、当事者の意思表示によって行われる「意思表示による相殺」と、法律の規定によって当然に行われる「法定相殺」があります。債務整理の場面では、特に意思表示による相殺が重要となります。
相殺の要件
相殺を行うためには、いくつかの要件を満たす必要があります。民法上の相殺の基本的な要件は以下の通りです。
| 相殺の要件 |
|
|---|---|
| 相殺の効果 |
|
この表は相殺の基本的な要件と効果を示しています。特に債権の種類や弁済期の到来が重要なポイントとなります。
相殺の種類
相殺には主に以下の種類があります。債務整理や過払い金請求の場面では、特に「意思表示による相殺」と「契約による相殺」が問題となることが多いです。
- 意思表示による相殺:当事者の一方が相殺の意思表示をすることで行われる相殺(民法第506条)
- 法定相殺:法律の規定により当然に行われる相殺
- 契約による相殺(約定相殺):契約であらかじめ相殺の条件を定めておく方法
- 差押禁止債権に対する相殺:通常は差押えが禁止されている債権に対する特例的な相殺
- 受働債権の差押えと相殺:債権が差し押さえられた場合の相殺の取扱い
このリストは相殺の主な種類を示しています。特に意思表示による相殺は、債権者(金融機関など)から債務者に対して行われることが多く、債務整理において重要な意味を持ちます。
相殺の意思表示
意思表示による相殺は、相手方に対する一方的な意思表示によって行われ、特に方式は定められていません。ただし、相殺の意思表示が明確であることが重要です。
| 相殺の意思表示の方法 | 特徴と注意点 |
|---|---|
| 書面による通知 | 最も一般的で、証拠として残る確実な方法 |
| 口頭での意思表示 | 法的には有効だが、証拠が残らないため紛争の原因になりやすい |
| 契約書等であらかじめ定める方法 | 特定の事由が生じた場合に相殺する旨を契約で定める方法(約定相殺) |
| 訴訟上の相殺 | 訴訟の中で相殺の抗弁として主張する方法 |
この表は相殺の意思表示の主な方法と特徴を示しています。債務整理の場面では、金融機関からの書面による相殺通知が一般的です。
債務整理における相殺
債務整理を検討・実施する際には、金融機関による相殺が重要な問題となることがあります。特に、預金と貸付金の相殺は、債務整理前に金融機関が取る一般的な対応です。
金融機関による預金と貸付金の相殺
債務者が債務整理の手続きを開始すると、金融機関は自行の預金と貸付金を相殺することがよくあります。この相殺は、金融機関の債権回収を確実にするための措置です。
- 相殺の対象:債務者名義の預金(普通預金、定期預金など)と同じ金融機関からの借入金
- 相殺のタイミング:債務整理の申立てを知った時点や、返済の遅延が発生した時点
- 相殺の方法:金融機関から債務者に対して相殺通知が送付される
- 相殺の効果:預金額分だけ借入金が減少し、預金は消滅する
- 事前対策の必要性:債務整理を検討する際は、事前に預金の扱いを考慮する必要がある
このリストは金融機関による預金と貸付金の相殺に関する主なポイントを示しています。債務整理を検討する際には、借入先の金融機関に預金がある場合の相殺リスクを理解しておくことが重要です。
各種債務整理と相殺の関係
債務整理の種類によって、相殺の扱いや制限が異なります。主な債務整理方法ごとの相殺の特徴を理解しておきましょう。
| 債務整理の種類 | 相殺の特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 相殺の制限はなく、金融機関は自由に相殺可能 | 手続き開始前に預金が相殺されることが多い |
| 特定調停 | 相殺の制限はなく、金融機関は自由に相殺可能 | 調停申立て前に相殺されることが一般的 |
| 個人再生 | 再生手続開始決定後も一定の条件下で相殺可能 | 再生計画認可までの間に相殺権を行使することが多い |
| 自己破産 | 破産手続開始決定前の相殺適状にあれば相殺可能 | 破産法上の相殺権の制限に注意が必要 |
この表は各種債務整理と相殺の関係を示しています。特に任意整理や特定調停では相殺の制限がないため、事前の対策が重要となります。
自己破産における相殺の特則
自己破産においては、破産法に相殺に関する特別な規定があります。破産手続開始決定を受けると、財産の処分が制限されますが、相殺権については一定の保護があります。
- 破産法第67条:破産債権者は、破産手続開始時に債務者に対して債務を負っている場合、相殺権を行使できる
- 破産手続開始決定前に相殺適状にあった場合は、原則として相殺が可能
- 破産法第71条:債務者の破産状態を知った後に取得した債権による相殺は禁止される
- 破産法第72条:債務者の破産状態を知って行った行為によって生じた債務による相殺も禁止
- 担保権付債権者の相殺:別除権として扱われ、破産手続の外で権利行使が可能
このリストは自己破産における相殺の特則に関する主なポイントを示しています。破産手続においては相殺に関する制限が詳細に定められており、特に債権取得の時期や態様が重要な要素となります。
過払い金請求と相殺
過払い金請求の場面でも、相殺は重要な問題となります。特に、消費者金融やクレジットカード会社に対する過払い金請求に対して、残債務がある場合には相殺が行われるケースが一般的です。
過払い金と残債務の相殺
過払い金請求を行う際、債権者(消費者金融など)に対して現在も債務がある場合には、過払い金と残債務が相殺されることが一般的です。
| 相殺のパターン |
|
|---|---|
| 相殺の方法 |
|
この表は過払い金と残債務の相殺に関するパターンと方法を示しています。過払い金請求を検討する際には、現在の残債務との関係を考慮することが重要です。
複数の債権者間での過払い金の充当問題
複数の金融機関から借入れがある場合、ある金融機関への過払い金を他の金融機関への債務に充当できるかという問題があります。
- 原則として、異なる債権者間での相殺はできない(債権・債務の当事者が同一である必要がある)
- 過払い金返還請求権は、その取引を行った金融機関に対してのみ行使可能
- 債権者が同じグループ会社の場合でも、法人格が異なれば原則として相殺不可
- 債権譲渡がある場合は、状況によって相殺が認められる場合がある
- 任意整理や債務整理の和解交渉の中で、柔軟な解決策を模索することは可能
このリストは複数の債権者間での過払い金の充当問題に関する主なポイントを示しています。過払い金は発生した取引先との間でのみ相殺が可能であり、他の債権者への債務には原則として充当できないことを理解しておく必要があります。
過払い金請求における相殺の事例
過払い金請求における相殺のケースとしては、以下のような事例が見られます。
- 完済後の過払い金請求:取引が完済しているため相殺の問題が生じず、過払い金全額の返還を求められる
- 取引継続中の過払い金請求:過払い金が発生しているが取引が継続中の場合、残債務と相殺される
- 複数口座での取引の場合:同一金融機関内の複数口座間で相殺が行われることがある
- 過払い金請求と同時に債務整理を行う場合:和解条件の中で相殺を含めた解決が図られる
- 訴訟での相殺の抗弁:過払い金請求訴訟に対して、貸金業者が相殺の抗弁を主張するケース
このリストは過払い金請求における相殺の主な事例を示しています。過払い金請求を検討する際には、取引状況や債務残高を考慮した上で、相殺の可能性を予測しておくことが重要です。
相殺禁止の場合と制限
法律上、相殺が禁止または制限されるケースがあります。債務整理や過払い金請求を検討する際には、これらの制限を理解しておくことが重要です。
法律で相殺が禁止されるケース
民法や破産法などで、相殺が禁止されるケースが定められています。主な相殺禁止の事例を理解しておきましょう。
| 相殺禁止の類型 | 根拠法と内容 |
|---|---|
| 不法行為に基づく債権への相殺 | 民法第509条:故意の不法行為に基づく損害賠償請求権に対する相殺は禁止 |
| 差押禁止債権への相殺 | 民法第510条:差押えが禁止されている債権に対する相殺は原則禁止(例外あり) |
| 悪意で取得した債権による相殺 | 破産法第71条:債務者の支払不能を知った後に取得した債権による相殺は禁止 |
| 破産状態を知って行った行為による相殺 | 破産法第72条:債務者の破産状態を知った後に生じた債務による相殺は禁止 |
| 預金債権の差押え後の相殺 | 民事執行法:第三債務者(銀行等)が差押え後に取得した債権による相殺は制限される |
この表は法律で相殺が禁止される主なケースを示しています。特に債務整理の場面では、破産法上の相殺禁止規定が重要な意味を持ちます。
差押禁止債権と相殺
差押禁止債権(給与の一定部分や年金など)に対する相殺については、特別な規定があります。
- 民法第510条:差押えが禁止されている債権に対しては相殺できない
- 例外:差押禁止債権の債務者が相殺する場合は可能(自分の受け取るべき給与等を自分の債務と相殺する場合)
- 給与債権:給与の一定割合は差押禁止債権だが、金融機関が預金と貸付金を相殺することは可能
- 年金債権:年金も一定範囲で差押禁止債権だが、年金が預金口座に入金された後は相殺可能
- 生活保護費:生活保護費は全額が差押禁止債権であり、相殺も原則として認められない
このリストは差押禁止債権と相殺の関係に関する主なポイントを示しています。差押禁止債権であっても、預金口座に入金された後は相殺の対象となりうる点に注意が必要です。
契約による相殺(約定相殺)とその限界
金融機関との契約では、相殺に関する特約(約定相殺)が定められていることが一般的です。しかし、この約定相殺にも法律上の限界があります。
| 約定相殺の主な内容 |
|
|---|---|
| 約定相殺の限界 |
|
この表は契約による相殺(約定相殺)の主な内容とその限界を示しています。金融機関との契約に約定相殺の条項がある場合でも、法律上の制限が優先されることがあります。
相殺への対応と注意点
債務整理や過払い金請求を検討する際には、相殺に関する対応策や注意点を理解しておくことが重要です。適切な知識と準備によって、トラブルを回避し、効果的な債務整理を進めることができます。
債務整理前に検討すべき相殺対策
債務整理を検討している場合、事前に相殺リスクへの対策を講じることが重要です。以下のような対策が考えられます。
- 借入先の金融機関の預金を事前に引き出す(ただし破産法上の否認リスクに注意)
- 債務整理の申立て前に生活に必要な資金を別の金融機関に移す
- 給与や年金の振込口座を、借入のない金融機関に変更する
- 相殺リスクを考慮した上で債務整理の方法を選択する
- 相殺される可能性がある資産を債務整理計画に織り込む
このリストは債務整理前に検討すべき相殺対策の主なポイントを示しています。ただし、債務整理直前の不自然な預金引出しは、破産手続において否認される可能性があるため注意が必要です。
相殺通知を受けた場合の対応
金融機関から相殺通知を受け取った場合、以下のような対応を検討します。
| 相殺通知受領時の対応 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 相殺の内容確認 | 相殺対象の債権・債務、金額、計算方法などを確認する |
| 相殺の有効性検討 | 相殺の要件を満たしているか、相殺禁止事由に該当しないか確認する |
| 専門家への相談 | 弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相殺通知の内容を相談する |
| 異議申立ての検討 | 相殺に法的な問題がある場合は、異議を申し立てることを検討する |
| 債務整理計画の修正 | 相殺の結果を踏まえて、債務整理の計画を修正する |
この表は相殺通知を受けた場合の対応方法を示しています。相殺通知の内容を正確に理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
相殺をめぐる紛争と解決方法
相殺をめぐって紛争が生じた場合の解決方法について理解しておきましょう。
- 交渉による解決:債権者と直接交渉し、相殺の範囲や方法について合意を目指す
- 専門家による代理交渉:弁護士や司法書士などの専門家に依頼して交渉を行う
- 裁判外紛争解決手続(ADR):金融ADRなどの制度を利用して中立的な第三者の仲介で解決を図る
- 訴訟による解決:相殺の有効性や金額について裁判所の判断を求める
- 破産手続内での異議申立て:破産手続内で相殺に対する異議を申し立てる
このリストは相殺をめぐる紛争の主な解決方法を示しています。紛争の内容や状況に応じて、適切な解決方法を選択することが重要です。
まとめ
相殺は、お互いに債権・債務関係がある場合に、それらを対等額で消滅させる重要な法的手続きです。債務整理や過払い金請求の場面では、借金の負担を大きく軽減できる可能性がある有効な手段といえます。
相殺を活用するためには、相互性や同種性などの要件を満たす必要があり、また一定の制限もあります。過払い金がある場合には、その過払い金返還請求権と現在の借金を相殺することで、借金を減額または消滅させることができます。
債務整理や過払い金請求を検討している場合は、まず取引履歴を取り寄せて過払い金の有無を確認し、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、相殺を含めた最適な債務整理の方法を見つけることができるでしょう。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



