債権届出(さいけんとどけで)について詳しく解説
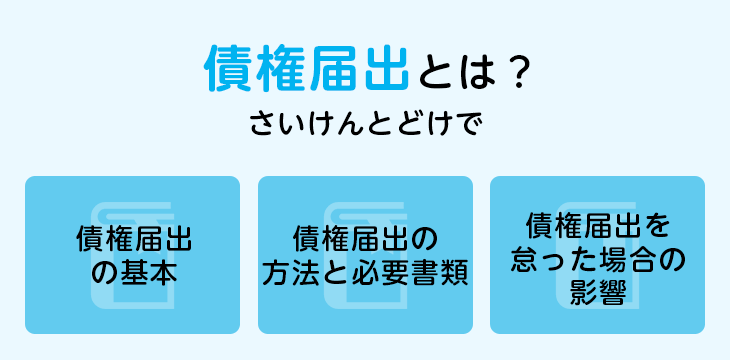
債権届出とは、主に自己破産や民事再生などの法的債務整理手続きにおいて、債権者が自分の債権(お金を返してもらう権利)の存在を裁判所に申し出る手続きです。債権者が債務整理手続きに参加し、配当や弁済を受けるためには、この届出が必要となります。
債務整理を行う際、債務者は債権者一覧表を提出しますが、それだけでは債権の内容が確定しません。各債権者は債権届出を行い、その内容が調査・確定されることで、正式に債務整理手続きの対象となる債権として認められます。
債権届出の基本
債権届出は、債務整理手続きにおいて債権者が自分の債権を正式に主張するための手続きです。債権者は、債権の種類や金額などを記載した書面を裁判所に提出します。
債権届出は主に以下のような法的債務整理手続きで必要となります。任意整理では基本的に必要ありません。
- 自己破産手続き
- 民事再生手続き(個人再生を含む)
- 会社更生手続き
- 特別清算手続き
これらの手続きでは、裁判所から債権者に対して債権届出を促す通知が送られます。債権者はその通知に従って、定められた期間内に債権届出書を提出する必要があります。
債権届出の目的
債権届出には、主に以下のような目的があります。
| 債権届出の主な目的 |
|
|---|
この表は債権届出の主な目的を示しています。債権届出を行わなければ、原則として債務整理手続きに参加できず、配当や弁済を受けることができません。
届出対象となる債権
債権届出の対象となるのは、債務整理手続き開始時点で存在する債権です。主に以下のような債権が届出の対象となります。
- 金銭債権(借入金、売掛金、未払金など)
- 非金銭債権(物品の引渡請求権など)
- 条件付債権(保証債務など)
- 将来の請求権(継続的契約の解除に伴う損害賠償請求権など)
- 優先債権(担保権付き債権など)
ただし、手続きの種類によって、届出が不要な債権もあります。例えば、個人再生では一般的に住宅ローンは再生手続の対象外となり、別除権として扱われるため届出は不要です。
債権届出の方法と必要書類
債権届出は、裁判所から送られてくる「債権届出書」の用紙に必要事項を記入して提出します。債権届出の方法と必要書類について解説します。
債権届出の期間
債権届出には期間が設けられています。この期間は「債権届出期間」と呼ばれ、裁判所によって決定されます。
一般的に、自己破産では破産手続開始決定から約2週間〜1ヶ月程度、個人再生では再生手続開始決定から約1ヶ月程度の期間が設定されることが多いです。
債権届出期間内に届出ができなかった場合でも、債権調査期日前までであれば事後届出が可能です。ただし、既に配当が行われた後は、その配当分については権利を主張できなくなります。
債権届出書の記載事項
債権届出書には、主に以下のような事項を記載します。
| 債権届出書の主な記載事項 |
|
|---|
この表は債権届出書に記載する主な事項を示しています。正確な情報を記載することが重要です。特に債権額は、元本、利息、遅延損害金などを区別して記載します。
債権届出に必要な添付書類
債権届出の際には、債権の存在と内容を証明するための書類を添付する必要があります。主な添付書類は以下の通りです。
- 契約書や金銭消費貸借契約書のコピー
- 取引明細書や残高証明書
- 担保権に関する書類(抵当権設定登記事項証明書など)
- 直近の取引履歴や返済予定表
- 催告書や請求書のコピー
- 委任状(代理人が届出を行う場合)
添付書類は債権の種類や状況によって異なります。裁判所からの通知に記載されている指示に従って、必要な書類を用意することが重要です。
債権届出の流れ
債権届出の一般的な流れは以下の通りです。
- 裁判所から債権者に対して債権届出の通知が送付される
- 債権者が債権届出書に必要事項を記入し、必要書類を添付する
- 債権届出書を裁判所に提出する(郵送または持参)
- 裁判所が債権届出を受理し、債権者表に記載する
- 債権調査期日において債権の内容が調査される
- 債権が確定し、弁済や配当の対象となる
上記の流れは一般的なものであり、実際の手続きは事案によって異なる場合があります。また、債権者によっては専門の代理人(弁護士など)に依頼して手続きを進めることもあります。
債権調査と債権確定
届け出られた債権は、そのまま確定するわけではありません。「債権調査期日」において、届出内容の調査が行われ、その結果に基づいて債権が確定します。
債権調査期日の意義
債権調査期日は、債権の存在や金額を確定させるための公式な手続きです。裁判所の主宰のもと、債務者(またはその代理人)、破産管財人(または再生委員)、債権者などが出席して行われます。
債権調査期日では、届け出られた債権の内容が正確かどうかを調査し、債権の存否や金額について「認否」(認めるか認めないか)が行われます。
債権の認否
債権調査における認否は、主に以下の4種類があります。
| 債権の認否の種類 |
|
|---|
この表は債権調査における認否の種類を示しています。認否の結果は「債権者表」に記載され、その内容によって債権の取扱いが決まります。
債権が「認める」とされた場合、その債権は確定し、配当や弁済の対象となります。一方、「認めない」とされた場合、債権者は別途「債権確定訴訟」を提起する必要があります。
債権確定訴訟
債権調査において債権が「認めない」とされた場合、債権者は「債権確定訴訟」を提起することができます。この訴訟は、債権の存在と金額を裁判所に確定してもらうための手続きです。
債権確定訴訟を提起する期間は限定されており、一般的には債権調査期日から1ヶ月以内とされています。この期間内に訴訟を提起しないと、債権は「存在しない」と確定してしまいます。
債権確定訴訟では、債権者が債権の存在と金額を証明する必要があります。裁判所の判断によって債権が確定すると、その内容に基づいて配当や弁済が行われます。
債権届出を怠った場合の影響
債権者が債権届出を行わなかった場合、様々な不利益を被る可能性があります。債権届出の重要性を理解するために、届出を怠った場合の影響について解説します。
配当・弁済を受けられない
最も重大な影響は、配当や弁済を受けられなくなることです。債権届出を行わなかった債権は、原則として債務整理手続きにおける配当や弁済の対象外となります。
例えば、自己破産では債務者の財産が換価され、債権者に配当されますが、債権届出を行わなかった債権者はこの配当を受けることができません。
また、個人再生では再生計画に基づいて弁済が行われますが、債権届出を行わなかった債権者は再生計画の対象外となり、弁済を受けられません。
債権者集会での議決権がない
債権届出を行わなかった債権者は、債権者集会での議決権を持つことができません。これにより、再生計画案の決議などに参加できなくなります。
例えば、個人再生では再生計画案が債権者の決議にかけられますが、債権届出を行わなかった債権者はこの決議に参加できず、自分の意見を反映させることができません。
免責の効力から除外されない
債権届出を行わなかったとしても、自己破産における免責の効力からは除外されません。つまり、債務者が免責を受けると、届出を行わなかった債権も含めて、原則としてすべての債務が免除されます。
このため、債権者が債権届出を怠ると、配当も受けられず、債務も免除されるという「最悪の結果」になる可能性があります。ただし、非免責債権(租税等)は例外で、免責後も請求が可能です。
| 債権届出を怠った場合の主な影響 |
|
|---|
この表は債権届出を怠った場合の主な影響を示しています。債権者にとって大きな不利益となるため、通知を受けた場合は必ず対応することが重要です。
よくある質問
債権届出の通知が届かない場合はどうすればよいですか?
債務者が債権者の住所を正確に把握していない場合や、債権譲渡が行われている場合などに、債権届出の通知が届かないことがあります。
債務者が債務整理を行っていることを知った場合は、自ら裁判所に問い合わせて、債権届出手続きについて確認することをおすすめします。裁判所の破産部や再生部に連絡すれば、必要な情報を得ることができます。
債権届出期間を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
債権届出期間を過ぎた場合でも、債権調査期日前までであれば「事後届出」として債権届出を行うことができます。ただし、既に配当が行われている場合は、その配当分については権利を主張できません。
債権調査期日後は、原則として債権届出が認められなくなります。ただし、「免責不許可事由該当申立」や「異議申述」など、別の手続きで債権の存在を主張できる場合もあります。具体的な対応については、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
債権届出は債権者自身が行わなければならないのですか?
債権届出は債権者本人だけでなく、代理人を通じて行うこともできます。多くの金融機関や大手企業は、弁護士などの専門家に依頼して債権届出手続きを行っています。
代理人に依頼する場合は、委任状が必要となります。また、代理人の費用は債権者の負担となるため、費用対効果を考慮して判断することが重要です。少額の債権の場合は、自分で手続きを行った方が経済的なケースもあります。
債権調査で「認めない」とされた場合、必ず訴訟を提起する必要がありますか?
債権調査で「認めない」とされた場合、その債権を確定させるためには債権確定訴訟を提起する必要があります。しかし、訴訟にはコストと時間がかかるため、債権額が少額の場合や回収見込みが低い場合は、訴訟を提起しないという選択肢もあります。
訴訟を提起しない場合、その債権は「存在しない」と確定し、配当や弁済を受けることができなくなります。債権額や回収可能性、訴訟コストなどを総合的に考慮して判断することが重要です。
まとめ
債権届出は、自己破産や民事再生などの法的債務整理手続きにおいて、債権者が自分の債権の存在を裁判所に申し出る重要な手続きです。この手続きを通じて、債権の内容が調査・確定され、配当や弁済の対象となります。
債権届出書には、債権者の情報、債権の種類と額、債権の発生原因、担保権の有無などを記載し、債権の存在を証明する書類を添付します。債権届出期間内に提出することが原則ですが、債権調査期日前までであれば事後届出も可能です。
届け出られた債権は、債権調査期日において調査され、「認める」「一部認める」「認めない」「留保」のいずれかの認否が行われます。「認めない」とされた場合は、債権確定訴訟を提起する必要があります。
債権届出を怠ると、配当や弁済を受けられない、債権者集会での議決権がないなどの不利益を被ります。ただし、免責の効力からは除外されないため、債務は免除されることになります。
債権者にとって、債権届出は債務整理手続きにおける権利を確保するための重要なステップです。裁判所からの通知を受けた場合は、速やかに対応することをおすすめします。不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが賢明です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



