債権(さいけん)について詳しく解説
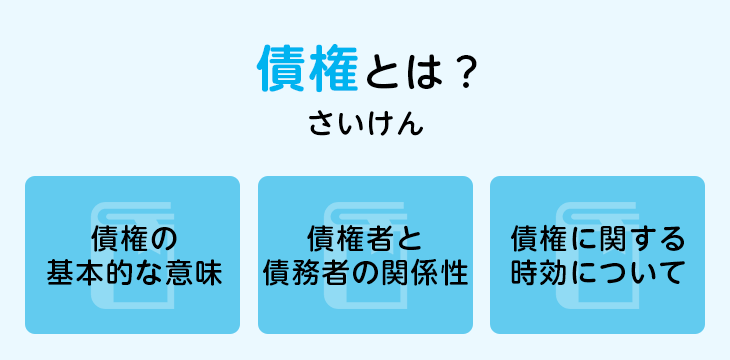
債権とは、特定の人に対して一定の行為を請求できる権利のことです。債務整理や過払い金請求の場面では、貸金業者やクレジット会社が持つ「お金を返してもらう権利」を指すことが多いです。
債務整理や過払い金請求において重要な「債権」について詳しく解説します。債権の基本的な意味から、債務整理における役割、さらには過払い金請求との関係性まで幅広く説明します。
債権の基本的な意味
債権とは、特定の相手(債務者)に対して、一定の行為を要求できる権利のことです。民法上の概念で、お金を貸した側が持つ「返してもらう権利」が典型的な例です。
例えば、消費者金融からお金を借りた場合、消費者金融は「貸したお金を返してもらう権利」を持ちます。この権利が債権であり、消費者金融は債権者、借りた人は債務者となります。
| 債権の主な特徴 | 特定の相手に対してのみ行使できる権利です |
|---|---|
| 債権の例 |
|
上記の表は債権の主な特徴と具体例を示しています。債務整理においては特に貸金債権が重要になりますが、過払い金請求では立場が逆転し、借主が債権者になるケースもあります。
債権の種類と債務整理との関係
債務整理の場面では、いくつかの種類の債権が関わってきます。それぞれの特徴を理解することで、債務整理の全体像がつかみやすくなります。
- 貸金債権:消費者金融やカードローンなど、お金を貸したことによる債権
- 売買代金債権:クレジットカードでの買い物など商品購入に関する債権
- 保証債権:連帯保証人などに対して持つ債権
- 優先債権:債務整理の中でも優先的に弁済される債権(税金など)
上記のリストは債務整理で関わる主な債権の種類です。債務整理の方法(任意整理、個人再生、自己破産)によって、これらの債権がどう扱われるかが変わってきます。
債務整理の各手続きと債権の扱い
| 任意整理 | 債権者と個別に交渉し、利息カットや元金の分割払いなどを行います。債権そのものは消滅しません。 |
|---|---|
| 個人再生 | 裁判所の管理のもと、債権額の一定割合を3〜5年で返済します。残りの債権は消滅します。 |
| 自己破産 | 裁判所の決定により、原則としてすべての債権が免責されます(消滅します)。ただし税金や養育費などの一部債権は残ります。 |
この表は各債務整理手続きにおける債権の扱いを比較したものです。債務の状況に応じて、最適な手続きを選ぶことが重要になります。
債権者と債務者の関係性
債権者とは債権を持つ側、つまり「お金を返してもらう権利を持つ人」のことです。一方、債務者は債務を負う側、つまり「お金を返す義務がある人」を指します。
債務整理では、多くの場合、消費者金融やクレジットカード会社などが債権者、借入れをしている個人が債務者となります。しかし過払い金請求では、この関係が逆転することもあります。
| 債権者の権利 | |
|---|---|
| 債務者の義務 |
|
上記の表は債権者と債務者それぞれの基本的な権利と義務を示しています。債務整理を進める際には、これらの関係性を理解することが重要です。
債権譲渡と債権回収について
債権譲渡とは、債権者がその債権を第三者に売却することです。長期滞納などの場合、消費者金融などの債権者は債権回収会社に債権を譲渡することがあります。
債権譲渡が行われると、債務者は新しい債権者(債権回収会社など)に対して支払いを行うことになります。この場合、債務者には通知が届きます。
- 債権譲渡の通知を受け取る
- 新しい債権者(譲受人)の確認をする
- 必要に応じて取引履歴などの開示を求める
- 新しい債権者との間で返済や債務整理の交渉を行う
上記のリストは債権譲渡が行われた際の対応の流れです。債権譲渡が行われたからといって、債務そのものが増えたり厳しくなったりするわけではありません。
債権回収との関係
債権回収会社は、金融機関などから譲り受けた債権の回収を専門に行う会社です。電話や文書での請求、場合によっては法的手続きを行うこともあります。
債権回収会社からの連絡があった場合でも、過度に動揺する必要はありません。法律の範囲内での請求行為しかできませんので、冷静に対応しましょう。
| 債権回収会社の主な行動 | |
|---|---|
| 債権回収会社にできないこと |
|
この表は債権回収会社が行える行動と行えない行動を比較したものです。違法な取立てを受けた場合は、弁護士や司法書士、または貸金業協会に相談することができます。
過払い金請求における債権の逆転現象
過払い金請求では、通常の債権債務関係が逆転します。過去に利息制限法を超える金利で支払いを続けていた場合、その過払い分を取り戻す権利(債権)が発生します。
この場合、借主だった消費者が「過払い金返還請求権」という債権を持つ債権者となり、貸主だった金融機関が債務者となります。立場が逆転するのです。
| 通常の債権関係 | 金融機関(債権者)→ 消費者(債務者) |
|---|---|
| 過払い金発生時の債権関係 | 消費者(債権者)→ 金融機関(債務者) |
上記の表は過払い金が発生した場合の債権債務関係の逆転を示しています。この権利を行使するのが過払い金請求です。
過払い金返還請求権の特徴
- 利息制限法超過分が対象となります
- 請求権の時効は原則10年です
- 貸金業者が廃業していても請求できる場合があります
- 相殺や一部弁済の計算が複雑になることがあります
上記のリストは過払い金返還請求権の主な特徴です。過払い金請求は専門的な計算が必要なため、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
債権に関する時効について
債権には時効があります。一定期間、権利行使(請求)がなければ、債権は時効によって消滅する可能性があります。2020年4月の民法改正により、債権の消滅時効は原則5年となりました。
ただし、改正前に発生した債権については旧法が適用される場合もあります。また、最後の取引や支払いから時効が進行するため、計算には注意が必要です。
| 債権の種類と時効期間 |
|
|---|---|
| 時効の中断事由 |
上記の表は債権の種類ごとの時効期間と時効を中断する主な事由をまとめたものです。時効が成立しそうな債務については、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
債権とは、特定の相手に対して一定の行為を請求できる権利のことで、債務整理や過払い金請求において非常に重要な概念です。通常、金融機関などが「お金を返してもらう権利」として債権を持ちますが、過払い金請求では立場が逆転します。
債務整理では、債権がどのように扱われるかが手続きごとに異なります。任意整理では減額や分割払いの交渉、個人再生では一部弁済後の免除、自己破産では原則として全額免責されます。
また、債権には時効があり、一定期間行使されなければ消滅する可能性があります。2020年4月の民法改正により、一般の債権は原則5年となりました。
債権譲渡や債権回収会社との対応も債務整理では重要な場面です。法律の範囲内での請求しかできないことを理解し、冷静に対応することが大切です。
債務整理や過払い金請求を検討されている方は、債権の概念を理解した上で、ご自身の状況に最適な解決策を専門家と相談しながら進めていくことをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



