連帯保証人(れんたいほしょうにん)について詳しく解説
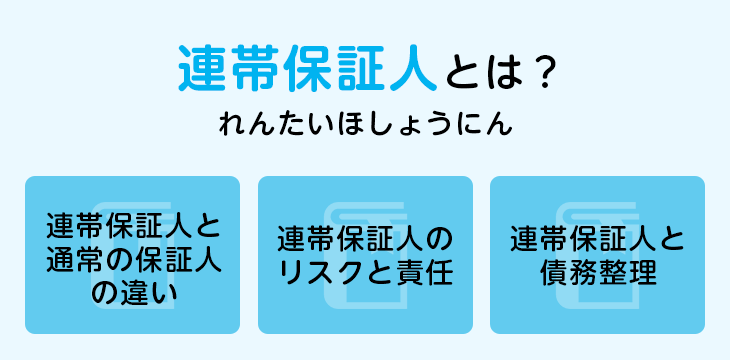
連帯保証人とは、主たる債務者が債務を返済できなくなった場合に、債務者と同等の責任を負って返済する義務を持つ人のことです。通常の保証人と異なり、催告の抗弁権や検索の抗弁権などの権利がなく、債権者から請求があればすぐに支払いの義務が生じます。
キャッシングやカードローン、住宅ローンなどの借入れを行う際に、連帯保証人を求められるケースが多くあります。連帯保証人になることは大きなリスクを伴うため、その役割と責任を十分に理解することが重要です。
連帯保証人と通常の保証人の違い
連帯保証人と通常の保証人(単純保証人)には、法的な権利と責任において重要な違いがあります。通常の保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という二つの重要な権利が認められていますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
| 催告の抗弁権 | 通常の保証人は、債権者からの請求に対して「まず主債務者に請求してください」と主張できる権利です。連帯保証人にはこの権利がないため、債権者は最初から連帯保証人に請求できます。 |
|---|---|
| 検索の抗弁権 | 通常の保証人は、主債務者に財産があれば「まずその財産から回収してください」と主張できる権利です。連帯保証人にはこの権利もないため、債務者に支払能力があっても請求されたら支払わなければなりません。 |
| 責任の範囲 |
この表は連帯保証人と通常の保証人の権利の違いを示しています。連帯保証人は通常の保証人より法的に不利な立場にあり、債権者からすると回収がしやすい保証形態となっています。
連帯保証人のリスクと責任
連帯保証人になることは、想像以上に大きなリスクを伴います。主債務者が返済不能になった場合、連帯保証人は自分の財産や収入から返済しなければなりません。以下は連帯保証人が負うリスクと責任です。
- 主債務者と同等の返済義務を負うため、全額の支払い責任があります
- 債権者は債務者と連帯保証人のどちらに対しても自由に請求できます
- 主債務者の破産や債務整理をしても、連帯保証人の債務は消滅しません
- 連帯保証人自身の信用情報に影響が出る可能性があります
- 主債務者が行方不明になっても返済義務は続きます
これらのリスクは連帯保証人にとって重大な問題となります。特に親族間での連帯保証の場合、関係性の悪化につながるケースも少なくありません。また、自分自身のローンやクレジットカードの審査にも影響する可能性があるため注意が必要です。
連帯保証人と債務整理
債務整理を行う場合、連帯保証人の存在は重要な考慮点となります。主債務者が債務整理をすると、通常は連帯保証人への請求が強まります。以下は債務整理の種類ごとの連帯保証人への影響です。
| 任意整理 | 主債務者が任意整理をすると、連帯保証人には全額の請求が来る可能性があります。主債務者と連帯保証人が同時に任意整理を行うケースもありますが、債権者の同意が必要です。 |
|---|---|
| 個人再生 | 主債務者が個人再生をしても、連帯保証人の債務は減額されません。債権者は減額された分を連帯保証人に請求できるため、むしろ連帯保証人の負担は増加します。 |
| 自己破産 | 主債務者が自己破産で免責を受けても、連帯保証人の債務は消滅しません。債権者は全額を連帯保証人に請求することが一般的です。このため連帯保証人も債務整理を検討する必要が生じることがあります。 |
この表は主債務者の債務整理が連帯保証人に与える影響を示しています。債務整理を検討する際は、連帯保証人への影響も考慮し、事前に専門家に相談することが重要です。連帯保証人にも債務整理の方法について説明しておくことが望ましいでしょう。
連帯保証人自身が債務整理をする場合
連帯保証人自身も返済が困難になった場合は、債務整理を検討することができます。連帯保証債務も債務整理の対象となりますが、いくつか注意点があります。
- 任意整理:主債務者への影響を考慮しつつ、分割払いなどの和解を交渉できます
- 個人再生:連帯保証債務も再生計画に含めることができますが、主債務者への請求は継続します
- 自己破産:連帯保証債務も免責の対象となりますが、債権者は主債務者への請求を強化します
- 事前準備:債務整理前に主債務者と連絡を取り、状況を説明しておくことが望ましいです
連帯保証人が債務整理をする場合の流れと各手続きにおける注意点です。連帯保証人の債務整理は主債務者との関係性にも影響するため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることをおすすめします。
連帯保証人になる前に確認すべきこと
連帯保証人の依頼を受けた場合、安易に引き受けることは避け、以下の点を十分に確認することが重要です。特に家族や親族からの依頼は断りにくいものですが、将来のトラブルを防ぐためにも慎重な判断が必要です。
- 借入の目的と金額を詳しく確認する
- 返済計画の実現可能性を冷静に判断する
- 主債務者の収入状況や他の借入状況を把握する
- 自分が支払うことになった場合の対応策を考えておく
- 契約書の内容を必ず確認し、不明点は質問する
- 債務の一部だけの保証など、条件交渉の可能性を探る
連帯保証人になる前のチェックポイントです。特に重要なのは、「最悪の場合、自分が全額支払うことになっても問題ないか」という視点で判断することです。感情的な判断ではなく、冷静な経済判断が求められます。
連帯保証人に関する法律の改正点
2020年4月に施行された改正民法では、連帯保証に関する規定が大きく変更されました。特に個人が事業用融資の連帯保証人になる場合の規制が強化されています。主な改正点は以下の通りです。
| 極度額の設定 | 貸金等の根保証契約において、極度額(上限額)の定めが必要になりました。極度額の定めがない契約は無効となります。 |
|---|---|
| 事業用融資の保証制限 | 事業のための借入に対する個人の連帯保証については、公証人による意思確認手続きが必要となりました。経営者など一定の例外はあります。 |
| 情報提供義務 |
|
この表は改正民法における連帯保証制度の主な変更点を示しています。これらの改正は個人の連帯保証人を保護する目的で行われましたが、すべての連帯保証に適用されるわけではないため、契約内容の確認は依然として重要です。
まとめ
連帯保証人は、主債務者が返済できない場合に債務者と同等の責任を負う重い立場です。通常の保証人と違い、催告の抗弁権や検索の抗弁権がなく、債権者から直接請求されればすぐに支払わなければなりません。
債務整理との関係では、主債務者が債務整理をしても連帯保証人の債務は消滅せず、むしろ連帯保証人への請求が強まることが一般的です。連帯保証人自身も債務整理は可能ですが、主債務者との関係性にも配慮が必要です。
2020年の改正民法により、事業用融資の個人連帯保証に対する規制強化や情報提供義務の明確化など、連帯保証人を保護する制度が整備されました。しかし依然としてリスクは大きいため、連帯保証人になる前には十分な検討と情報収集が欠かせません。
債務問題でお悩みの場合は、連帯保証人の立場であっても債務整理の選択肢はあります。早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談し、最適な解決策を見つけることをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



