求償権(きゅうしょうけん)について詳しく解説
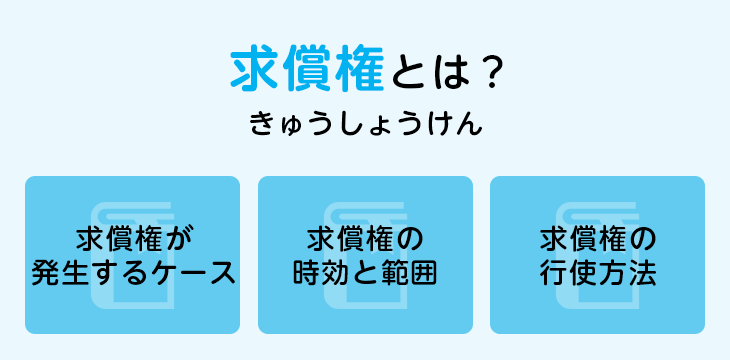
求償権とは、他人の債務を弁済した者が、本来支払うべき債務者に対して支払った金額の返還を求める権利のことです。債務整理において重要なのは、連帯保証人や連帯債務者が債務を代わりに支払った場合に発生する求償権の問題です。
求償権は民法に規定されている権利で、保証人が主債務者に代わって債務を弁済した場合や、連帯債務者の一人が債務全額を支払った場合などに発生します。債務整理を行う際には、この求償権の発生と対応について理解しておくことが重要です。
求償権の基本概念
求償権は、本来負担すべきではない債務を弁済した人が、本来の債務者に対して支払った金額の返還を求める権利です。弁済によって債権者の権利は消滅しますが、弁済者は求償権という新たな権利を取得します。
民法では、保証債務の弁済による求償権(民法459条)や連帯債務者間の求償権(民法442条)などが規定されています。これらは債務整理や過払い金請求の場面でしばしば問題になります。
| 法的根拠 | 民法第442条、第459条など |
|---|---|
| 求償権者 |
|
| 求償権の内容 | 弁済した元本、利息、損害金、費用など |
この表は求償権の基本的な概要をまとめたものです。求償権は様々な状況で発生する可能性があり、債務整理を検討する際には注意が必要です。
求償権が発生するケース
債務整理や過払い金請求に関連して求償権が発生する主なケースを理解しておくことが重要です。以下のような状況で求償権が発生します。
- 保証人が主債務者に代わって債務を弁済した場合
- 連帯債務者の一人が債務の全部または自己の負担部分を超える額を弁済した場合
- 物上保証人(自分の財産を担保に提供した人)の財産が差し押さえられた場合
- 第三者が債務者のために弁済した場合
特に多いのは、保証人が主債務者の債務を代わりに返済したケースです。例えば、友人や家族の借金の保証人になっていた人が、主債務者の返済が滞ったために代わりに支払うことになった場合などです。
また、夫婦や親子で住宅ローンなどの連帯債務者になっているケースも多く、一方が債務整理をする場合に求償権の問題が発生することがあります。
債務整理における求償権の問題
債務整理を行う際、求償権は大きな問題となることがあります。特に自己破産や個人再生などの法的整理においては、主債務者の債務は免責されても、保証人に対する債権者の請求権は消滅しません。
そのため、主債務者が債務整理をした後、保証人が債務を弁済すると、保証人から主債務者に対して求償権が発生します。これは主債務者にとって新たな債務問題を引き起こす可能性があります。
| 債務整理の種類 | 求償権に関する問題点 |
|---|---|
| 任意整理 | 保証人に対する請求は継続。保証人が弁済すると求償権が発生 |
| 個人再生 | 保証債務は減額されない。保証人からの求償権は再生計画に含まれない場合あり |
| 自己破産 | 免責後に保証人が弁済した場合の求償権は免責されない(免責後の新債務) |
この表は各債務整理手続きにおける求償権の問題点をまとめたものです。債務整理を検討する際には、保証人や連帯債務者の存在を確認し、求償権の問題も含めて対策を考える必要があります。
求償権の時効と範囲
求償権にも消滅時効があります。2020年4月の改正民法施行後は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効となります。改正前の債権は原則として10年の時効です。
求償権の範囲は、弁済した元本だけでなく、利息や遅延損害金、必要費なども含まれます。例えば、主債務者の債務を弁済するために保証人が負担した弁護士費用なども求償の対象になる可能性があります。
| 求償権の時効 |
|
|---|---|
| 求償できる範囲 |
|
この表は求償権の時効と範囲についてまとめたものです。債務整理を検討する際には、求償権の消滅時効や求償できる範囲も考慮する必要があります。
求償権の行使方法
求償権を行使するためには、まず主債務者に対して求償の意思表示を行います。支払いがない場合は、裁判手続きによって債務名義を取得し、強制執行を行うことも可能です。
ただし、主債務者が債務整理をしていたり、資力がなかったりする場合は、求償権を行使しても実効性がない可能性があります。そのため、事前に主債務者の資力や債務状況を確認することが重要です。
上記は求償権を行使する際の一般的な流れです。ただし、主債務者との関係性や状況によっては、別の解決策を模索することも重要です。
よくある質問
自己破産後に保証人から求償権を行使されたらどうなりますか?
自己破産による免責決定後に保証人が債務を弁済して発生した求償権は、免責の対象外となる「免責後の新債務」と考えられています。そのため、保証人は免責後でも求償権を行使できる可能性があります。
ただし、裁判所の判断によっては、免責前の保証債務に基づく求償権は免責の対象になるとした事例もあります。具体的な状況に応じて弁護士に相談することをおすすめします。
連帯保証人と通常の保証人では求償権に違いがありますか?
基本的な求償権の性質に違いはありませんが、連帯保証人は催告の抗弁権や検索の抗弁権を持たないため、より早い段階で債務の弁済を求められる可能性があります。その結果、求償権も早期に発生することがあります。
また、2020年4月の改正民法施行後は、事業用融資以外の個人保証については、極度額(上限額)の定めのない包括根保証契約は無効となりました。これにより、保証人の責任範囲が明確になり、求償権の範囲も限定される場合があります。
過払い金が発生している債務を保証人が返済した場合、求償権はどうなりますか?
過払い金が発生している債務を保証人が返済した場合、法律上は主債務者に対する求償権が発生します。しかし、過払い金の存在が後から判明した場合、保証人は本来支払う必要のなかった金額も支払っていることになります。
このような場合、保証人は貸金業者に対して過払い金返還請求を行える可能性があります。また、主債務者に対する求償権の範囲も、過払い金を控除した正当な債務額に限られるべきと考えられます。
まとめ
求償権は、他人の債務を弁済した者が本来の債務者に対して支払った金額の返還を求める権利です。債務整理や過払い金請求において、保証人や連帯債務者が関わる場合には、この求償権の問題を考慮する必要があります。
特に主債務者が債務整理をする場合、保証人が債務を弁済すると求償権が発生し、主債務者にとって新たな債務問題となる可能性があります。自己破産の場合、免責後に発生した求償権は免責の対象外となることが多いため、注意が必要です。
求償権の範囲は弁済した元本だけでなく、利息や遅延損害金、必要費なども含まれます。また、2020年4月の改正民法施行後は、求償権の時効期間は原則として権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年となります。
債務整理を検討している方は、保証人や連帯債務者の有無を確認し、求償権の問題も含めて専門家に相談することをおすすめします。特に家族や友人が保証人になっている場合は、彼らへの影響も考慮した上で、最適な解決策を模索することが大切です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



