保証人(ほしょうにん)について詳しく解説
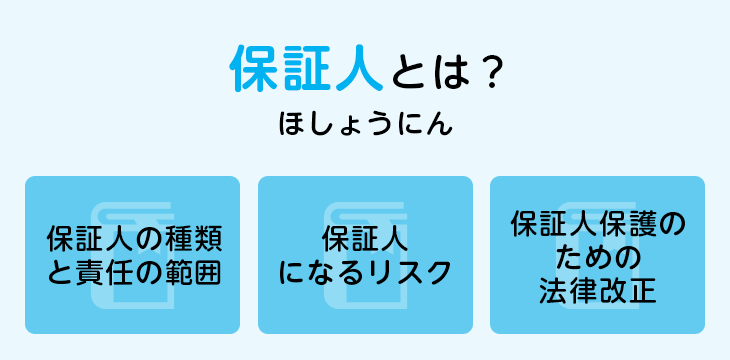
保証人とは、主たる債務者(お金を借りた人)が債務を返済できなくなった場合に、その債務を肩代わりして支払う義務を負う人のことです。保証人は主たる債務者の信用を補完する役割を果たし、万が一の場合に債権者(お金を貸した人)への返済を保証します。
たとえば、友人や家族がローンを組む際に「保証人になってほしい」と頼まれて承諾すると、その方が返済できなくなった場合に、あなたが代わりに支払わなければならない責任を負うことになります。債務整理において保証人の存在は重要な要素となります。
保証人の種類と責任の範囲
保証人には複数の種類があり、それぞれ責任の範囲や債権者からの請求を受ける条件が異なります。主な保証人の種類と特徴を見ていきましょう。
| 保証人の種類 |
|
|---|
上記の表は保証人の主な種類と特徴を示しています。日本の金融実務では、個人向けローンのほとんどで連帯保証人が求められることが多く、これは保証人にとって責任が最も重い形態です。
通常保証人と連帯保証人の違い
通常保証人と連帯保証人は、債権者からの請求時期や抗弁権の有無などで大きく異なります。その主な違いを以下にまとめました。
| 通常保証人 | |
|---|---|
| 連帯保証人 |
|
この表は通常保証人と連帯保証人の主な違いを示しています。連帯保証人は主たる債務者と同様の責任を負うため、債務整理を検討する際は特に注意が必要です。
保証人になるリスク
保証人になることには様々なリスクが伴います。特に連帯保証人の場合、そのリスクは非常に大きいものです。保証人になる前に以下のリスクを十分に理解しておくことが大切です。
- 主たる債務者が返済不能になると、保証した全額を支払う義務が生じる
- 連帯保証人の場合、いきなり請求を受ける可能性がある
- 主たる債務者の返済状況を把握しづらく、突然の請求に備えることが難しい
- 保証債務の支払いにより自身の生活が圧迫される恐れがある
- 支払いができない場合、自分自身も債務整理や自己破産を検討せざるを得なくなる可能性がある
- 保証人になったことでブラックリストに載るわけではないが、代位弁済すると信用情報に記録される
このリストは保証人になることの主なリスクを示しています。特に注意すべきは、自分の収入や資産で対応できる範囲を超えた保証をすると、自身の生活基盤を失うリスクがあることです。
主たる債務者の債務整理と保証人への影響
主たる債務者が債務整理をした場合、保証人にはどのような影響があるのでしょうか。債務整理の種類によって影響は異なります。
- 主たる債務者が破産した場合:主たる債務者の債務は免責されますが、保証人の保証債務は消滅しません。債権者は保証人に対して全額の支払いを請求することができます。
- 主たる債務者が民事再生をした場合:再生計画で認められた減額は保証人には及びません。保証人は元の債務額について保証責任を負います。
- 主たる債務者が任意整理をした場合:和解内容(減額や分割払いなど)は保証人には及びず、保証人は原則として元の債務について保証責任を負います。
上記のリストは主たる債務者が債務整理をした場合の保証人への影響を示しています。いずれの場合も、主たる債務者の債務整理によって保証人の責任は軽減されないことが重要なポイントです。
保証人への請求と対応
主たる債務者が債務整理をすると、債権者は保証人に対して請求を行うことが多くなります。保証人への請求があった場合の対応方法を見ていきましょう。
| 保証人への請求時の対応 |
|
|---|
この表は保証人への請求があった場合の主な対応方法を示しています。保証人自身の経済状況に応じた対応が必要となります。
保証人が債務整理をする場合の注意点
保証人自身が債務整理をする場合、保証債務も整理の対象となりますが、いくつかの注意点があります。
| 保証人の債務整理の種類と特徴 |
|
|---|---|
| 債務整理の影響 |
|
この表は保証人が債務整理をする場合の特徴と影響を示しています。保証人が債務整理をしても、主たる債務者の債務には直接影響しないことが重要なポイントです。
保証人保護のための法律改正
近年、保証人保護のための法律改正が行われています。2020年4月から施行された改正民法では、個人保証人を保護するための規定が強化されました。
- 事業用融資の第三者保証には公正証書による意思確認が必要になった
- 個人根保証契約には極度額(上限額)の定めが必要になった
- 保証契約締結時に主たる債務者の財産や収支状況などの情報を保証人に提供する義務が定められた
- 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合に債権者が保証人に通知する義務が新設された
このリストは改正民法による保証人保護のための主な変更点を示しています。特に事業用融資における第三者保証の制限は、安易に保証人になることを防ぐ重要な改正です。
安全に保証人になるための注意点
どうしても保証人になる必要がある場合は、以下の点に注意することで、リスクを最小限に抑えることができます。
- 主たる債務者の返済能力を十分に確認する:収入や他の借入状況、返済実績などを確認しましょう。
- 保証する金額や期間を限定する:無制限の保証は避け、自分が対応できる範囲内に限定することが大切です。
- 定期的に返済状況を確認する:主たる債務者の返済状況を定期的に確認し、問題があれば早めに対処しましょう。
- 自分の資力を超える保証はしない:自分自身の収入や資産で対応できる範囲内の保証にとどめるべきです。
- 契約内容をよく確認する:保証契約の内容、特に保証の種類(連帯保証か通常保証か)を必ず確認しましょう。
上記のリストは安全に保証人になるための注意点を示しています。保証人になる際は、感情に流されず冷静に判断することが重要です。
まとめ
保証人とは、主たる債務者が債務を返済できなくなった場合に、その債務を肩代わりして支払う義務を負う人のことです。特に連帯保証人は主たる債務者と同等の責任を負うため、そのリスクは非常に大きいものとなります。
主たる債務者が債務整理をした場合でも、保証人の責任は軽減されません。主たる債務者が破産しても、保証人は全額の支払い義務を負います。逆に保証人が債務整理をしても、主たる債務者の債務には直接影響しません。
2020年の改正民法により保証人保護のための規定が強化され、特に事業用融資における第三者保証には公正証書による意思確認が必要になりました。また、個人根保証契約には極度額の定めが必要となりました。
保証人になる際は、そのリスクを十分に理解し、主たる債務者の返済能力を確認するとともに、自分の資力を超える保証はしないことが大切です。すでに保証人になっている場合で支払いが困難な場合は、自身の債務整理も検討する必要があるでしょう。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



