分断計算(ぶんだんけいさん)について詳しく解説
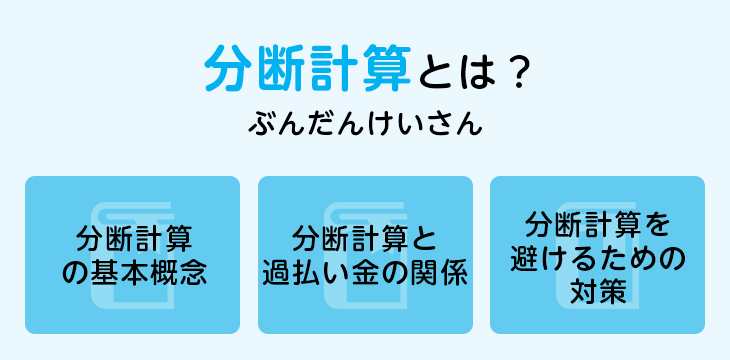
分断計算とは、過払い金請求や債務整理において、一連の取引を特定の時点で区切って計算する方法です。主に貸金業者との間で、長期間にわたって複数の契約・取引が続いていた場合に用いられる計算手法です。
特に、取引の途中で契約が切り替わった場合や、一度完済後に再度借入れを行った場合などに、取引を連続したものとして扱うか、区切って別々の取引として扱うかで、過払い金の額や債務の残高が大きく変わることがあります。
分断計算の基本概念
分断計算とは、長期間にわたる貸金取引を特定の時点で区切り、それぞれ別個の取引として計算する方法です。これに対して、取引を一連のものとして継続的に計算する方法を「一連計算」または「継続的取引」と呼びます。
| 分断計算 | 取引を特定の時点で区切り、別々の取引として計算する方法 |
|---|---|
| 一連計算(継続的取引) | 取引を途切れなく一連のものとして連続的に計算する方法 |
分断計算と一連計算のどちらを適用するかによって、特に過払い金請求においては計算結果が大きく異なることがあります。一般的に、債務者(借りる側)にとっては一連計算、貸金業者(貸す側)にとっては分断計算が有利になることが多いです。
分断計算が適用される主な場面
分断計算が問題となる主な場面は以下の通りです。
- カードローンからキャッシングに契約を切り替えた場合
- 一度完済した後、再度借入れを行った場合
- 貸金業者が合併や営業譲渡によって変わった場合
- 取引の名義が変更された場合
- 契約番号(口座番号)が変更された場合
上記のような場合に、取引を区切るべきか継続的に扱うべきかが争いになることがあります。特に過払い金請求においては、この判断が請求金額に大きく影響します。
分断計算が問題となるケース
具体的にどのようなケースで分断計算が問題になるのか、いくつかの典型的な例を見てみましょう。
ケース1:契約の切り替え
貸金業者が新しい商品を導入したり、システムを変更したりした際に、既存の契約から新しい契約への切り替えが行われることがあります。このとき、形式上は契約が変わりますが、実質的には同じ借入れが継続していると考えられるケースが多いです。
| 貸金業者の主張 | 新旧の契約は別物であり、古い契約は完済して終了し、新しい契約で新たに借入れを開始したという分断計算を主張します。 |
|---|---|
| 債務者側の主張 | 実質的には同じ借入れが継続しており、古い契約の残高をそのまま新しい契約に引き継いだだけという一連計算を主張します。 |
上記のような場合、契約書の内容だけでなく、資金の流れや取引の実態を詳しく調査して判断する必要があります。
ケース2:完済後の再借入れ
一度借入れを完済した後、短期間のうちに再度同じ貸金業者から借入れを行う場合があります。このとき、完済によって取引が終了したと見るか、実質的には借入れが継続していると見るかが問題になります。
| 分断される可能性が高いケース |
|
|---|---|
| 一連と判断される可能性が高いケース |
|
上記のような要素を総合的に考慮して、取引が分断されるべきか一連のものとして扱われるべきかが判断されます。
ケース3:貸金業者の変更
貸金業者が合併や営業譲渡により変わった場合も、分断計算が問題になることがあります。法的には別の業者になりますが、実質的には同じ借入れが継続しているとも考えられます。
このような場合、営業譲渡の経緯や債権譲渡の方法、利用者への通知方法などを詳しく調査して判断することになります。同一グループ内での会社変更であれば、一連の取引と判断される可能性が高まります。
分断計算と過払い金の関係
分断計算は特に過払い金請求において重要な意味を持ちます。過払い金の計算方法と分断計算の関係について見ていきましょう。
利息制限法による引き直し計算の基本
過払い金請求では、利息制限法の上限金利(15%~20%)で取引を最初から引き直し計算します。グレーゾーン金利(利息制限法の上限を超え、出資法の上限である29.2%以下の金利)で支払った利息の超過分が過払い金となります。
この引き直し計算において、取引をどこで区切るかによって結果が大きく異なることがあります。
分断計算と過払い金計算の具体例
例えば、以下のような取引があったとします。
| 取引①(2005年~2007年) | 300万円を借り、高金利(25%)で返済を続け、2007年に「完済」 |
|---|---|
| 取引②(2007年~2010年) | 同じ貸金業者から再度200万円を借り、高金利(20%)で返済を続け、2010年に完済 |
この場合、分断計算と一連計算では以下のような違いが生じます。
- 分断計算の場合:取引①と取引②を別々に計算します。取引①では「完済」時点で過払いが発生していなかった場合、過払い金は発生しません。取引②のみで過払い金が発生していれば、その分だけ請求できます。
- 一連計算の場合:取引①と取引②を連続した一つの取引として計算します。取引①の高金利で支払った利息の超過分が、取引②の元本に充当されることになり、結果として大きな過払い金が発生する可能性があります。
上記の例からもわかるように、一連計算の方が債務者にとって有利になるケースが多いです。そのため、貸金業者は分断計算を主張し、債務者側は一連計算を主張するという対立が生じやすいのです。
判例にみる分断計算の考え方
分断計算に関しては、最高裁判所を含む多くの裁判例があります。これらの判例から、どのような場合に取引が分断されるか、または一連のものとして扱われるかの判断基準を見ていきましょう。
最高裁判例の基本的な考え方
最高裁判所は、以下のような基本的な考え方を示しています。
- 形式的な契約の切り替えや完済だけでなく、取引の実質や当事者の意思を考慮すべき
- 借入れと返済が繰り返される継続的な取引関係にあったかどうかが重要
- 完済から再借入れまでの期間が短く、同一条件での借入れであれば一連の取引と判断される可能性が高い
- 貸金業者の主導で契約が切り替えられた場合、一連の取引と判断される可能性が高い
上記のような判断基準に基づき、個別のケースごとに取引が分断されるか一連のものとして扱われるかが判断されます。
具体的な裁判例
実際の裁判例では、以下のような判断がなされています。
| 一連の取引と判断された例 |
|
|---|---|
| 分断された取引と判断された例 |
|
上記の裁判例は一般的な傾向を示すものであり、個別のケースによって判断が異なる可能性があります。実際の過払い金請求では、専門家による詳細な取引履歴の分析が必要です。
分断計算を避けるための対策
過払い金請求を行う債務者側にとって、分断計算によって請求額が減少するのは不利益となります。分断計算を避けるために、以下のような対策や証拠収集が重要です。
取引履歴の徹底的な収集
分断計算の争いにおいては、取引の実態を示す証拠が重要です。貸金業法に基づく開示請求などを活用して、可能な限り詳細な取引履歴を収集しましょう。
| 収集すべき主な資料 |
|
|---|
上記のような資料を収集することで、取引の連続性を示す証拠となります。特に完済前後の状況を示す資料は重要です。
一連の取引であることを示す証拠
一連の取引であることを示すために、以下のような点に注目して証拠を収集・整理することが重要です。
- 完済と再借入れの時間的近接性:完済から再借入れまでの期間が短いことを示す資料
- 貸金業者からの勧誘:完済後すぐに新たな借入れを勧める文書やメール
- 手続きの簡略化:再契約時に審査が簡略化されていたことを示す資料
- 契約条件の同一性:金利や返済方法など、条件が同じであることを示す資料
- 同一の担当者:同じ担当者が対応していたことを示すメモや名刺
上記のような証拠があれば、形式的には別々の契約であっても、実質的には一連の取引であると主張しやすくなります。
専門家への相談
分断計算の問題は専門的な知識を要するため、過払い金請求を検討する際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は豊富な経験と知識に基づいて、分断計算の回避策や効果的な主張方法をアドバイスしてくれます。
特に訴訟になった場合は、判例や法律論に基づく専門的な主張が必要となりますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
分断計算とは、長期間にわたる貸金取引を特定の時点で区切り、別々の取引として計算する方法です。特に過払い金請求において、分断計算と一連計算のどちらを適用するかによって請求金額が大きく異なることがあります。
分断計算が問題となる主なケースとしては、契約の切り替え、完済後の再借入れ、貸金業者の変更などがあります。これらのケースでは、形式的な契約や完済の事実だけでなく、取引の実質や当事者の意思を考慮して判断する必要があります。
裁判例では、完済から再借入れまでの期間が短く同一条件での借入れであれば一連の取引と判断される傾向があります。また、貸金業者の主導で契約が切り替えられた場合も、一連の取引と判断される可能性が高くなっています。
過払い金請求を行う際には、分断計算を避けるために詳細な取引履歴を収集し、取引の連続性を示す証拠を整理することが重要です。また、専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



