小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)について詳しく解説
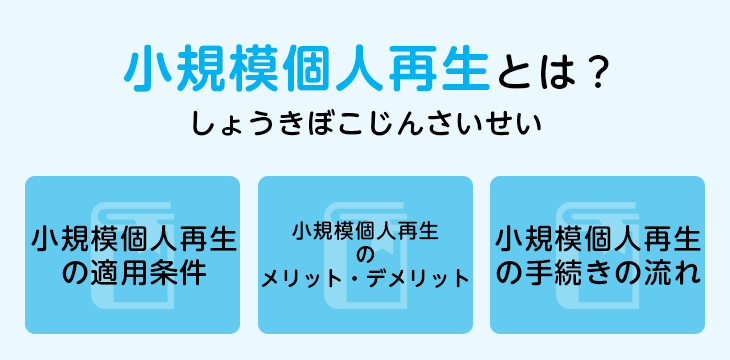
小規模個人再生とは、債務整理の一種で、個人の債務者が裁判所を通じて債務の減額を行い、残りを原則3年間で分割返済する手続きです。通常の個人再生手続のうち、債務総額が5,000万円以下の比較的少額な債務を抱える個人を対象としたものが小規模個人再生です。
この手続きは民事再生法に基づいており、自己破産とは異なり、一定の財産を手元に残しながら債務問題を解決できるという特徴があります。特に住宅を残したい場合には、「住宅資金特別条項」を利用することも可能です。
小規模個人再生とは
小規模個人再生は、民事再生法の中でも特に個人債務者の再生を目的とした手続きです。債務者が裁判所に申立てを行い、債権者の同意や裁判所の認可を得ることで、債務の一部を免除してもらい、残りを3〜5年(原則3年)で分割返済する制度です。
この制度の最大の特徴は、債務を大幅に減額できる点と、自己破産とは異なり一定の財産を手元に残せる点にあります。また、住宅ローンがある場合には「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅を手放さずに他の債務だけを整理することも可能です。
| 小規模個人再生の特徴 |
|
|---|
上記の表は小規模個人再生の主な特徴を示しています。この手続きは、借金が返済できなくなったものの、安定した収入があり、一部返済する能力はある方に適しています。
小規模個人再生の適用条件
小規模個人再生を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な適用条件は以下の通りです。
| 条件 | 詳細説明 |
|---|---|
| 債務総額 |
|
| 収入の見込み |
|
| 返済能力 |
|
| 申立資格 |
|
| 債務の性質 |
|
上記の表は小規模個人再生の主な適用条件を示しています。特に重要なのは、債務総額の上限と安定した収入の見込みです。
最低弁済額について
小規模個人再生では、債権者に対して「最低弁済額」以上の返済を行う必要があります。この最低弁済額は以下のように計算されます。
- 債務総額の1/5(20%)
- 100万円
上記のうち、いずれか多い方の金額が最低弁済額となります。例えば、債務総額が300万円の場合、1/5は60万円ですが、100万円の方が多いため、最低弁済額は100万円となります。一方、債務総額が700万円の場合、1/5は140万円であり、100万円より多いため、最低弁済額は140万円となります。
この最低弁済額を原則3年(最長5年)で返済できることが、小規模個人再生を利用するための重要な条件です。
小規模個人再生のメリット・デメリット
小規模個人再生には、他の債務整理方法と比較していくつかのメリットとデメリットがあります。これらを理解することで、自分の状況に最も適した債務整理方法を選ぶ助けになります。
メリット
- 債務の大幅減額:債務総額の最大80%が免除される可能性がある
- 財産の維持:自己破産と異なり、基本的に財産を処分する必要がない
- 住宅の維持:住宅資金特別条項を利用すれば住宅ローンを除外できる
- 信用情報への影響:自己破産よりも回復が早い傾向がある
- 資格制限がない:自己破産とは異なり、職業や資格の制限がほとんどない
- 非免責債権も含めた整理:税金や社会保険料なども再生計画に含められる
- 債権者の個別同意不要:債権者全体の過半数の同意があれば手続きが進められる
上記のリストは小規模個人再生の主なメリットです。特に住宅を維持できる点と、自己破産よりも社会的な不利益が少ない点が大きなメリットとなります。
デメリット
| デメリット | 詳細説明 |
|---|---|
| 手続きの複雑さ |
|
| 費用が高い |
|
| 時間がかかる |
|
| 最低弁済額の確保 |
|
| 信用情報への登録 |
|
| 再生計画違反のリスク |
|
上記の表は小規模個人再生の主なデメリットを示しています。特に手続きの複雑さと費用の高さは、小規模個人再生の大きなデメリットとなります。
小規模個人再生の手続きの流れ
小規模個人再生の手続きは、申立ての準備から再生計画の履行まで、いくつかの段階に分かれています。以下に一般的な流れを示します。
- 専門家への相談:まずは司法書士や弁護士に現在の債務状況を相談します
- 再生手続開始の申立て:裁判所に小規模個人再生の申立てを行います
- 再生手続開始決定:裁判所が手続開始を認めると、債権者への返済が一時停止します
- 債権者への通知:すべての債権者に手続開始が通知され、債権届出の期間が設けられます
- 再生計画案の提出:債務者は返済計画を記載した再生計画案を裁判所に提出します
- 再生計画の認可:債権者の反対が一定数以下であれば、裁判所が再生計画を認可します
- 再生計画の遂行:認可された計画に従って、通常3年間の返済を行います
- 再生手続の終結:すべての返済が完了すると、残りの債務が免除されます
上記のリストは小規模個人再生の一般的な手続きの流れです。申立てから再生計画認可までは約6ヶ月〜1年程度かかり、その後の返済期間(原則3年)も含めると長期間の手続きとなります。
なお、手続きの途中で返済が困難になった場合は、再生計画の変更を申し立てることもできますが、裁判所の許可が必要となります。また、返済が著しく困難になった場合は、自己破産への移行を検討することもあります。
小規模個人再生に関するよくある質問
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは何ですか?
小規模個人再生と給与所得者等再生は、どちらも個人再生手続の一種ですが、以下のような違いがあります。
| 項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 対象者 | 債務総額5,000万円以下の個人 | 定期的な収入がある個人(給与所得者や年金受給者など) |
| 債権者の同意 | 必要(過半数) | 不要(債権者の反対があっても裁判所が認可可能) |
| 最低弁済額 | 債務総額の1/5または100万円のいずれか多い額 | 可処分所得の2年分 |
| 手続きの特徴 | 比較的簡易な手続き | 可処分所得の算定が必要 |
どちらの手続きが適しているかは、債務者の状況(収入の種類や金額、債務額など)によって異なります。弁護士や司法書士に相談し、最適な手続きを選ぶことをおすすめします。
小規模個人再生中に返済が困難になった場合はどうなりますか?
小規模個人再生の再生計画認可後に、病気や失業などの予期せぬ事情で返済が困難になった場合、以下のような対応が考えられます。
- 再生計画の変更申立て:返済条件(金額や期間)の変更を裁判所に申し立てる
- 履行の一時猶予:一時的な支払い猶予を債権者に交渉する
- 再生計画の取消し:返済が著しく困難な場合は、計画が取り消される可能性がある
- 自己破産への移行:最終的な選択肢として自己破産を検討
返済が困難になった場合は、早めに代理人(弁護士・司法書士)に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
小規模個人再生をすると自宅は残せますか?
小規模個人再生では、基本的に財産を処分する必要がないため、自宅を所有している場合でも手放す必要はありません。特に住宅ローンがある場合は「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンを再生計画から除外し、これまで通り返済を続けながら、他の債務だけを整理することができます。
ただし、住宅資金特別条項を利用するには、①住宅ローンの返済が滞っていないこと、②住宅の価値が住宅ローン残債を上回っていること、③今後も返済を継続できる見込みがあることなどの条件があります。条件を満たさない場合は、自宅を残せない可能性もあるため、専門家に相談することをおすすめします。
小規模個人再生の費用はどのくらいかかりますか?
小規模個人再生にかかる主な費用は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 弁護士・司法書士費用 |
|
| 予納金 (裁判所に納める費用) |
|
| その他の費用 |
|
費用の総額は、約50〜70万円程度が一般的です。ただし、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すると、弁護士・司法書士費用を分割払いにできる場合があります。費用面で不安がある場合は、法テラスに相談してみることをおすすめします。
まとめ
小規模個人再生は、債務総額が5,000万円以下の個人債務者が利用できる債務整理の方法で、裁判所を通じて債務の大幅な減額を行い、残りを原則3年間で分割返済する手続きです。最大のメリットは、債務を最大80%減額できる可能性があること、自己破産と異なり財産を手元に残せること、特に住宅資金特別条項を利用すれば住宅を維持したまま債務整理ができることなどが挙げられます。
一方で、手続きが複雑で費用が高額になること、最低弁済額(債務総額の1/5または100万円のいずれか多い額)を確保する必要があること、信用情報機関に記録が残ることなどのデメリットもあります。手続きには弁護士や司法書士のサポートが必要で、申立てから再生計画認可までは約6ヶ月〜1年程度、その後の返済期間も含めると長期間の手続きとなります。
小規模個人再生は、安定した収入があり、一部返済する能力はあるものの全額の返済は困難な方や、住宅を手放したくない方に適した債務整理方法です。自分の状況に最も適した債務整理方法を選ぶために、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



