サービサー(さーびさー)について詳しく解説
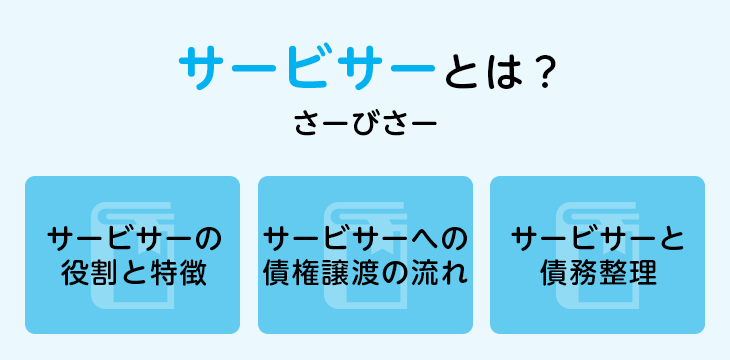
サービサーとは、「債権回収会社」のことを指します。正式名称は「債権管理回収業者」で、特定金銭債権の管理・回収を専門的に行う法務大臣の許可を受けた会社です。
金融機関等から債権(主に不良債権)を買い取り、または委託を受けて回収業務を代行します。1999年に施行された「サービサー法」(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づいて設立された法人であり、債務整理を検討する方にとって重要な知識となります。
サービサーとは
サービサーは、金融機関や信販会社などの債権者から債権を買い取ったり、回収業務を委託されたりして、債権回収を専門的に行う会社です。日本では、1999年に施行された「サービサー法」によって制度化されました。
それまで弁護士しかできなかった債権回収業務を、法務大臣(法務省)の許可を受けた株式会社が行えるようになりました。主に不良債権の回収を専門としており、法的な知識や回収ノウハウを持ったプロフェッショナル集団です。
サービサーが取り扱える債権
サービサーが取り扱えるのは「特定金銭債権」と呼ばれる以下のような債権です。
- 銀行等の金融機関の貸付債権
- 保険会社等の貸付債権
- 貸金業者の貸付債権
- リース・クレジット債権
- 法人税等の国税滞納処分による徴収権
- 国民健康保険料等の公共料金
上記のリストはサービサーが取り扱える主な債権の種類です。一般の商取引から生じた売掛金などは原則として取り扱うことができません。
サービサーの役割と特徴
サービサーは債権回収のプロフェッショナルとして、以下のような役割と特徴を持っています。
| 債権回収の専門性 | 法的知識や交渉スキルを持った専門スタッフが債権回収業務を行います。弁護士や法律事務所とも連携して効率的な回収を図ります。 |
|---|---|
| 法的権限 | 債権を譲り受けた場合は債権者として訴訟提起や強制執行などの法的手続きを行う権限を持ちます。委託を受けた場合でも、一定の範囲で回収業務を行えます。 |
| 不良債権の買取 | 金融機関から不良債権を割引価格で買い取ることで、金融機関のバランスシート改善に貢献します。買取価格は債権額の数%〜数十%が一般的です。 |
| 厳格な業務規制 | 法務省の監督下にあり、違法な取立て行為は禁止されています。債務者の私生活や業務の平穏を害する行為や脅迫的な言動は法律で禁止されています。 |
上記の表はサービサーの主な役割と特徴を示しています。サービサーは法律に基づいて設立された正規の債権回収会社であり、違法な取立て行為を行う「闇金融」とは全く異なります。
サービサーへの債権譲渡の流れ
債権がサービサーに移る一般的な流れは以下の通りです。
- 金融機関等で返済が滞り、長期延滞債権となる
- 金融機関がサービサーに債権を譲渡または回収を委託
- サービサーから債務者に「債権譲渡通知」または「受任通知」が送付される
- サービサーによる返済交渉や法的手続きの開始
- 和解交渉または強制執行による回収
このリストは債権がサービサーに移るまでの一般的なプロセスを示しています。債権譲渡通知が届いた場合は、その債権の返済先がサービサーに変更になったことを意味します。
債権譲渡と委託の違い
| 債権譲渡 | 債権そのものが金融機関からサービサーに移ります。債権者がサービサーとなり、返済先もサービサーになります。サービサーは自らの名義で法的手続きを行えます。 |
|---|---|
| 債権回収の委託 | 債権者は金融機関のままで、回収業務のみをサービサーが代行します。返済先は金融機関ですが、交渉窓口はサービサーになります。 |
上記の表は債権譲渡と債権回収委託の違いを説明しています。どちらの場合も、債務者はサービサーと交渉することになりますが、法的な権限や返済先が異なります。
サービサーと債務整理
サービサーが債権者となっている場合の債務整理についても、基本的な流れは他の債権者と同じです。ただし、いくつかの特徴があります。
サービサーが債権者の場合の債務整理の特徴
- 債権買取時に大幅に割引されているため、和解条件が柔軟になる場合がある
- 専門的な交渉ノウハウを持っているため、弁護士や司法書士を介した方が有利な場合が多い
- 時効が近い債権では、時効援用の可能性を検討できる
- 複数の債権をまとめて一括和解できるケースもある
- 債権譲渡の経緯によっては、取引履歴の取得が難しい場合がある
このリストはサービサーが債権者となっている場合の債務整理の特徴を示しています。サービサーは債権回収のプロフェッショナルなので、個人での交渉は不利になることが多く、専門家に依頼することをおすすめします。
サービサーとの和解条件の例
| 一括払いでの減額 | 債権額の30〜70%程度での一括和解が可能なケースがあります。特に古い債権や少額債権では大幅減額になることも。 |
|---|---|
| 分割払いでの和解 | 将来利息のカットと3〜5年程度の分割返済が一般的です。ただし、減額幅は一括払いより小さくなります。 |
| 時効援用 | 最終返済や債務承認から一定期間(5年または10年)経過していれば、時効を援用できる可能性があります。 |
上記の表はサービサーとの一般的な和解条件の例です。実際の条件は個々の状況や債権の性質、サービサーの方針によって大きく異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。
サービサーに関するよくある質問
サービサーから連絡が来ましたが、心当たりがありません。どうすればいいですか?
まずは連絡してきたサービサーの正式名称や許可番号を確認しましょう。法務省のホームページで許可を受けたサービサーかどうか確認できます。
次に、どの債権に関する連絡なのか、債権の詳細(債権者名、契約日、金額など)を書面で送付してもらうよう依頼しましょう。心当たりがない場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
サービサーに債権が移っても時効は進みますか?
債権がサービサーに譲渡されても、時効期間は継続して進みます。ただし、債権譲渡自体は時効の中断事由にはなりません。
しかし、サービサーからの督促状に対して支払いを約束したり、一部でも返済したりすると、その時点で時効が中断(更新)されるので注意が必要です。時効が近いと思われる場合は、専門家に相談してから対応しましょう。
サービサーの取立てに問題がある場合はどうすればいいですか?
サービサーは「サービサー法」や「貸金業法」などの規制を受けており、違法な取立て行為は禁止されています。具体的には以下のような行為は禁止されています。
- 深夜(午後9時〜午前8時)の電話や訪問
- 職場への電話や訪問による迷惑行為
- 脅迫的な言動や執拗な督促
- 虚偽の内容を告げること
- 第三者への債務内容の漏洩
違法な取立てを受けた場合は、内容を記録(録音など)した上で、弁護士や司法書士に相談しましょう。また、法務省や都道府県の貸金業担当窓口に苦情を申し立てることもできます。
まとめ
サービサー(債権回収会社)は、金融機関等から債権を買い取ったり、回収業務を委託されたりして債権回収を専門的に行う法務大臣許可の会社です。1999年に施行された「サービサー法」によって制度化され、不良債権処理の円滑化に貢献しています。
サービサーが取り扱えるのは「特定金銭債権」と呼ばれる一定の債権に限られており、違法な取立て行為は厳しく規制されています。債権がサービサーに移った場合でも、債務整理の基本的な流れは変わりませんが、専門的な知識を持つサービサーとの交渉には注意が必要です。
サービサーから連絡があった場合は、債権の詳細を確認し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。特に時効が近い債権や、複数の債権がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで有利な条件での和解が可能になることもあります。
債務整理を検討する際には、サービサーの特性を理解し、適切な対応をすることが重要です。一人で悩まず、早めに専門家に相談して、最適な解決策を見つけることが借金問題解決の第一歩となります。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



