再生債務者(さいせいさいむしゃ)について詳しく解説
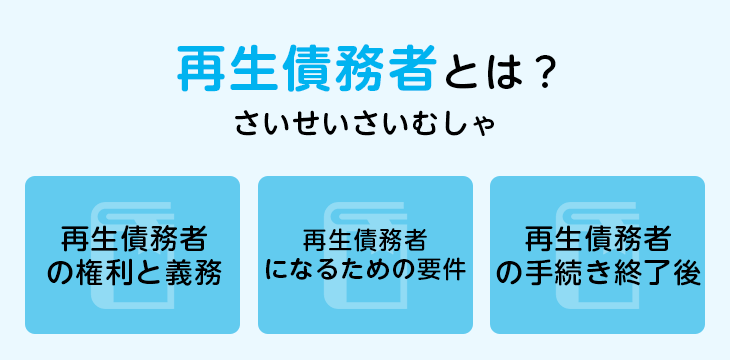
再生債務者とは、民事再生法に基づく債務整理手続きである「民事再生」や「個人再生」の申立てを行い、裁判所から再生手続開始決定を受けた債務者のことを指します。過大な債務を抱えているものの、収入や財産がある程度あり、債務の一部を返済しながら経済的再生を目指す人や法人が該当します。
再生債務者は、裁判所の監督のもとで再生計画を立て、債権者との合意を目指します。再生計画が認可されると、債務の一部免除や返済条件の変更などの法的効果が生まれ、経済的な再出発が可能になります。一般的な債務整理の中でも、自己破産よりも財産を保持しながら債務整理ができる制度です。
再生債務者とは
再生債務者とは、借金の返済が困難になったものの、一定の収入があり将来的に債務の一部返済が可能な状況にある人や法人が、裁判所に民事再生や個人再生の申立てを行い、手続開始決定を受けた状態にある債務者のことです。
自己破産と異なり、再生債務者は原則として財産を維持したまま債務の一部を免除してもらい、残りの債務を分割して返済していく道を選ぶことになります。収入や財産状況に応じた返済計画(再生計画)を立て、債権者の同意を得ながら経済的再生を目指します。
| 法的根拠 | 民事再生法第2条第2項 |
|---|---|
| 主な対象者 |
|
| 適用される再生手続き | |
| 再生債務者になる時期 | 裁判所による再生手続開始決定時 |
この表は再生債務者の基本情報をまとめたものです。民事再生法では「再生債務者」は申立人が再生手続開始決定を受けた後の法的地位を指します。再生手続き中は様々な権利と義務が発生します。
再生債務者の権利と義務
再生債務者には、再生手続きを進める中でいくつかの重要な権利と義務が発生します。これらを理解し、適切に行動することが再生手続きを成功させるために不可欠です。
再生債務者の主な権利
- 再生計画案を提出する権利
- 債権者集会に出席し意見を述べる権利
- 債権届出に対して異議を述べる権利
- 一定の範囲内で財産を管理・処分する権利
- 住宅ローン特則の適用を申し立てる権利(個人再生の場合)
- 再生手続き中の強制執行等の中止・取消しを受ける権利
- 特定の契約を解除する権利(双方未履行の契約)
上記のリストは再生債務者の主な権利です。特に重要なのは再生計画案を提出する権利で、自らの返済能力に見合った再生計画を提案できることが民事再生・個人再生の大きな特徴です。
再生債務者の主な義務
- 裁判所や監督委員等に対して財産状況を正確に報告する義務
- 再生手続きを誠実に遂行する義務
- 財産目録・債権者一覧表などの書類を提出する義務
- 債権者平等の原則を遵守する義務
- 裁判所の許可なく重要な財産を処分しない義務
- 再生計画認可後は計画に従って返済を行う義務
- 定期的な収支報告を行う義務(裁判所から求められた場合)
上記のリストは再生債務者の主な義務です。再生手続きでは債務者の誠実さが重視されます。特に財産状況の正確な報告や、再生計画に従った返済の履行は非常に重要です。
再生債務者の行為制限
再生債務者は手続き中、以下のような行為制限を受けることがあります。これらの制限は債権者の利益を保護するために設けられています。
| 制限される行為 | 内容 |
|---|---|
| 財産処分の制限 |
|
| 新規借入の制限 |
|
| 債権者への弁済制限 |
|
| 事業活動の制限 |
|
この表は再生債務者に課される主な行為制限をまとめたものです。これらの制限に違反すると、再生手続きの廃止事由となる可能性があるため注意が必要です。特に財産処分については慎重な対応が求められます。
再生債務者になるための要件
再生債務者になるためには、まず再生手続開始の申立てを行い、裁判所から手続開始決定を受ける必要があります。そのためには、以下のような要件を満たす必要があります。
積極的要件
- 債務超過または支払不能のおそれがあること
- 継続的な収入があること(個人の場合)
- 事業の継続可能性があること(事業者の場合)
- 最低弁済額(清算価値)以上の返済が可能なこと
- 債権者間の公平が保てること
上記のリストは再生債務者になるための積極的要件です。特に重要なのは、債務整理が必要な状況にありながらも、一定の収入があり、最低限の返済能力がある点です。これにより自己破産よりも財産を維持したまま債務整理ができます。
消極的要件(欠格事由)
- 過去7年以内に免責を受けていること
- 再生計画の遂行が明らかに不可能と認められること
- 不誠実な行為や詐欺的な行為があること
- 再生手続きの費用を納付できないこと
- 債権者一般の利益に反すると認められること
上記のリストは再生債務者になれない欠格事由です。特に過去の免責歴や不誠実な行為の有無は重要なチェックポイントとなります。これらに該当すると再生手続開始申立てが棄却される可能性があります。
個人再生の特殊要件
| 再生手続きの種類 | 債務総額の要件 | その他の要件 |
|---|---|---|
| 小規模個人再生 | 無担保債務総額5,000万円以下 |
|
| 給与所得者等再生 | 無担保債務総額5,000万円以下 |
|
この表は個人再生の種類別に見た再生債務者の特殊要件をまとめたものです。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、収入の安定性や債務額によって適用される種類が異なります。
再生債務者の財産管理
再生債務者は自己破産と異なり、原則として財産の管理処分権を失わず、自らの財産を保持したまま手続きを進めることができます。しかし、再生手続中は一定の財産管理上の制限や義務があります。
再生債務者が管理できる財産
- 不動産(自宅など)
- 預貯金
- 自動車
- 生活必需品
- 事業用資産
- 有価証券
- 将来受け取る給与や年金
上記のリストは再生債務者が管理できる主な財産です。自己破産では処分される可能性のある財産も、再生手続きでは原則として維持できるのが大きな特徴です。特に自宅などの重要な資産を手放さずに済む点が再生手続きの利点といえます。
管理処分権の制限
再生債務者は財産の管理処分権を持ちますが、以下のような制限を受けます。
| 制限の種類 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所の許可が必要な行為 |
|
| 監督委員の同意が必要な行為 |
|
| 再生債務者自身の判断で可能な行為 |
|
この表は再生債務者の管理処分権の制限についてまとめたものです。再生手続きでは債務者の誠実性が重視されるため、これらの制限を遵守することが非常に重要です。特に重要な財産の処分には裁判所の許可が必要となります。
監督委員・管財人が選任される場合
事案の複雑さや規模によっては、裁判所が監督委員や管財人を選任することがあります。その場合の再生債務者の立場は以下のようになります。
- 監督委員が選任された場合:財産管理処分権は保持するが、一定の行為に監督委員の同意が必要
- 管財人が選任された場合:財産管理処分権が管財人に移り、債務者は管財人の管理下に置かれる
- 再生委員が選任された場合:再生計画案の作成など再生手続きの遂行を補助・監督される
上記のリストは監督委員等が選任された場合の再生債務者の立場です。個人再生では監督委員等が選任されないケースも多いですが、事業再生や複雑な債務関係がある場合は選任されることがあります。
再生債務者の手続き終了後
再生計画が認可され確定すると、再生債務者は計画に従って返済を行っていきます。計画の履行完了後や手続きが廃止された場合の再生債務者の状況について説明します。
再生計画履行完了後
- 再生計画に従った返済が完了すると残債務は免除される
- 信用情報機関に登録された事故情報は一定期間後に削除される
- 財産処分の制限がなくなり、自由に財産を管理・処分できる
- 新規の借入なども可能になる(ただし審査は厳しくなる傾向がある)
- 経済的に再スタートを切ることができる
上記のリストは再生計画履行完了後の再生債務者の状況です。計画を完遂することで法的に債務が整理され、経済的な再生が実現します。ただし、信用情報機関への事故情報登録は一定期間(5〜10年程度)継続するため、その間は新規借入れなどに制限がかかる場合があります。
手続きが廃止された場合
| 廃止の原因 | 再生債務者への影響 |
|---|---|
| 再生計画案が否決または不認可 |
|
| 再生計画の不履行 |
|
| 詐欺再生等の不正行為 |
|
この表は再生手続きが廃止された場合の再生債務者への影響をまとめたものです。手続きが廃止されると、債務減額の効果が得られず、債権者からの債権回収が再開される可能性があります。計画の認可を得て確実に履行することの重要性がわかります。
よくある質問
再生債務者と自己破産の債務者はどう違いますか?
最大の違いは財産の取扱いと返済義務にあります。再生債務者は原則として財産を保持したまま債務の一部を分割返済していきますが、自己破産の債務者は一部の免責財産を除いて財産を換価処分され、債権者への配当に充てられます。
また、再生債務者は再生計画に沿った返済を継続する必要がありますが、自己破産では免責決定が出れば原則として返済義務がなくなります。再生債務者は一定の収入があり将来的に返済能力がある方に適した制度といえます。
再生債務者になると、どのくらい債務が減額されますか?
債務の減額幅は個々の状況によって異なりますが、個人再生では一般的に債務総額の80〜90%程度が減額されるケースが多いです。ただし、最低弁済額(清算価値)を下回る減額はできません。
また、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分または清算価値のいずれか大きい額以上の返済が必要です。住宅ローンなどの担保付債務は原則として減額対象外となり、無担保債権(クレジットカードやカードローンなど)が主な減額対象となります。具体的な減額幅については、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
再生債務者として再生計画を履行中に、収入が増えた場合はどうなりますか?
再生計画認可後に収入が増加しても、原則として再生計画の返済額が自動的に増額されることはありません。認可された再生計画は裁判所の決定により確定しているため、債務者が自主的に返済額を増やさない限り、計画通りの返済を続けることになります。
ただし、著しく収入が増加した場合に、債権者から再生計画の変更を求められることもあります。また、道義的には収入が大幅に増えた場合には自主的に返済額を増やすことも検討されるべきでしょう。いずれにせよ、収入状況が変化した場合は、担当の弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
まとめ
再生債務者とは、民事再生法に基づく債務整理手続きである「民事再生」や「個人再生」の申立てを行い、裁判所から再生手続開始決定を受けた債務者のことです。自己破産と異なり、財産を維持したまま債務の一部を減額し、残りを分割返済していくことで経済的再生を目指します。
再生債務者には再生計画案を提出する権利や、一定範囲内で財産を管理・処分する権利がある一方、財産状況を正確に報告する義務や再生計画に従って返済を行う義務などが発生します。手続き中は重要な財産の処分や新規借入れなどに制限が課されますが、計画を完遂すれば残債務が免除され、経済的に再スタートを切ることができます。
再生債務者になるためには、債務超過または支払不能のおそれがあることや、継続的な収入があることなどの要件を満たす必要があります。債務整理の選択肢の中でも、自己破産よりも財産を維持でき、任意整理よりも大幅な債務減額が可能な中間的な位置づけとなっています。収入や財産状況に応じた適切な債務整理方法を選ぶためにも、専門家への相談をおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



