再生計画の変更(さいせいけいかくのへんこう)について詳しく解説
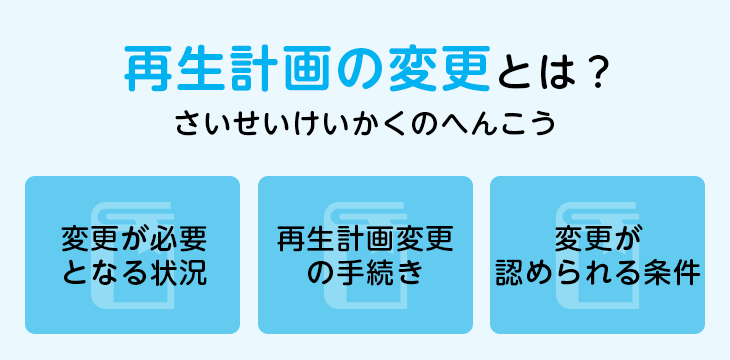
再生計画の変更とは、個人再生や民事再生の債務整理手続きにおいて、すでに裁判所に認可された再生計画の内容を事後的に変更する手続きのことです。債務者の収入減少や病気、事業不振など、やむを得ない事情により当初の計画通りの返済が困難になった場合に利用されます。
再生計画の変更では、月々の返済額の減額や返済期間の延長などが認められる可能性があり、債務者の経済状況に合わせた柔軟な対応が可能です。ただし、安易な変更は認められず、変更を認めるべき合理的な理由と裁判所の許可が必要となります。
再生計画の変更とは
再生計画の変更とは、個人再生や民事再生の手続きにおいて、すでに裁判所に認可され履行中の再生計画の内容を、債務者の状況変化に応じて修正する法的手続きです。再生計画は本来、認可後はその内容に従って返済を継続することが原則ですが、予期せぬ事情変更により当初の計画通りの返済が不可能になることもあります。
そのような場合に、裁判所の許可を得て計画内容を修正することで、債務者の返済継続を可能にし、債務整理の目的達成を図るのが再生計画の変更制度です。変更内容としては、月々の返済額の減額や返済期間の延長などが一般的です。
| 法的根拠 | 民事再生法第187条の2、第188条 |
|---|---|
| 申立先 | 再生手続きを行った管轄裁判所 |
| 申立可能期間 | 再生計画認可決定の確定後から再生計画の最終弁済期日まで |
| 変更の効果 | 裁判所の許可を得て変更された再生計画は、新たに法的拘束力を持つ |
この表は再生計画の変更に関する基本情報をまとめたものです。法的根拠は民事再生法に規定されており、再生計画認可後から最終弁済期日までの間に申立てが可能です。変更が許可されると新たな計画に法的拘束力が生じます。
変更が必要となる状況
再生計画の変更が必要となるのは、主に以下のような状況です。いずれも債務者の責任によらない事情変更が前提となります。
収入の減少
- 失業や転職による収入減
- 勤務先の業績悪化による給与カット
- 労働時間の削減
- 自営業の売上減少
- 予定していたボーナスが支給されない
上記のリストは収入減少に関連する状況の例です。特に安定した収入を前提に再生計画が立てられている場合、収入の大幅な減少は返済計画に直接影響します。自己都合退職ではなく、会社都合や病気などやむを得ない理由による収入減少であることが重要です。
支出の増加
- 病気やケガによる医療費の増加
- 家族の介護が必要になった
- 子どもの教育費の増加
- 住居の移転を余儀なくされた
- 自然災害による被害
上記のリストは支出増加に関連する状況の例です。特に医療費や介護費など、生活上必要不可欠な支出の増加は、返済計画に影響を与える合理的な理由となり得ます。ただし、趣味や嗜好品への支出増加は認められません。
その他のやむを得ない事情
- 離婚や家族構成の変化
- 扶養家族の増加
- 事業環境の急変(自営業者の場合)
- 自然災害による資産の喪失
- 為替変動など外部経済環境の急変
上記のリストはその他のやむを得ない事情の例です。これらも債務者の責任によらない外部要因であることが重要です。再生計画変更の申立ては、単に「返済が厳しい」という理由だけでは認められず、具体的かつ客観的な事情変更の証明が必要となります。
再生計画変更の手続き
再生計画の変更を行うには、以下のような手続きを踏む必要があります。専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
変更申立ての手順
- 変更の必要性を検討(収入減少や支出増加の状況確認)
- 変更内容の検討(返済額減額や返済期間延長など)
- 弁護士や司法書士などの専門家への相談
- 変更申立書と疎明資料の準備
- 裁判所への申立て
- 裁判所による審査
- 債権者からの意見聴取(必要に応じて)
- 裁判所による決定
上記のリストは再生計画変更の一般的な手順です。特に重要なのは、変更の必要性を客観的に証明する資料の準備です。収入証明書や医療費の領収書など、状況変化を示す具体的な証拠が必要となります。
必要な書類と疎明資料
| 基本書類 |
|
|---|---|
| 収入減少の証明 |
|
| 支出増加の証明 |
|
| その他の疎明資料 |
|
この表は再生計画変更申立てに必要な書類と疎明資料をまとめたものです。事情変更の内容に応じて適切な証拠書類を準備することが重要です。証拠が不十分だと変更が認められない可能性が高まります。
変更が認められる条件
再生計画の変更が認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。裁判所は厳格な審査を行い、安易な変更は認められません。
主な認可条件
- やむを得ない事情の存在(債務者の責任によらない事情変更)
- 変更後も再生計画の遂行可能性があること
- 変更内容が債権者にとって不当に不利益でないこと
- 清算価値保障原則の充足(破産した場合より有利な返済額の確保)
- 返済の誠実な履行実績(これまで可能な限り返済努力をしていたこと)
上記のリストは再生計画変更が認められるための主な条件です。特に重要なのは「やむを得ない事情」の存在と「返済の誠実な履行実績」です。自己都合による事情や、これまで返済を怠っていた場合は、変更が認められにくくなります。
裁判所の判断基準
裁判所は以下のような観点から再生計画変更の妥当性を判断します。
| 判断の観点 | 具体的な審査内容 |
|---|---|
| 事情変更の程度 | 収入減少や支出増加がどの程度深刻か、一時的か継続的か |
| 債務者の帰責性 | 状況変化が債務者の責任によるものかどうか |
| これまでの履行状況 | 再生計画を誠実に履行してきたか、滞納はなかったか |
| 変更の合理性 | 提案されている変更内容が状況に照らして合理的か |
| 変更後の実現可能性 | 変更後の計画を確実に履行できる見込みがあるか |
| 債権者の利益 | 変更により債権者の利益が不当に害されないか |
この表は裁判所が再生計画変更を判断する際の主な観点をまとめたものです。複数の要素から総合的に判断されるため、すべての観点において説得力のある説明と証拠を提示することが重要です。
変更が認められない場合の対応
再生計画の変更申立てが認められない場合や、そもそも変更では対応できないほど状況が悪化している場合には、以下のような対応を検討する必要があります。
再生計画が遂行できなくなった場合の選択肢
- 返済条件の見直し交渉(裁判外での調整)
- 再度の変更申立て(より詳細な資料を準備)
- 親族からの援助や借入れ
- 再生手続きの廃止と自己破産の検討
- 特定調停など他の債務整理方法の検討
上記のリストは変更が認められない場合の対応策です。状況によっては自己破産を検討する必要があるケースもありますが、まずは専門家に相談して最適な対応を検討することが重要です。
再生手続きの廃止とその影響
再生計画が遂行できず、変更も認められない場合、最終的には再生手続きの廃止という事態になることがあります。その場合の影響は以下の通りです。
| 再生手続廃止の影響 |
|---|
この表は再生手続きが廃止された場合の主な影響をまとめたものです。再生手続きの廃止は債務者にとって大きな不利益をもたらすため、可能な限り避けるべき事態といえます。返済が困難になった場合は早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
再生計画の変更は何回でも申し立てられますか?
法律上は再生計画変更の回数に明確な制限はありませんが、実務上は何度も変更が認められるケースは稀です。特に短期間に繰り返し変更を申し立てると、裁判所から計画の実現可能性自体を疑問視されることになります。
初回の変更申立てであれば、やむを得ない事情が適切に証明されれば認められる可能性が高いですが、2回目以降は非常に高いハードルがあると考えるべきです。変更を申し立てる際は、変更後の計画が確実に履行できるよう、慎重に内容を検討することが重要です。
一時的な収入減少でも計画変更は認められますか?
一時的な収入減少の場合、再生計画の変更よりも、裁判所への状況説明と一時的な猶予の相談が適切なケースが多いです。再生計画の変更は、比較的長期にわたる継続的な状況変化を前提としています。
例えば、数ヶ月間の病気による休職で一時的に収入が減少した場合などは、完全な計画変更よりも、その期間の返済猶予を求める方が現実的です。ただし、一時的な猶予を求める場合でも、裁判所や債権者への適切な説明と資料提示は必要です。回復の見込みがある一時的な状況なのか、継続的な変化なのかを見極めることが大切です。
変更申立ての費用はどのくらいかかりますか?
再生計画変更の申立てには、裁判所に納める収入印紙代(約1,000円程度)と、弁護士や司法書士に依頼する場合の専門家報酬がかかります。専門家報酬は、事案の複雑さや変更内容によって異なりますが、一般的には5万円〜20万円程度が目安です。
経済的に困窮している状況での申立てとなるため、費用面で心配がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できる可能性もあります。また、当初の再生手続きを担当した弁護士や司法書士に相談すると、状況に応じた柔軟な対応をしてくれることもあります。いずれにせよ、費用面の不安がある場合は、まずは相談時に費用について確認することをおすすめします。
まとめ
再生計画の変更は、個人再生や民事再生の手続きにおいて、すでに認可された再生計画の内容を事後的に修正する重要な制度です。債務者の収入減少や支出増加など、やむを得ない事情により当初の計画通りの返済が困難になった場合に利用できます。
変更が認められるためには、状況変化が債務者の責任によらないものであること、これまで誠実に返済を行ってきたこと、変更後の計画にも実現可能性があることなどが重要です。申立ては裁判所に対して行い、収入証明書や医療費の領収書など、状況変化を証明する資料の提出が必要となります。
再生計画の変更は債務者の経済状況に合わせた柔軟な対応を可能にする制度ですが、安易な変更は認められません。変更が認められない場合には、最終的に再生手続きの廃止という深刻な事態に発展する可能性もあります。返済が困難になった場合は早めに専門家に相談し、最適な対応を検討することが重要です。適切な変更により再生計画を完遂することが、債務整理の目的達成への最善の道といえるでしょう。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



