催告(さいこく)について詳しく解説
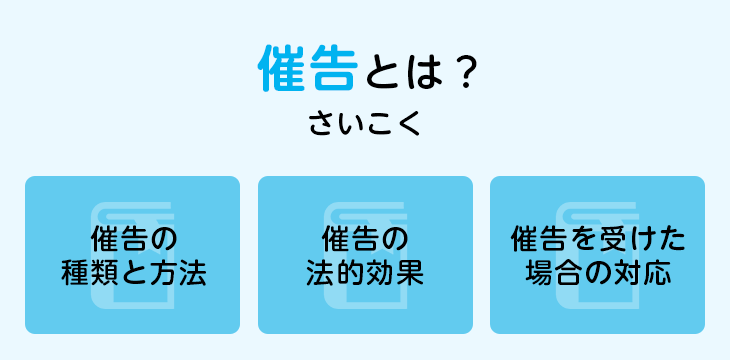
催告とは、債権者が債務者に対して債務の履行(返済)を求める通知のことです。特に債務整理や過払い金請求の場面では、債権者が返済が滞っている債務者に対して支払いを促すために行う重要な手続きとなります。
催告には法的効果があり、債務者の時効の援用を妨げたり、遅延損害金の発生根拠となったりします。また、裁判や強制執行の前段階として行われることも多く、債務整理を検討している方にとって理解しておくべき重要な概念です。
催告の基本
催告とは、債権者が債務者に対して債務の履行(返済)を求める通知や請求のことです。「支払いをしてください」という内容の文書やメッセージが典型的な催告にあたります。
債務整理の文脈では、主に返済が遅れている場合に債権者(貸金業者、クレジットカード会社など)から債務者に対して行われる支払いの請求が催告として重要になります。
催告の目的
催告には主に以下のような目的があります。
| 催告の主な目的 |
|---|
この表は催告が持つ主な目的を示しています。単なる支払いの依頼ではなく、法的な意味を持つ通知であることが重要なポイントです。
催告と通知の違い
日常的な「お知らせ」や「通知」と、法的な意味での「催告」は異なります。通知が単に情報を伝えるものであるのに対し、催告は債務者に対して一定の行為(主に返済)を求める法的な意味を持ちます。
例えば、「○月○日に返済期日が到来します」という連絡は単なる通知ですが、「期日までに返済してください。返済がない場合は法的手続きを取ります」という連絡は催告に該当します。
催告の種類と方法
催告にはいくつかの種類があり、その方法や形式も様々です。債務整理を検討する上で、どのような催告が行われるのかを理解しておくことは重要です。
催告の種類
催告は、法的な効力や形式によって以下のように分類されます。
- 通常の催告:電話、メール、郵便などでの支払い請求
- 最終催告:法的手続きの前に行う最後の請求
- 内容証明郵便による催告:証拠能力の高い書面での請求
- 裁判上の催告:訴訟手続きの一環として行われる請求
- 支払督促に伴う催告:支払督促手続きにおける請求
上記のうち、債務整理の場面で最も頻繁に見られるのは、通常の催告と内容証明郵便による催告です。特に滞納が長期化すると、内容証明郵便による催告が行われることが多くなります。
催告の方法
催告は様々な方法で行われますが、主な方法としては以下のようなものがあります。
| 催告の主な方法 |
|
|---|
この表は催告が行われる主な方法を示しています。債権者は状況に応じて適切な方法を選択します。特に重要なのは内容証明郵便による催告で、これは後の法的手続きへの移行を示す重要なサインとなることが多いです。
内容証明郵便による催告
内容証明郵便は、その内容と発送日が公的に証明される特殊な郵便サービスです。債権者が法的手続きを視野に入れている場合、通常はこの内容証明郵便による催告が行われます。
内容証明郵便による催告には、通常以下のような内容が含まれます。
- 債権者の名称・住所・連絡先
- 債務者の氏名・住所
- 債務の内容(契約日、契約番号、借入金額など)
- 延滞の事実と金額
- 支払期限(通常は発送日から1週間〜1ヶ月程度)
- 支払いがない場合の対応(裁判手続きの開始など)
- 連絡先や支払方法の案内
内容証明郵便を受け取った場合、債権者が法的手続きを検討していることを示すサインであるため、早急に対応を検討する必要があります。無視し続けると、訴訟や差押えなどの強制執行手続きに発展する可能性が高くなります。
催告の法的効果
催告は単なる連絡や依頼ではなく、法的な効果を持ちます。債務整理を検討する上で、催告がもたらす法的効果を理解しておくことは重要です。
時効の完成猶予
債権には時効があり、一定期間(現行民法では、原則として権利を行使できるときから5年)が経過すると消滅時効が完成し、債務者は「時効の援用」によって債務の支払いを拒むことができるようになります。
しかし、催告があると、その後6ヶ月間は時効の完成が猶予(延期)されます。これを「時効の完成猶予」といいます。つまり、時効期間が満了しそうな時点で債権者が催告を行うと、さらに6ヶ月間は時効が完成しなくなるのです。
ただし、この完成猶予の効果を得るためには、催告後6ヶ月以内に訴訟の提起などの「時効の更新事由」が必要です。そうでなければ、6ヶ月経過後に時効が完成することになります。
債務不履行の発生根拠
催告は、債務不履行の責任を明確にする役割も持ちます。特に期限の定めのない債務や、期限が到来していても当事者間で猶予が認められているような場合、催告によって初めて債務者に履行義務が発生することがあります。
民法の規定では、「期限の定めのない債務」については、債権者はいつでも履行を請求でき、債務者は催告を受けた後、すみやかに履行する義務を負います(民法第412条)。
遅延損害金の発生根拠
催告は遅延損害金の発生根拠にもなります。特に期限の定めのない債務では、催告を受けた時点から債務者は遅滞に陥り、遅延損害金が発生し始めることがあります。
期限の定めのある債務(返済日が決まっている債務)の場合は、原則としてその期限が到来した時点で当然に遅滞に陥りますが、実務上は催告を行ってから遅延損害金を請求することが多いです。
訴訟提起の前提条件
催告は、多くの場合、訴訟提起の前提条件としても機能します。法的には催告なしでも訴訟提起は可能ですが、実務上は催告を行い、債務者に自主的な返済の機会を与えることが一般的です。
特に消費者金融やクレジットカード会社などは、内部規定で「内容証明郵便による最終催告を行った後に訴訟提起する」というプロセスを定めていることが多いです。
| 催告の主な法的効果 |
|
|---|
この表は催告がもたらす主な法的効果を示しています。これらの効果から、催告が単なる連絡ではなく、重要な法的意味を持つ行為であることがわかります。
催告を受けた場合の対応
債務整理を検討している場合、催告を受けるとどのように対応すべきか悩むことがあります。ここでは、催告を受けた場合の適切な対応方法について解説します。
内容の確認
催告を受けた場合、まず内容を確認することが重要です。具体的には以下の点を確認しましょう。
- 債権者(請求元)は誰か
- 請求の原因となっている債務は何か
- 請求金額の内訳(元本、利息、遅延損害金など)
- 支払期限はいつか
- 支払わない場合の対応(法的手続きの予告など)
内容に不明な点や疑問点がある場合は、債権者に直接問い合わせて確認することも重要です。また、身に覚えのない請求や明らかに金額が誤っている場合は、詐欺的な催告の可能性もあるため注意が必要です。
対応の選択肢
催告を受けた後の主な対応の選択肢は以下の通りです。
- 全額支払い:資金的に可能であれば、請求額を全額支払う
- 分割払いの交渉:一括払いが難しい場合、分割払いを交渉する
- 減額交渉:支払能力に応じた金額に減額してもらえないか交渉する
- 債務整理の検討:弁護士や司法書士に相談し、任意整理や法的債務整理を検討する
- 時効の援用:消滅時効が完成している場合、時効を援用して支払いを拒む
どの選択肢が適切かは、債務の金額、自分の収入や資産状況、他の債務の有無など様々な要素によって異なります。特に複数の債務がある場合や、支払いが困難な状況にある場合は、専門家に相談して総合的な債務整理を検討することが重要です。
連絡方法
催告に対して何らかの対応をする場合、適切な連絡方法を選ぶことも重要です。
| 連絡方法の選択肢 |
|
|---|
この表は催告に対する連絡方法の選択肢と、それぞれの特徴を示しています。重要な交渉や合意を行う場合は、後で証拠として残る方法(メールや内容証明郵便)を選ぶことをおすすめします。
無視することのリスク
催告を無視し続けることには、以下のようなリスクがあります。
- 訴訟を提起される
- 支払督促を申し立てられる
- 債務名義(強制執行できる権利)が作られる
- 給与や預金口座が差し押さえられる
- 財産(自動車や不動産など)が差し押さえられる
- 信用情報に金融事故情報が登録される
これらのリスクを考えると、催告を受けた場合は無視せずに何らかの対応をすることが望ましいです。支払いが難しい場合でも、債権者に状況を説明し、話し合いの姿勢を示すことが重要です。
特に内容証明郵便による催告を受けた場合は、法的手続きに移行する前の最終警告である可能性が高いため、早急に対応を検討する必要があります。
よくある質問
催告を無視し続けるとどうなりますか?
催告を無視し続けると、債権者は裁判所を通じた法的手続きに移行する可能性が高くなります。具体的には、訴訟の提起や支払督促の申立てなどが行われ、債務名義が作られると、財産の差押えなどの強制執行が可能になります。
また、金融機関は信用情報機関に延滞情報を登録するため、新たな借入やクレジットカードの作成、住宅ローンの審査などに悪影響が出る可能性があります。状況を放置するのではなく、何らかの対応をすることが重要です。
催告を受けた後、債務整理を検討するタイミングはいつがよいですか?
債務整理を検討するタイミングは、返済が困難になったと感じた時点で早めに行うことが望ましいです。特に内容証明郵便による催告を受けた場合は、法的手続きに移行する前段階であることが多いため、すぐに専門家に相談することをおすすめします。
ただし、債務整理の手続きが始まっても、裁判所からの呼出状などが届いたら必ず対応する必要があります。債務整理中だからといって裁判所からの呼出しを無視すると、不利な判決が下される可能性があります。
催告状の時効中断効果はどのくらい続きますか?
2020年4月施行の改正民法では、催告による時効の「中断」ではなく「完成猶予」という概念に変わりました。催告によって、その後6ヶ月間は時効の完成が猶予(延期)されます。
ただし、この6ヶ月の間に訴訟の提起などの時効の更新事由がなければ、6ヶ月経過後に時効が完成します。また、催告が時効の完成猶予効を持つのは、時効期間が満了する前に行われた場合に限られます。
内容証明郵便以外の催告にも法的効力はありますか?
はい、内容証明郵便以外の催告(電話、メール、普通郵便など)にも法的効力はあります。催告の方法によって法的効力の有無が変わるわけではありません。
ただし、内容証明郵便は「いつ、どのような内容の催告が行われたか」を公的に証明できるため、後の訴訟などで証拠として使いやすいという特徴があります。電話などの口頭での催告は、後で証明することが難しいため、債権者としては証拠能力の高い内容証明郵便を選ぶことが多いです。
まとめ
催告とは、債権者が債務者に対して債務の履行(返済)を求める通知のことです。債務整理や過払い金請求の場面では、返済が滞っている債務者に対して債権者が行う重要な手続きとなります。
催告には様々な種類や方法があり、通常の催告から内容証明郵便による催告、裁判上の催告まで、状況に応じて適切な方法が選択されます。特に内容証明郵便による催告は、法的手続きへの移行を予告する重要なサインであることが多いです。
催告には法的効果があり、時効の完成猶予、債務不履行責任の発生、遅延損害金の発生根拠、訴訟提起の前提条件などの役割を果たします。単なる連絡ではなく、法的な意味を持つ行為だということを理解しておくことが重要です。
催告を受けた場合は、内容をよく確認し、自分の状況に応じた対応を検討する必要があります。全額支払い、分割払いの交渉、減額交渉、債務整理の検討、時効の援用など、様々な選択肢がありますが、無視することは最も避けるべき対応です。
特に複数の債務がある場合や返済が困難な状況にある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、総合的な債務整理を検討することをおすすめします。適切な対応によって、将来的な生活の再建に向けた第一歩を踏み出すことができます。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



