債権者一覧表(さいけんしゃいちらんひょう)について詳しく解説
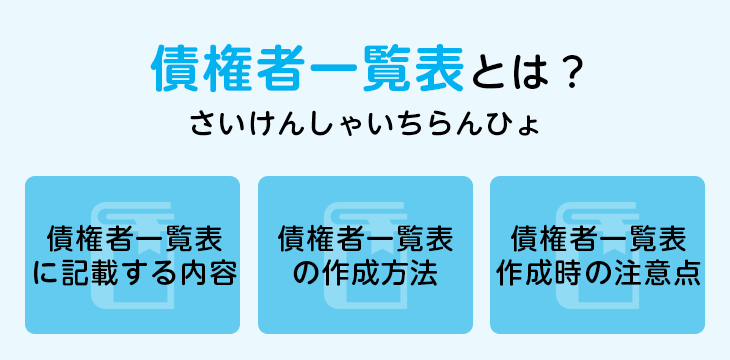
債権者一覧表とは、債務整理を行う際に作成する書類の一つで、借入先の金融機関や業者の名称、借入金額、借入日などを一覧にしたものです。この書類は債務整理の手続きを進める上で必要不可欠な資料となります。
債務整理の種類(任意整理、個人再生、自己破産など)を問わず、債権者一覧表の作成は必須のステップとなっています。正確な情報を記載することで、借金の全体像を把握し、適切な債務整理方法を選択するための判断材料となります。
債権者一覧表とは
債権者一覧表は、債務者(借金をしている人)が抱えているすべての借金について、誰にいくら借りているのかを明確にするための書類です。債務整理を行う際、弁護士や司法書士に依頼する場合も、この一覧表を基に手続きが進められます。
また、裁判所に提出する必要がある個人再生や自己破産の手続きでは、債権者一覧表は必須の提出書類となっています。債務の全体像を正確に把握することで、最適な債務整理方法を選択するための重要な判断材料となります。
| 債権者一覧表の役割 |
|
|---|
この表は債権者一覧表が債務整理において果たす主な役割を示しています。債務整理の種類を問わず、まずは自分の借金状況を正確に把握することが第一歩となります。
債権者一覧表に記載する内容
債権者一覧表には、以下のような情報を記載します。これらの情報は債務整理手続きを進める上で必要となるため、できるだけ正確に記入することが大切です。
- 債権者(貸金業者、クレジットカード会社など)の名称
- 債権者の住所・連絡先
- 契約日・借入日
- 借入金額(元本)
- 現在の残高
- 金利
- 取引履歴の有無
- 担保の有無
- 保証人の有無とその情報
上記の項目は債権者一覧表に記載する基本的な内容です。債務整理の種類や依頼する専門家によって、必要とされる項目が若干異なる場合があります。
特に過払い金請求を検討している場合は、取引開始日や取引履歴の有無が重要な情報となります。グレーゾーン金利で取引をしていた期間がある場合、過払い金が発生している可能性があるためです。
債権者一覧表の作成方法
債権者一覧表を作成するためには、まず自分の借金状況を正確に把握する必要があります。以下の手順で作成していきましょう。
- 借入先を全て思い出し、リストアップする
- 各借入先から取引履歴(取引明細)を取り寄せる
- 取り寄せた資料を基に、各項目を正確に記入する
- 記入漏れがないか確認する
- 専門家(弁護士・司法書士)に確認してもらう
上記の手順で債権者一覧表を作成していきます。特に重要なのは、すべての借入先を漏れなくリストアップすることです。思い出せない場合は、信用情報機関に信用情報開示請求を行うことも検討しましょう。
| 取引履歴の取り寄せ方 |
|
|---|
この表は取引履歴を取り寄せる主な方法を示しています。弁護士や司法書士に依頼すると、専門家が代理で取引履歴を取り寄せてくれるため、手間を省くことができます。
債権者一覧表作成時の注意点
債権者一覧表を作成する際には、以下の点に注意しましょう。正確な情報を記載することで、債務整理手続きがスムーズに進みます。
- すべての借入先を漏れなく記載する
- 債権者の正式名称を使用する
- 最新の残高情報を記載する
- 保証人がいる場合は必ず記載する
- 抵当権などの担保権が設定されている場合は明記する
- 不明な点は空欄にせず、「不明」と記載する
特に注意すべき点は、すべての借入先を記載することです。意図的に隠した場合、債務整理手続きが無効になったり、免責不許可事由となったりする可能性があります。
また、保証人がいる場合は、債務整理によって保証人に請求が行く可能性があるため、必ず記載するようにしましょう。債務整理の方法によっては、保証人の同意が必要になるケースもあります。
| 記載漏れが起きやすい債務の例 |
|
|---|
この表は債権者一覧表への記載を忘れやすい債務の例です。消費者金融やクレジットカードだけでなく、公共料金の滞納なども債務に含まれることを忘れないようにしましょう。
よくある質問
債権者一覧表は自分で作成しなければならないのですか?
債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、専門家が債権者一覧表の作成をサポートしてくれます。ただし、借入先の情報や大まかな金額は依頼者自身が把握している必要があります。
専門家に依頼する場合でも、手元にある借金関連の書類(契約書、返済予定表、取引履歴など)はすべて準備しておくことをおすすめします。
すべての借入を思い出せない場合はどうすればよいですか?
すべての借入先を思い出せない場合は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に信用情報開示請求を行うことで、自分の借入状況を確認することができます。
ただし、信用情報は一定期間で削除されるため、古い借入については記録が残っていない場合があります。その場合は、手元にある古い書類や通帳の記録を確認することも大切です。
過払い金請求をする場合、債権者一覧表に何か追加情報が必要ですか?
過払い金請求を検討している場合は、取引開始日や取引履歴の保存状況についても記載しておくと良いでしょう。特に2010年6月17日以前(グレーゾーン金利時代)から取引がある場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求では、取引履歴の取り寄せが非常に重要となるため、取引履歴の有無や保存状況についても記載しておくことをおすすめします。
まとめ
債権者一覧表は、債務整理を行う上で欠かせない基本的な書類です。すべての借入先と借入状況を正確に記載することで、債務整理手続きがスムーズに進みます。
自分で作成することも可能ですが、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する場合は、専門家のサポートを受けながら作成することができます。その場合でも、自分の借入状況をできるだけ正確に把握しておくことが大切です。
特に、すべての借入先を漏れなく記載することは非常に重要です。意図的に隠した場合、債務整理手続きが無効になったり、免責不許可事由となったりする可能性があるため注意しましょう。
また、過払い金請求を検討している場合は、取引開始日や取引履歴の有無についても記載しておくと、過払い金の有無を判断する際に役立ちます。債権者一覧表を正確に作成することが、成功する債務整理への第一歩となります。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



