債権認否一覧表(さいけんにんぴいちらんひょう)について詳しく解説
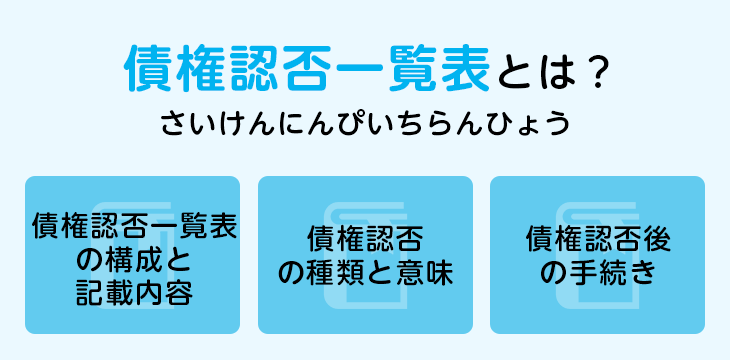
債権認否一覧表とは、自己破産や民事再生などの法的債務整理手続きにおいて、債権調査期日に提出される書類で、債権者が届け出た債権について、その存在や金額を認めるか否かを一覧にしたものです。破産管財人や再生委員、債務者などが各債権について「認める」「一部認める」「認めない」などの判断を示します。
この一覧表は、どの債権が債務整理手続きの対象となるかを決定する重要な文書であり、配当や弁済の基礎となります。認否の結果によっては、債権確定訴訟が必要になる場合もあります。
債権認否一覧表とは
債権認否一覧表は、債権調査期日において作成される公式文書で、債権者が届け出た債権の内容と、それに対する破産管財人や再生委員、債務者の認否結果を一覧形式で記載したものです。
この一覧表は、裁判所に提出され、債務整理手続きにおける債権の確定や配当・弁済の基礎資料となります。債権者にとっては、自分の債権が認められたかどうかを確認する重要な文書です。
債権認否一覧表の役割
債権認否一覧表には、主に以下のような役割があります。
| 債権認否一覧表の主な役割 |
|
|---|
この表は債権認否一覧表が果たす主な役割を示しています。債権認否一覧表は、債務整理手続きの透明性と公平性を確保するための重要な文書です。
債権認否一覧表が使用される手続き
債権認否一覧表は、主に以下のような法的債務整理手続きで使用されます。
- 自己破産手続き
- 民事再生手続き(個人再生を含む)
- 会社更生手続き
- 特別清算手続き
これらの手続きでは、債権調査期日において債権認否一覧表が作成され、各債権の認否が行われます。任意整理では、裁判所が関与しないため、このような公式な一覧表は作成されません。
債権認否一覧表の構成と記載内容
債権認否一覧表には、債権者が届け出た債権の詳細情報と、それに対する認否結果が記載されます。一覧表の具体的な構成と記載内容について解説します。
債権認否一覧表の基本構成
債権認否一覧表は、通常、以下のような項目で構成されています。
| 債権認否一覧表の主な項目 |
|
|---|
この表は債権認否一覧表に記載される主な項目を示しています。実際の一覧表は裁判所によって形式が若干異なる場合がありますが、基本的な情報は共通しています。
債権者情報の記載
債権認否一覧表には、債権者ごとに以下のような情報が記載されます。
まず、債権者の基本情報として、氏名(法人の場合は名称)、住所、連絡先などが記載されます。また、代理人がいる場合は、代理人の氏名や所属事務所なども記載されます。
債権者の情報は、債権届出書に基づいて記載されるため、債権届出時に正確な情報を提供することが重要です。特に、配当金の振込先となる金融機関の口座情報も含まれる場合があります。
債権情報の記載
各債権者の債権内容として、以下の情報が記載されます。
- 債権額:元本、利息、遅延損害金などを区別して記載
- 債権の種類:一般債権、優先債権、劣後債権など
- 債権の発生原因:契約の種類、契約日など
- 担保権の有無:抵当権、質権、譲渡担保などの詳細
これらの情報も債権届出に基づいて記載されますが、破産管財人や再生委員が調査した結果、実際の債権内容が異なると判断した場合は、その点も一覧表に反映されます。
認否結果の記載
債権認否一覧表の最も重要な部分が、各債権に対する認否結果です。認否結果は、通常、以下のいずれかで示されます。
- 認める:債権の存在と金額を全て認める
- 一部認める:債権の一部のみを認める(どの部分を認めるかも記載)
- 認めない:債権の存在自体を否定する(理由も記載)
- 留保:判断を保留する(保留の理由も記載)
一部認める場合や認めない場合は、その理由も記載されます。例えば、利息や遅延損害金の計算が誤っている場合や、時効が完成している場合などです。
債権認否の種類と意味
債権認否一覧表における認否の種類と、各認否が持つ法的な意味について詳しく解説します。
「認める」の意味と効果
債権が「認める」とされた場合、債権の存在と金額が確定し、そのまま配当や弁済の対象となります。債権者にとっては最も望ましい結果です。
「認める」とされた債権は、特別な手続きを経ることなく確定し、債権者表に確定債権として記載されます。債権者は債権確定のための追加の手続きを行う必要はありません。
ただし、他の債権者が異議を述べた場合は、その債権者との間で債権確定訴訟が必要になることがあります。
「一部認める」の意味と効果
債権が「一部認める」とされた場合、認められた部分については確定しますが、認められなかった部分については債権者が異議を述べなければ確定しません。
例えば、元本100万円、利息20万円、遅延損害金30万円の債権について、元本と利息は認めるが遅延損害金は計算に誤りがあるため15万円しか認めないという場合、元本100万円と利息20万円は確定しますが、遅延損害金は15万円に減額されます。
債権者が減額に納得できない場合は、認められなかった部分(この例では遅延損害金の差額15万円分)について、債権確定訴訟を提起する必要があります。
「認めない」の意味と効果
債権が「認めない」とされた場合、その債権は確定せず、配当や弁済の対象外となります。債権者が債権の存在を主張するためには、債権確定訴訟を提起する必要があります。
「認めない」とされる主な理由としては、以下のようなものがあります。
- 債権の存在を証明する資料が不十分
- 既に弁済済みの債権
- 時効が完成している債権
- 債権の計算に根本的な誤りがある
- 債権譲渡の手続きに不備がある
「認めない」とされた債権について債権確定訴訟を提起しない場合、その債権は「存在しない」と確定し、債務整理手続きにおいて一切考慮されなくなります。
「留保」の意味と効果
債権が「留保」とされた場合、現時点では判断を保留し、追加の調査や資料提出を経て後日判断するということを意味します。
「留保」とされる主な理由としては、以下のようなものがあります。
- 債権の内容を判断するための資料が不足している
- 債権の計算方法が複雑で検証に時間がかかる
- 他の債権との関連性を調査する必要がある
- 債権の法的性質に疑義がある
「留保」とされた債権は、後日改めて認否が行われます。債権者は追加資料の提出を求められることが多いため、速やかに対応することが重要です。
| 認否の種類と債権者の対応 |
|
|---|
この表は各認否の種類に応じた債権者の対応を示しています。債権者は認否結果に応じて適切な対応をとることが重要です。
債権認否後の手続き
債権認否一覧表に基づいて債権の認否が行われた後、債権者や債務者はどのような手続きを取ることができるのか、また、債権はどのように確定するのかについて解説します。
債権者による異議申立て
債権者は、自分の債権が「一部認める」または「認めない」とされた場合、その結果に不服があれば異議を申し立てることができます。
異議申立ての期間は、通常、債権調査期日から2週間程度とされていますが、裁判所によって異なる場合があります。この期間内に異議を申し立てなければ、認否結果が確定してしまいます。
異議申立ては、裁判所に「債権確定訴訟提起予告届」などを提出することで行います。その後、一定期間内に債権確定訴訟を提起する必要があります。
債権確定訴訟
債権確定訴訟は、債権の存在や金額について争いがある場合に、裁判所の判断によって債権を確定させるための訴訟です。
訴訟の提起期間は、通常、異議申立てから1ヶ月以内とされていますが、裁判所によって異なる場合があります。この期間内に訴訟を提起しなければ、異議申立ての効力が失われ、認否結果が確定します。
債権確定訴訟では、債権者が債権の存在と金額を証明する責任があります。訴訟の結果、債権の存在や金額が裁判所によって確定されると、その内容に基づいて配当や弁済が行われます。
他の債権者による異議
債権認否において、他の債権者も他の債権者の債権に対して異議を述べることができます。これは、不当な債権によって自分の取り分が減ることを防ぐためです。
例えば、A社がB社の債権について「架空の債権ではないか」と異議を述べると、B社はA社に対して債権確定訴訟を提起する必要があります。
他の債権者による異議は、主に以下のような場合に行われます。
- 架空の債権や水増しされた債権が疑われる場合
- 関連会社間の不自然な債権が疑われる場合
- 債権の優先順位に異議がある場合
- 債権の計算方法に誤りがある場合
他の債権者による異議は、債務整理手続きの公平性を確保するための重要な制度ですが、実際にはあまり頻繁には行われません。
債権の最終確定と配当・弁済
債権認否の結果に対する異議申立期間が経過し、債権確定訴訟がある場合はその判決が確定すると、債権が最終的に確定します。
確定した債権は「債権者表」に記載され、その内容に基づいて配当や弁済が行われます。配当や弁済の方法や時期は、債務整理の種類や事案によって異なります。
- 自己破産:債務者の財産が換価され、優先順位に従って配当が行われる
- 個人再生:再生計画に基づいて、一定期間にわたり弁済が行われる
- 会社更生:更生計画に基づいて、会社の再建と並行して弁済が行われる
- 特別清算:清算計画に基づいて、会社の財産から弁済が行われる
配当や弁済は、確定した債権額に基づいて行われます。債権者にとっては、債権の確定プロセスを適切に進めることが、最大限の回収を図るために重要です。
| 債権確定から配当・弁済までの流れ |
|
|---|
この表は債権確定から配当・弁済までの一般的な流れを示しています。実際の手続きは事案によって異なる場合がありますが、基本的な流れは共通しています。
よくある質問
債権認否一覧表はどこで確認できますか?
債権認否一覧表は、債権調査期日後に裁判所で閲覧することができます。また、自分の債権に関する部分については、裁判所から通知が送られてくる場合もあります。
債権者が弁護士などの代理人を立てている場合は、代理人を通じて認否結果を確認することができます。不明な場合は、裁判所の破産部や再生部に問い合わせるとよいでしょう。
債権が「一部認める」とされた場合、必ず異議を申し立てる必要がありますか?
「一部認める」とされた場合でも、認められなかった部分の金額が少額であったり、異議申立てや訴訟のコストを考慮すると見合わないと判断できる場合は、異議を申し立てない選択肢もあります。
例えば、100万円の債権のうち95万円が認められ、5万円が認められなかった場合、5万円分のために訴訟を提起するコストと労力を考えると、認められた95万円で納得するという判断も合理的です。
債権確定訴訟はどのくらいの期間と費用がかかりますか?
債権確定訴訟の期間は、事案の複雑さや裁判所の状況によりますが、一般的には半年〜1年程度かかることが多いです。複雑な事案や争点が多い場合は、さらに長期化することもあります。
費用については、訴額(争いのある債権額)によって変わりますが、裁判所に納める印紙代、弁護士に依頼する場合は弁護士費用などがかかります。債権額が少額の場合は、訴訟費用が回収可能額を上回ることもあるため、費用対効果を考慮する必要があります。
債権者が複数ある場合、全ての債権者の認否結果が分かりますか?
債権認否一覧表には、原則として全ての届出債権とその認否結果が記載されます。債権者は、裁判所で債権認否一覧表を閲覧することで、他の債権者の債権内容や認否結果を知ることができます。
ただし、プライバシーの観点から、個人情報や特に秘匿性の高い情報については一部非公開となる場合もあります。また、大規模な事案では、膨大な数の債権者がいるため、全ての情報を確認するのは実務的に困難なこともあります。
まとめ
債権認否一覧表は、自己破産や民事再生などの法的債務整理手続きにおいて、債権者が届け出た債権に対する認否結果を一覧にした重要な文書です。この一覧表は、どの債権が債務整理手続きの対象となるかを決定し、配当や弁済の基礎となります。
債権認否一覧表には、債権者の情報、債権の種類と金額、債権の発生原因、担保権の有無など、債権に関する詳細情報と、それに対する「認める」「一部認める」「認めない」「留保」などの認否結果が記載されます。
債権者は、自分の債権に対する認否結果に不服がある場合、一定期間内に異議を申し立て、債権確定訴訟を提起することができます。また、他の債権者の債権に対しても異議を述べることができます。
債権の最終確定後は、その内容に基づいて配当や弁済が行われます。債権者にとっては、自分の債権が適切に認められ、最大限の回収を図るために、債権認否の結果を確認し、必要に応じて適切な対応をとることが重要です。
債権認否一覧表に関して不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、債務整理手続きにおける自分の権利を守ることができます。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



