押し貸し(おしがし)について詳しく解説
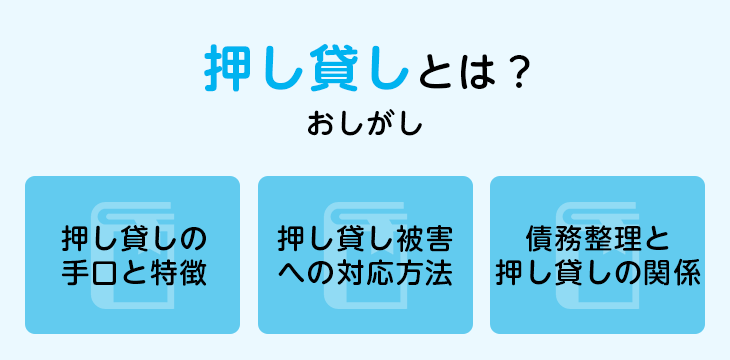
押し貸しとは、消費者金融業者や闇金融業者が、借り手が希望していないにもかかわらず、強引に融資を行う違法な貸付行為のことです。この手口では、借り手の意思に反して契約を結ばせ、不当に高い金利での返済を迫ります。特に過払い金請求や債務整理の相談を始めた人が標的にされるケースが多く見られます。
押し貸しは貸金業法違反であり、犯罪行為にあたります。押し貸しの被害に遭った場合は、支払い義務がないのが原則ですが、適切な対応が必要です。債務整理を検討している方は、このような手口に注意し、不審な融資の申し出があった場合は専門家に相談することが大切です。
押し貸しとは
押し貸しとは、消費者金融業者や闇金融業者が、借り手が希望していないにもかかわらず強引に融資を行う違法な貸付行為です。貸金業法で禁止されている不適切な勧誘行為の一種であり、犯罪行為に該当します。
このような行為は、一般的に高金利での返済を迫るために行われ、後に取り立てや嫌がらせを伴うケースも少なくありません。押し貸しでは、金銭を借りる意思がなくても「契約した」とみなされ、借金を背負わされる危険性があります。
| 押し貸しの定義 | 借り手の意思に反して、または借り手が希望していないにもかかわらず、強引に融資を行う違法な貸付行為 |
|---|---|
| 法的位置づけ | 貸金業法第16条(不適切な勧誘行為の禁止)違反、場合によっては詐欺罪や強要罪に該当 |
| 主な実行者 |
|
この表は押し貸しの基本情報をまとめたものです。押し貸しは違法行為であり、被害者には法的保護が与えられますが、実際に被害回復は容易ではないケースも多いです。
押し貸しの手口と特徴
押し貸しにはいくつかの典型的な手口があります。これらの手口を知ることで、被害を未然に防ぐことができます。主な手口と特徴は以下のとおりです。
- 突然の振込:断っているにもかかわらず、銀行口座に勝手に融資金を振り込む
- 契約書の偽造:借り手の署名を偽造して契約したことにする
- クレジットカード不正利用:キャッシングの申し込みを装い、不正にカード情報を入手して融資を行う
- 過去の取引を利用:過去に取引があった顧客に対して「以前の契約に基づく融資」と称して押し付ける
- 債務整理相談者への接触:債務整理の相談をした人を狙い、「整理前の最後の融資」などと持ちかける
- 違法な個人情報の入手:何らかの方法で個人情報を入手し、その情報を元に融資を行う
上記のリストは押し貸しの主な手口です。いずれも借り手の意思に反して融資を行い、後に返済を迫るという点が共通しています。
押し貸しには以下のような特徴があります。これらの特徴に該当する場合は、押し貸しの可能性が高いため注意が必要です。
| 強引な勧誘 |
|
|---|---|
| 不透明な契約内容 |
|
| 異常な金利設定 |
|
この表は押し貸しの主な特徴をまとめたものです。これらの特徴を知っておくことで、押し貸しの被害を未然に防ぐ手助けとなります。
押し貸しが行われる状況
押し貸しは特定の状況や対象者を狙って行われることが多いです。どのような状況で押し貸しが行われやすいかを知ることで、注意を促すことができます。
- 債務整理相談後:弁護士や司法書士に債務整理の相談をした直後
- 過払い金請求後:過払い金請求を行った後、貸金業者から情報が漏れた場合
- 多重債務状態:複数の金融機関から借入がある状態
- 返済困難な状況:返済に行き詰まり、新たな借入先を探している状況
- 個人情報流出後:何らかの理由で個人情報が流出した後
- 借入申込の断念後:正規の借入を断念せざるを得なかった後
上記のリストは押し貸しが行われやすい主な状況です。特に債務整理の相談を始めた後に、見知らぬ業者から突然の融資の申し出があった場合は注意が必要です。
押し貸しの標的となりやすい人には以下のような特徴があります。
| 経済的に困窮している人 |
|
|---|---|
| 債務整理関連の行動をした人 |
|
| 金融知識が不足している人 |
|
この表は押し貸しの標的となりやすい人の特徴をまとめたものです。これらの状況に該当する方は、見知らぬ業者からの融資の申し出には特に注意が必要です。
押し貸しの法的問題点
押し貸しは様々な法律に違反する違法行為です。押し貸しがどのような法律に違反しているのかを理解することで、被害者の法的保護についても理解が深まります。
- 貸金業法違反:不適切な勧誘行為の禁止(第16条)に違反
- 利息制限法違反:法定金利を超える金利での貸付
- 出資法違反:上限金利を超える金利での貸付
- 詐欺罪:虚偽の説明や契約内容で融資を行う行為
- 強要罪:脅迫めいた言動で融資を受けるよう強要する行為
- 個人情報保護法違反:不正に入手した個人情報の利用
上記のリストは押し貸しが違反する主な法律です。押し貸しは単なる悪質な商法ではなく、刑事罰の対象となる犯罪行為である点が重要です。
押し貸しによる契約は法的に無効となる可能性が高いです。その理由は以下の通りです。
| 公序良俗違反 |
|
|---|---|
| 強迫・詐欺による意思表示 |
|
| 契約不成立 |
|
この表は押し貸しによる契約が法的に無効となる理由をまとめたものです。押し貸しの被害者は原則として返済義務を負わないとされていますが、適切な法的手続きが必要です。
押し貸し被害への対応方法
押し貸しの被害に遭った場合、適切な対応が必要です。以下に具体的な対応方法をご紹介します。
- 振り込まれた金銭に手を付けない:使用すると「黙示の承諾」とみなされるリスクがある
- 契約書や振込通知などの証拠を保存する:後の法的手続きのために重要
- 業者からの連絡記録を残す:通話録音や着信履歴、メールなどを保存
- 専門家(弁護士・司法書士)に相談する:適切な法的対応を相談
- 警察に被害届を提出する:特に脅迫や暴力を伴う場合は必須
- 金融庁や消費者センターに相談する:被害の拡大防止のため
- 振込先の銀行に状況を説明する:場合によっては返金手続きが可能
上記のリストは押し貸し被害に遭った場合の主な対応方法です。特に重要なのは、振り込まれた金銭に手を付けないことと、専門家に相談することです。
振り込まれた金銭への対応
- 振り込まれた金銭には絶対に手を付けない
- 業者に対して書面で契約の意思がないことを通知する
- 返金方法について専門家に相談する
- 専門家の指示に従って返金手続きを行う
- 返金した証拠(振込控えなど)を保管する
上記のリストは振り込まれた金銭への対応手順です。振り込まれた金銭を使用すると「黙示の承諾」とみなされるリスクがあるため、絶対に手を付けないことが重要です。
取立てへの対応
| 迷惑電話・訪問 |
|
|---|---|
| 脅迫・暴力 |
|
| 周囲への嫌がらせ |
|
この表は押し貸し業者からの取立てへの対応方法をまとめたものです。脅迫や暴力を伴う取立ては犯罪行為であり、すぐに警察に通報することが重要です。
債務整理と押し貸しの関係
債務整理と押し貸しには深い関係があります。債務整理を検討している人や手続きを始めた人が、押し貸しの標的になることが少なくありません。その関係性と対応方法を理解しましょう。
債務整理と押し貸しの関連性
- 情報漏洩:債務整理の相談をした情報が何らかの形で漏れ、押し貸し業者に渡る
- 最後の融資:「債務整理前の最後のチャンス」と称して融資を持ちかける
- 返済不能の悪用:返済が困難な状況を悪用して融資を押し付ける
- 過払い金の狙い:過払い金返還請求後に「つなぎ融資」と称して接触
- 整理後の狙い:債務整理後の借入制限期間中に融資を持ちかける
上記のリストは債務整理と押し貸しの主な関連性です。債務整理を検討している方は、これらの状況に特に注意する必要があります。
債務整理中の押し貸し対応
| 債務整理前・相談中 |
|
|---|---|
| 債務整理手続き中 |
|
| 債務整理後 |
|
この表は債務整理の各段階での押し貸し対応をまとめたものです。債務整理中は新たな借入ができないことを理解し、不審な融資の申し出には絶対に応じないことが重要です。
よくある質問
押し貸しで振り込まれたお金を使ってしまった場合はどうなりますか?
振り込まれたお金を使ってしまうと、「黙示の承諾」があったとみなされる可能性があります。その場合、契約の成立を否定することが難しくなり、返済義務を負う可能性が高まります。
ただし、脅迫や詐欺など違法な手段で融資が行われた場合は、消費したとしても契約の無効や取消しを主張できる余地があります。いずれにせよ、このような状況になった場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
正規の貸金業者も押し貸しを行うことがありますか?
登録された正規の貸金業者が明らかな押し貸しを行うことは稀ですが、グレーゾーンの勧誘行為を行うケースはあります。例えば、執拗な勧誘や不十分な説明、書面を十分に確認させない契約などは、正規業者でも見られることがあります。
正規業者による不適切な勧誘行為があった場合は、金融庁や各都道府県の貸金業監督部署に相談・通報することができます。貸金業法に基づく業務改善命令や行政処分の対象となる可能性があります。
押し貸しの被害にあった場合、返済する必要はありますか?
押し貸しは違法行為であり、原則として返済義務はありません。特に契約書の偽造や無断振込など、そもそも契約が成立していない場合や、脅迫・詐欺などによる契約の場合は、法的に無効または取消可能とされています。
ただし、実際には返済を強要されるケースも多いため、専門家(弁護士・司法書士)に相談して適切な対応を取ることが重要です。専門家に依頼することで、契約の無効確認や不当利得返還請求など、法的な手続きを進めることができます。
まとめ
押し貸しとは、消費者金融業者や闇金融業者が、借り手が希望していないにもかかわらず強引に融資を行う違法な貸付行為です。貸金業法をはじめとする各種法律に違反する犯罪行為であり、被害者は法的保護の対象となります。
押し貸しの手口には、突然の振込、契約書の偽造、クレジットカードの不正利用などがあります。特に債務整理の相談をした後や、多重債務状態にある人が標的になりやすいため、このような状況にある方は特に注意が必要です。
押し貸しの被害に遭った場合は、振り込まれた金銭に手を付けない、証拠を保存する、専門家に相談する、警察に被害届を提出するなどの対応が重要です。特に振り込まれた金銭を使用すると「黙示の承諾」とみなされるリスクがあるため、絶対に手を付けないことが大切です。
債務整理と押し貸しには深い関係があり、債務整理を検討している人や手続きを始めた人が押し貸しの標的になることが少なくありません。債務整理の各段階で適切な対応を取り、不審な融資の申し出には絶対に応じないことが重要です。
押し貸しは違法行為であり、原則として返済義務はありませんが、実際には返済を強要されるケースも多いため、専門家(弁護士・司法書士)に相談して適切な対応を取ることをおすすめします。健全な家計管理を心がけ、借入に頼らない生活を目指すことが、根本的な解決策となります。
債務問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが大切です。押し貸しの被害予防と対応のために、正しい知識を身につけ、不審な融資の申し出には注意しましょう。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



