公正証書(こうせいしょうしょ)について詳しく解説
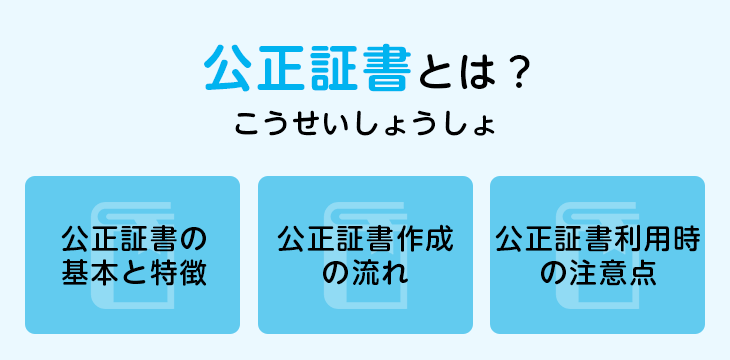
公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公文書のことです。債務整理の場面では、債権者と債務者の間で和解や分割払いの合意をする際に作成されることが多く、強い法的効力を持ちます。特に任意整理において、返済条件の変更を確実に履行するための手段として利用されます。
公正証書には「執行認諾文言」を付けることができ、これにより裁判を経ずに強制執行が可能になるため、債権者にとっては債権回収の確実性が高まり、債務者にとっては誠意を示す手段となります。
公正証書の基本と特徴
公正証書は、公証人法に基づいて公証人が作成する公文書です。単なる私文書とは異なり、高い証明力と法的効力を持ちます。債務整理の場面では、債務の存在や返済条件を明確に記録する役割を果たします。
公証人は法務大臣から任命された法律の専門家で、公正証書の作成は公証役場で行われます。作成された公正証書は原本が公証役場に保管され、当事者には正本や謄本が交付されます。
| 公正証書の法的効力 |
|
|---|---|
| 公正証書の種類 |
|
上記の表は公正証書の基本的な法的効力と種類をまとめたものです。債務整理の場面で利用されるのは主に契約や和解を証明する公正証書です。執行認諾文言を付けることで、裁判を経ずに強制執行が可能になる点が大きな特徴です。
債務整理における公正証書の役割
債務整理の各手続きにおいて、公正証書はそれぞれ異なる役割を果たします。特に任意整理では重要な役割を持ち、債権者と債務者の合意内容を明確にして法的に担保する機能があります。
- 任意整理:債権者との和解内容(元金カット、利息カット、分割払いなど)を公正証書にして法的に確定させる
- 特定調停:調停条項を公正証書にして執行力を付与することがある
- 個人再生:公正証書は直接関係しないが、再生計画案の履行を担保する手段として使われることもある
- 自己破産:公正証書は直接関係しないが、破産前の債務証明として使われることがある
- 過払い金請求:和解内容を公正証書にして法的に確定させることがある
上記のリストは債務整理の各手続きにおける公正証書の役割をまとめたものです。特に任意整理では、債権者が債務者の誠意を確認する手段として公正証書の作成を求めることが多く、和解成立の条件となることもあります。
公正証書作成の流れ
公正証書の作成は一定の手順に従って行われます。債務整理の場面では、債権者と債務者(または代理人)が合意した内容を公正証書化するプロセスとなります。
- 事前準備:公正証書に記載する合意内容の確認、必要書類の準備
- 公証役場への予約:電話や公証役場のウェブサイトで予約
- 必要書類の提出:本人確認書類、合意書のドラフトなど
- 公証人による内容確認:法的に問題がないか審査
- 公正証書案の作成:公証人が原案を作成
- 公証日の出頭:当事者(または代理人)が公証役場に出頭
- 公証人による読み聞かせと確認:内容を確認し、不明点があれば質問
- 署名・押印:当事者と公証人が署名・押印
- 手数料の支払い:公証人手数料と印紙代を支払う
- 公正証書の交付:正本や謄本が交付される
上記のステップは公正証書作成の一般的な流れです。債務整理の場合、特に任意整理では弁護士や司法書士が代理人として手続きを行うことが多いです。公正証書の作成には費用がかかりますが、その額は記載される債務額などによって変動します。
公正証書に含まれる主な条項
債務整理における公正証書には、債務の弁済に関する様々な条項が含まれます。特に重要な条項について理解しておくことで、債務者は自分の権利と義務を明確に把握できます。
| 基本事項 |
|
|---|---|
| 弁済条件 |
|
| 期限の利益喪失条項 | |
| 執行認諾文言 |
|
上記の表は債務整理における公正証書に含まれる主な条項をまとめたものです。特に「期限の利益喪失条項」と「執行認諾文言」は債務者にとって重要な意味を持ちます。これらにより債務者が返済を怠った場合、残債務の一括請求や強制執行の対象となる可能性があります。
公正証書利用時の注意点
公正証書を利用する際には、債務者として知っておくべきいくつかの重要な注意点があります。公正証書は強い法的効力を持つため、その内容を十分に理解してから作成することが重要です。
執行認諾文言の意味を理解する
執行認諾文言が付された公正証書は、債務名義となります。これは支払いを怠った場合、裁判を経ることなく債務者の財産に対して強制執行が可能になることを意味します。
具体的には、給与や預金の差押え、不動産や動産の競売などの対象となる可能性があります。この文言の重大性を十分に理解した上で公正証書を作成する必要があります。
期限の利益喪失条項を確認する
公正証書には通常、支払いを怠った場合に期限の利益を失う条項が含まれます。例えば「2回連続して支払いを怠った場合」などの条件が設定されます。
期限の利益を喪失すると、残りの債務を一括で支払う義務が生じます。この条項の内容と効果を十分に理解し、自分の返済能力に見合った条件になっているか確認することが重要です。
作成費用の負担を確認する
公正証書の作成には公証人手数料と印紙代がかかります。一般的に債務者負担となることが多いですが、債権者との交渉次第では分担することも可能です。
費用は債務額によって変動するため、事前に概算額を確認しておくとよいでしょう。司法書士や弁護士に依頼している場合は、別途手数料がかかることも考慮する必要があります。
よくある質問
公正証書の返済条件は変更できる?
公正証書の内容は、原則として一方的に変更することはできません。返済条件の変更が必要になった場合は、債権者との再交渉が必要です。
債権者が同意すれば、新たな公正証書を作成することで返済条件を変更することが可能です。病気や失業など、やむを得ない事情がある場合は、早めに債権者に相談することをおすすめします。
執行認諾文言なしの公正証書は意味がある?
執行認諾文言がなくても、公正証書には高い証明力があり、債務の存在や返済条件を明確に証明する効果があります。債権者が後から条件を変更しようとしても、公正証書があれば防ぐことができます。
ただし、執行認諾文言がない場合、債務者が返済を怠っても直ちに強制執行はできず、債権者は改めて訴訟を起こす必要があります。債権者が執行認諾文言なしの公正証書作成に応じるかどうかは、交渉次第です。
まとめ
公正証書は、公証人が作成する高い法的効力を持つ公文書です。債務整理、特に任意整理の場面では、債権者と債務者の合意内容を法的に確定させる重要な役割を果たします。執行認諾文言を付けることで、裁判を経ずに強制執行が可能になるという特徴があります。
公正証書の作成は公証役場で行われ、当事者または代理人の立会いのもと、公証人が内容を確認して作成します。債務整理における公正証書には、債務額、返済条件、期限の利益喪失条項、執行認諾文言などの重要な条項が含まれます。
公正証書を利用する際の注意点としては、執行認諾文言の意味を理解すること、期限の利益喪失条項を確認すること、作成費用の負担を確認することなどが挙げられます。これらを十分に理解せずに公正証書を作成すると、後々トラブルの原因となる可能性があります。
債務整理の手続きにおいて公正証書を作成する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自分の状況に合った内容になっているか確認することをおすすめします。公正証書は債務者の返済意思を示す重要な文書であると同時に、履行されなかった場合の強制力も持つため、その意味を十分に理解した上で利用することが大切です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



