期限の利益(きげんのりえき)について詳しく解説
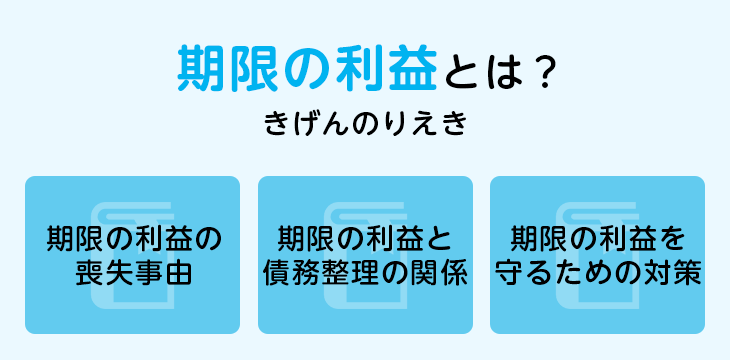
期限の利益とは、債務の支払いについて、一定の期限まで支払いを猶予されることによって債務者が受ける利益のことです。
例えば、ローンやクレジットカード契約では、毎月の返済日まで支払いを延期できることが「期限の利益」にあたります。この利益が失われると、残りの債務を一括で支払わなければならなくなります。債務整理を検討する際は、期限の利益の喪失が大きな問題となることがあります。
期限の利益とは
期限の利益とは、契約で定められた支払期限まで支払いを猶予されるという債務者の利益のことです。例えば、住宅ローンを35年間で返済する契約を結んだ場合、35年間にわたって分割払いができるという利益を得ています。
この「期限の利益」があるからこそ、私たちは将来の収入を見込んで高額な買い物やローンを組むことができます。もし期限の利益がなければ、借りたその場で全額を返済しなければならず、ローンやクレジットカードの分割払いは成立しません。
| 期限の利益がある場合 |
|
|---|---|
| 期限の利益がない場合 |
|
この表は期限の利益がある場合とない場合の違いを示しています。期限の利益があることで私たちは計画的な返済が可能になり、大きな買い物やローンを組むことができます。
期限の利益の喪失(失われる場合)
期限の利益は永続的に保証されているわけではなく、一定の条件に該当すると喪失(失われる)ことがあります。期限の利益を喪失すると、残りの債務を一括で支払わなければならなくなります。
期限の利益の喪失は、債務整理を検討する方にとって重要な概念です。多くの場合、返済が困難になって債務整理を考え始める時点で、すでに期限の利益を喪失している可能性があるからです。
| 期限の利益喪失の意味 | 契約で定められた分割払いの権利を失い、残債務を一括で支払う必要が生じること |
|---|---|
| 喪失の法的根拠 | 民法第137条および各種契約書の期限の利益喪失条項 |
| 喪失の通知方法 | 通常は「期限の利益喪失通知」として書面で通知される |
この表は期限の利益喪失の基本的な情報をまとめたものです。期限の利益の喪失は法律と契約に基づいており、一般的には書面で通知されます。
期限の利益の喪失事由
期限の利益が喪失する原因(喪失事由)には、様々なものがあります。契約書には通常、期限の利益喪失事由が詳細に記載されています。以下に代表的な喪失事由を紹介します。
- 支払いの遅延(一般的に2回以上の延滞で喪失)
- 虚偽の申告や契約違反
- 差押え・仮差押え・仮処分を受けた場合
- 破産・民事再生などの法的整理の申立て
- 他の債務の不履行(クロスデフォルト条項)
- 死亡または行方不明
- 担保価値の著しい減少
特に注意すべきは支払いの遅延です。一般的なローン契約では、2回以上の延滞で期限の利益を喪失すると定められていることが多いです。また、一部の契約では1回の延滞でも喪失する厳しい条件となっている場合もあります。
また、一つの借入れで期限の利益を喪失すると、他の借入れにも影響が及ぶことがあります。これは「クロスデフォルト条項」と呼ばれる契約条項によるものです。
期限の利益を喪失した場合の影響
期限の利益を喪失すると、債務者にとって様々な不利益が生じます。主な影響は以下の通りです。
- 残債務の一括返済義務が生じる
- 延滞情報が信用情報機関に登録される
- 新たな借入れやクレジットカードの利用が困難になる
- 督促や法的手続きが強化される
- 遅延損害金が発生する
- 担保がある場合は担保権の実行(競売など)が開始される可能性がある
この一覧は期限の利益喪失後に発生する主な影響をまとめたものです。残債務の一括返済義務だけでなく、信用情報への影響や督促の強化など、様々な不利益が生じます。
特に大きな影響として、信用情報機関への延滞情報の登録があります。これにより、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなり、住宅ローンの審査にも影響します。この情報は一般的に5〜10年間保存されるため、長期間にわたって影響が続きます。
期限の利益と債務整理の関係
債務整理と期限の利益は密接な関係があります。債務整理を検討する多くの方は、すでに返済が困難になっており、期限の利益を喪失している場合が少なくありません。
また、債務整理の種類によっては、手続き自体が期限の利益喪失事由となることもあります。債務整理の各手続きと期限の利益の関係は以下の通りです。
| 債務整理の種類 | 期限の利益との関係 |
|---|---|
| 任意整理 |
|
| 個人再生 |
|
| 自己破産 |
|
この表は債務整理の各手続きと期限の利益の関係を示しています。債務整理の種類によって期限の利益との関わり方が異なるため、手続きを選択する際は専門家に相談することが重要です。
期限の利益を守るための対策
返済が困難になった場合でも、できるだけ期限の利益を守ることが重要です。期限の利益を喪失すると、状況はさらに悪化することが多いためです。以下に期限の利益を守るための対策を紹介します。
- 支払日前に必ず口座残高を確認する
- 返済が難しい場合は事前に債権者に相談する
- リスケジュール(返済計画の見直し)を交渉する
- 一時的な返済猶予を申し出る
- 最低限の支払い(約定返済額の一部でも)を続ける
- 早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談する
返済が困難になった場合、多くの人は債権者との接触を避けがちですが、それは最悪の選択です。むしろ積極的に債権者と連絡を取り、状況を説明して交渉することが重要です。
多くの金融機関は、返済が困難になった債務者に対して、一定の条件下でリスケジュール(返済計画の見直し)や返済猶予などの対応を行っています。可能な限り早期に相談することで、期限の利益を守れる可能性が高まります。
よくある質問
期限の利益を喪失した後、復活させることはできますか?
場合によっては可能です。期限の利益喪失後でも、延滞分の支払いや債権者との交渉によって、期限の利益を復活させられることがあります。これは「期限の利益の回復」と呼ばれています。
ただし、期限の利益の回復は債権者の判断によるものであり、必ず認められるわけではありません。特に延滞が長期間続いている場合や、過去に何度も延滞を繰り返している場合は、回復が認められにくくなります。
クレジットカードの支払いを1回延滞しただけで期限の利益は喪失しますか?
クレジットカードの契約内容によって異なります。多くのクレジットカード契約では、2回以上の延滞で期限の利益を喪失すると定められていますが、1回の延滞でも喪失する厳しい条件の場合もあります。
また、同じカード会社でも、延滞の状況や過去の取引履歴によって対応が異なることがあります。正確な条件は、契約書(会員規約)で確認するか、カード会社に直接問い合わせることをおすすめします。
任意整理をすると期限の利益は必ず喪失しますか?
任意整理の手続き自体は、直接的には期限の利益喪失事由ではありません。ただし、任意整理を検討する段階ですでに返済が滞っており、期限の利益を喪失している場合が多いです。
また、任意整理では債権者に受任通知を送付しますが、これにより債権者側が期限の利益喪失の手続きを進めることもあります。しかし、任意整理の交渉がまとまれば、新たな返済計画に基づく期限の利益が設定されます。
まとめ
期限の利益とは、契約で定められた支払期限まで支払いを猶予されるという債務者の利益のことです。この利益があるからこそ、私たちは分割払いやローンを利用することができます。
しかし、支払いの遅延や契約違反などの一定の条件に該当すると、この期限の利益は喪失します。期限の利益を喪失すると、残りの債務を一括で支払わなければならなくなるだけでなく、信用情報に悪影響を及ぼし、督促や法的手続きが強化されるなど、様々な不利益が生じます。
債務整理と期限の利益は密接な関係があり、債務整理を検討する段階ですでに期限の利益を喪失しているケースが多くあります。また、債務整理の種類によっては、手続き自体が期限の利益喪失事由となることもあります。
返済が困難になった場合は、できるだけ期限の利益を守るために早めに対策を講じることが重要です。支払い前の口座残高確認や、返済が難しい場合の事前相談、リスケジュールの交渉などが有効な対策となります。
また、期限の利益を喪失した後でも、状況によっては「期限の利益の回復」が認められることがあります。返済問題に直面した際は、一人で抱え込まず、早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



