貸付停止(かしつけていし)について詳しく解説
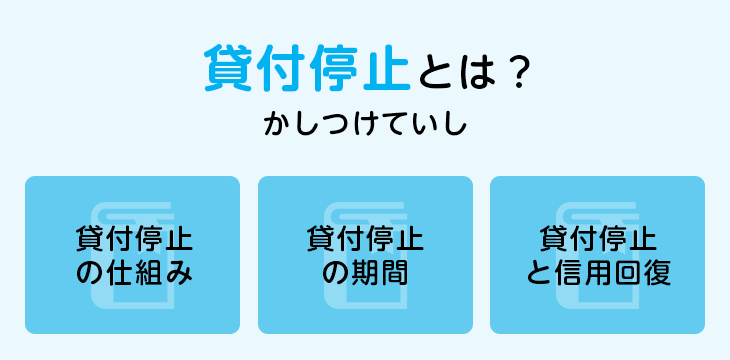
貸付停止とは、債務整理の手続きが開始された際に、債権者(貸金業者など)が債務者に対して新たな貸付や融資を停止する措置のことです。
債務整理の申立てや相談を行うと、信用情報機関に事故情報として登録され、その結果として貸金業者からの新規借入れや借り増しができなくなる状態を指します。
貸付停止とは
貸付停止とは、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)の手続きが開始された際に、債権者(貸金業者など)が債務者に対して新たな貸付や融資を停止する措置のことです。また、債務整理の相談や申立てを行うと、信用情報機関に事故情報として登録され、その結果として多くの金融機関から新規借入れや借り増しができなくなる状態も指します。
貸付停止は、債務者の返済能力に問題が生じていると判断された場合や、複数の債権者間の公平性を確保するために行われます。債務整理は借金問題を解決するための手段ですが、その一方で一定期間は新たな借入れが難しくなるという側面もあります。
| 貸付停止の主な理由 | |
|---|---|
| 貸付停止の対象範囲 |
|
上記の表は貸付停止の主な理由と対象範囲をまとめたものです。貸付停止は、債務整理を行う上での一時的な制約と考えることができます。
貸付停止が発生するケース
貸付停止が発生する主なケースには、以下のようなものがあります。債務整理の種類や状況によって、貸付停止の範囲や期間は異なります。
| 任意整理の場合 |
|
|---|---|
| 個人再生の場合 |
|
| 自己破産の場合 |
|
上記の表は債務整理の種類別に貸付停止の特徴をまとめたものです。いずれの債務整理でも、程度の差はあれ貸付停止の影響を受けることになります。
また、債務整理の前段階として、返済の延滞や滞納が発生した場合にも、信用情報機関に延滞情報が登録され、貸付停止に近い状態になることがあります。このため、返済が困難になった場合は、早めに対応策を検討することが重要です。
貸付停止の仕組み
貸付停止は、主に信用情報機関を通じた情報共有によって機能しています。債務整理や返済遅延などの情報は信用情報機関に登録され、金融機関はこの情報を審査時に参照します。
日本には、主に「CIC(シー・アイ・シー)」「JICC(日本信用情報機構)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つの信用情報機関があり、多くの金融機関がこれらの機関に加盟しています。債務整理の情報は、これらの信用情報機関に共有されます。
- 債務整理の申立てや相談を行う
- 債権者(貸金業者など)に情報が伝わる
- 債権者は信用情報機関に事故情報として登録
- 他の金融機関も情報を共有
- 融資審査時に事故情報が確認される
- 審査落ちとなり、貸付停止状態になる
上記のリストは貸付停止が発生する一般的な流れを示しています。信用情報機関のネットワークにより、一部の債権者との債務整理を行った場合でも、他の金融機関からの借入が困難になります。
なお、任意整理の場合は、債権者ごとに対応が異なり、整理対象外の債権者からの借入れが理論上は可能です。しかし、実際には信用情報の共有により、他の金融機関からの借入れも難しくなることが一般的です。
貸付停止の期間
貸付停止の期間は、債務整理の種類や信用情報機関によって異なります。一般的な登録期間は以下の通りです。
| 任意整理 | 完済から約5年間 |
|---|---|
| 個人再生 | 再生手続開始決定から約5〜10年間 |
| 自己破産 | 免責許可決定から約5〜10年間 |
| 返済遅延 | 完済から約5年間(遅延の程度により異なる) |
上記の表は信用情報機関における一般的な登録期間をまとめたものです。ただし、これらの期間はあくまで目安であり、各信用情報機関や金融機関によって取り扱いが異なる場合があります。
また、信用情報機関からの情報が削除された後も、各金融機関が独自に情報を保持している場合があります。このため、登録期間が経過したからといって、必ずしもすぐに借入れができるようになるわけではありません。信用を回復するためには、安定した収入を得て、計画的な資金管理を行うことが重要です。
貸付停止中の生活への対応
貸付停止中は新たな借入れが難しくなるため、生活面での対応が必要になります。以下に貸付停止中の主な対応策をまとめました。
- 収支の見直し(固定費の削減、不要な支出の見直しなど)
- 収入増加の工夫(副業、転職、資格取得など)
- 公的支援制度の利用(生活福祉資金貸付制度、生活保護など)
- 家族からの援助(可能な場合)
- デビットカードやプリペイドカードの活用
- 分割払いや後払いサービスの利用(与信審査の条件によっては利用できない場合も)
上記のリストは貸付停止中の主な対応策をまとめたものです。特に緊急時の資金需要に備えて、少額でも貯蓄を行うことが重要です。
また、貸付停止中でも利用できる可能性がある制度として「生活福祉資金貸付制度」があります。これは都道府県社会福祉協議会が運営する低利または無利子の貸付制度で、一定の条件を満たせば債務整理後でも利用できる場合があります。資金使途は限定されていますが、生活再建のための有効な選択肢の一つです。
貸付停止と信用回復
貸付停止の状態から信用を回復し、再び借入れができるようになるためには、一定の時間と努力が必要です。信用回復のための主なステップは以下の通りです。
| 債務整理の完了 | 債務整理手続きを確実に完了させ、残債務を計画通りに返済する |
|---|---|
| 信用情報の改善 | 信用情報機関の登録期間が経過するのを待つ (任意整理:約5年、個人再生・自己破産:約5〜10年) |
| 安定した収入の確保 | 継続的かつ安定した収入源を確保し、雇用の安定性を示す |
| 計画的な資金管理 | 貯蓄習慣の確立、計画的な支出管理の実践 |
| 段階的な信用構築 | デビットカードの利用から始め、少額のクレジットカードへと段階的に移行 |
上記の表は信用回復のための主なステップをまとめたものです。信用回復には時間がかかりますが、一歩ずつ着実に進めることが重要です。
なお、債務整理後でも比較的早い段階から利用できる可能性があるのがデビットカードやプリペイドカードです。これらのカードは預金残高の範囲内でしか利用できないため、与信審査が緩やかな傾向があります。また、一部のクレジットカード会社では、債務整理後でも一定期間が経過すれば審査に通る可能性があります。
よくある質問
債務整理をすると必ず貸付停止になりますか?
基本的には、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を行うと、ほぼ確実に一定期間の貸付停止状態になります。これは債務整理の情報が信用情報機関に登録され、多くの金融機関に共有されるためです。
ただし、任意整理の場合は整理対象外の債権者からの借入れが理論上は可能です。しかし、実際には信用情報の共有により、他の金融機関からの借入れも難しくなることが一般的です。債務整理を検討する際は、一時的に新規借入れができなくなることを前提に生活設計を考える必要があります。
貸付停止中でも利用できるローンはありますか?
貸付停止中でも、状況によっては利用できる可能性があるローンとして、「生活福祉資金貸付制度」があります。これは都道府県社会福祉協議会が運営する低利または無利子の貸付制度で、一定の条件を満たせば債務整理後でも利用できる場合があります。
また、親族や知人からの借入れ、勤務先の福利厚生制度による貸付制度などの選択肢もあります。ただし、これらはすべての人が利用できるわけではなく、条件や状況によって異なります。貸付停止中は、基本的には新たな借入れに頼らない生活設計を心がけることが重要です。
信用情報はどのように確認できますか?
自分の信用情報は、各信用情報機関に開示請求することで確認できます。主な信用情報機関は、「CIC(シー・アイ・シー)」「JICC(日本信用情報機構)」「全国銀行個人信用情報センター」の3つです。
開示請求の方法は、各機関のウェブサイトや窓口での申請、郵送による申請などがあります。本人確認書類が必要となりますが、自分の借入状況や返済状況、債務整理の記録などを確認することができます。定期的に信用情報を確認することで、信用回復の進捗状況を把握することができます。
まとめ
貸付停止とは、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)の手続きが開始された際に、債権者(貸金業者など)が債務者に対して新たな貸付や融資を停止する措置のことです。また、債務整理の相談や申立てを行うと、信用情報機関に事故情報として登録され、その結果として多くの金融機関から新規借入れや借り増しができなくなる状態も指します。
貸付停止は、主に信用情報機関を通じた情報共有によって機能しています。債務整理や返済遅延などの情報は信用情報機関に登録され、金融機関はこの情報を審査時に参照します。登録期間は債務整理の種類によって異なりますが、任意整理では完済から約5年間、個人再生や自己破産では手続開始・免責許可決定から約5〜10年間が一般的です。
貸付停止中は、収支の見直し、収入増加の工夫、公的支援制度の利用、デビットカードやプリペイドカードの活用などの対応が必要になります。特に緊急時の資金需要に備えて、少額でも貯蓄を行うことが重要です。
信用回復のためには、債務整理の完了、信用情報の改善(登録期間の経過)、安定した収入の確保、計画的な資金管理、段階的な信用構築などのステップを踏む必要があります。信用回復には時間がかかりますが、一歩ずつ着実に進めることが大切です。
債務整理は借金問題を解決するための有効な手段ですが、一時的に新規借入れができなくなるというデメリットもあります。債務整理を検討する際は、貸付停止の影響も考慮し、専門家(弁護士・司法書士)に相談しながら、自分の状況に最適な解決策を選ぶことが重要です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



