貸金業登録(かしきんぎょうとうろく)について詳しく解説
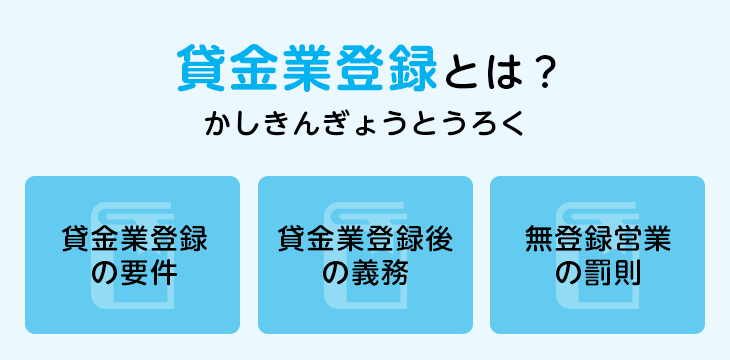
貸金業登録とは、金銭の貸付けを業として行うために必要な行政上の登録制度です。貸金業法に基づき、貸金業を営むためには内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。この登録制度は、違法な高金利貸付や悪質な取立てなどから借り手を保護するとともに、健全な貸金市場の形成を目的としています。
貸金業登録とは
貸金業登録とは、貸金業法(正式名称:貸金業法(昭和58年法律第32号))に基づき、金銭の貸付けを業として行うために必要な行政上の登録制度です。貸金業を営むためには、この登録を受けることが必須とされています。
この登録制度の目的は、違法な高金利貸付や悪質な取立てなどから借り手を保護するとともに、健全な貸金市場の形成を促進することにあります。2006年の貸金業法改正によって登録要件が厳格化され、貸金業者の数は大幅に減少しました。
| 法的根拠 | 貸金業法第3条「登録の義務」 |
|---|---|
| 登録の効果 | 適法に貸金業を営むことができる |
| 登録有効期間 | 3年間(更新可能) |
| 登録業者数の推移 | 改正前(2006年):約14,000業者 現在:約1,500業者程度 |
上記の表は貸金業登録の基本情報をまとめたものです。貸金業法改正後、登録要件の厳格化によって貸金業者数は大幅に減少し、より健全な業者のみが市場に残る形となりました。
貸金業登録の区分
貸金業登録には、営業所等の設置場所に応じて、「内閣総理大臣登録」と「都道府県知事登録」の2つの区分があります。それぞれの区分によって、登録申請先や監督官庁が異なります。
| 内閣総理大臣登録 |
|
|---|---|
| 都道府県知事登録 |
|
上記の表は貸金業登録の区分と特徴をまとめたものです。複数の都道府県で営業する場合は内閣総理大臣登録、一つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事登録となります。
なお、内閣総理大臣登録の場合、実際の申請先は金融庁ではなく、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(または沖縄総合事務局)となります。また、大手の消費者金融会社やクレジットカード会社の多くは内閣総理大臣登録を受けています。
貸金業登録の要件
貸金業登録を受けるためには、貸金業法で定められた様々な要件を満たす必要があります。2006年の貸金業法改正によって、登録要件は大幅に厳格化されました。主な登録要件は以下の通りです。
- 純資産要件:純資産が5,000万円以上(個人の場合は、資産から負債を控除した額が5,000万円以上)
- 人的要件:貸金業務取扱主任者の設置(営業所等ごとに1名以上)
- 組織要件:貸金業を適正に遂行するための組織体制の整備
- 欠格事由に該当しないこと
上記のリストは貸金業登録の主な要件をまとめたものです。特に純資産要件は、2006年の法改正で新たに導入された要件で、多くの小規模業者が登録を継続できなくなった大きな要因となりました。
また、欠格事由としては、貸金業法等に違反して罰金刑を受けた者、暴力団員等、破産者で復権を得ない者などが定められています。これらの欠格事由に該当する場合、登録を受けることができません。
| 主な欠格事由 |
|
|---|
上記の表は貸金業登録の主な欠格事由をまとめたものです。これらの欠格事由は、悪質な業者を排除し、健全な貸金市場を形成するために設けられています。
貸金業登録の手続き
貸金業登録を受けるための手続きは、申請書類の準備から始まり、審査を経て登録完了となります。一般的な流れは以下の通りです。
- 申請書類の準備(登録申請書、添付書類等)
- 申請書類の提出(内閣総理大臣登録は財務局へ、都道府県知事登録は都道府県へ)
- 登録免許税の納付(9万円)
- 審査(書類審査、必要に応じてヒアリングや現地調査)
- 登録可否の決定(通常は申請から1〜2ヶ月程度)
- 登録簿への登録
- 登録証の交付
上記のリストは貸金業登録の一般的な手続きの流れを示しています。登録申請には多くの書類が必要となり、準備にはある程度の時間がかかります。
主な申請書類としては、登録申請書のほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、純資産を証する書面、貸金業務取扱主任者証の写し、誓約書、業務運営規程などが必要です。また、役員等の住民票や身分証明書なども必要となります。
| 登録申請時の費用 |
|
|---|---|
| 登録審査のポイント |
|
上記の表は貸金業登録申請時の主な費用と審査のポイントをまとめたものです。登録審査は厳格に行われ、要件を満たさない場合は登録が拒否されることになります。
貸金業登録後の義務
貸金業登録を受けた後も、貸金業者には様々な義務が課せられています。これらの義務を遵守しなければ、業務改善命令や登録取消しなどの行政処分を受ける可能性があります。
| 帳簿書類の作成・保存 | 契約書、取引記録などの作成・保存義務(3年間) |
|---|---|
| 報告書の提出 | 半期ごとの業務報告書の提出義務 |
| 契約時の書面交付 | 契約締結時に必要事項を記載した書面の交付義務 |
| 取引履歴の開示 | 顧客からの請求に応じた取引履歴の開示義務 |
| 広告規制 | 誇大広告の禁止、必要事項の記載義務 |
| 上限金利の遵守 | 利息制限法・出資法の上限金利の遵守 |
| 総量規制の遵守 | 年収の3分の1を超える貸付けの原則禁止 |
| 登録更新 | 3年ごとの登録更新手続き |
上記の表は貸金業登録後の主な義務をまとめたものです。これらの義務は借り手の保護と健全な貸金市場の形成を目的としています。
特に重要なのは、上限金利の遵守と総量規制の遵守です。上限金利については、利息制限法の上限金利(元本に応じて年15%〜20%)が適用されます。また、総量規制により、原則として年収の3分の1を超える貸付けは禁止されています。
無登録営業の罰則
貸金業登録を受けずに貸金業を営むこと(無登録営業)は、貸金業法違反となり、厳しい罰則が科されます。また、無登録業者(いわゆる「ヤミ金融」)との取引は、借り手側にも様々なリスクがあります。
- 無登録営業の罰則:10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科
- 無登録営業の広告・勧誘の罰則:2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科
- 法人に対する両罰規定:行為者を罰するほか、法人に対しても罰金刑
上記のリストは無登録営業に対する主な罰則をまとめたものです。2006年の貸金業法改正によって罰則が強化され、無登録営業に対する取締りが厳格化されました。
なお、借り手側のリスクとしては、法外な高金利を請求される可能性、違法な取立てを受ける可能性、個人情報の悪用リスクなどがあります。また、無登録業者との契約は、法的保護を受けられない場合があります。貸金業者と取引をする際は、必ず貸金業登録の有無を確認することが重要です。
よくある質問
貸金業登録を受けている業者かどうかは、どのように確認できますか?
貸金業登録を受けている業者かどうかは、主に以下の方法で確認することができます。まず、金融庁が運営する「登録貸金業者情報検索サービス」を利用する方法があります。このサービスでは、業者名や登録番号から登録業者を検索できます。
また、貸金業者は広告や契約書に登録番号を記載する義務があるため、それらの書類でも確認できます。登録番号は「(財)第00000号」または「(○○都道府県知事)第00000号」という形式になっています。不明な点がある場合は、金融庁または都道府県の貸金業担当窓口に問い合わせることもできます。
無登録業者から借りた場合、返済義務はありますか?
無登録業者(ヤミ金融)から借りた場合でも、基本的には返済義務があります。ただし、違法な高金利(出資法の上限金利を超える金利)が設定されていた場合、その金利部分は無効となり、利息制限法の上限金利(元本に応じて年15%〜20%)が適用されます。
また、ヤミ金融の場合、そもそも貸付け自体が違法行為であるため、元本についても返済義務がないとする司法判断もあります。ヤミ金融とのトラブルに巻き込まれた場合は、すぐに警察や弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。安易に返済を続けると、被害が拡大する恐れがあります。
貸金業を少額・少人数に限って行う場合も登録は必要ですか?
貸金業法上、「業として」金銭の貸付けを行う場合には、貸付金額の大小や貸付先の多少にかかわらず、原則として貸金業登録が必要です。「業として」とは、反復継続して営利目的で行うことを意味します。
ただし、親族や知人など特定の関係にある者に対して、情誼によって一時的に貸付けを行う場合は、「業として」には該当せず、登録は不要とされています。また、法人が従業員に対して福利厚生として行う貸付けなども、一般的には貸金業には該当しません。判断に迷う場合は、金融庁または都道府県の貸金業担当窓口に事前に相談することをおすすめします。
まとめ
貸金業登録は、金銭の貸付けを業として行うために必要な行政上の登録制度です。貸金業法に基づき、貸金業を営むためには内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。この登録制度は、違法な高金利貸付や悪質な取立てなどから借り手を保護するとともに、健全な貸金市場の形成を目的としています。
貸金業登録には、営業所等の設置場所に応じて、「内閣総理大臣登録」と「都道府県知事登録」の2つの区分があります。登録を受けるためには、純資産が5,000万円以上であることや、貸金業務取扱主任者の設置など、様々な要件を満たす必要があります。2006年の貸金業法改正によって登録要件が厳格化され、貸金業者の数は大幅に減少しました。
貸金業登録後も、貸金業者には帳簿書類の作成・保存、報告書の提出、契約時の書面交付、取引履歴の開示、上限金利の遵守、総量規制の遵守など、様々な義務が課せられています。これらの義務を遵守しなければ、業務改善命令や登録取消しなどの行政処分を受ける可能性があります。
貸金業登録を受けずに貸金業を営むこと(無登録営業)は、貸金業法違反となり、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科という厳しい罰則が科されます。また、無登録業者(ヤミ金融)との取引は、借り手側にも様々なリスクがあります。
借入れを検討する際は、相手が貸金業登録を受けている業者かどうかを必ず確認しましょう。金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」や、広告・契約書に記載された登録番号で確認することができます。無登録業者との取引は思わぬトラブルの原因となるため、十分注意が必要です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



