仮処分(かりしょぶん)について詳しく解説
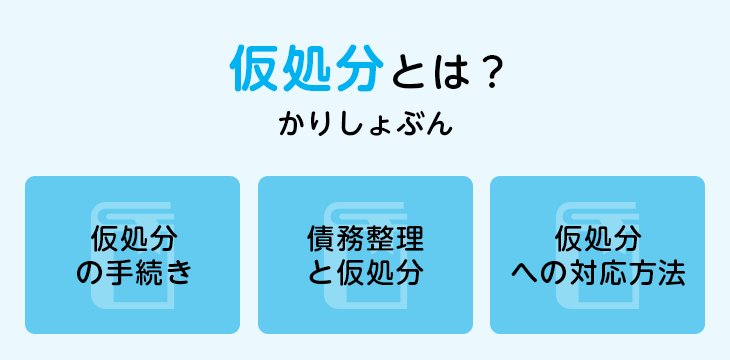
仮処分とは、債権者の権利を保全するために裁判所が発する一時的な緊急措置のことです。
民事保全法に基づき、本案訴訟の判決確定までの間、権利関係の現状を維持したり、争いのある権利を暫定的に実現したりする制度です。債務整理との関連では、債権者が債務者の財産処分を防止するために仮処分を申し立てるケースがあります。
仮処分とは
仮処分とは、金銭債権以外の権利(物や権利の引渡し、行為の差止め等)を保全するために、裁判所が債務者に対して発する一時的な緊急措置のことです。民事保全法に基づく制度で、本案訴訟の判決が確定するまでの間、権利関係の現状を維持したり、争いのある権利を暫定的に実現したりすることを目的としています。
仮処分は、債権者の権利に現に争いがあり、その権利が仮処分によって保全されなければ、将来判決が出ても権利の実現が不可能または困難になる恐れがある場合に認められます。
| 仮処分の目的 |
|
|---|---|
| 仮処分の要件 |
|
| 仮処分の根拠法 | 民事保全法(第23条〜第27条) |
上記の表は仮処分の基本的な概念をまとめたものです。仮処分は、本案訴訟(本格的な裁判)の結果を待っていたのでは手遅れになる可能性がある場合に、暫定的に権利を保全する制度です。
仮処分の種類
仮処分には大きく分けて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類があります。それぞれの内容と具体例は以下の通りです。
| 係争物に関する仮処分 (民事保全法第23条第1項) |
【具体例】
|
|---|---|
| 仮の地位を定める仮処分 (民事保全法第23条第2項) |
【具体例】
|
上記の表は仮処分の種類と具体例をまとめたものです。債務整理との関連では、主に「係争物に関する仮処分」が問題となることが多く、債権者が債務者の財産処分を防止するために申し立てるケースがあります。
また、仮処分の対象は多岐にわたり、不動産、動産、知的財産権、会社の株式など、様々な権利関係について仮処分が認められています。仮処分の内容も、処分禁止、占有移転禁止、一定の行為の禁止・命令など、事案に応じて様々な措置が取られます。
仮処分の手続き
仮処分は、債権者が裁判所に申し立てて行う手続きです。一般的な流れは以下の通りです。
- 債権者が管轄裁判所に仮処分命令の申立てを行う
- 債権者が担保(仮処分の内容により異なるが、一般的に申立額の約3割程度)を供託する
- 裁判所が審査(通常は債務者審尋を行う場合と行わない場合がある)
- 裁判所が仮処分命令を発令
- 仮処分命令が執行される(不動産なら登記、動産なら執行官による占有移転など)
- 債務者に仮処分命令が送達される
上記のリストは仮処分の一般的な手続きの流れを示しています。仮差押えと異なり、仮処分では裁判所が債務者の審尋(意見聴取)を行うことが多いですが、緊急性が高い場合には債務者審尋なしで発令されることもあります。
仮処分命令の申立てには、権利の存在と保全の必要性を証明する資料が必要です。一般的には以下のような書類が必要となります。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 管轄裁判所 |
|
| 担保金 |
|
上記の表は仮処分の申立てに必要な主な書類と手続き上の注意点をまとめたものです。仮処分は法的な専門知識が必要な手続きであるため、債権者側は通常、弁護士に依頼して行います。
債務整理と仮処分
債務整理を検討している段階で仮処分を受けると、債務整理の手続きに影響を与える可能性があります。各債務整理方法と仮処分の関係は以下の通りです。
| 任意整理と仮処分 |
|
|---|---|
| 個人再生と仮処分 |
|
| 自己破産と仮処分 |
|
上記の表は債務整理と仮処分の関係をまとめたものです。個人再生や自己破産では、申立てにより仮処分の効力を停止させることができますが、任意整理では仮処分が交渉の障害となる可能性があります。
特に注意が必要なのは、住宅や重要な財産に対する仮処分です。これらの財産を手放さずに債務整理を行いたい場合、仮処分によって処分が制限されると選択肢が狭まる可能性があります。このような状況では、迅速に専門家(弁護士・司法書士)に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
仮処分への対応方法
仮処分を受けた場合の対応方法は、状況によって異なります。以下に主な対応方法をまとめました。
- 専門家(弁護士・司法書士)に相談する
- 仮処分命令の内容を確認する(債権者、請求権の内容、対象財産など)
- 債権者と交渉し、和解を目指す
- 保証金(解放金)の供託による解除を検討する
- 不服申立て(異議)を検討する
- 本案訴訟での対応を検討する
- 債務整理(個人再生・自己破産)による解決を検討する
上記のリストは仮処分への主な対応方法をまとめたものです。特に専門家への相談は、適切な対応を取るための重要なステップです。
仮処分を受けた際の具体的な対応策としては、以下のようなものがあります。
| 不動産に対する 仮処分の場合 |
|
|---|---|
| 動産に対する 仮処分の場合 |
|
| 行為の差止めに関する 仮処分の場合 |
|
上記の表は仮処分の対象別の対応策をまとめたものです。いずれの場合も、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
仮処分と仮差押えの違い
仮処分と仮差押えは、いずれも民事保全法に基づく保全処分ですが、目的や対象、効果に違いがあります。両者の主な違いは以下の通りです。
| 対象となる債権 |
|
|---|---|
| 目的 |
|
| 効果 |
|
| 審理方法 |
|
上記の表は仮処分と仮差押えの主な違いをまとめたものです。債務整理との関連では、金銭債権に関わる問題が多いため、仮差押えが問題となるケースが比較的多いですが、担保権の実行や不動産の明渡しなどに関しては仮処分が問題となることもあります。
債務整理を検討する際には、仮差押えと仮処分のどちらを受けているのかを正確に把握し、それに応じた対応を取ることが重要です。専門家(弁護士・司法書士)に相談する際には、保全命令の正確な内容を伝えることで、より適切なアドバイスを受けることができます。
よくある質問
仮処分を受けると、どのような不利益がありますか?
仮処分を受けると、仮処分の内容に応じて様々な不利益が生じる可能性があります。不動産に対する処分禁止の仮処分であれば、その不動産の売却や担保設定ができなくなります。動産に対する占有移転禁止の仮処分であれば、その動産の移転や処分が制限されます。
また、特定の行為を禁止する仮処分の場合は、その行為を行うことができなくなり、違反すると間接強制(制裁金)が課される可能性があります。仮処分は本案訴訟の判決確定までの暫定的な措置ですが、長期間にわたって権利が制限されることもあります。債務整理との関連では、重要な財産に対する仮処分が債務整理の選択肢を狭める可能性があるため、早期に専門家に相談することが重要です。
仮処分命令に不服がある場合、どうすればよいですか?
仮処分命令に不服がある場合は、主に以下の方法で対応することができます。まず、仮処分命令を受けた日から2週間以内に、仮処分命令を発した裁判所に対して「保全異議」を申し立てることができます。保全異議では、仮処分の要件(被保全権利の存在や保全の必要性)が欠けていることなどを主張します。
また、仮処分債務者(仮処分を受けた側)が担保を立てることで、仮処分の執行を免れる「執行免脱」の申立てをすることも可能です。さらに、事情変更があった場合には「保全取消し」の申立てをすることもできます。これらの手続きは法的に複雑なため、弁護士に相談して進めることをおすすめします。なお、本案訴訟(本格的な裁判)において権利関係を争うことも重要です。
仮処分を受けた後、債務整理はできますか?
はい、仮処分を受けた後でも債務整理は可能です。むしろ、仮処分を受けた場合、債務問題が深刻化しているサインとも言えるため、債務整理を検討するタイミングとも言えます。特に個人再生や自己破産の申立てを行うと、中止命令や保全処分により仮処分の効力を停止させることができます。
任意整理の場合は、仮処分を行った債権者との交渉が必要になりますが、弁護士や司法書士が介入することで解決できるケースも多いです。仮処分の内容や対象財産によって、適切な債務整理の方法は異なる場合がありますので、仮処分の内容を正確に把握した上で、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
仮処分とは、金銭債権以外の権利を保全するために、裁判所が債務者に対して発する一時的な緊急措置のことです。権利関係の現状を維持したり、争いのある権利を暫定的に実現したりすることを目的とした、民事保全法に基づく制度です。
仮処分には「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類があり、前者は係争物の処分禁止や占有移転禁止などを内容とし、後者は一定の行為の禁止・命令や仮の権利関係を定めることを内容とします。債務整理との関連では、主に不動産や重要な財産に対する処分禁止の仮処分が問題となることがあります。
仮処分は、債権者が裁判所に申し立てて行う手続きで、権利の存在と保全の必要性を証明する資料を提出し、担保を供託する必要があります。通常は債務者の審尋(意見聴取)が行われますが、緊急性が高い場合には審尋なしで発令されることもあります。
債務整理と仮処分の関係では、任意整理の交渉中に債権者が財産の処分を防ぐために仮処分を申し立てることがありますが、個人再生や自己破産の申立てにより、仮処分の効力を停止させることができます。仮処分を受けた場合は、専門家(弁護士・司法書士)に相談し、仮処分命令の内容確認、債権者との交渉、保証金の供託、不服申立て、債務整理による解決などの対応を検討することが重要です。
仮処分と仮差押えは、いずれも民事保全法に基づく保全処分ですが、仮差押えが金銭債権を保全するための制度であるのに対し、仮処分は金銭債権以外の権利を保全するための制度という違いがあります。債務整理を検討する際には、受けている保全処分の種類や内容を正確に把握し、それに応じた対応を取ることが重要です。
仮処分は財産の処分制限など、権利に大きな制約を課す可能性があります。仮処分を受けた場合は放置せず、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることで、債務問題の解決につなげることができます。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



