受任通知(じゅにんつうち)について詳しく解説
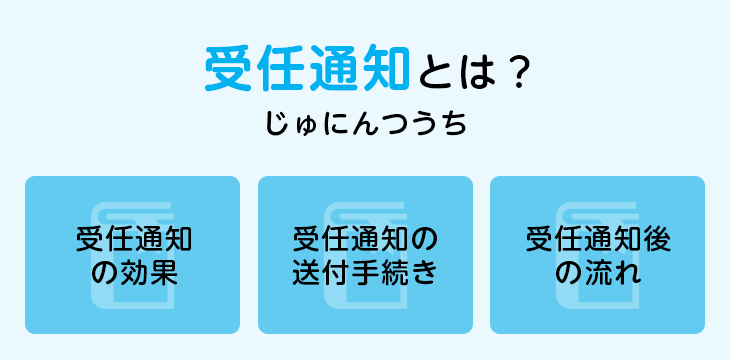
受任通知とは、債務者が弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼した際に、その専門家から債権者(貸金業者など)に対して送られる通知書のことです。専門家が債務者の代理人として債務整理の手続きを受任したことを正式に通知する文書で、この通知が債権者に到達すると、債権者からの直接的な取立てが法的に停止されます。
受任通知は債務者を過酷な取立てから守るための重要な法的手段であり、債務整理手続きの初期段階で行われる基本的なステップとなっています。
受任通知とは
受任通知は、債務者が弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼した際に、その専門家が債権者に対して送付する正式な文書です。債務整理の手続きを開始するための第一歩となるもので、債務者の代理人として債務整理を受任したことを債権者に通知します。
受任通知には通常、依頼者(債務者)の氏名、住所、生年月日などの基本情報、債務に関する情報(契約番号、口座番号など)、代理人の連絡先、今後の交渉方針などが記載されます。また、取立行為の禁止を通知する文言も含まれています。
| 受任通知の基本情報 |
|
|---|
上記の表は受任通知に含まれる基本的な情報です。この通知により、債務者と債権者の直接的なやりとりが遮断され、以後の交渉は専門家を通じて行われるようになります。
受任通知の効果
受任通知が債権者に届くと、様々な法的効果が生じます。特に債務者の立場からは、債権者からの取立てが止まるという重要な効果があります。
主な効果
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 取立ての停止 |
|
| 直接交渉の遮断 |
|
| 時効中断効 |
|
| 取引履歴開示請求 |
|
上記の表は受任通知の主な効果を示しています。特に取立ての停止効果は債務者にとって大きな安心感をもたらし、精神的な負担を軽減する効果があります。
効果が生じるタイミング
受任通知の効果が生じるタイミングは、通知が債権者に「到達」した時点です。通常は、以下のような状況で効果が発生します。
- 特定記録郵便や簡易書留などで送付した場合:配達完了時点
- FAXで送信した場合:送信完了の記録が残った時点
- 電子メールで送信した場合:相手方のサーバーに到達した時点(開封確認があるとより確実)
上記のリストは受任通知の効果が生じるタイミングを示しています。確実に到達を証明できるよう、特定記録郵便や簡易書留などの方法で送付することが一般的です。
受任通知の送付手続き
受任通知の送付は、債務整理を依頼された弁護士や司法書士が行います。正確かつ確実に債権者に届けるために、以下のような手順で進められます。
送付の流れ
- 債務者からの委任状と必要書類の受領
- 債権者の特定と送付先の確認
- 受任通知の作成
- 送付方法の選択
- 送付と記録の保管
・債務者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・債務に関する資料(契約書、取引明細、返済予定表など)
・収入や財産に関する資料
・正確な会社名、住所、部署名などを確認
・債務者が持つ書類や公開情報から特定
・必要な情報を記載
・取引履歴の開示請求や今後の方針も明記
・特定記録郵便や簡易書留など、到達を証明できる方法を選択
・必要に応じて FAX や電子メールで事前連絡
・送付した証拠(郵便物の追跡番号など)を保管
・債務者に送付完了の報告
上記のリストは受任通知の送付手続きの一般的な流れです。専門家はこの手続きを適切に行い、確実に債権者に通知が届くようにします。
送付先と送付方法
| 送付先 |
|
|---|---|
| 送付方法 |
|
上記の表は受任通知の主な送付先と送付方法を示しています。確実に到達したことを証明できる方法を選ぶことが重要です。
受任通知後の流れ
受任通知を送付した後の流れは、選択する債務整理の方法によって異なります。以下では主な債務整理方法ごとの流れを説明します。
任意整理の場合
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ①取引履歴の取得 |
|
| ②債務整理方針の決定 |
|
| ③債権者との交渉 |
|
| ④和解契約の締結 |
|
| ⑤返済の開始 |
|
上記の表は任意整理の場合の受任通知後の一般的な流れです。取引履歴の取得から和解契約の締結まで、約3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。
個人再生・自己破産の場合
個人再生や自己破産の場合は、受任通知後の流れが任意整理とは異なります。
| 個人再生の場合 | |
|---|---|
| 自己破産の場合 |
上記の表は個人再生と自己破産の場合の受任通知後の一般的な流れです。裁判所への申立てが行われると、法的な保護がより強固になります。
受任通知に関するよくある質問
受任通知を送っても取立てが続いている場合はどうすればよいですか?
受任通知が債権者に到達したにもかかわらず取立てが続く場合は、以下の対応が考えられます。
- まず代理人(弁護士・司法書士)に状況を報告する
- 代理人から債権者に対して再度通知を送付し、取立て行為の停止を求める
- 取立てが悪質な場合は、貸金業法違反として金融庁や財務局への申告を検討
- 特に悪質な場合は、取立て行為差止請求や損害賠償請求の法的手段を検討
正規の貸金業者であれば、受任通知到達後に取立てを継続することはほとんどありません。継続する場合は監督官庁からの処分対象となる可能性があるためです。ただし、ヤミ金融の場合は通知後も取立てが続くことがあり、その場合は警察への相談も検討すべきです。
受任通知を送ってからどのくらいで債権者からの連絡が止まりますか?
通常、受任通知が債権者に到達してから数日以内に債権者からの直接的な連絡(電話、訪問、手紙など)は止まります。ただし、以下のような例外的な状況があります。
- 通知が実際に処理されるまでに社内手続きで数日かかる場合がある
- 債権者が複数の部署や支店で管理している場合、情報共有に時間がかかることがある
- 郵便事情により通知の到達が遅れることがある
- 債務者が複数の商品(カードローン、クレジットカードなど)を利用している場合、商品ごとに対応が異なることがある
1週間以上経過しても連絡が止まらない場合は、代理人に報告し、適切な対応を取ってもらうことが重要です。
受任通知を送った後にも自分で返済を続けても問題ないですか?
受任通知を送付した後は、原則として債権者との直接のやりとり(返済を含む)は避けるべきです。以下の理由から、返済は代理人を通じて行うことが望ましいとされています。
- 債務整理の方針に反する可能性がある
- 債権者が債務者に直接接触する機会となり得る
- 任意整理の場合、返済条件の交渉に影響を与える可能性がある
- 過払い金が発生している可能性がある場合、余計な支払いになる可能性がある
返済を継続したい場合は、必ず事前に代理人に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。代理人の了解を得た上で返済を継続するケースもあります。
受任通知を送った後に債権者から代理人ではなく自分に直接連絡がきた場合はどうすればよいですか?
債権者から直接連絡があった場合は、以下のように対応することをおすすめします。
- 「債務整理を○○法律事務所(司法書士事務所)の△△先生に依頼しているので、すべての連絡は代理人にお願いします」と伝える
- 代理人の連絡先を伝える(事前にメモしておくとよい)
- それ以上の会話は避け、できるだけ短く切り上げる
- 連絡があった事実(日時、相手、内容など)を記録しておく
- すぐに代理人に報告する
貸金業法では、受任通知後の取立行為は禁止されているため、このような連絡自体が違法な可能性があります。代理人に状況を報告し、適切な対応を取ってもらいましょう。
まとめ
受任通知は、債務整理を依頼された弁護士や司法書士が債権者に送付する通知書で、債務者の代理人として手続きを受任したことを正式に知らせるものです。この通知が債権者に到達すると、債権者からの直接的な取立てが法的に禁止され、以後の交渉は代理人を通じて行われるようになります。
受任通知の主な効果として、取立ての停止、直接交渉の遮断、時効中断効(場合による)、取引履歴開示請求の基盤となることなどが挙げられます。特に取立ての停止効果は債務者の精神的負担を大きく軽減するため、債務整理を検討している方にとって重要な意味を持ちます。
受任通知後の流れは債務整理の方法(任意整理、個人再生、自己破産など)によって異なりますが、いずれの場合も代理人が債権者との交渉や法的手続きを進めていきます。債務者は代理人の指示に従い、必要な情報提供や書類提出などで協力することが重要です。
受任通知後も債権者から直接連絡があった場合は、すべての連絡は代理人を通すよう伝え、その事実を代理人に報告しましょう。また、返済を含む債権者との直接のやりとりは避け、すべて代理人を通じて行うことが望ましいです。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



