自由財産(じゆうざいさん)について詳しく解説
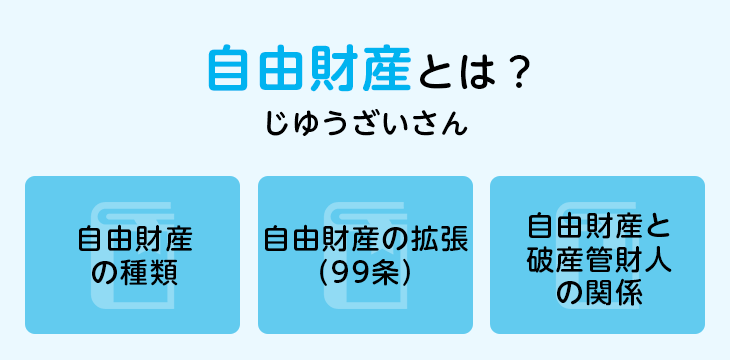
自由財産とは、自己破産手続きにおいて、債務者が手元に残すことができる財産のことを指します。破産法上で保護された財産であり、破産管財人が換価(現金化)して債権者に配当することができない財産です。
自己破産では原則としてすべての財産が債権者への返済に充てられますが、債務者の生活再建のため、最低限の生活に必要な財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。
自由財産とは
自由財産とは、自己破産手続きにおいて債務者が保持できる財産のことです。破産法では、債務者の財産は原則として「破産財団」を構成し、債権者への返済に充てられます。しかし、最低限の生活を維持するために必要な財産は「自由財産」として債務者の手元に残すことが認められています。
この制度は、債務者が経済的に再出発するための基盤を確保するという観点から設けられています。自由財産があることで、自己破産後も最低限の生活を維持し、社会復帰を果たすことができるのです。
| 自由財産の意義 |
|
|---|
上記の表は自由財産の主な意義を示しています。自由財産制度は、債務者の生活再建を支援するための重要な法的仕組みです。
自由財産の種類
自由財産は、法律で定められた「法定の自由財産」と裁判所の裁量で認められる「裁量の自由財産」の2種類に大きく分けられます。それぞれの内容と特徴を以下に説明します。
法定の自由財産
法定の自由財産は、破産法上で明確に規定されている自由財産で、以下のようなものがあります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 現金 |
|
| 差押禁止財産 |
|
| 給与・報酬 |
|
| その他 |
|
上記の表は法定の自由財産の主な種類と内容を示しています。これらの財産は自己破産手続きにおいても債務者の手元に残ります。
裁量の自由財産(99条の財産)
裁量の自由財産は、破産法第99条に基づいて裁判所の裁量によって自由財産とすることが認められた財産です。債務者の申立てにより、裁判所が個別に判断します。
| よく認められる例 | 裁量の判断基準 |
|---|---|
| 自動車 |
|
| 少額の不動産 |
|
| 保険の解約返戻金 |
|
| 仕事道具 |
|
上記の表は裁量の自由財産としてよく認められる例と、その判断基準を示しています。裁量の自由財産は裁判所によって判断が異なる場合があります。
裁量の自由財産として認めるかどうかの判断は、債務者の生活状況、年齢、健康状態、家族構成、職業などを総合的に考慮して行われます。特に、その財産が債務者の生活再建や職業継続に必要かどうかが重要な判断基準となります。
自由財産の拡張(99条)
破産法第99条に基づく自由財産の拡張(裁量の自由財産)を申し立てる場合、以下の手続きと基準を理解しておくことが重要です。
- 申立ての時期:原則として破産手続開始決定前に申し立てる必要があります
- 申立ての方法:自由財産拡張の申立書を作成し、裁判所に提出します
- 必要な資料:財産の価値を証明する資料や、その財産が生活に必要である理由を説明する資料を添付します
- 裁判所の判断:裁判所は債権者や破産管財人の意見も聞いた上で判断します
- 決定:裁判所が自由財産として認める場合は、その旨の決定が出されます
上記のリストは自由財産拡張の手続きの流れです。申立ては弁護士や司法書士に依頼することが一般的ですが、自己申立ても可能です。
裁判所が自由財産の拡張を判断する際の主な基準は以下の通りです。
| 判断基準 | 具体的な考慮要素 |
|---|---|
| 必要性 |
|
| 価値 |
|
| 債権者の利益 |
|
| 債務者の状況 |
|
上記の表は裁判所が自由財産拡張を判断する際の主な基準です。これらの基準を踏まえて、説得力のある申立てを行うことが重要です。
以下のような場合には、自由財産の拡張が認められやすい傾向があります。
- 財産価値が低く、換価しても債権者への配当がわずかな場合
- 債務者の職業継続や生活再建に明らかに必要と認められる場合
- 高齢者や障害者など、特別な配慮が必要な場合
- 地方在住で公共交通機関が不便な地域に住んでいる場合の自動車
- 専門職(理容師、大工など)の仕事道具
ただし、最終的な判断は裁判所によって行われるため、確実に認められるというものではありません。
自由財産と破産管財人の関係
自己破産手続きにおいて、破産管財人は債務者の財産を調査し、換価して債権者に配当する役割を担いますが、自由財産に対しては特別な扱いがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 破産管財人の権限 |
|
| 自由財産の調査 |
|
| 自由財産の引渡し |
|
| 争いがある場合 |
|
上記の表は自由財産と破産管財人の関係についての主な内容です。自由財産として認められるためには、破産管財人や裁判所に対して適切に説明することが重要です。
なお、同時廃止(管財人が選任されない簡易な破産手続き)の場合は、裁判所が直接自由財産の判断を行います。少額管財や管財事件の場合は、破産管財人との協議や交渉が必要になることがあります。
自由財産に関するよくある質問
自動車は自由財産になりますか?
自動車は法定の自由財産には含まれていませんが、裁量の自由財産(99条の財産)として認められる可能性があります。特に以下のような場合は認められやすい傾向があります。
- 通勤や仕事に自動車が不可欠な場合
- 公共交通機関が不便な地域に住んでいる場合
- 高齢者や障害者など、移動に配慮が必要な場合
- 比較的安価な車種(概ね50万円以下)の場合
ただし、高級車や複数の車両を所有している場合は認められにくいです。また、裁判所や地域によって判断が異なる場合があります。
住宅ローン付きの家は自由財産になりますか?
住宅ローン付きの家は、原則として自由財産にはなりません。ただし、以下の選択肢があります。
- 個人再生手続きを選択し、住宅資金特別条項を利用する(住宅ローンを除外して債務を整理する方法)
- 自己破産後に住宅ローンを引き継いでくれる親族がいる場合は、その親族に家を譲渡する
- 住宅の価値が非常に低く、換価しても債権者への配当がほとんど見込めない場合は、裁量の自由財産として認められる可能性がある
住宅を残したい場合は、自己破産ではなく個人再生を検討することをおすすめします。
生命保険は自由財産になりますか?
生命保険の取扱いは以下のようになります。
- 保険金請求権:被保険者(債務者)が死亡した場合に発生する保険金請求権は、受取人が債務者以外(配偶者や子どもなど)であれば自由財産となります
- 解約返戻金:保険契約を解約した場合に受け取れる解約返戻金は、原則として破産財団に組み込まれますが、少額(概ね20〜30万円以下)であれば裁量の自由財産として認められる可能性があります
- 払戻金のない保険:解約返戻金のない掛け捨て型の保険は、破産財団を構成しないため問題になりません
生命保険の取扱いについては、保険の種類や契約内容によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
99万円を超える現金や預金は全て没収されますか?
法定の自由財産として認められる現金や預金は99万円までですが、これを超える部分は原則として破産財団に組み込まれます。ただし、以下のような例外があります。
- 近い将来の必要経費(医療費や教育費など)が明確に予定されている場合
- 高齢者の老後の生活資金として必要と認められる場合
- 障害者の生活支援のために必要と認められる場合
これらの場合、裁量の自由財産として99万円を超える現金や預金が認められる可能性がありますが、明確な理由と必要性を示す必要があります。
まとめ
自由財産とは、自己破産手続きにおいて債務者が手元に残すことができる財産のことです。法律で定められた「法定の自由財産」と裁判所の裁量で認められる「裁量の自由財産」の2種類があります。
法定の自由財産には、99万円以下の現金や預金、日常生活に必要な家財道具、生活や職業に欠かせない道具・器具などが含まれます。また、破産法第99条に基づく裁量の自由財産として、自動車や少額の不動産、保険の解約返戻金などが認められる場合もあります。
自由財産制度は、債務者が自己破産後も最低限の生活を維持し、経済的に再出発するための基盤を確保するという重要な役割を果たしています。自己破産を検討する際は、どの財産が自由財産として手元に残せるかを事前に確認することが大切です。
自由財産の範囲や裁量の判断は裁判所によって異なる場合があるため、自己破産を考えている方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、自分のケースでどの財産が自由財産として認められる可能性があるかを確認することをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



