時効(じこう)について詳しく解説
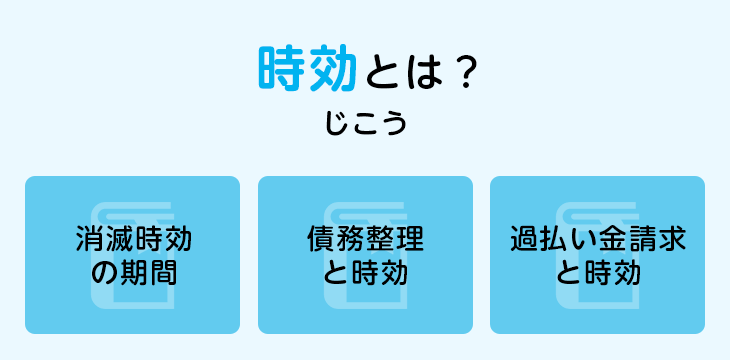
時効とは、一定期間が経過することで法律上の権利や義務が消滅したり、新たに権利が発生したりする制度です。債務整理や過払い金請求において特に重要なのは「消滅時効」で、一定期間行使されない債権は時効によって消滅します。
2020年4月の民法改正により、消滅時効の期間は「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方とされました。ただし、商事債権など特別な債権では異なる時効期間が適用される場合もあります。
時効とは
時効とは、一定期間の経過によって法律関係に変動が生じる制度です。大きく分けて「取得時効」と「消滅時効」の2種類があります。債務整理や過払い金請求で主に問題となるのは消滅時効です。
消滅時効は、権利者がその権利を一定期間行使しない状態が続くと、その権利が消滅する制度です。この制度は、長期間行使されない権利を消滅させることで法律関係の安定を図り、古い権利関係についての立証の困難さを解消するという目的があります。
| 時効の種類 |
|
|---|---|
| 消滅時効の要件 |
|
| 時効制度の目的 |
|
上記の表は時効制度の基本的な分類や要件、目的をまとめたものです。消滅時効は自動的に完成するものではなく、時効の利益を受ける者(債務者)が「時効を援用する」という意思表示をすることで初めて効力が生じます。
消滅時効の期間
消滅時効の期間は債権の種類によって異なります。2020年4月の民法改正により、一般的な債権の消滅時効期間が変更されました。改正前と改正後で時効期間が異なるため注意が必要です。
| 民法改正後の一般的な債権 | 「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方 |
|---|---|
| 民法改正前の一般的な債権 | 権利を行使できる時から10年間 |
| 商事債権 | 5年間(商法第522条) |
| 定期給付債権 | 5年間(民法第169条) |
| 過払い金返還請求権 | 不当利得返還請求権として、「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」 |
| 貸金業者の取立権 | 最後の取引から5年間または10年間(改正前後で異なる) |
上記の表は主な債権の消滅時効期間をまとめたものです。民法改正は2020年4月1日に施行されましたが、経過措置があり、改正前に発生した債権については、原則として改正前の時効期間が適用されます。
債務整理や過払い金請求を検討する際には、自分の債権・債務がいつ発生したものか、どの時効期間が適用されるかを確認することが重要です。時効期間が経過していると、債権回収や過払い金請求が困難になる可能性があります。
時効の起算点
時効の起算点とは、時効期間の計算を始める時点のことです。債権の種類や契約内容によって起算点が異なるため、時効が完成しているかどうかを判断する際には正確な起算点の特定が重要です。
- 一般的な債権:権利を行使できる時(債務の弁済期)
- 定期預金:満期日
- 普通預金:最後の預入れまたは払戻しの日
- カードローンなどの継続的取引:最後の取引日
- 過払い金返還請求権:過払い金の発生を知った時、または取引終了時
- 保証債務:主債務者が期限内に弁済しなかった時
上記のリストは主な債権の時効起算点をまとめたものです。特に継続的な取引関係がある場合や、複数回の取引がある場合は、起算点の特定が複雑になることがあります。
また、民法改正により導入された「権利を行使できることを知った時」という主観的起算点では、債権者が実際に権利の存在を知った時点が重要になります。債務整理や過払い金請求では、この起算点の特定が争点になることもあります。
時効の中断と更新
時効の進行を止める方法として、改正前の民法では「時効の中断」が、改正後の民法では「時効の更新」と「時効の完成猶予」が規定されています。債務整理や過払い金請求では、これらの制度を理解することが重要です。
| 改正後の時効の更新事由 | |
|---|---|
| 改正後の時効の完成猶予事由 |
|
| 時効更新の効果 | 更新事由が生じた時点で時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進行します。 |
| 時効完成猶予の効果 | 猶予事由が続いている間は時効は完成せず、猶予事由が終了した後に一定期間(多くの場合6ヶ月)が経過するまで時効は完成しません。 |
上記の表は時効の更新と完成猶予の主な事由と効果をまとめたものです。債権者側は時効の完成を防ぐために、これらの事由を活用することがあります。一方、債務者側は時効の利益を守るために、これらの事由が発生しないよう注意する必要があります。
特に債務整理や過払い金請求では、時効が完成しているかどうかが重要な争点となるため、取引履歴や債権者とのやり取りを丁寧に確認することが必要です。少しでも不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。
債務整理と時効
債務整理を検討する際、時効の問題は非常に重要です。時効が完成している債務については、時効を援用することで支払い義務を免れる可能性があります。以下では、各債務整理方法と時効の関係について説明します。
- 任意整理と時効:時効が完成している債務は、時効を援用することで債務整理の対象から外すことができます。
- 個人再生と時効:再生計画に含める債務について、時効が完成しているものは除外できる可能性があります。
- 自己破産と時効:破産手続開始決定があると時効の完成が猶予されます。ただし、時効が完成している債務は免責の対象にする必要がない場合もあります。
- 特定調停と時効:時効が完成している債務は、調停の対象から除外できる可能性があります。
上記のリストは債務整理の各方法と時効の関係をまとめたものです。債務整理を検討する際は、まず自分の債務がいつ発生したものか、時効期間がどれくらいか、時効の中断事由が発生していないかを確認することが重要です。
ただし、時効の判断は専門的な知識が必要なため、債務整理を検討する際は弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。時効が完成していると思っても、知らないうちに時効の更新事由が発生している可能性もあります。
過払い金請求と時効
過払い金請求権も時効の適用を受けます。過払い金請求権は不当利得返還請求権の一種であり、その時効期間は「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方となります。
| 過払い金請求権の時効期間 | 「過払い金の発生を知った時から5年間」または「過払い金が発生した時から10年間」のいずれか早い方 |
|---|---|
| 過払い金の発生時期 | 利息制限法の上限金利を超える利息の支払いがあった時点で過払い金が発生します。継続的な取引では、取引終了時に一括して発生するとみなされる場合もあります。 |
| 「知った時」の解釈 | 過払い金の存在を具体的に認識した時点が基準となります。一般的には、弁護士や司法書士に相談して過払い金の存在を知った時点という解釈が多いです。 |
| 時効の更新事由 | 裁判上の請求、債務者による過払い金の存在の承認などにより時効が更新されます。 |
上記の表は過払い金請求権の時効に関する主なポイントをまとめたものです。過払い金請求を検討する際は、取引履歴を取り寄せて過払い金の発生時期を確認し、時効が完成していないかを確認することが重要です。
特に、取引終了から長期間が経過している場合は、時効が完成している可能性があります。しかし、「過払い金の発生を知った時」という起算点の解釈については争いがあるため、一度専門家に相談することをおすすめします。
時効の援用
時効は自動的に効力を生じるものではなく、時効の利益を受ける者(債務者)が「時効を援用する」という意思表示をすることで初めて効力が生じます。この「時効の援用」の方法と効果について説明します。
| 時効援用の方法 | 口頭でも書面でも可能ですが、証拠として残るよう内容証明郵便などの書面で行うことが一般的です。 |
|---|---|
| 時効援用の効果 | 時効の援用により、債務は初めから存在しなかったものとみなされます(遡及効)。 |
| 時効援用の対象 | すべての債務に時効援用が可能ですが、一部の債務(自然債務)については道義的な問題が生じる場合があります。 |
| 時効援用の制限 | 信義則や権利濫用の法理により、時効の援用が認められない場合もあります。 |
上記の表は時効の援用に関する主なポイントをまとめたものです。時効の援用は債務者の権利ですが、すべての場合に無条件で認められるわけではありません。特に、債権者を欺いたり、意図的に時効完成を待ったりした場合などは、権利濫用として援用が認められないこともあります。
時効の援用を検討する際は、単に時効期間が経過しているかどうかだけでなく、債権者との関係や取引の経緯なども考慮する必要があります。特に道義的な問題が生じる可能性がある場合は、専門家に相談の上で判断することをおすすめします。
よくある質問
時効が完成した債務を支払ってしまった場合、返還請求はできますか?
時効が完成した債務であっても、時効を援用せずに支払った場合、原則として返還請求はできません。時効完成後の弁済は「自然債務の弁済」として有効とされるためです。
ただし、時効の完成を知らずに錯誤(勘違い)によって支払った場合には、民法の錯誤に関する規定に基づいて返還を求められる可能性があります。また、債権者が脅迫や強要によって支払いを迫った場合なども、不当利得として返還請求できる可能性があります。
時効の援用は誰でもできますか?
時効の援用は、原則として時効の利益を受ける者(債務者本人)だけでなく、保証人や物上保証人、差押債権者など「時効の援用について法律上の利益を有する者」も行うことができます。
ただし、債務者が時効の利益を放棄した後に、第三者が時効を援用することはできません。また、債務者が時効を援用しない意思を明確にしている場合に、第三者が時効を援用できるかどうかは、個別の状況によって判断されます。
債権者から「時効が中断している」と言われました。これは本当ですか?
時効の中断(改正後は「更新」)は、裁判上の請求、強制執行、仮差押え、仮処分、債務の承認などの事由がある場合に発生します。債権者がこれらの事由があると主張する場合は、その証拠(訴状の写し、差押通知書、債務承認書など)の提示を求めるべきです。
特に「債務の承認」については、一部弁済や利息の支払い、債務の存在を認める旨の書面の作成などが該当します。電話で債務の存在を認めただけでは、通常、時効の更新事由とはなりませんが、録音されていた場合などは注意が必要です。債権者の主張に不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
時効は、一定期間が経過することで法律上の権利や義務が消滅したり、新たに権利が発生したりする制度です。債務整理や過払い金請求において特に重要なのは消滅時効で、一定期間行使されない債権は時効によって消滅します。
2020年4月の民法改正により、消滅時効の期間は「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方とされました。ただし、改正前に発生した債権については、原則として改正前の時効期間が適用されます。
時効は自動的に効力を生じるものではなく、時効の利益を受ける者(債務者)が「時効を援用する」という意思表示をすることで初めて効力が生じます。また、裁判上の請求や債務の承認などにより時効が更新され、時効期間がリセットされることがあります。
債務整理や過払い金請求を検討する際は、自分の債務や請求権がいつ発生したものか、時効期間がどれくらいか、時効の更新事由が発生していないかを確認することが重要です。時効の判断は専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



