非免責債権(ひめんせきさいけん)について詳しく解説
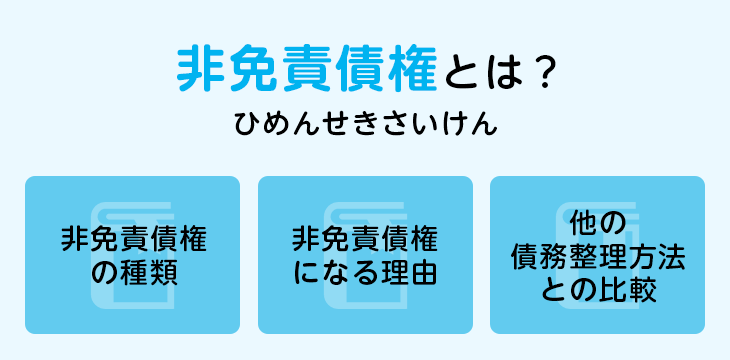
非免責債権とは、自己破産手続きにおいて免責(債務の支払い義務が免除されること)の対象とならない債務のことです。自己破産をしても免責されず、破産後も支払い義務が残る特別な種類の債務を指します。
一般的に自己破産では、裁判所から免責許可決定を受けることで大部分の債務が免除されますが、法律によって免責が認められない特定の債務が「非免責債権」として定められています。これらの債務については、破産手続き後も引き続き返済義務があるため、債務整理を検討する際には注意が必要です。
非免責債権の種類
破産法第253条では、免責許可の決定があっても免責されない債権が定められています。主な非免責債権は以下の通りです。
| 租税等の請求権 | 所得税、住民税、固定資産税などの税金債務 |
|---|---|
| 罰金・過料等 | 刑事罰としての罰金、行政上の過料、科料など |
| 悪意による不法行為に基づく損害賠償 | 詐欺や横領などの故意による不法行為の賠償金 |
| 養育費等 | 子どもの養育費、親族への扶養料など |
| 浪費等による債務 | ギャンブルや贅沢な浪費によって発生した債務(個別判断) |
| 破産手続き開始後の債務 | 破産手続き開始決定後に発生した債務 |
上記は主な非免責債権の種類です。特に税金や養育費などの公的性質の強い債務や、故意に発生させた債務については免責されないケースが多いです。
非免責債権の法的根拠
非免責債権は破産法第253条に具体的に規定されています。特に重要な条項は以下の通りです。
- 第1号:租税等の請求権
- 第2号:破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 第3号:破産者が知っていながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 第4号:養育費、婚姻費用分担に関する請求権
- 第5号:浪費や賭博など裁量的免責不許可事由があるのに免責された場合の債権
上記の法的根拠に基づき、裁判所は免責許可の決定をする際に、これらの債権については免責の効力が及ばないと判断します。そのため、破産後も債務者は支払い義務を負うことになります。
非免責債権になる理由
特定の債務が非免責債権となる理由には、社会的公正性や債権の性質など様々な観点があります。主な理由は以下の通りです。
公益性が高い債務
税金や公的な罰金などは、国や地方公共団体の財源となるものであり、社会全体の利益のために使われる重要な資金です。これらを免責してしまうと、公的なサービスの提供に支障が出る可能性があるため、非免責債権とされています。
モラルに関わる債務
故意による不法行為や浪費、ギャンブルなどによって生じた債務を免責すると、モラルハザードを引き起こす恐れがあります。債務者の道徳的責任を問うという観点から、これらの債務は非免責とされているのです。
| 社会的弱者保護の観点 | 養育費や扶養料などは、子どもや扶養を必要とする家族の生活を支えるためのものです。これらを免責すると、社会的弱者の生活が脅かされるため非免責となっています。 |
|---|---|
| 債権者の信頼保護 | 債権者名簿に故意に記載しなかった債権は、債権者が自らの権利を主張する機会を奪われたことになります。そのため、債権者保護の観点から非免責とされています。 |
上記のように、非免責債権は単に債務者の返済負担を考慮するだけでなく、社会的な公正性やモラル、弱者保護など、様々な観点から決められています。
非免責債権の具体例と注意点
非免責債権について、より具体的な例と注意すべきポイントを見ていきましょう。
税金関係の非免責債権
| 所得税・住民税 | 確定申告で発生した所得税や住民税は、自己破産しても免責されません。特に自営業者や個人事業主は注意が必要です。 |
|---|---|
| 固定資産税 | 不動産を所有している場合の固定資産税も非免責債権です。ただし、破産手続きで不動産を手放した場合、その後の固定資産税は発生しません。 |
| 国民健康保険料 | 保険料と税金の性質を併せ持つ国民健康保険料も、基本的には非免責債権として扱われることが多いです。 |
| 延滞税・加算税 | 本税に付随する延滞税や加算税も、非免責債権として扱われます。 |
税金関係の非免責債権については、管轄の税務署や市区町村役場に相談して、分割納付などの対応を検討することが重要です。
不法行為に基づく損害賠償
悪意(故意)による不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権となります。ただし、過失による不法行為の場合は、原則として免責の対象となります。
| 非免責となる例 |
|
|---|---|
| 免責される可能性がある例 |
|
不法行為に基づく損害賠償が非免責となるかどうかは、「悪意(故意)」があったかどうかが重要なポイントです。過失による不法行為は原則として免責の対象となりますが、個別のケースによって判断が異なる場合もあります。
養育費・婚姻費用
子どもの養育費や配偶者への婚姻費用分担は、非免責債権として扱われます。これは子どもや家族の生活を守るための重要な債務だからです。
養育費については、過去の未払い分だけでなく、将来発生する分についても非免責債権となります。養育費の支払い義務は子どもが成人するまで継続するため、自己破産後も支払い義務は残ります。
非免責債権の取り扱い方法
自己破産をしても非免責債権の支払い義務は残りますが、いくつかの対応方法があります。
税金の場合
- 徴収猶予・換価の猶予:納税が困難な事情を説明し、一時的な支払い猶予を申請する
- 分割納付:税務署や自治体と相談して分割納付の計画を立てる
- 滞納処分の執行停止:生活困窮などの理由で、最長3年間の滞納処分の執行停止を受ける
- 欠損処分:執行停止が3年間継続した場合などに、税金が消滅する可能性がある
上記のような対応方法があり、特に生活再建中の場合は、税務署や市区町村役場に相談することで柔軟な対応を受けられることがあります。
養育費の場合
養育費については、以下のような対応が考えられます。
| 養育費の減額請求 | 経済状況の悪化を理由に、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることができます。ただし、子どもの生活に必要な最低限の養育費は支払う必要があります。 |
|---|---|
| 元配偶者との協議 | 直接元配偶者と協議して、支払い金額や方法の見直しを行うことも可能です。ただし、合意内容は書面にして残しておくことが重要です。 |
養育費は子どもの生活に直結する重要な債務であるため、支払いを怠ると差押えなどの強制執行を受ける可能性があります。生活再建と並行して計画的に支払っていくことが重要です。
不法行為に基づく損害賠償の場合
不法行為に基づく損害賠償が非免責となった場合は、債権者と直接交渉して、分割払いなどの和解を目指すことが考えられます。和解が成立すれば、新たな返済計画に基づいて支払いを続けることになります。
他の債務整理方法との比較
非免責債権は自己破産では免除されませんが、他の債務整理方法ではどのように扱われるのでしょうか。主な債務整理方法と非免責債権の関係を比較してみましょう。
| 自己破産 | 非免責債権は免除されず、破産後も返済義務が継続します。 |
|---|---|
| 個人再生 | 原則として全ての債務が再生計画に含まれますが、税金や罰金などの一部の債務は「別除権付債権」として個別に取り扱われることがあります。再生計画で定められた返済計画に従って支払いを行います。 |
| 任意整理 | 債権者との個別交渉によるため、非免責債権かどうかは関係なく、全ての債務について交渉可能です。ただし、税金など公的債務は通常、任意整理の対象外です。 |
| 特定調停 | 税金や公的債務も含めて調停の対象となりますが、債権者の同意が必要であり、公的債権者は応じないことも多いです。 |
上記の比較からわかるように、非免責債権は自己破産以外の債務整理方法でも特別な扱いを受けることが多いです。特に税金や公的債務については、それぞれの債権者と個別に交渉することが必要になるケースが多いでしょう。
債務整理方法の選択と非免責債権
非免責債権の割合が大きい場合は、自己破産よりも個人再生や任意整理などの方法が適している可能性があります。債務の内容を詳細に分析し、最適な債務整理方法を選ぶことが重要です。
特に税金や養育費などの非免責債権が多い場合は、これらを含めた総合的な返済計画を立てられる個人再生が有利なケースもあります。専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択することをおすすめします。
まとめ
非免責債権とは、自己破産をしても免責されず、破産後も支払い義務が残る特別な種類の債務です。主に税金や罰金、悪意による不法行為の損害賠償、養育費などが該当します。これらは社会的公正性や弱者保護などの観点から、破産法第253条で明確に非免責債権として定められています。
非免責債権は自己破産後も支払い義務が残りますが、税務署や自治体との分割納付の交渉や、養育費の減額調停など、様々な対応方法があります。生活再建との両立を図りながら、計画的に返済していくことが重要です。
債務整理を検討する際には、自分の債務のうちどれが非免責債権に該当するかを把握し、自己破産が最適な選択肢かどうかを慎重に判断する必要があります。非免責債権の割合が大きい場合は、個人再生や任意整理などの他の債務整理方法も検討する価値があるでしょう。
いずれにしても、債務整理は専門的な知識が必要な手続きです。弁護士や司法書士などの専門家に相談して、自分の状況に最適な債務整理方法を選ぶことをおすすめします。正しい知識と適切なアドバイスを得ることで、効果的な債務整理を行い、新たな生活への第一歩を踏み出せるでしょう。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



