第三債務者(だいさんさいむしゃ)について詳しく解説
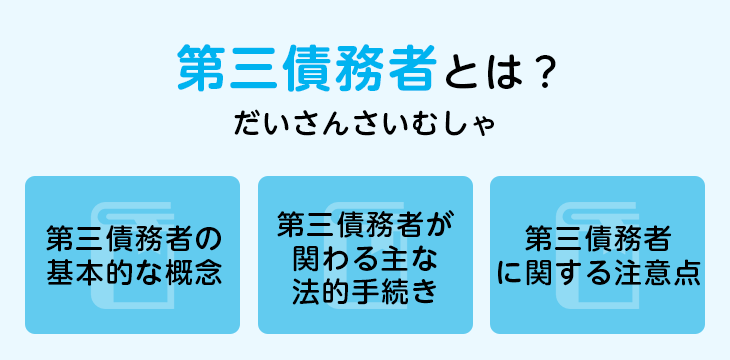
第三債務者とは、債権者と債務者の間に存在する第三者のことで、債務者に対して債務を負っている人や法人を指します。債務整理や過払い金請求の場面では、債権者が債務者の持つ債権(第三債務者に対する請求権)を差し押さえる際に重要な役割を持ちます。
具体的には、債務者があなたに借金をしておらず、あなたが債務者に借金をしている場合、あなたは「第三債務者」となります。債権者が債務者の財産を差し押さえる際、あなたへの返済請求権も差押えの対象となり得ます。
第三債務者の基本的な概念
第三債務者は、債権債務関係において特殊な立場にある第三者です。債務者に対して何らかの債務を負っている人や法人が該当します。これは給料を支払う会社や、貸金の返済義務がある人などが含まれます。
第三債務者の概念を理解するためには、債権者・債務者・第三債務者という三者間の関係を把握することが重要です。以下の表で三者の関係性を整理してみましょう。
| 債権者 | 債務者に対して債権(お金を返してもらう権利)を持つ人や法人 |
|---|---|
| 債務者 | 債権者に対して債務(お金を返す義務)を負う人や法人。同時に第三債務者に対しては債権を持つ |
| 第三債務者 | 債務者に対して債務を負う人や法人(債務者からみると、お金を返してもらう相手) |
上記の表は債権債務関係における三者の関係を示しています。債権者が債務者からの回収が困難になった場合、債務者が第三債務者に対して持つ債権を差し押さえることができます。
第三債務者の具体例
第三債務者には様々な例があります。日常生活でも意外と身近に存在する関係性です。以下に代表的な例をご紹介します。
- 債務者の勤務先(給料債権の債務者として)
- 債務者に家賃を支払う賃借人
- 債務者に対して商品代金などの支払義務がある取引先
- 債務者に貸付金を返済する義務のある人
- 債務者の銀行口座を管理する金融機関
このリストは第三債務者となり得る代表的な例です。特に債務者の給料を支払う勤務先は、債権回収の場面で差押えの対象となることが多い第三債務者です。
債務整理における第三債務者の位置づけ
債務整理の各手続きにおいて、第三債務者はそれぞれ異なる位置づけを持ちます。債務者が債務整理を行う際、第三債務者がどう影響するか理解しておくことが重要です。
| 任意整理 | 原則として第三債務者への影響は少ないですが、債権者が任意整理前に債務者の債権(給料など)を差し押さえている場合は関係します |
|---|---|
| 個人再生 | 再生手続き中に債務者の給料債権などが差し押さえられていた場合、中止命令によって差押えが一時的に止まることがあります |
| 自己破産 |
上記の表は債務整理の各手続きと第三債務者の関係を示しています。特に自己破産の場合は、債務者の財産に対する強制執行が効力を失うため、第三債務者への影響が大きくなります。
第三債務者が関わる主な法的手続き
第三債務者は主に以下のような法的手続きに関わることになります。これらの手続きは債務整理や債権回収の過程で頻繁に発生します。
- 債権差押命令:債権者が裁判所に申立てを行い、債務者が第三債務者に対して持つ債権を差し押さえる手続きです
- 債権差押通知:裁判所から第三債務者に対して差押命令が送達され、債務者への支払いが禁止されます
- 取立訴訟:差押債権者が第三債務者に対して直接取立てを行うための訴訟です
- 第三者異議の訴え:第三債務者が差押えに対して異議を述べる訴えです
このリストは第三債務者が関わる主な法的手続きを示しています。第三債務者は差押命令を受け取ったら、債務者への支払いを止め、裁判所の指示に従う必要があります。
差押命令の効果
債権差押命令が第三債務者に送達されると、以下のような法的効果が発生します。これらの効果を理解することで、第三債務者としての適切な対応が可能になります。
| 支払禁止効 | 差押命令を受けた第三債務者は、債務者に対して支払いをしてはならなくなります |
|---|---|
| 処分禁止効 | 債務者は、差し押さえられた債権について処分(譲渡や放棄など)ができなくなります |
| 優先弁済効 | 差押債権者は、差し押さえた債権から優先的に弁済を受ける権利を得ます |
上記の表は債権差押命令の主な効果を示しています。特に支払禁止効は第三債務者にとって重要で、この効果により債務者への支払いが法的に禁止されます。
第三債務者になった場合の対応
第三債務者として差押命令を受けた場合、適切に対応することが重要です。誤った対応は法的責任を問われる可能性があります。具体的な対応方法を以下に示します。
- 差押命令を確認する:裁判所からの差押命令書を詳細に確認し、どの債権が差し押さえられているか把握します
- 支払いを停止する:差し押さえられた債権について、債務者への支払いを停止します
- 陳述書を提出する:第三債務者は裁判所に対して、債務の存否や金額などを記載した陳述書を提出する義務があります
- 裁判所の指示に従う:差押命令に基づき、裁判所や差押債権者の指示に従って支払いを行います
- 専門家に相談する:不明点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします
このリストは第三債務者になった場合の基本的な対応手順です。特に陳述書の提出は法律で定められた義務であり、正確な情報を提供することが求められます。
第三債務者陳述書の記載事項
第三債務者は差押命令を受けた後、裁判所に陳述書を提出する義務があります。陳述書には以下の事項を記載する必要があります。
- 差し押さえられた債権の存否
- 債権の種類、額、弁済期
- 差押えを妨げる事由の有無
- 他の差押命令の有無とその内容
- 債権に関する担保権の有無とその内容
このリストは第三債務者陳述書に記載すべき主な事項です。虚偽の陳述をした場合は罰則があるため、正確な情報を記載することが重要です。
第三債務者に関する注意点
第三債務者として注意すべき点は多くあります。特に以下の点に注意することで、法的なトラブルを避けることができます。
- 差押命令を無視した場合、債権者に対して二重払いの責任を負う可能性があります
- 陳述書の提出を怠ったり虚偽の陳述をした場合、過料(罰金)の対象となります
- 複数の差押命令がある場合は、到達順に従って対応する必要があります
- 差押命令の範囲を超えて支払いを止めると、債務者との間でトラブルになる可能性があります
- 債務者と示談を結んでも、差押命令の効力は消滅しません
このリストは第三債務者として特に注意すべき点です。差押命令を適切に処理せず、誤った対応をすると法的な責任を問われる可能性があります。
第三債務者としての会社の対応
従業員の給料債権が差し押さえられた場合、勤務先企業は第三債務者として対応する必要があります。企業として特に注意すべき点を以下に示します。
| 給料計算の注意点 | 差押禁止債権(給料の一部は差押え対象外)の計算を正確に行う必要があります |
|---|---|
| プライバシーへの配慮 | 従業員のプライバシーに配慮し、差押えの事実を不必要に社内に広めないようにします |
| 人事部門の対応 |
|
上記の表は従業員の給料債権が差し押さえられた場合の企業側の注意点です。特に差押禁止債権の計算は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
第三債務者とは、債務者に対して債務を負っている第三者のことです。典型的な例としては、債務者に給料を支払う会社や、債務者にお金を返す義務のある人などが挙げられます。債権者が債務者からの回収が困難になった場合、債務者が第三債務者に対して持つ債権(給料債権など)を差し押さえることがあります。
第三債務者として差押命令を受けた場合は、命令内容を確認し、債務者への支払いを停止して、裁判所に陳述書を提出する必要があります。陳述書には差し押さえられた債権の存否や金額などを正確に記載しなければなりません。虚偽の陳述や陳述書の提出を怠ると、法的な責任を問われる可能性があります。
債務整理の各手続き(任意整理、個人再生、自己破産)によって第三債務者への影響は異なります。特に自己破産の場合は、債務者の財産に対する強制執行が効力を失うため、それまでの差押命令の効力も失われることがあります。第三債務者としての立場で不明点がある場合は、早め
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



