遅延損害金(ちえんそんがいきん)について詳しく解説
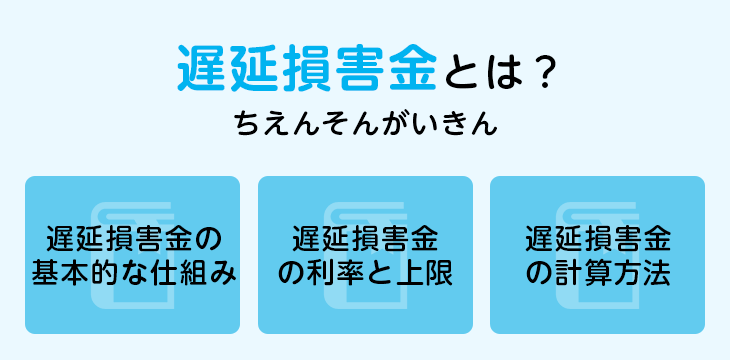
遅延損害金とは、借金やローンなどの債務の返済が遅れた場合に、約定の期日を過ぎた日数分だけ追加で支払う必要が生じるお金のことです。これは債務の支払いが遅れたことによる債権者の損害を補償するためのものです。
債務整理や過払い金請求の場面では、この遅延損害金が大きく膨らんでいるケースも少なくありません。元金に加えて遅延損害金も請求されるため、返済額が想像以上に増えてしまうことがあります。
遅延損害金の基本的な仕組み
遅延損害金は、債務の支払いが遅れた場合に発生する「ペナルティ」です。法律上は「債務不履行による損害賠償」という位置づけで、民法に基づいています。
遅延損害金は通常の利息とは異なり、返済期日を過ぎた後に初めて発生するものです。また、元金だけでなく利息の支払いが遅れた場合にも遅延損害金が発生することがあります。
| 法的根拠 | 民法第419条(金銭債務の特則)に基づいています |
|---|---|
| 発生条件 | 約定の返済期日を過ぎると自動的に発生します |
| 計算期間 | 返済期日の翌日から実際に支払いが行われる日まで |
| 対象金額 |
|
上記の表は遅延損害金の基本的な仕組みを示しています。返済期日を過ぎると自動的に発生し、日々増加していくため、返済が遅れれば遅れるほど支払う総額が大きくなります。
遅延損害金の利率と上限
遅延損害金の利率は、契約書等で定められていることが一般的です。ただし、利息制限法や貸金業法により上限が設けられており、それを超える利率の約定は無効となります。
遅延損害金の利率の上限は、借入の金額や種類によって異なります。利息制限法に基づく上限は以下の通りです。
| 借入金額 | 上限金利 | 遅延損害金上限 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% | 年15% |
上記の表は借入金額別の上限金利と遅延損害金の上限を示しています。法改正により、現在では遅延損害金の上限も通常の金利と同じになっています。以前は遅延損害金の上限が通常金利より高く設定されていたケースもありました。
契約で定めがない場合の遅延損害金
契約書等で遅延損害金の利率が定められていない場合は、民法の法定利率が適用されます。2024年3月現在の法定利率は年3%です。
なお、2020年4月の民法改正により、法定利率は固定制から変動制に変わりました。3年ごとに見直しが行われ、必要に応じて変更されます。商事取引の場合は別の利率が適用されることもあります。
- 2020年3月31日以前に発生した債務:年5%
- 2020年4月1日以降に発生した債務:年3%(2024年3月現在)
- 商事債務(事業者間の取引など):特別な取り決めがある場合あり
- 特約がある場合:上限の範囲内で契約で定めた利率
このリストは契約で定めがない場合の遅延損害金の利率を示しています。民法改正により利率が変わったため、債務の発生時期によって適用される利率が異なる点に注意が必要です。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金は、元金×利率×遅延日数÷365で計算されます。なお、うるう年の場合は366日で計算することもあります。具体的な計算方法を以下の例で見てみましょう。
| 基本計算式 | 遅延損害金 = 元金 × 遅延損害金の利率 × 遅延日数 ÷ 365 |
|---|---|
| 計算例 |
|
| 実務上の計算方法 |
|
上記の表は遅延損害金の基本的な計算方法と具体例を示しています。実際の債務整理の現場では、専門家がソフトウェアなどを使って正確に計算を行います。
遅延損害金が膨らむ仕組み
遅延損害金は日々増加していくため、長期間返済が滞ると元金を大きく上回ることもあります。特に高金利の契約の場合、遅延損害金の増加は急速です。
- 初期段階:返済が数日〜数週間遅れた程度なら、遅延損害金は比較的少額
- 数ヶ月の遅延:元金の数%程度の遅延損害金が発生する可能性
- 1年以上の遅延:元金の10%以上の遅延損害金が発生することも
- 数年の遅延:元金に匹敵する、あるいは上回る遅延損害金が発生することも
このリストは遅延損害金が時間の経過とともに膨らんでいく仕組みを示しています。返済が長期間滞ると、当初の借入額以上の遅延損害金が発生することもあり、債務問題をさらに深刻化させる原因となります。
債務整理における遅延損害金の扱い
債務整理では、遅延損害金も整理の対象となります。ただし、債務整理の種類によって遅延損害金の扱いが異なりますので、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
| 任意整理 |
|
|---|---|
| 個人再生 |
|
| 自己破産 |
|
| 過払い金請求 |
|
上記の表は債務整理の各手続きにおける遅延損害金の扱いを示しています。どの債務整理方法を選択するかによって、遅延損害金の扱いも大きく変わってきます。
遅延損害金に関する注意点
遅延損害金について知っておくべき注意点をいくつか挙げます。債務整理を検討している方は、これらの点に特に注意が必要です。
- 一度でも支払いが遅れると信用情報に記録される可能性がある
- 支払いが滞るほど遅延損害金は膨らみ、返済がさらに困難になる
- 法外な遅延損害金を請求されている場合は、利息制限法に基づく引き直し計算が有効
- 時効が完成していない限り、長期間経過後も遅延損害金を含めて請求される可能性がある
- 債権譲渡が行われると、新しい債権者から遅延損害金を含めた請求がくることがある
このリストは遅延損害金に関する主な注意点です。特に信用情報への影響や遅延損害金の膨張には注意が必要です。返済が困難な状況になった場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
遅延損害金を抑えるための対策
遅延損害金の発生や増加を抑えるためには、以下のような対策が考えられます。返済が困難な状況になった場合の参考にしてください。
- 支払い期日を守る:可能な限り期日内に返済し、遅延損害金の発生を防ぐ
- 一部返済する:全額返済が難しい場合でも、一部でも返済すれば遅延損害金の発生額を減らせる
- 債権者と交渉する:返済計画の見直しや遅延損害金の減免について相談する
- 借換えを検討する:低金利の借入に借り換えて、遅延損害金の発生を止める
- 債務整理を検討する:返済が困難な場合は、早めに債務整理を検討する
このリストは遅延損害金を抑えるための主な対策です。返済が困難になった場合でも、放置せずに何らかの行動を取ることが重要です。特に債権者との交渉や債務整理の検討は、状況の改善につながる可能性があります。
まとめ
遅延損害金とは、借金やローンなどの債務の返済が遅れた場合に、約定の期日を過ぎた日数分だけ追加で支払う必要が生じるお金のことです。返済期日の翌日から実際に返済される日までの期間について発生し、日々増加していきます。
遅延損害金の利率は契約で定められていることが多いですが、利息制限法や貸金業法による上限があります。具体的には、借入金額が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%が上限となります。契約で定めがない場合は、2020年4月以降の債務については年3%の法定利率が適用されます。
債務整理では、遅延損害金も整理の対象となります。任意整理では交渉により減額や免除が可能、個人再生では再生計画により大幅に減額、自己破産では免責により免除されるのが一般的です。返済が困難になった場合は、放置せずに早めに専門家に相談し、適切な債務整理の方法を検討することが大切です。それにより、膨らみ続ける遅延損害金の問題を解決し、経済的な再スタートを切ることができます。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



