少額管財(しょうがくかんざい)について詳しく解説
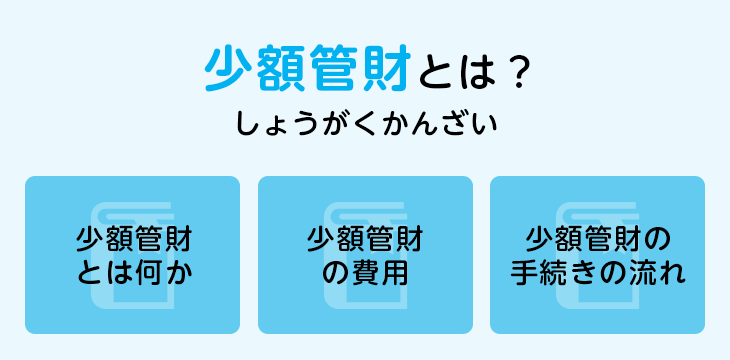
少額管財とは、自己破産手続きの一種で、債務者に一定の財産があるものの、その財産額が少額であるケースにおいて適用される管財手続きのことを指します。通常の破産手続きでは「管財人」という専門家が選任され、債務者の財産を管理・換価して債権者に配当する作業を行いますが、少額管財はその簡易版といえるものです。
少額管財手続きは、債務者の財産が少額であるために通常の管財手続きを行うと費用倒れになってしまう場合に、手続きを簡略化して行われます。債務者の負担を軽減しつつ、債権者への適切な配当を実現するための制度として機能しています。
少額管財とは何か
少額管財とは、自己破産における管財手続きの一種で、債務者に換価できる財産があるものの、その価値が少額である場合に適用される簡易的な手続きです。裁判所は破産管財人を選任しますが、通常の管財手続きと比べて手続きが簡略化されています。
一般的に債務者に20万円以上の換価できる財産がある場合は、少額管財または管財事件として処理されることが多いです。ただし、具体的な基準は裁判所によって異なり、20万円以下でも少額管財になるケースや、それ以上でも同時廃止で処理されるケースもあります。
| 少額管財の適用基準 |
|
|---|
上記の表は少額管財が適用される一般的な基準です。裁判所や地域によって運用に差があるため、実際の適用については弁護士や司法書士に確認することをおすすめします。
少額管財と同時廃止の違い
自己破産には「少額管財」と「同時廃止」という二つの主要な手続き方法があります。どちらの手続きになるかは、主に債務者の財産状況によって判断されます。
| 項目 | 少額管財 | 同時廃止 |
|---|---|---|
| 適用条件 | 債務者に換価できる財産がある場合 | 債務者に換価できる財産がほとんどない場合 |
| 破産管財人 | 選任される | 選任されない |
| 手続期間 | 約6ヶ月〜1年程度 | 約3ヶ月〜6ヶ月程度 |
| 予納金 | 約15万円〜30万円程度 | 約5万円〜15万円程度 |
| 債権者への配当 | ある | ない |
上記の表は少額管財と同時廃止の主な違いを示しています。同時廃止は財産がほとんどないケースで適用され、手続きが簡略化されているため期間も短く費用も安くなっています。
なお、少額管財の場合は破産管財人への報酬が必要となるため、予納金(裁判所に事前に納める費用)が高くなる傾向があります。ただし、財産状況や裁判所によって金額は変動します。
少額管財の費用
少額管財手続きを行う場合、いくつかの費用が発生します。主な費用は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 説明 |
|---|---|---|
| 予納金 | 約15万円〜30万円 | 裁判所に納める費用で、破産管財人の報酬や諸経費に充てられます |
| 収入印紙代 | 約1万6千円 | 破産申立書と免責申立書に貼付する印紙代 |
| 郵便切手代 | 約5千円〜1万円 | 裁判所からの通知等の郵送費用 |
| 弁護士・司法書士報酬 | 約20万円〜40万円 | 専門家に依頼する場合の費用 |
上記の表は少額管財手続きにかかる主な費用の目安です。裁判所や地域、また債務者の状況によって費用は異なります。特に弁護士や司法書士への報酬は事務所によって差があります。
費用の支払いが難しい場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することも検討できます。この制度を利用すると、弁護士・司法書士費用を分割払いにすることができ、場合によっては予納金の立替えも可能です。
少額管財の手続きの流れ
少額管財の手続きは、通常の自己破産手続きと基本的な流れは同じですが、管財人が選任される点が特徴です。おおよその流れは以下のとおりです。
- 専門家への相談・依頼:自己破産を検討している旨を弁護士または司法書士に相談します
- 必要書類の収集・準備:住民票、戸籍謄本、資産証明書、債権者に関する資料などを準備します
- 自己破産・免責申立書の作成:弁護士または司法書士が書類を作成します
- 裁判所への申立て:作成した書類と予納金を裁判所に提出します
- 破産手続開始決定:裁判所が破産手続きの開始を決定します
- 破産管財人の選任:裁判所が破産管財人(通常は弁護士)を選任します
- 債権者集会:債権者が集まり、債務者の状況について確認します
- 財産の換価・配当:破産管財人が債務者の財産を換価し、債権者に配当します
- 管財人による調査:債務者の経済状況や破産原因について調査します
- 免責審尋:裁判官との面談で破産に至った経緯などを説明します
- 免責許可決定:問題がなければ免責が許可され、債務の支払い義務が免除されます
上記のリストは少額管財手続きの一般的な流れです。手続き全体の期間は、通常6ヶ月〜1年程度かかります。同時廃止よりも時間がかかるのは、管財人による財産の換価や債権者への配当手続きが入るためです。
少額管財のメリット・デメリット
少額管財手続きには、同時廃止や通常の管財手続きと比較していくつかのメリットとデメリットがあります。
| メリット |
|
|---|
| デメリット |
|
|---|
上記の表は少額管財手続きの主なメリットとデメリットです。債務者の状況によってどちらの手続きが適しているかは異なるため、専門家に相談して判断することをおすすめします。
なお、少額管財か同時廃止かを選択できるわけではなく、債務者の財産状況によって裁判所が判断します。そのため、破産申立ての前に、弁護士や司法書士と十分に相談して、予想される手続き方法と必要な費用について確認しておくことが重要です。
よくある質問
少額管財と通常の管財手続きの違いは何ですか?
少額管財は通常の管財手続きの簡易版といえるもので、基本的な流れは同じです。主な違いは、少額管財の場合は財産価値が比較的少額であるため、手続きが簡略化されている点です。例えば、債権者集会が省略されることもあり、また管財人の報酬も通常より低額に設定されています。
少額管財になると必ず財産はすべて失うのですか?
すべての財産を失うわけではありません。自己破産手続きでは、一定の生活必需品(日常生活に最低限必要な家財道具、一定額以下の現金など)は「自由財産」として手元に残すことができます。また、「99条の財産」という制度を利用すれば、裁判所の許可を得て一定の財産を残せる可能性もあります。
具体的にどの財産が処分対象になるかは、個々のケースや裁判所によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
少額管財とは、自己破産手続きの一種で、債務者に一定の財産があるものの、その財産額が比較的少額である場合に適用される簡易的な管財手続きです。通常は債務者の財産が20万円以上ある場合に少額管財となる可能性が高くなりますが、具体的な基準は裁判所によって異なります。
少額管財の手続きでは、裁判所から破産管財人が選任され、債務者の財産を換価して債権者に配当する作業が行われます。同時廃止と比較すると手続き期間が長く(約6ヶ月〜1年程度)、費用も高額(予納金約15万円〜30万円)になる傾向がありますが、財産がある場合の適切な処理方法として機能しています。
少額管財か同時廃止かは債務者が選択できるものではなく、裁判所が債務者の財産状況に基づいて判断します。自己破産を検討している場合は、事前に弁護士や司法書士に相談し、自分のケースではどのような手続きになる可能性が高いか、必要な費用はいくらかを確認しておくことが重要です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



