債務(さいむ)について詳しく解説
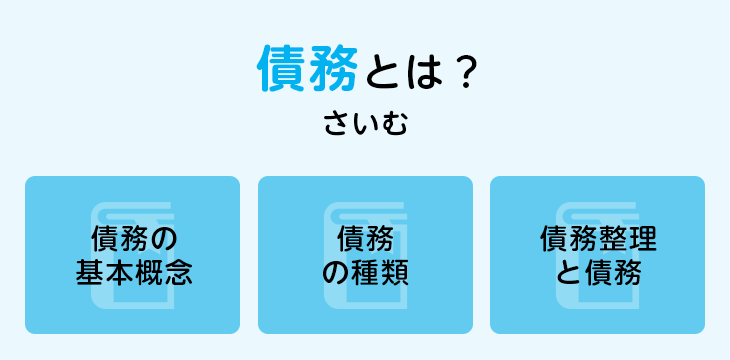
債務とは、法律上の義務として、特定の相手(債権者)に対して一定の行為をする義務のことを指します。特に、金銭を支払う義務のことを「金銭債務」と呼び、借金問題を扱う債務整理の分野では、この金銭債務が中心となります。
債務は契約、不法行為、法律の規定などによって発生し、それぞれに応じた返済義務や責任が生じます。債務整理を検討する上で、自分の債務の種類や性質を理解することは重要です。
債務の基本概念
債務とは、法律上の義務として、特定の相手(債権者)に対して一定の行為をする義務のことです。債務者は債権者に対して何らかの行為をする義務を負っており、これを「債務関係」と呼びます。
債務の反対側には「債権」があり、債権者は債務者に対して一定の行為を請求する権利を持っています。債権と債務は表裏一体の関係にあり、同じ法律関係の異なる側面を表しています。
債務の基本的な構成要素
- 債務者(さいむしゃ):債務を負う側の人
- 債権者(さいけんしゃ):債権を持つ側の人
- 給付内容:債務者が行うべき行為(金銭の支払い、物の引渡し、サービスの提供など)
- 履行期:債務を履行すべき期限
- 履行場所:債務を履行すべき場所
このリストは債務の基本的な構成要素を示しています。これらの要素は債務の内容を具体的に規定し、債務者の義務の範囲を明確にします。
債務の種類
債務はその内容や性質によって様々な種類に分類されます。主な分類は以下の通りです。
| 給付内容による分類 |
|
|---|---|
| 発生原因による分類 |
|
| 責任範囲による分類 |
|
上記の表は債務の主な分類を示しています。債務整理の文脈では、主に金銭債務が対象となり、その中でも特に消費者金融やクレジットカード会社などからの借入金が中心となります。
債務整理の対象となる主な債務
- 消費者金融からの借入金
- 銀行カードローン
- クレジットカードのキャッシング・ショッピング枠
- 銀行ローン(住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど)
- 保証債務(他人の借金の保証人になった場合)
- 賃料・公共料金の滞納
- 税金の滞納
- 医療費の滞納
- 損害賠償債務
このリストは債務整理の対象となる主な債務を示しています。ただし、税金や罰金などの非免責債権は、自己破産をしても免責されない場合があります。
債務の発生と消滅
債務は様々な原因によって発生し、また様々な事由によって消滅します。主な発生原因と消滅事由は以下の通りです。
債務の発生原因
| 契約 | 最も一般的な債務発生原因。当事者の合意により債務が発生します。ローン契約、売買契約、賃貸借契約などがあります。 |
|---|---|
| 不法行為 | 他人に損害を与えた場合に発生する損害賠償債務。交通事故や名誉毀損などによる賠償責任が該当します。 |
| 事務管理 | 他人の事務を本人の意思に関わらず管理した場合に発生する債務。管理に必要な費用の償還請求権などが生じます。 |
| 不当利得 | 法律上の原因なく利益を得た場合に発生する返還債務。誤振込みや過払い金の返還義務などが該当します。 |
| 法律の規定 | 法律の規定により直接発生する債務。税金、保険料、親族間の扶養義務などがあります。 |
上記の表は債務の主な発生原因を示しています。債務整理の対象となるのは、主に契約に基づく金銭債務です。
債務の消滅事由
- 弁済(通常の返済):債務の本来の消滅原因。債務の内容に従った給付を行うことで債務は消滅します。
- 相殺:互いに同種の債権・債務を有する場合、その対当額で債務が消滅します。
- 更改:旧債務を消滅させ、新債務を成立させる合意。リスケジュールなどが該当します。
- 免除:債権者が債権を放棄することで債務が消滅します。債権放棄や和解などの形で行われます。
- 混同:債権者と債務者が同一人となった場合に債務が消滅します。
- 時効:一定期間権利を行使しないことで債務が消滅します。
- 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産):法的手続きにより債務が整理・免除されます。
このリストは債務の主な消滅事由を示しています。債務整理は、通常の弁済が困難になった場合に利用される債務の消滅方法です。
債務の時効
債務には消滅時効があり、一定期間権利行使がなされないと時効により消滅する可能性があります。主な債務の時効期間は以下の通りです。
| 商事債権 | 5年(2020年4月1日以降に発生した債権) 改正前の商法では5年(商人間の取引) |
|---|---|
| 民事債権 | 10年(2020年4月1日以降に発生した債権) 改正前の民法では10年 |
| 短期消滅時効 | 2020年4月1日の民法改正により、3年・2年・1年の短期消滅時効は廃止され、原則5年となりました。 |
| 定期給付債権 | 5年(利息、家賃、給料など定期的に発生する債権) |
| 不法行為債権 | 損害および加害者を知った時から3年 不法行為の時から20年 |
上記の表は主な債務の時効期間を示しています。2020年4月に民法が改正され、時効期間が変更されているため注意が必要です。時効の援用(時効による消滅を主張すること)は債務者自身が行う必要があります。
債務整理と債務
債務整理は、返済が困難になった債務を法的手続きによって整理する方法です。債務整理の種類によって、債務の扱いが異なります。
| 任意整理 | 債権者と個別に交渉して、将来利息のカットや分割返済などの条件変更を行います。元金は基本的にそのまま返済する必要がありますが、和解により一部減額されることもあります。 |
|---|---|
| 特定調停 | 裁判所を通じて債権者と返済条件の変更について話し合います。任意整理と同様に、将来利息のカットと分割返済が一般的です。 |
| 個人再生 | 裁判所を通じて債務を大幅に減額(最大で5分の1まで)し、残りを3〜5年で分割返済します。住宅ローンがある場合、住宅を残したまま債務整理ができる「住宅ローン特則」があります。 |
| 自己破産 | 裁判所に申立てを行い、債務の支払い義務をなくします。資産がある場合は処分されますが、一定の生活必需品は手元に残すことができます。すべての債務が免除されるわけではなく、税金や養育費などは免責されない場合があります。 |
上記の表は債務整理の種類と債務の扱いを示しています。どの方法が適しているかは、債務の総額、収入状況、資産状況などによって異なります。
債務整理の対象外となる主な債務
- 租税債務(所得税、住民税など)
- 罰金・科料・過料
- 養育費や扶養料
- 故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償債務
- 詐欺や横領などの不正行為による債務
- 自己破産申立て後に発生した債務
- 学生ローン(JASSO奨学金など)※一部例外あり
このリストは主に自己破産で免責されない(免除されない)債務を示しています。これらの債務は、自己破産をしても支払い義務が残る場合が多いため注意が必要です。
債務に関するよくある質問
連帯債務とは何ですか?連帯保証との違いは?
連帯債務とは、複数の債務者が同一の債務について、それぞれが独立して全額の支払い責任を負う債務のことです。例えば、夫婦で住宅ローンを組む場合、連帯債務者として契約することがあります。
一方、連帯保証は、主たる債務者とは別に、保証人が債務の全額について主たる債務者と同様の責任を負うものです。連帯債務者は最初から債務者ですが、連帯保証人は主たる債務者が支払えない場合に責任を負います。どちらも請求があれば全額の支払い義務があるという点では同じです。
債務の時効はどのように計算されますか?
債務の時効は、権利を行使できるときから進行します。例えば、借金の場合は返済期日の翌日から時効が進行します。時効期間は債務の種類によって異なりますが、2020年4月の民法改正により、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方となりました。
また、時効は一定の事由により中断(更新)されます。具体的には、債務者が債務を承認した場合(一部返済や返済の約束など)、債権者が訴訟を提起した場合などです。時効が中断すると、その時点から再び時効期間がカウントされ直します。
親の借金を子が引き継ぐことになりますか?
原則として、親の借金(債務)は相続の対象となります。親が亡くなった場合、子供を含む法定相続人は、プラスの財産(不動産、預貯金など)とともに、マイナスの財産(借金など)も相続します。
ただし、相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。借金が財産を上回る場合は、相続放棄(すべての相続財産を放棄する)または限定承認(相続した財産の範囲内でのみ債務を弁済する)を検討する必要があります。相続放棄は原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
まとめ
債務とは、法律上の義務として、特定の相手(債権者)に対して一定の行為をする義務のことを指します。特に金銭を支払う義務である金銭債務は、債務整理において中心となる概念です。
債務は契約、不法行為、法律の規定などによって発生し、弁済、相殺、免除、時効などによって消滅します。時効については、2020年4月の民法改正により、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」となりました。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などの方法があり、それぞれ債務の扱いが異なります。任意整理や特定調停では主に将来利息のカットと分割返済、個人再生では債務の大幅減額と分割返済、自己破産では原則として債務の免除が行われます。
ただし、税金、罰金、養育費など一部の債務は債務整理(特に自己破産)の対象外となる場合があります。また、連帯債務や保証債務など、他人の債務に関連して責任を負うケースもあるため、自分の債務の性質や内容を正確に把握することが重要です。債務問題を抱えている場合は、早めに専門家に相談し、適切な解決方法を見つけることをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



