通常管財(つうじょうかんざい)について詳しく解説
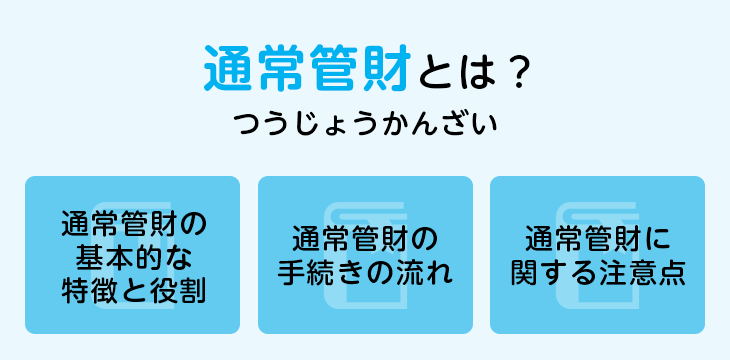
通常管財とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を管理・換価し、債権者に配当する手続きのことです。比較的財産額が多い場合や調査すべき事項が複雑な事案において採用される破産手続きの形態です。
自己破産には「同時廃止」と「管財」の2つの手続き形態があり、管財はさらに「少額管財」と「通常管財」に分けられます。通常管財は最も本格的な破産手続きであり、破産管財人による詳細な財産調査と適正な配当が行われます。
通常管財の基本的な特徴と役割
通常管財は、破産管財人が破産者の財産を管理・換価し、債権者に公平に分配するという破産手続きの本来の形態です。破産管財人は主に弁護士が選任され、破産者の財産調査から債権者への配当までの一連の手続きを担当します。
通常管財の主な役割は、破産者の財産を適正に把握し、換価価値の高い財産については売却して債権者に配当することです。また、破産前の財産処分が不当でないかも調査します。
| 破産管財人の役割 |
|
|---|---|
| 通常管財の特徴 | |
| 通常管財と同時廃止の違い |
|
上記の表は通常管財の基本的な特徴と役割を示しています。通常管財では破産管財人が選任され、本格的な財産調査と配当手続きが行われるため、同時廃止や少額管財に比べて時間と費用がかかります。
通常管財が選択される条件
自己破産の申立てをした場合、裁判所は事案の内容に応じて同時廃止、少額管財、通常管財のいずれかの手続きを選択します。通常管財が選択される主な条件は以下の通りです。
- 換価すべき財産が多額にある場合
- 破産者が事業者(個人事業主や会社役員)である場合
- 債権者数が多い場合(数十社以上)
- 負債額が高額な場合(数千万円以上)
- 否認対象となる可能性がある財産処分がある場合
- 免責不許可事由の有無について詳しい調査が必要な場合
- 破産者の生活状況や職業に特殊性がある場合
- 詐欺的破産の疑いがある場合
このリストは通常管財が選択される主な条件を示しています。特に事業者の破産や財産状況が複雑な場合は通常管財となる可能性が高くなります。最終的な判断は裁判所が行いますが、上記の条件に該当する場合は通常管財を前提に準備を進めるとよいでしょう。
通常管財、少額管財、同時廃止の比較
自己破産の3つの手続き形態(通常管財、少額管財、同時廃止)の主な違いを比較してみましょう。
| 通常管財 | 少額管財 | 同時廃止 | |
|---|---|---|---|
| 適用条件 | 配当すべき財産が比較的多額 | 配当すべき財産が少額 | 配当すべき財産がほとんどない |
| 予納金 | 50万円〜100万円程度 | 20万円〜40万円程度 | 15,000円〜20,000円程度 |
| 期間 | 半年〜1年程度 | 3ヶ月〜6ヶ月程度 | 2ヶ月〜4ヶ月程度 |
| 債権者集会 | あり(複数回) | あり(通常1回) | なし |
| 配当手続き | あり | あり(簡易) | なし |
上記の表は通常管財、少額管財、同時廃止の主な違いを示しています。通常管財は最も本格的な破産手続きであり、予納金や期間も他の形態に比べて大きくなります。
通常管財の手続きの流れ
通常管財の具体的な手続きの流れを見ていきましょう。申立てから免責決定までには複数の段階があり、破産者は各段階で必要な対応をする必要があります。
- 破産申立て:必要書類の提出と予納金の納付
- 破産手続開始決定:裁判所が破産管財人を選任
- 破産管財人による財産調査:破産者の面談、資料収集
- 財産の管理・換価:破産管財人が財産を売却
- 第1回債権者集会:破産管財人の調査結果報告、債権者からの質問
- 調査期日:裁判所による破産者の調査
- 第2回債権者集会:配当方針の決定
- 配当手続き:債権者への配当の実施
- 破産手続終結決定:裁判所による破産手続の終了宣言
- 免責審尋:裁判官による破産者の免責についての審査
- 免責許可決定・免責不許可決定:裁判所による最終判断
このリストは通常管財の基本的な手続きの流れを示しています。実際の手続きでは、事案の複雑さによって期間や債権者集会の回数が変わることがあります。特に第1回債権者集会と調査期日は破産者本人の出席が必要な重要な期日です。
債権者集会と調査期日
通常管財では、債権者集会と調査期日が重要な手続きとなります。これらの期日での主な内容を見てみましょう。
| 第1回債権者集会 |
|
|---|---|
| 調査期日 |
|
| 第2回債権者集会 |
|
上記の表は通常管財における主要な期日の内容を示しています。債権者集会と調査期日は重要な手続きであり、破産者は真摯に対応する必要があります。特に嘘をついたり、財産を隠したりすると免責不許可事由となる可能性があるので注意が必要です。
通常管財のメリットとデメリット
通常管財には、他の破産手続きと比べていくつかのメリットとデメリットがあります。自己破産を検討する際には、これらを理解しておくことが重要です。
メリット
- 詳細な財産調査により、適正な破産手続きが実現できる
- 破産管財人が財産の換価を専門的に行うため、適切な価格での売却が期待できる
- 債権者への公平な配当が実施される
- 否認権の行使などにより、破産前の不当な財産処分が是正される
- 適正な手続きを経ることで、免責の可能性が高まる
- 複雑な事案でも専門家である破産管財人が適切に対応する
このリストは通常管財の主なメリットを示しています。特に財産状況が複雑な場合や事業者の破産では、破産管財人の専門的な関与によって適正な手続きが実現します。
デメリット
- 予納金が高額(50万円〜100万円程度)
- 手続き期間が長い(半年〜1年程度)
- 免責までの期間が長くなる
- 債権者集会や調査期日など、裁判所への出頭機会が多い
- 破産管財人による厳密な財産調査が行われる
- 換価可能な財産はすべて売却される
- 自由財産以外の財産処分権が破産管財人に移る
このリストは通常管財の主なデメリットを示しています。特に予納金の高さと手続き期間の長さは、通常管財の大きなデメリットとなります。経済的に苦しい状況での高額な予納金の準備は負担となることが多いです。
通常管財に関する注意点
通常管財による自己破産を検討する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらの点を事前に理解しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
| 予納金の準備 |
|
|---|---|
| 財産の取扱い |
|
| 破産管財人への協力 |
|
| 期日への出席 |
|
上記の表は通常管財に関する主な注意点を示しています。特に予納金の準備と破産管財人への協力は重要なポイントです。通常管財は本格的な破産手続きであるため、破産者にとっても一定の負担がありますが、誠実に対応することで円滑な免責につながります。
法テラスの利用
通常管財の高額な予納金が負担となる場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度の利用を検討する価値があります。
- 収入や資産が一定基準以下であれば利用可能
- 予納金の立替制度がある(月々の分割返済)
- 弁護士費用の立替も可能
- 生活保護受給者などは返済免除の可能性あり
- 申込みには法テラスでの面談が必要
このリストは法テラスの民事法律扶助制度の概要です。経済的に困窮している状態で通常管財となる場合は、この制度の利用を検討すると良いでしょう。詳細については法テラスや弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
通常管財とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を管理・換価し、債権者に配当する手続きのことです。比較的財産額が多い場合や事業者の破産、債権者数が多い場合など、調査すべき事項が複雑な事案において採用されます。
通常管財の特徴としては、破産管財人による詳細な財産調査、債権者集会の開催、配当手続きの実施などがあります。また、予納金が50万円〜100万円程度と高額であり、手続き期間も半年〜1年程度と長くなる傾向があります。破産者は債権者集会や調査期日への出席が必要であり、破産管財人の調査に誠実に協力する義務があります。
通常管財のメリットとしては、専門家である破産管財人による適正な手続きの実現、適切な価格での財産換価、債権者への公平な配当などが挙げられます。一方、デメリットとしては高額な予納金、長い手続き期間、複数回の裁判所出頭などがあります。経済的に困窮している場合は、法テラスの民事法律扶助制度の利用も検討する価値があります。自己破産を検討する際には、弁護士などの専門家に相談し、自分の状況に最適な手続き形態を選択することが重要です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



