最低弁済基準(さいていべんさいきじゅん)について詳しく解説
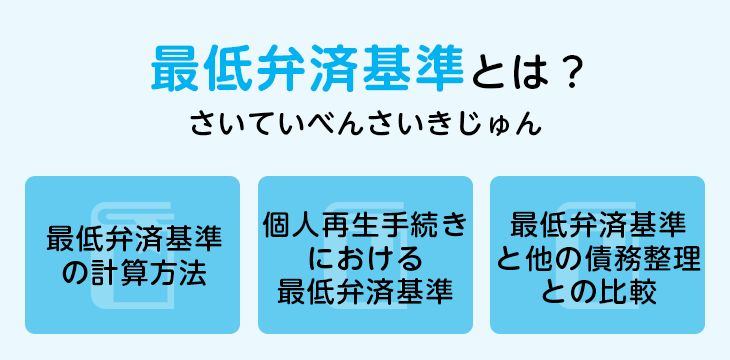
最低弁済基準とは、個人再生や民事再生などの債務整理手続きにおいて、債務者が債権者に対して最低限支払うべき金額の基準のことです。これは「清算価値保障原則」とも呼ばれ、債務者が自己破産したと仮定した場合に債権者が受け取れるであろう配当額(清算価値)以上の返済を保障するという考え方に基づいています。
個人再生では、この最低弁済基準を下回る返済計画は認められず、債務者はこの基準額以上の返済を提案する必要があります。この基準は債務者の財産状況や収入状況によって異なり、特に不動産や自動車といった資産の評価が重要になります。
最低弁済基準とは
最低弁済基準は、個人再生や民事再生といった債務整理手続きにおいて、債務者が債権者に対して支払うべき最低限の金額を定める基準です。この基準は「清算価値保障原則」という考え方に基づいており、債務者が再生手続きではなく自己破産を選択した場合に債権者が受け取れるであろう配当額(清算価値)以上の返済を保障するものです。
つまり、債務者にとっては債務の大幅な減額というメリットがある一方で、債権者にとっても自己破産より不利にならないという保障があります。この原則によって、債務者と債権者の利害バランスを取りながら、債務者の経済的再生を図ることができます。
| 法的根拠 | 民事再生法第174条第2項第4号、第229条の2第2項第2号 |
|---|---|
| 別名 | 清算価値保障原則(せいさんかちほしょうげんそく) |
| 主な対象手続き | 個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)、民事再生 |
| 基準の性質 | 再生計画認可のための必須条件 |
この表は最低弁済基準の基本情報をまとめたものです。法的には民事再生法に規定されており、個人再生や民事再生といった債務整理手続きにおいて適用されます。この基準を満たすことは再生計画が認可されるための必須条件の一つです。
最低弁済基準の計算方法
最低弁済基準(清算価値)を計算するためには、債務者の財産を評価し、自己破産した場合に債権者に配当される金額を算出する必要があります。主な計算方法は以下の通りです。
財産評価のポイント
- 不動産(土地・建物)の時価評価
- 自動車などの動産の時価評価
- 預貯金の残高
- 有価証券(株式・債券など)の評価額
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金の見込み額(按分計算)
- 貴金属・美術品などの評価額
上記のリストは最低弁済基準を計算する際に評価対象となる主な財産です。これらの財産を時価評価し、その合計額から自由財産(差押禁止財産)や担保権付財産の担保権の額などを差し引いて計算します。
計算式
最低弁済基準(清算価値)の基本的な計算式は以下のようになります。
| 清算価値の計算式 | |
|---|---|
|
|
| 項目 | 説明 |
| 総財産評価額 | 債務者が所有するすべての財産の時価評価額の合計 |
| 自由財産 | 差押禁止財産(99万円以下の現金など) |
| 担保権の被担保債権額 | 住宅ローンなど担保権付債権の金額 |
| 共益債権・優先債権 | 租税債権、手続費用などの優先的に支払われる債権 |
この表は最低弁済基準を計算するための基本的な計算式と各項目の説明をまとめたものです。債務者が所有する財産から自由財産や担保権付債権などを差し引き、自己破産した場合に一般債権者に配当される金額を算出します。
財産評価の具体例
| 財産の種類 | 評価方法 | 計算への反映 |
|---|---|---|
| 不動産 | 固定資産評価額や不動産鑑定評価額 | 担保権額を差し引いた余剰価値 |
| 自動車 | 中古車市場の価格 | ローン残高を差し引いた額 |
| 預貯金 | 残高そのまま | 99万円を超える部分 |
| 生命保険 | 解約返戻金 | 返戻金がある場合のみ |
| 退職金請求権 | 退職時の見込み額の一部 | 勤続年数に応じた按分計算 |
この表は主な財産の評価方法と計算への反映方法をまとめたものです。特に不動産や自動車などの高額資産の評価が重要で、専門家による適切な評価が必要です。また、自由財産として守られる99万円以下の現金などは清算価値の計算から除外されます。
個人再生手続きにおける最低弁済基準
個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれで最低弁済基準の考え方に違いがあります。また、住宅ローンがある場合の特則も重要なポイントです。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
| 手続きの種類 | 対象者 | 最低弁済基準 |
|---|---|---|
| 小規模個人再生 | 個人の債務者全般 |
|
| 給与所得者等再生 | 安定した収入がある個人 |
|
この表は個人再生の2つの手続きにおける最低弁済基準の違いをまとめたものです。小規模個人再生では清算価値のみが基準となりますが、給与所得者等再生では清算価値と可処分所得の2年分を比較し、大きい方が基準となります。
住宅資金特別条項の場合
住宅ローンがある債務者が住宅資金特別条項を利用する場合、最低弁済基準の計算には特別な考慮が必要です。
- 住宅ローンは再生計画から除外され、従来通り返済を継続
- 住宅の価値から住宅ローン残高を差し引いた余剰価値がある場合、それが清算価値に含まれる
- 住宅ローン残高が住宅の価値を上回る場合(担保割れ)、清算価値への影響はない
- 住宅以外の財産から算出される清算価値に基づいて最低弁済額が決まる
上記のリストは住宅資金特別条項を利用する場合の最低弁済基準の考え方です。住宅を維持しながら債務整理ができるメリットがありますが、住宅に余剰価値がある場合はその分を返済計画に反映させる必要があります。
最低弁済基準と債務減額の関係
- 債務総額の上限は、原則として5,000万円以下(住宅ローンを除く)
- 再生計画では、債務総額の1/5以上または100万円以上のいずれか大きい額を返済
- ただし、最低弁済基準(清算価値)がこれを上回る場合は、その金額以上の返済が必要
- 最低弁済基準と法定最低額のいずれか大きい方が実際の返済額の下限となる
- 返済期間は原則として3年間(最長5年まで延長可能)
上記のリストは最低弁済基準と実際の債務減額の関係を示しています。債務総額の1/5(最低100万円)という法定最低額と、清算価値を比較して大きい方が実際の返済額の下限となります。財産が多い債務者は、法定最低額よりも高い返済額が求められることがあります。
最低弁済基準を満たせない場合の対応
債務者の財産状況から算出された最低弁済基準(清算価値)が高額で、その金額を返済することが難しい場合、以下のような対応策が考えられます。
財産の処分による対応
- 清算価値が高くなっている原因となる財産(不動産、自動車など)の売却
- 生命保険の解約や一部解約
- 貴金属・美術品などの処分
- 退職金請求権に関する特別な取り決め
- 親族からの援助を受けて最低弁済額を確保
上記のリストは最低弁済基準を満たすための財産処分による対応策です。清算価値を引き上げている財産を処分することで、最低弁済基準額を下げることができる場合があります。ただし、生活に必要な財産の処分は慎重に検討する必要があります。
他の債務整理手続きの検討
| 代替手続き | メリット・デメリット |
|---|---|
| 自己破産 | |
| 任意整理 |
|
| 特定調停 |
|
この表は最低弁済基準を満たせない場合に検討すべき他の債務整理手続きをまとめたものです。特に自己破産は最低弁済基準の制約がなく、債務を全額免除できる可能性がありますが、財産が処分されるなどのデメリットもあります。個人の状況に応じた最適な手続きを専門家と相談して選ぶことが重要です。
最低弁済基準と他の債務整理との比較
個人再生の最低弁済基準と他の債務整理手続きを比較することで、どの手続きが自分に適しているか判断する材料になります。
債務整理手続き別の返済基準比較
| 債務整理の種類 | 返済基準 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 個人再生 |
|
|
| 自己破産 |
|
|
| 任意整理 |
|
|
この表は各債務整理手続きの返済基準と向いている人の特徴をまとめたものです。個人再生は最低弁済基準という制約がありますが、財産を維持しながら債務を大幅に減額できるというメリットがあります。どの手続きが最適かは、債務額や財産状況、収入などを総合的に判断する必要があります。
財産状況別の最適な債務整理
債務者の財産状況によって、最適な債務整理手続きは異なります。
- 財産が少なく、清算価値が低い場合:個人再生が有利(債務総額の1/5で返済可能)
- 財産が多く、清算価値が高い場合:自己破産を検討(高額な財産は失うが債務は全額免除)
- 住宅がある場合:住宅資金特別条項付き個人再生を検討(住宅を維持しながら債務整理)
- 退職金請求権が主な財産の場合:退職金の按分計算を考慮した個人再生を検討
- 収入が少なく返済能力に乏しい場合:自己破産を検討
上記のリストは財産状況別の最適な債務整理手続きをまとめたものです。特に清算価値が高い場合は、個人再生では高額な返済が必要になるため、自己破産の方が有利になるケースもあります。専門家に相談して自分の状況に最適な手続きを選ぶことが重要です。
よくある質問
最低弁済基準が高すぎて返済できない場合はどうすればよいですか?
最低弁済基準が高額で返済が困難な場合、いくつかの対応策があります。まず、清算価値を押し上げている財産(不動産や高額な動産など)の処分を検討できます。また、親族からの援助を受けることも一つの方法です。
それでも対応が難しい場合は、個人再生ではなく自己破産などの他の債務整理手続きを検討する必要があるかもしれません。自己破産では財産は処分されますが、債務が全額免除される可能性があります。どのような選択が最適かは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
住宅ローンがある場合、最低弁済基準はどうなりますか?
住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンは再生手続きから除外され、従来通り返済を継続します。最低弁済基準(清算価値)の計算においては、住宅の価値から住宅ローン残高を差し引いた余剰価値がある場合、それが清算価値に含まれます。
例えば、住宅の価値が2,000万円で住宅ローン残高が1,800万円の場合、余剰価値は200万円となり、この金額が清算価値に含まれます。一方、住宅ローン残高が住宅の価値を上回る場合(担保割れ)は、清算価値への影響はありません。住宅以外の財産から算出される清算価値に基づいて最低弁済額が決まります。
再生計画の返済期間はどのくらいですか?
個人再生の返済期間は原則として3年間(36回の分割払い)です。ただし、最長5年間(60回の分割払い)まで延長することが可能です。返済期間を延ばすことで毎月の返済額を減らすことができますが、その分長期間にわたって返済を続ける必要があります。
返済期間は債務者の収入や最低弁済額などを考慮して設定されます。毎月の返済額が債務者の返済能力を超えないように適切な期間を設定することが重要です。なお、返済期間中に収入が増えても、原則として返済額が自動的に増額されることはありません。
まとめ
最低弁済基準(清算価値保障原則)は、個人再生や民事再生などの債務整理手続きにおいて、債務者が債権者に対して最低限支払うべき金額の基準です。債務者が自己破産した場合に債権者が受け取れるであろう配当額(清算価値)以上の返済を保障するという考え方に基づいています。
最低弁済基準は債務者の財産状況によって異なり、不動産や自動車、預貯金、有価証券などの財産価値から自由財産や担保権付債権などを差し引いて算出されます。個人再生では、この最低弁済基準と債務総額の1/5(最低100万円)のいずれか大きい方が実際の返済額の下限となります。
最低弁済基準が高額で返済が困難な場合は、財産の処分や他の債務整理手続きの検討が必要になることもあります。債務者の財産状況や収入状況に応じて最適な債務整理の方法を選ぶことが重要です。債務整理は専門的な知識が必要な手続きですので、弁護士や司法書士などの専門家に相談して進めることをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



