再生計画案(さいせいけいかくあん)について詳しく解説
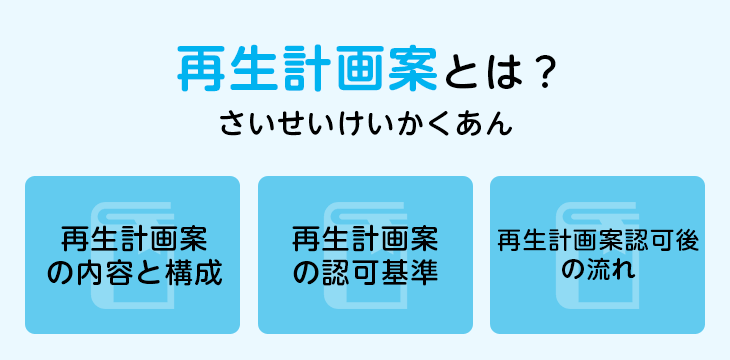
再生計画案とは、個人再生や民事再生といった債務整理手続きにおいて、債務者が作成する将来の返済計画を示した文書です。この計画案には、債務の減額や返済期間の延長など、債務者の経済状況に応じた返済条件が詳細に記載されます。
再生計画案は裁判所に提出され、債権者の意見を踏まえた上で裁判所の認可を受けることで法的拘束力を持ちます。認可された再生計画に従って返済を完了すれば、残りの債務は免除されるため、債務整理を成功させるための最も重要な書類の一つといえます。
再生計画案とは
再生計画案は、個人再生や民事再生の手続きにおいて、債務者が債権者に対してどのように返済を行っていくかを具体的に示した計画書です。債務者の収入や財産状況を考慮して、実現可能な返済計画を立てることが重要となります。
この計画案には、債務の減額(いわゆる「カット」)や返済期間、毎月の返済額などが具体的に記載され、裁判所と債権者の審査を受けます。再生計画案が裁判所に認可されると法的効力を持ち、債権者はこの計画に従った返済以外を債務者に求めることができなくなります。
| 法的根拠 | 民事再生法第154条(個人再生の場合は第229条) |
|---|---|
| 提出先 | 管轄裁判所 |
| 提出時期 | 再生手続開始決定から約1〜3ヶ月以内 |
| 作成者 | 債務者本人(代理人弁護士や司法書士が補助することが多い) |
この表は再生計画案の基本情報をまとめたものです。法的根拠は民事再生法に規定されており、再生手続開始決定から一定期間内に裁判所へ提出する必要があります。計画案の作成は専門知識が必要なため、弁護士や司法書士のサポートを受けることが一般的です。
再生計画案の内容と構成
再生計画案には、債務の返済に関する具体的な内容が盛り込まれます。主な構成要素は以下の通りです。
基本的な記載事項
- 債務者の基本情報(氏名、住所、職業など)
- 債権者一覧と債権額
- 債務の弁済方法と弁済額
- 弁済期間と分割回数
- 各債権者への返済予定額
- 住宅ローン特則を利用する場合はその旨
- 債務者の収入と支出の状況
上記のリストは再生計画案に記載される基本的な項目です。債務者や債権者の情報、具体的な返済計画など、債務整理に必要な情報を漏れなく記載することが重要です。
最低弁済額(清算価値)
再生計画案では、「最低弁済額」(清算価値)以上の返済を提案する必要があります。最低弁済額とは、もし債務者が自己破産した場合に債権者が受け取れるであろう配当額のことで、主に債務者の財産価値から算出されます。
| 最低弁済額の算定基礎 |
|
|---|
この表は最低弁済額の算定基礎となる財産の種類をまとめたものです。債務者の財産評価額から、自由財産(99万円以下の現金など)や差押禁止財産を除いた額が最低弁済額の基準となります。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生には主に「小規模個人再生」と「給与所得者等再生生」の2種類があり、それぞれ再生計画案の内容に違いがあります。
| 種類 | 対象者 | 債務額の上限 | 最低返済額 |
|---|---|---|---|
| 小規模個人再生 | 個人の債務者全般 | 5,000万円以下 | 清算価値以上 |
| 給与所得者等再生 | 安定した収入がある個人 | 5,000万円以下 | 可処分所得の2年分または清算価値のいずれか大きい額 |
この表は小規模個人再生と給与所得者等再生の主な違いをまとめたものです。給与所得者等再生は安定した収入がある人向けで、可処分所得に基づく返済が求められます。どちらの手続きが適しているかは、債務者の収入状況や財産状況によって異なります。
再生計画案の作成方法
再生計画案を作成するには、債務者の経済状況を正確に把握し、実現可能な返済計画を立てることが重要です。以下のステップに沿って計画案を作成します。
- 債務総額の確認(すべての債権者と債権額を確認)
- 財産の評価(不動産や自動車などの資産価値を算出)
- 最低弁済額(清算価値)の算定
- 月々の返済可能額の算出(収入から必要経費を差し引いた可処分所得を基に計算)
- 返済期間の設定(通常3〜5年)
- 具体的な返済計画の作成
- 再生計画案の作成と提出
上記のリストは再生計画案を作成するための一般的なステップです。適切な計画を立てるためには、債務者の財産状況や収入状況を正確に把握することが大前提となります。
返済可能額の算出方法
再生計画案で提案する返済額は、債務者が無理なく続けられる金額である必要があります。以下の手順で返済可能額を算出します。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①収入の確認 |
|
| ②生活必要費の算出 |
|
| ③可処分所得の計算 | 収入(①)- 生活必要費(②)= 可処分所得 |
| ④返済可能額の設定 | 可処分所得の範囲内で、長期間継続できる金額 |
この表は返済可能額を算出するためのステップをまとめたものです。収入から生活に必要な支出を差し引いた額が返済に充てられる可処分所得となります。無理のない返済計画を立てることが、再生計画の成功につながります。
専門家のサポートを受ける重要性
再生計画案の作成には法律や財務の専門知識が必要です。以下の理由から、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが強く推奨されます。
- 最低弁済額の正確な算定には専門知識が必要
- 法的要件を満たした計画案の作成が求められる
- 債権者からの異議に対する対応が必要
- 裁判所との交渉や手続きに関する知識が必要
- 実現可能で効果的な返済計画の策定には経験が重要
上記のリストは専門家のサポートを受ける重要性を示しています。再生計画案が裁判所に認可されるかどうかは債務整理の成否を左右する重要な要素であるため、専門家の知識と経験を活用することが成功への近道といえます。
再生計画案の認可基準
再生計画案が裁判所に認可されるためには、以下の基準を満たす必要があります。これらの基準を意識した計画案を作成することが重要です。
法律上の認可要件
- 再生手続きの法律要件を満たしていること
- 公正かつ衡平な内容であること(債権者間で不当な差別がないこと)
- 再生計画の遂行可能性が高いこと
- 誠実に手続きが行われていること
- 最低弁済額(清算価値)以上の返済が提案されていること
- 債権者の権利保護が図られていること
上記のリストは再生計画案が認可されるための法律上の要件です。特に重要なのは、計画の遂行可能性と最低弁済額以上の返済提案です。無理な返済計画は認可されない可能性が高いため、実現可能な計画を立てることが大切です。
債権者の同意と決議
再生計画案は債権者の決議にかけられ、一定の同意が得られると裁判所による認可審査に進みます。債権者の同意要件は以下の通りです。
| 債権者の決議 |
|
|---|---|
| 書面決議の場合 |
|
| 同意が得られない場合 | 裁判所が「cramdown(クラムダウン)」として認可可能 |
この表は債権者の同意要件についてまとめたものです。債権者の同意が得られない場合でも、裁判所が特別に認可する「cramdown」という制度があります。これは、最低弁済額以上の返済が提案されている場合などに適用される可能性があります。
再生計画案認可後の流れ
再生計画案が裁判所に認可されると、債務者はその計画に従って返済を行っていくことになります。認可後の主な流れは以下の通りです。
返済の開始と管理
- 再生計画認可決定の確定
- 返済の開始(通常は認可決定確定から1ヶ月以内)
- 定期的な返済の継続(毎月や3ヶ月ごとなど計画に基づく)
- 返済状況の記録と管理
- 計画に沿った完済
- 債務整理の完了
上記のリストは再生計画認可後の流れです。計画に沿って返済を完了すれば、残りの債務は免除され、債務整理が成功したことになります。返済は確実に行い、記録をきちんと残しておくことが重要です。
計画の変更や不履行の場合
再生計画の履行中に予期せぬ状況変化が生じた場合の対応策について説明します。
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 収入減少など返済困難な事態 |
|
| 一時的な返済困難 |
|
| 計画の不履行が続く場合 |
|
この表は再生計画の変更や不履行時の対応策をまとめたものです。やむを得ない事情で返済が困難になった場合には、早めに裁判所や代理人に相談することが重要です。放置すると再生手続きが廃止され、本来の債務額に戻ってしまう可能性があります。
よくある質問
再生計画案の返済期間はどのくらいですか?
一般的な返済期間は3年間(36回払い)から5年間(60回払い)程度です。債務額や返済能力によって適切な期間が設定されますが、あまりに長期間の計画は裁判所に認められにくい傾向があります。
返済期間が長すぎると計画の実現可能性が低くなるとみなされ、短すぎると毎月の返済額が高くなって返済困難になるリスクがあります。債務者の状況に合わせた適切な期間設定が重要です。
住宅ローンがある場合、再生計画案ではどのように扱われますか?
住宅ローンがある場合、「住宅資金特別条項」を利用することができます。この特則を適用すると、住宅ローンは再生手続きの対象から除外され、従来通りの返済を継続することができます。
ただし、住宅資金特別条項を利用するには、①住宅ローンの返済を継続する能力があること、②住宅の価値が住宅ローン残高を上回っていないこと(担保割れしていないこと)、などの条件があります。これにより、住宅を手放すことなく他の債務の整理ができるというメリットがあります。
再生計画案の返済中に収入が増えた場合、返済額は増えますか?
基本的には、認可された再生計画に基づく返済額が固定されるため、収入が増えても自動的に返済額が増えることはありません。再生計画は裁判所に認可された法的な返済計画であり、債務者と債権者の双方を拘束します。
ただし、債務者が自主的に返済額を増やしたり、繰り上げ返済をしたりすることは可能です。収入が大幅に増加した場合には、債権者への配慮として自主的に返済額を増やすことも検討するとよいでしょう。なお、再生計画の履行中に新たな借入を行うことは、裁判所の許可なく行うと再生手続きの廃止事由となる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
再生計画案は、個人再生や民事再生といった債務整理手続きにおいて、債務者が債権者に対してどのように返済を行っていくかを具体的に示した計画書です。債務の減額や返済期間、毎月の返済額などを具体的に定め、裁判所の認可を受けることで法的効力を持ちます。
適切な再生計画案を作成するためには、債務者の財産状況や収入状況を正確に把握し、最低弁済額(清算価値)以上の返済を提案することが重要です。また、無理のない返済計画とすることで、計画の遂行可能性を高めることが成功の鍵となります。
再生計画案の作成や手続きには専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが強く推奨されます。計画が認可され、それに従って返済を完了すれば、残りの債務は免除され、新たな経済生活をスタートすることができます。債務整理は経済的再生への第一歩であり、適切な再生計画案の作成がその成功を大きく左右するのです。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



