給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)について詳しく解説
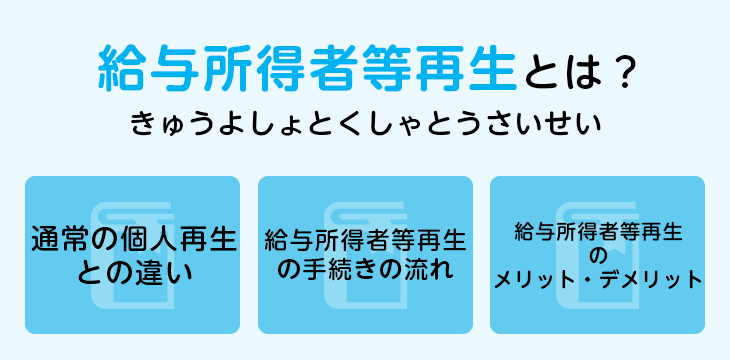
給与所得者等再生とは、定期的な収入のある個人が利用できる特則を使った個人再生手続きのことです。通常の個人再生よりも少ない返済額で債務の整理ができる特徴があります。給与所得者や年金受給者など、安定した定期収入がある方が対象となる債務整理の一種です。
給与所得者等再生は民事再生法第239条第1項に基づいており、最低弁済額の基準が緩和される特則が適用されます。通常の小規模個人再生と比較して債務者の負担が軽減されるため、安定収入はあるものの返済能力に限界がある方に適した手続きです。
給与所得者等再生の基本概念
給与所得者等再生は、安定した収入がある債務者を対象とした個人再生手続きの特則です。通常の個人再生(小規模個人再生)より返済負担が軽減されるため、返済能力はあるものの、通常の個人再生では返済額が重すぎる方に適しています。
この制度は、債務者の生活の立て直しを容易にし、同時に債権者にも一定の返済を保証することで、双方にとって有益な解決策を提供することを目的としています。2001年の民事再生法施行時に導入されました。
| 法的根拠 | 民事再生法第239条〜第245条 |
|---|---|
| 対象者 |
|
| 主な特徴 | 最低弁済額の基準が緩和される |
この表は給与所得者等再生の基本的な性質をまとめたものです。安定した収入がある方が対象で、債務の返済負担が軽減される特徴があります。
通常の個人再生との違い
給与所得者等再生と通常の個人再生(小規模個人再生)には、いくつかの重要な違いがあります。最も大きな違いは最低弁済額の基準で、給与所得者等再生の方が債務者にとって有利な条件となっています。
また、返済期間や手続きの流れにも違いがあり、給与所得者等再生では収入の変動に応じて返済計画が見直される可能性があるなどの特徴があります。
| 比較項目 | 給与所得者等再生 | 小規模個人再生 |
|---|---|---|
| 最低弁済額 | 可処分所得の2年分 | 債務総額の1/5または100万円のいずれか大きい額 |
| 返済期間 | 原則3年以内(最長5年) | 原則3年以内(最長5年) |
| 返済計画の修正 | 収入の変動に応じて修正可能 | 原則として修正不可 |
この表は給与所得者等再生と小規模個人再生の主な違いを示しています。特に最低弁済額の違いは重要で、債務総額が多い場合には給与所得者等再生の方が有利になることが多いです。
給与所得者等再生の申立要件
給与所得者等再生を申し立てるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件としては、安定した定期収入があることや、債務額が一定の範囲内であることなどが挙げられます。
- 給与所得者、年金受給者など定期的収入がある個人であること
- 将来において継続的に収入を得る見込みがあること
- 債務総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く無担保債務)
- 自己破産の免責不許可事由に該当しないこと
- 過去7年以内に免責許可または再生計画認可を受けていないこと
これらの要件を満たしていることが、給与所得者等再生を申し立てるための前提条件となります。特に安定した収入の見込みがあることが重要な要素です。
なお、個人事業主でも、安定した収入を得ている場合には給与所得者等再生を利用できる可能性があります。詳細については専門家に相談することをおすすめします。
給与所得者等再生の手続きの流れ
給与所得者等再生の手続きは、申立てから再生計画の遂行完了まで、いくつかのステップに分かれています。全体の流れを理解しておくことで、見通しを持って手続きに臨むことができます。
- 弁護士・司法書士への相談
- 必要書類の収集・準備
- 裁判所への申立て
- 再生手続開始決定
- 債権者への通知と債権届出
- 債権調査
- 再生計画案の作成・提出
- 再生計画案の決議
- 再生計画の認可決定
- 再生計画の遂行(原則3年以内)
上記は給与所得者等再生の一般的な手続きの流れです。実際の手続きは個々の状況により異なる場合がありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
特に再生計画案の作成は重要で、可処分所得の算定方法や最低弁済額の計算など、専門的な知識が必要となります。また、収入に変動があった場合には、計画の変更も可能です。
給与所得者等再生のメリット・デメリット
給与所得者等再生には様々なメリットとデメリットがあります。自己の状況に合った債務整理方法を選択するためには、これらを十分に理解しておくことが重要です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
この表は給与所得者等再生の主なメリットとデメリットをまとめたものです。個々の状況によってメリット・デメリットの重要度は異なりますので、専門家と相談した上で判断することをおすすめします。
よくある質問
給与所得者等再生中に収入が増えた場合、返済額は変わりますか?
給与所得者等再生では、手続き中に収入が大幅に増加した場合、債権者から再生計画の変更を求められる可能性があります。民事再生法第239条の6に基づき、収入の変動に応じた計画の変更が認められています。
ただし、通常の昇給程度の収入増加であれば、必ずしも返済額が変更されるわけではありません。具体的な変更の要否は、収入増加の程度や状況によって異なります。
個人事業主でも給与所得者等再生を利用できますか?
個人事業主でも、安定した収入が見込める場合には給与所得者等再生を利用できる可能性があります。例えば、継続的な契約に基づいて定期的な収入がある場合などが該当します。
ただし、収入の安定性や継続性が重要な判断要素となるため、事業の性質や収入状況によっては、通常の小規模個人再生が適用される場合もあります。専門家に相談して適切な方法を選択することをおすすめします。
給与所得者等再生で住宅ローンはどうなりますか?
給与所得者等再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを再生計画から除外し、従来通りの返済を続けることができます。これにより、住宅を手放すことなく債務整理が可能です。
ただし、住宅ローンの返済に延滞がないことや、住宅の価値が残債よりも高いことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。また、住宅ローン以外の債務についても返済能力があることが前提となります。
まとめ
給与所得者等再生は、安定した収入がある個人を対象とした債務整理手続きの一つです。通常の個人再生(小規模個人再生)と比較して、最低弁済額の基準が緩和されており、より少ない返済額で債務の整理ができる特徴があります。
この手続きの最大のメリットは、「可処分所得の2年分」という基準が適用されることで、特に債務総額が多い場合に返済負担が大幅に軽減される点にあります。また、住宅資金特別条項を利用することで住宅を手放さずに債務整理することも可能です。
申立てには、給与所得者や年金受給者などの安定した収入がある個人であること、債務総額が5,000万円以下であることなどの要件があります。手続きの流れは複雑で専門的知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
給与所得者等再生は、自己破産よりも社会的制約が少なく、任意整理よりも大幅な債務減額が可能という特徴があります。安定した収入はあるものの返済が困難な状況に陥っている方にとって、生活再建の有効な手段となるでしょう。債務問題でお悩みの方は、自分の状況に合った最適な債務整理方法を専門家と相談して選択されることをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



