期限の利益喪失条項(きげんのりえきそうしつじょうこう)について詳しく解説
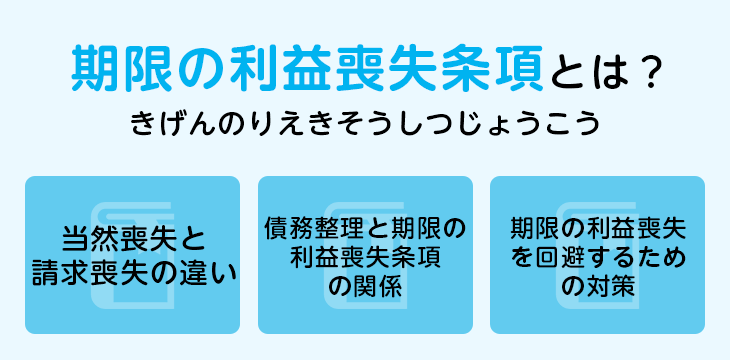
期限の利益喪失条項とは、ローンやクレジットカードなどの契約書に記載されている条項で、どのような場合に期限の利益(分割で返済できる権利)を失うかを定めたものです。
一般的には、支払いの遅延や破産申立てなど、特定の事由が発生した場合に、残りの債務を一括で支払わなければならなくなることを規定しています。債務整理を検討する際は、この条項の内容を理解しておくことが重要です。
■もくじ
期限の利益喪失条項とは
期限の利益喪失条項とは、ローン契約やクレジットカード契約などに記載されている条項で、債務者が分割払いの権利(期限の利益)を失う条件を定めたものです。
通常、ローンやクレジットカードの利用者は、契約で定められた返済期限まで支払いを猶予されるという「期限の利益」を有しています。しかし、特定の事由が発生した場合、この利益は失われ、残りの債務を一括で支払わなければならなくなります。
| 期限の利益喪失条項の目的 |
|
|---|---|
| 期限の利益喪失条項の記載場所 |
|
この表は期限の利益喪失条項の目的と一般的な記載場所を示しています。この条項は債権者が債権回収を確実にするために設けられていますが、条件は契約書や規約によって異なる場合があります。
期限の利益喪失条項に含まれる主な事由
期限の利益喪失条項には、様々な喪失事由が規定されています。主な事由は以下の通りです。
- 支払いの遅延(一般的に2回以上の延滞)
- 契約違反や虚偽申告
- 破産・民事再生などの法的整理の申立て
- 差押え・仮差押え・仮処分を受けた場合
- 他の債務の不履行(クロスデフォルト)
- 保証人の信用不安
- 死亡または行方不明
- 担保価値の著しい減少
最も一般的な喪失事由は支払いの遅延です。多くの契約では、2回以上の延滞で期限の利益を喪失すると規定されていますが、契約によっては1回の延滞でも喪失する厳しい条件となっている場合もあります。
また、「クロスデフォルト条項」と呼ばれる規定により、他の債務の不履行が期限の利益喪失事由となることもあります。例えば、あるカードローンの返済を延滞すると、同じ金融機関の住宅ローンなども期限の利益を喪失する可能性があります。
当然喪失と請求喪失の違い
期限の利益喪失条項には、「当然喪失」と「請求喪失」の2種類があります。この違いは、期限の利益が喪失するタイミングと債権者の意思によるものです。
| 区分 | 定義 | 主な事由 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 当然喪失 | 事由発生と同時に自動的に期限の利益を喪失 |
|
債権者の意思表示不要 |
| 請求喪失 | 事由発生後、債権者の請求により期限の利益を喪失 |
|
債権者の判断で猶予の可能性あり |
この表は「当然喪失」と「請求喪失」の違いを示しています。当然喪失は事由発生と同時に自動的に期限の利益が失われますが、請求喪失は債権者の請求があって初めて喪失します。
「請求喪失」の場合、債権者は喪失事由が発生しても期限の利益を喪失させない判断をすることができます。そのため、返済が困難になった場合でも、早めに債権者に相談することで、期限の利益を守れる可能性があります。
期限の利益喪失条項の効力と法的根拠
期限の利益喪失条項は、契約自由の原則に基づいて有効とされています。その法的根拠は民法に求められます。
民法第137条では「期限の利益の喪失」について規定しており、債務者が破産手続開始の決定を受けたときや、担保を滅失させたときなどに期限の利益を主張できなくなるとしています。契約書の期限の利益喪失条項は、この民法の規定を拡張したものといえます。
| 民法第137条(期限の利益の喪失) | 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき 2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき 3 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき |
|---|---|
| 消費者契約法との関係 | 期限の利益喪失条項が消費者にとって不当に不利益な場合、消費者契約法に基づき無効となる可能性もある |
この表は期限の利益喪失条項の法的根拠となる民法の規定と、消費者契約法との関係を示しています。契約の自由は認められていますが、消費者保護の観点から一定の制限が設けられています。
なお、契約書に記載された期限の利益喪失条項が著しく不当な場合は、消費者契約法に基づき無効となる可能性もあります。例えば、わずかな遅延でも直ちに期限の利益を喪失するような条項は、裁判で無効と判断されることがあります。
債務整理と期限の利益喪失条項の関係
債務整理を検討する場合、期限の利益喪失条項との関係を理解しておくことが重要です。債務整理の各手続きと期限の利益喪失条項の関係は以下の通りです。
-
任意整理
- 債権者への受任通知送付により期限の利益喪失となる場合がある
- 交渉がまとまれば新たな返済条件で期限の利益が認められる
- 個人再生
- 申立て自体が期限の利益喪失事由となることが多い
- 再生計画認可後は計画に沿った返済が可能になる
- 自己破産
- 申立て自体が期限の利益喪失事由となる(当然喪失)
- 免責により債務そのものがなくなる
この一覧は債務整理の各手続きと期限の利益喪失条項との関係を示しています。債務整理の方法によって期限の利益への影響が異なるため、適切な手続きを選択することが重要です。
なお、任意整理では、弁護士や司法書士が債権者に送付する受任通知に「支払い停止の抗弁」を記載すると、それが期限の利益喪失事由となることがあります。ただし、これは債務整理の交渉を進めるための一般的な手続きであり、最終的には和解により新たな返済条件が設定されます。
期限の利益喪失を回避するための対策
期限の利益を喪失すると、残債務の一括返済や信用情報への悪影響など、様々な不利益が生じます。以下に、期限の利益喪失を回避するための対策を紹介します。
- 契約書の期限の利益喪失条項をよく読み、条件を理解する
- 返済日前に必ず口座残高を確認する
- 返済困難が予想される場合は事前に債権者に相談する
- リスケジュール(返済計画の見直し)を交渉する
- 一時的な支払猶予を申し出る
- 複数の債務がある場合は、優先順位をつけて対応する
- 早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談する
返済が困難になった場合、多くの人は債権者との接触を避けがちですが、それは最善の選択ではありません。むしろ積極的に債権者と連絡を取り、状況を説明して交渉することが重要です。
特に「請求喪失」の場合は、債権者の判断で期限の利益を維持できる可能性があります。多くの金融機関では、誠意をもって相談に来た顧客に対しては、一定の条件下でリスケジュールや支払猶予などの対応を行っています。
よくある質問
期限の利益喪失通知が来た場合、どう対応すべきですか?
期限の利益喪失通知を受け取った場合は、まず内容を確認し、早急に対応することが重要です。通知に記載された連絡先に連絡して状況を説明し、対応策を相談してください。
すでに返済が困難な状況であれば、債務整理を含めた対応を検討する必要があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な解決策を見つけることをおすすめします。
1回の支払い遅れで期限の利益を喪失することはありますか?
契約内容によって異なります。多くのローンやクレジットカード契約では、2回以上の延滞で期限の利益を喪失すると規定されていますが、契約によっては1回の延滞でも喪失する条件となっている場合もあります。
また、延滞の状況や金額、過去の取引履歴によっても対応が異なることがあります。1回の延滞でも、金額が大きい場合や過去に延滞を繰り返している場合は、期限の利益を喪失するリスクが高まります。
期限の利益を喪失した後、復活させることはできますか?
場合によっては可能です。これは「期限の利益の回復」と呼ばれています。延滞分の支払いや債権者との交渉によって、期限の利益を復活させられることがあります。
ただし、期限の利益の回復は債権者の判断によるものであり、必ず認められるわけではありません。特に延滞が長期間続いている場合や、過去に何度も延滞を繰り返している場合は、回復が認められにくくなります。早めに債権者に相談することが重要です。
まとめ
期限の利益喪失条項とは、ローンやクレジットカードなどの契約書に記載されている条項で、どのような場合に期限の利益(分割で返済できる権利)を失うかを定めたものです。
主な喪失事由には、支払いの遅延、契約違反、破産申立て、差押えなどがあります。また、期限の利益喪失には「当然喪失」と「請求喪失」の2種類があり、前者は事由発生と同時に自動的に期限の利益が失われ、後者は債権者の請求があって初めて喪失します。
期限の利益を喪失すると、残債務の一括返済義務や信用情報への悪影響など、様々な不利益が生じます。そのため、契約書の内容をよく理解し、返済日前の口座残高確認や、返済困難時の事前相談など、期限の利益喪失を回避するための対策を講じることが重要です。
債務整理を検討する場合も、期限の利益喪失条項との関係を理解しておく必要があります。債務整理の種類によって期限の利益への影響が異なるため、自分の状況に合った手続きを選択することが大切です。
返済が困難になった場合は、一人で抱え込まず、早めに債権者や専門家(弁護士・司法書士)に相談することをおすすめします。誠意をもって対応することで、期限の利益を維持できる可能性が高まります。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



