管財事件(かんざいじけん)について詳しく解説
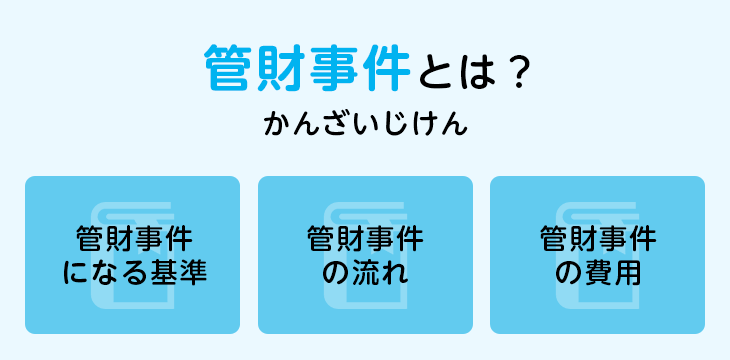
管財事件とは、自己破産の申立てを行った際に、裁判所によって破産管財人が選任され、債務者の財産を調査・換価し、債権者に公平に配当する手続きのことを指します。
債務者に一定以上の財産がある場合や、否認権の行使、免責不許可事由の調査が必要な場合などに管財事件として取り扱われます。
管財事件とは
管財事件とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を調査・換価し、債権者に公平に配当するための手続きです。自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があり、債務者の財産状況や事案の複雑さなどによって、どちらの手続きになるかが決まります。
管財事件では、弁護士などが破産管財人に選任され、債務者の財産の調査・管理・換価、債権者への配当、免責不許可事由の調査などを行います。債務者には管財人に対する協力義務があり、管財人の調査に誠実に応じる必要があります。
| 管財事件の目的 |
|
|---|---|
| 破産管財人の役割 |
|
上記の表は管財事件の目的と破産管財人の主な役割をまとめたものです。管財事件は、債務者の財産を公平に分配するとともに、債務者が免責を受けるにふさわしいかどうかを調査するための重要な手続きです。
管財事件と同時廃止事件の違い
自己破産手続きには「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。債務者にはどちらの手続きが適用されるのか、その違いを理解しておくことが重要です。
| 管財事件 |
|
|---|---|
| 同時廃止事件 |
|
上記の表は管財事件と同時廃止事件の主な違いをまとめたものです。債務者の財産状況や事案の複雑さによって、どちらの手続きになるかが決まります。
同時廃止事件は、債務者に配当すべき財産がほとんどなく、事案が比較的単純な場合に適用されます。一方、管財事件は、債務者に一定以上の財産がある場合や、否認権の行使、免責不許可事由の調査が必要な場合などに適用されます。
管財事件になる基準
自己破産の申立てを行った場合、どのような基準で管財事件となるのかを理解しておくことは重要です。以下に主な基準をまとめました。
- 債務者に20万円を超える財産がある場合
- 債務者が経営者(個人事業主や会社役員)である場合
- 債務総額が高額(数千万円以上)の場合
- 浪費や賭博など免責不許可事由の疑いがある場合
- 破産前の財産隠し、偏頗弁済(特定の債権者だけに返済)の疑いがある場合
- 否認権の行使(詐害行為の取消しなど)が必要な場合
- 過去に破産歴がある場合
- 債権者から異議が出ている場合
上記のリストは管財事件となる主な基準をまとめたものです。ただし、これらはあくまで一般的な基準であり、最終的には裁判所の判断によって決定されます。
なお、裁判所によって管財事件となる基準には若干の違いがあります。例えば、東京地方裁判所では債務者の財産が20万円超の場合に管財事件となる傾向がありますが、他の裁判所では基準額が異なる場合もあります。
管財事件の流れ
管財事件の一般的な流れは以下の通りです。手続きの期間は、事案の複雑さにもよりますが、通常は破産手続開始決定から約6か月〜1年程度かかります。
- 自己破産の申立て
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 債権者集会の期日の指定
- 破産管財人による財産調査・換価(財産の現金化)
- 債権調査(債権者からの届出債権の確認)
- 第1回債権者集会(破産管財人の調査報告など)
- 免責審尋(裁判官による債務者への質問)
- 第2回債権者集会(配当の実施)
- 破産手続終結決定
- 免責許可決定
上記のリストは管財事件の一般的な流れを示しています。事案によっては債権者集会が3回以上行われることもあります。
管財事件では、破産管財人が債務者の財産を調査・換価し、債権者への配当を行います。また、債務者の免責不許可事由の有無についても調査を行います。債務者には管財人に対する協力義務があり、財産状況の説明や必要書類の提出などが求められます。
管財事件の費用
管財事件には、同時廃止事件よりも高額な費用がかかります。主な費用内訳は以下の通りです。
| 予納金(管財人報酬等) | 約20〜50万円(裁判所に予め納付する費用) |
|---|---|
| 弁護士費用 | 着手金:約20〜30万円 報酬金:約10〜20万円 |
| その他の費用 | 印紙代:約1万5千円 郵便切手代:約5千円 予納郵便切手代:約5千円 |
| 合計 | 約50〜100万円程度 |
上記の表は管財事件にかかる主な費用の内訳と相場をまとめたものです。実際の費用は、依頼する弁護士事務所や地域、事案の複雑さによって異なります。
管財事件の費用が高額になる主な理由は、破産管財人の報酬(予納金)です。破産管財人は、債務者の財産調査や換価、債権者への配当など、多くの業務を行うため、その報酬として予納金が必要となります。
なお、管財事件の費用を支払う資力がない場合でも、分割払いや法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があります。費用面で不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
管財事件における債務者の義務
管財事件において、債務者には以下のような義務が課せられます。これらの義務に違反すると、免責不許可事由となる可能性があるため、誠実に対応することが重要です。
| 管財人に対する協力義務 |
|
|---|---|
| 裁判所に対する義務 |
|
| その他の義務 |
|
上記の表は管財事件における債務者の主な義務をまとめたものです。これらの義務に違反すると、免責不許可事由となる可能性があります。
特に重要なのは、破産管財人に対する協力義務です。破産管財人からの質問には誠実に回答し、必要な書類を提出するなど、積極的に協力することが求められます。また、裁判所から呼出しがあった場合には必ず出頭し、住所変更などがあった場合には速やかに届け出る必要があります。
よくある質問
管財事件になると免責が認められにくくなりますか?
管財事件になること自体が免責を認められにくくする要因ではありません。むしろ、破産管財人による調査を通じて、債務者が誠実に手続きに協力していることが確認されれば、免責の判断にプラスに働くこともあります。
免責が認められるかどうかは、免責不許可事由(浪費や賭博による債務、詐欺的な借入など)の有無によって判断されます。管財事件では、破産管財人がこれらの事由について詳細に調査しますが、そのような事由がなければ、通常は免責が認められます。
管財事件の費用を分割で支払うことはできますか?
破産手続開始決定前に裁判所に納付する予納金は、原則として一括払いとなりますが、弁護士費用については分割払いに応じている弁護士事務所も多くあります。また、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を分割払いにすることが可能です。
ただし、予納金については裁判所に納付する費用であり、分割払いには原則として対応していません。費用面で不安がある場合は、弁護士に相談し、法テラスの利用可能性なども含めて具体的な支払い方法を検討することをおすすめします。
管財事件では財産をすべて失うのですか?
管財事件では、債務者の財産は原則として破産財団に組み込まれ、破産管財人によって換価・処分されますが、すべての財産を失うわけではありません。法律で定められた「自由財産」と呼ばれる範囲内の財産は手元に残すことができます。
自由財産には、99万円以下の現金、差押禁止財産(生活に必要な家財道具、2ヶ月分の生活費に相当する額の給与など)が含まれます。また、裁判所の自由財産拡張の決定により、一定の財産を手元に残せる場合もあります。財産の取扱いについては、事前に弁護士によく相談することをおすすめします。
まとめ
管財事件は、自己破産の申立てを行った際に、裁判所によって選任された破産管財人が債務者の財産を換価・処分し、債権者に公平に配当する手続きです。債務者に一定以上の財産がある場合や、否認権の行使、免責不許可事由の調査が必要な場合などに管財事件として取り扱われます。
管財事件と同時廃止事件の大きな違いは、破産管財人が選任されるか否か、費用の金額、手続き期間の長さなどです。管財事件では破産管財人が選任され、費用が高額(約50〜100万円程度)で、手続き期間も長い(約6か月〜1年程度)という特徴があります。
管財事件となる主な基準は、債務者に20万円を超える財産がある場合、債務者が経営者である場合、債務総額が高額の場合、免責不許可事由の疑いがある場合などです。ただし、最終的には裁判所の判断によって決定されます。
管財事件の一般的な流れは、自己破産の申立て、破産手続開始決定・破産管財人の選任、債権者集会、破産管財人による財産調査・換価、債権調査、配当の実施、破産手続終結決定、免責許可決定などがあります。
管財事件において、債務者には破産管財人に対する協力義務があり、財産状況の説明や必要書類の提出などが求められます。これらの義務に違反すると、免責不許可事由となる可能性があるため、誠実に対応することが重要です。
管財事件の費用は高額ですが、弁護士費用については分割払いに応じている事務所も多くあります。また、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合もあります。費用面で不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



