簡易裁判所(かんいさいばんしょ)について詳しく解説
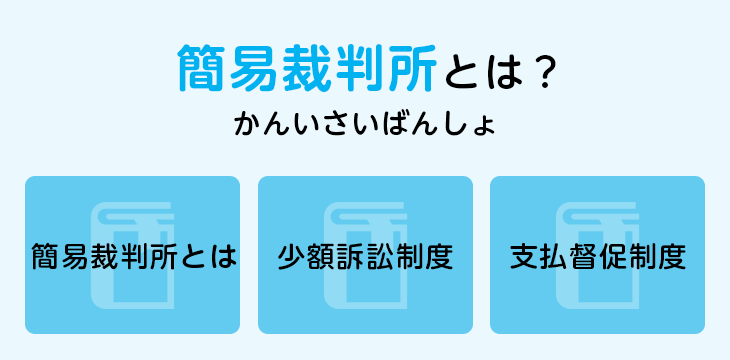
簡易裁判所とは、民事・刑事の比較的軽微な事件を取り扱う裁判所です。通常の地方裁判所よりも手続きが簡素化されており、費用も安く、専門的な法律知識がなくても自分で手続きを行いやすいのが特徴です。債務整理や過払い金請求の場合、訴額が140万円以下の事件は簡易裁判所で取り扱われます。
簡易裁判所とは
簡易裁判所は、日本の司法制度において最も身近な裁判所として位置づけられています。全国に438か所設置されており、比較的軽微な事件を迅速かつ簡易な手続きで解決することを目的としています。
簡易裁判所では、民事事件、刑事事件のほか、調停事件も取り扱います。裁判官のほか、民事調停委員や司法委員などが配置され、法律の専門家でない当事者でも利用しやすいように配慮されています。
| 設置数 | 全国438か所(2023年現在) |
|---|---|
| 主な取扱事件 |
|
上記の表は簡易裁判所の概要をまとめたものです。地方裁判所に比べて全国に多く設置されているため、アクセスが良く、市民にとって利用しやすい裁判所となっています。
簡易裁判所の管轄
簡易裁判所が取り扱う事件の範囲(管轄)は、民事事件と刑事事件で異なります。特に債務整理や過払い金請求に関連する民事事件の管轄は以下の通りです。
| 民事訴訟事件 | 訴額が140万円以下の事件 |
|---|---|
| 少額訴訟事件 | 訴額が60万円以下の金銭の支払いを求める事件 |
| 民事調停事件 | 金銭の支払い、不動産の明渡し等に関する紛争 |
| 支払督促事件 | 金銭の支払いを求める事件(訴額の制限なし) |
上記の表は簡易裁判所が取り扱う主な民事事件の種類と範囲をまとめたものです。債務整理や過払い金請求の多くは、訴額が140万円以下であるため、簡易裁判所での手続きとなります。
なお、民事事件の場合、原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを提起します。過払い金請求の場合は、貸金業者の本店または支店所在地を管轄する簡易裁判所に訴えを提起することも可能です。
債務整理における簡易裁判所の役割
債務整理や過払い金請求において、簡易裁判所は重要な役割を果たしています。主な関わり方は以下の通りです。
- 過払い金請求訴訟(訴額140万円以下の場合)
- 少額訴訟による過払い金請求(訴額60万円以下の場合)
- 債権者からの支払督促への対応(異議申立て)
- 特定調停による債務整理
- 個人再生手続きにおける再生計画案の認可
上記のリストは債務整理に関連する簡易裁判所の主な役割です。特に過払い金請求は、訴額が140万円以下であれば簡易裁判所で取り扱われることが一般的です。
また、特定調停は、債務者が債権者との話し合いによって返済計画を立て直す手続きで、簡易裁判所で行われます。個人再生手続きは地方裁判所の管轄ですが、再生計画認可後の返済は簡易裁判所を通じて行われることがあります。
簡易裁判所での訴訟手続きの流れ
簡易裁判所での訴訟手続きは、地方裁判所よりも簡易な手続きで進行します。過払い金請求訴訟を例にとった一般的な流れは以下の通りです。
- 訴状の提出(必要書類と印紙を添えて簡易裁判所に提出)
- 訴状の審査と相手方への送達
- 答弁書の提出(相手方が裁判所に提出)
- 口頭弁論期日の指定と当事者への通知
- 口頭弁論(当事者が裁判所に出頭して主張を行う)
- 証拠調べ(必要に応じて実施)
- 和解協議(多くの場合、裁判所が和解を勧める)
- 判決または和解
- 判決確定後の強制執行(必要に応じて)
上記のリストは簡易裁判所での訴訟手続きの一般的な流れを示しています。過払い金請求訴訟の場合、多くは和解によって解決されることが多いです。
簡易裁判所での訴訟は比較的迅速に進行し、通常は数ヶ月程度で解決することが多いです。また、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で手続きを行うこともできますが、専門的な知識があった方が有利に進めることができます。
少額訴訟制度
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を終え、迅速に紛争を解決するための特別な訴訟手続きです。過払い金請求でも、訴額が60万円以下であれば利用可能です。
| 対象となる訴え | 60万円以下の金銭の支払いを求める訴え |
|---|---|
| 審理の特徴 | 原則として1回の期日で審理を終える |
| 証拠の制限 | 即時に取り調べることができる証拠に限定 |
| 判決 | 原則として口頭弁論終結後直ちに言い渡される |
| 控訴の制限 | 控訴はできず、異議の申立てのみ可能 |
| 利用制限 | 同一の当事者は1年間に10回まで |
上記の表は少額訴訟の主な特徴をまとめたものです。通常の訴訟よりも迅速に解決できる反面、証拠や控訴に制限があることに注意が必要です。
少額訴訟は、訴状を提出する際に「少額訴訟による審理及び裁判を求める」旨を記載することで選択できます。ただし、被告が異議を述べた場合は通常訴訟に移行します。また、裁判所が少額訴訟に適さないと判断した場合も通常訴訟に移行することがあります。
支払督促制度
支払督促は、債権者が裁判所に申し立てることで、債務者に対して支払いを命じる制度です。訴訟より簡易な手続きで債権回収を行うことができます。債務整理との関連では、債権者が債務者に対して支払督促を申し立てるケースがあります。
| 制度の概要 | 債権者の申立てにより、裁判所が債務者に支払いを命じる手続き |
|---|---|
| 特徴 | 債務者の審尋(意見聴取)なしに発せられる |
| 債務者の対応 | 異議申立て(2週間以内)をしないと、確定判決と同じ効力を持つ |
| 異議申立て後 | 通常訴訟に移行する |
上記の表は支払督促制度の概要をまとめたものです。債務者が支払督促を受け取った場合、異議申立ての期間(2週間)を過ぎると仮執行宣言が付され、差押えなどの強制執行が可能になるため注意が必要です。
債務整理を検討している方が支払督促を受け取った場合は、期間内に必ず異議申立てを行うことが重要です。異議申立てをすると通常訴訟に移行するため、その間に債務整理の手続きを進めることができます。
よくある質問
簡易裁判所での過払い金請求にかかる費用はいくらですか?
簡易裁判所での過払い金請求にかかる主な費用は、訴額に応じた収入印紙代と郵便切手代です。例えば、訴額が100万円の場合、収入印紙代は約1万円程度です。
弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。一般的に着手金と成功報酬の形態をとり、着手金は0〜5万円程度、成功報酬は回収額の20%〜25%程度が相場です。ただし、事務所によって料金体系は異なります。
簡易裁判所での訴訟は自分でもできますか?
はい、簡易裁判所での訴訟は法律の専門家でなくても自分で行うことができます。簡易裁判所には、手続きを案内する窓口があり、必要書類の書き方などについてアドバイスを受けることも可能です。
ただし、過払い金請求のような専門的な計算が必要な事案や、複雑な法律問題が絡む場合は、弁護士や司法書士に依頼した方が有利に進められることが多いです。また、司法書士は140万円以下の事件であれば訴訟代理人となることができます。
簡易裁判所での和解と判決の違いは何ですか?
和解は当事者間の合意に基づいて紛争を解決するもので、裁判所が仲介役となります。当事者双方が納得できる条件で合意できれば、裁判所の和解調書に記載され、確定判決と同じ効力を持ちます。
一方、判決は裁判所が法律に基づいて下す判断で、当事者の意向に関わらず裁判所の判断が示されます。和解の場合は控訴できませんが、判決の場合は不服があれば地方裁判所に控訴することができます。過払い金請求訴訟では、和解で解決することが多いです。
まとめ
簡易裁判所は、訴額140万円以下の民事事件や軽微な刑事事件を取り扱う、市民にとって最も身近な裁判所です。全国に438か所設置されており、手続きが簡素化され、費用も比較的安いのが特徴です。
債務整理や過払い金請求において、簡易裁判所は重要な役割を果たしています。過払い金請求訴訟(訴額140万円以下)、少額訴訟(訴額60万円以下)、特定調停による債務整理などが簡易裁判所で行われます。
簡易裁判所での訴訟手続きは、訴状の提出から始まり、口頭弁論、和解協議などを経て、判決または和解で終結します。過払い金請求訴訟の場合、多くは和解によって解決されることが一般的です。
また、少額訴訟制度は60万円以下の金銭請求について、1回の期日で審理を終える迅速な手続きです。支払督促制度は、債権者の申立てにより裁判所が債務者に支払いを命じる簡易な手続きですが、債務者は異議申立てによって通常訴訟に移行させることができます。
簡易裁判所での手続きは比較的簡素化されており、自分で行うことも可能ですが、過払い金請求のような専門的な計算が必要な事案では、弁護士や司法書士のサポートを受けることで、より確実に権利を守ることができます。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



