復権(ふっけん)について詳しく解説
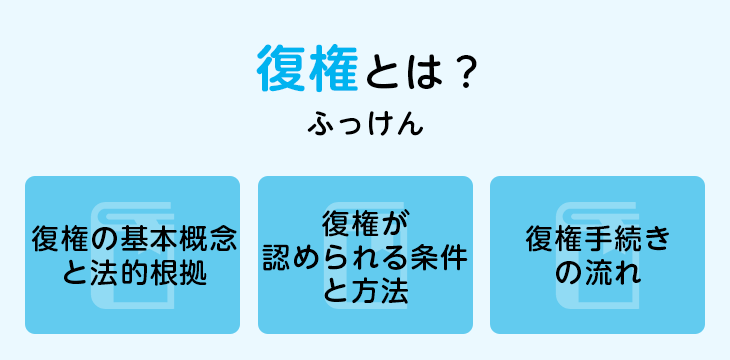
復権とは、自己破産後に制限されていた資格や権利が回復することです。自己破産をすると、破産者には一定の資格制限や就業制限などが課されますが、これらの制限が解除されて権利が回復することを「復権」と呼びます。
破産手続が終了しても、免責許可決定を受けただけでは資格制限などは自動的には解除されません。復権によってはじめて破産者の資格制限が解除され、破産前と同様の権利を行使できるようになります。債務整理の中でも自己破産を選択した方にとって、復権は社会復帰の重要なステップとなります。
復権の基本概念と法的根拠
復権とは、破産手続によって制限されていた破産者の資格や権利が回復することです。破産法第255条から第257条にかけて規定されており、破産者が社会的・経済的に再出発するための重要な制度となっています。
復権の法的根拠
復権制度は破産法に明確に規定されています。主な条文は以下の通りです。
| 破産法第255条 | 復権の効力について規定しています。復権によって破産者であることによる資格制限等が効力を失うことが明記されています。 |
|---|---|
| 破産法第256条 | 当然復権の事由について規定しています。一定の条件を満たすと自動的に復権することが明記されています。 |
| 破産法第257条 | 裁判所による復権の許可について規定しています。裁判所に申立てを行い、復権が許可される条件が明記されています。 |
上記の法的根拠に基づき、復権制度は運用されています。破産者にとって、この制度を理解することは生活再建の第一歩となります。
免責と復権の違い
自己破産において「免責」と「復権」は異なる概念です。両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。
| 免責 |
|
|---|---|
| 復権 |
|
上記のように、免責は「債務からの解放」、復権は「資格制限からの解放」という違いがあります。自己破産後の完全な社会復帰のためには、両方が必要となります。
復権するまでの制限される権利・資格
自己破産すると、復権するまでの間、いくつかの権利や資格が制限されます。これらの制限は法律や業界規則によって定められています。主な制限は以下の通りです。
法律で定められた資格制限
| 公職関係 |
|
|---|---|
| 金融・商事関係 |
|
上記は法律で明確に定められた資格制限の一部です。これらの職業に就くためには、復権することが必要です。
業界団体や企業による制限
法律での制限のほかに、業界団体の規則や企業の採用基準によって、事実上の制限が設けられているケースもあります。
- 金融機関への就職(銀行、信用金庫など)
- 生命保険・損害保険会社への就職
- 公務員への採用
- 一部の民間企業への採用
- クレジットカードの新規作成
- 住宅ローンなどの借入れ
上記の制限は法律で明確に定められたものではありませんが、破産者であることを理由に事実上の制限を受けることがあります。これらの制限も復権によって解消される可能性があります。
ただし、企業の採用基準や金融機関の審査基準は各機関の方針によるため、復権しても一定期間は制限が続く場合があります。特に信用情報機関に破産の事実が登録されている期間(通常5~10年)は、影響が残ることがあります。
復権が認められる条件と方法
復権には「当然復権」と「裁判所の許可による復権」の2種類があります。それぞれの条件と方法について見ていきましょう。
当然復権(自動的に復権する場合)
破産法第256条によれば、以下の条件を満たすと自動的に復権します。裁判所への申立てなどの手続きは不要です。
| 免責許可決定の確定 | 裁判所から免責許可決定を受け、それが確定すると自動的に復権します。通常、自己破産手続きで免責を受ける場合はこのケースが多いです。 |
|---|---|
| 破産手続きの廃止 | 破産財団が管財費用を支払うのに不足する場合などに、破産手続きが廃止されることがあります。この場合も自動的に復権します。 |
| 破産手続きの終結 | すべての破産財団が換価・配当されて破産手続きが終結した場合も、自動的に復権します。 |
| 破産債権者全員の同意 | すべての破産債権者が復権に同意した場合も、自動的に復権します。ただし、実務上は非常にまれなケースです。 |
上記のうち、最も一般的なのは「免責許可決定の確定」による当然復権です。多くの自己破産者は、免責許可決定を受けることで自動的に復権することになります。
裁判所の許可による復権
当然復権の条件を満たさない場合でも、破産法第257条に基づき、裁判所に復権の許可を申し立てることができます。主な条件は以下の通りです。
- 破産手続開始の決定から10年経過:破産手続開始から10年が経過していれば、裁判所に復権の許可を申し立てることができます
- 誠実な生活態度:申立人が誠実な生活態度を示していることが必要です
- 債権者保護への配慮:過去の債権者の利益を不当に害さないことが求められます
上記の条件を満たしていれば、免責を受けていない場合や免責不許可となった場合でも、復権が認められる可能性があります。ただし、裁判所の審査があり、必ずしも認められるとは限りません。
復権手続きの流れ
復権手続きは、当然復権の場合と裁判所の許可による復権の場合で異なります。それぞれの流れを見ていきましょう。
当然復権の場合
当然復権は法律の規定により自動的に効力が生じるため、特別な手続きは不要です。一般的な流れは以下の通りです。
| 免責許可決定 | 破産手続開始から約4~6ヶ月後に、裁判所から免責許可決定が出ます。 |
|---|---|
| 確定 | 免責許可決定から2週間以内に債権者から即時抗告がなければ、決定が確定します。 |
| 復権の効力発生 | 免責許可決定の確定と同時に、自動的に復権が効力を生じます。 |
| 復権証明書の取得(必要な場合) | 就職や資格取得の際に必要であれば、裁判所から復権証明書を取得できます。 |
上記のように、当然復権の場合は免責許可決定の確定を待つだけで復権の効力が生じます。特別な申請や手続きは必要ありません。
裁判所の許可による復権の場合
裁判所の許可による復権を希望する場合は、以下の流れで手続きを進めます。
- 復権許可の申立書作成:必要事項を記載した申立書を作成します
- 裁判所への提出:破産手続きを行った裁判所に申立書を提出します
- 審査・調査:裁判所が申立人の生活状況や債務の履行状況などを調査します
- 債権者への意見聴取:必要に応じて、債権者から意見を聴取することがあります
- 審尋(審問):裁判所が申立人に直接質問することがあります
- 復権許可決定:要件を満たしていれば、裁判所が復権を許可します
- 確定:復権許可決定から2週間以内に異議がなければ確定します
裁判所の許可による復権は比較的複雑な手続きが必要となります。弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
復権証明書の取得方法
復権したことを証明する必要がある場合(就職や資格取得の際など)は、裁判所から「復権証明書」を取得することができます。
| 申請先 | 破産手続きを行った裁判所の破産係 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 発行期間 | 申請から約1~2週間程度 |
復権証明書の発行手続きは裁判所によって若干異なる場合がありますので、事前に破産手続きを行った裁判所に確認することをおすすめします。
復権後の生活再建と注意点
復権によって法律上の資格制限は解除されますが、実際の生活再建にはいくつかの注意点があります。
信用情報機関への登録
復権しても、信用情報機関に破産の事実が登録されている期間は、金融サービスの利用に制限がかかる場合があります。
| CIC(シー・アイ・シー) | 破産情報は登録から5年間保存されます。この期間はクレジットカードの作成や借入れが難しい場合があります。 |
|---|---|
| JICC(日本信用情報機構) | 破産情報は登録から5~10年間保存されます。この期間は住宅ローンなどの審査に影響する場合があります。 |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 破産情報は登録から10年間保存されます。この期間は銀行取引に制限がかかる場合があります。 |
上記の信用情報機関への登録期間が経過すれば、破産の情報は削除され、金融サービスの利用も徐々に可能になっていきます。それまでは、現金での生活基盤を整えることが重要です。
就職や転職時の注意点
復権後の就職や転職では、以下の点に注意するとよいでしょう。
- 履歴書への記載:原則として自己破産の事実を履歴書に記載する法的義務はありません
- 面接での質問:自己破産について尋ねられた場合、嘘をつくべきではありませんが、経緯や反省、今後の計画などを前向きに説明することが大切です
- 業種の選択:金融関連の業種では採用に影響する可能性が高いため、他の業種を検討するのも一つの選択肢です
- 復権証明書:必要に応じて復権証明書を提出できるよう準備しておくと安心です
上記のポイントを意識しながら、新たな職場を探すことで、復権後の生活再建が進みやすくなります。
再び債務を負う際の注意点
復権後に再び債務を負う際は、以下の点に注意することが重要です。
まず、自己破産から7年以内に再度自己破産をしても、免責が認められない可能性があります(破産法第252条第1項第10号)。そのため、無理のない返済計画を立て、計画的に借入れを行うことが大切です。
また、信用の回復には時間がかかるため、当面は少額からの取引を積み重ね、徐々に信用を築いていくことが重要です。借入れの際は、総量規制(年収の3分の1まで)を意識し、無理のない範囲での利用を心がけましょう。
まとめ
復権(ふっけん)とは、自己破産によって制限されていた資格や権利が回復することです。免責が「債務からの解放」を意味するのに対し、復権は「資格制限からの解放」を意味します。
復権には「当然復権」と「裁判所の許可による復権」の2種類があります。多くの場合、免責許可決定の確定によって自動的に復権する当然復権のケースに該当します。特別な手続きは不要ですが、証明が必要な場合は裁判所から復権証明書を取得できます。
復権によって法律上の資格制限は解除されますが、信用情報機関への登録は5~10年間続くため、その間はクレジットカードの作成や借入れに制限がかかる場合があります。就職や転職の際には、自己破産の事実を前向きに説明し、新たな出発を目指しましょう。
復権後に再び債務を負う際は、7年以内の再破産は免責が難しいことを念頭に置き、計画的な借入れを心がけることが重要です。自己破産と復権を経験した後は、健全な金銭管理の習慣を身につけ、安定した生活基盤を築いていくことをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



