元金・元本(がんきん・がんぽん)について詳しく解説
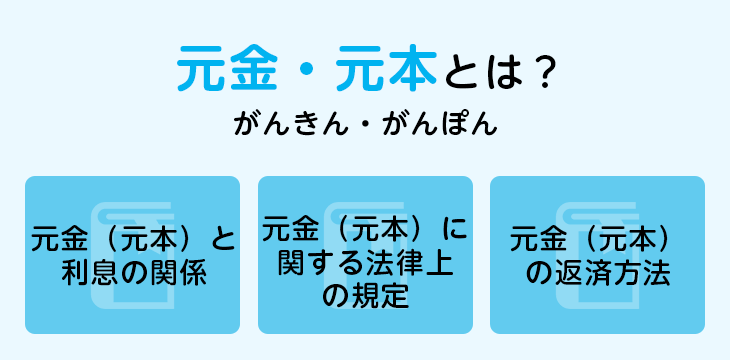
元金・元本とは、債務において借り入れた当初の金額のことを指します。利息の計算の基礎となる金額であり、返済においては元金(元本)と利息を合わせて支払っていくことになります。債務整理や過払い金請求の場面では、元金の返済と利息の支払いを区別することが重要となります。
■もくじ
元金・元本とは
元金・元本とは、借入や融資において最初に借りた金額のことを指します。「元金」と「元本」は同じ意味で使われることが多く、消費者金融やクレジットカードのキャッシングでは「元金」、住宅ローンや事業資金の融資では「元本」という表現が使われる傾向があります。
元金(元本)は、債務の中核をなす部分であり、これに対して発生する利息と合わせて返済していくことになります。返済が進むにつれて、元金(元本)の残高は減少していきますが、利息は残高に応じて計算されるため、返済額に占める利息の割合も変化します。
| 元金(元本)の定義 | 借入や融資において最初に借りた金額のこと |
|---|---|
| 元金と元本の違い | 基本的に同じ意味だが、使用される文脈によって使い分けられることが多い |
| 主な特徴 |
|
上記の表は元金(元本)の基本的な概念をまとめたものです。借入契約における最も基本的な用語であり、債務整理や過払い金請求を理解する上でも重要な概念です。
元金(元本)と利息の関係
元金(元本)と利息は、借入返済において密接な関係にあります。利息は元金(元本)に対して一定の割合(金利)で計算され、返済は通常、元金(元本)と利息を合わせて行われます。
例えば、100万円を年利10%で借りた場合、1年間の利息は10万円となります。返済が進むにつれて元金(元本)残高が減少するため、それに応じて発生する利息も減少していきます。
| 利息の計算方法 | 元金(元本)× 金利 × 期間 |
|---|---|
| 元利均等返済 | 毎回の返済額は一定だが、返済額に占める元金(元本)と利息の割合は変化する |
| 元金均等返済 | 毎回の元金(元本)返済額は一定だが、返済額全体(元金+利息)は減少していく |
上記の表は元金(元本)と利息の関係、および主な返済方法における元金(元本)と利息の扱いをまとめたものです。返済方法によって、返済額に占める元金(元本)と利息の割合が異なります。
債務整理や過払い金請求においては、この元金(元本)と利息の区別が非常に重要になります。特に過払い金計算では、支払った金額がまず元金(元本)に充当され、その後に法定利息に充当されるという「引き直し計算」が行われます。
元金(元本)に関する法律上の規定
元金(元本)に関しては、民法や利息制限法、貸金業法などでいくつかの重要な規定が設けられています。これらの規定は債務者保護の観点から重要です。
- 民法491条(元本充当の原則)
- 利息制限法による上限金利の規制
- 貸金業法による総量規制(年収の3分の1まで)
- 債権の時効に関する規定
上記のリストは元金(元本)に関連する主な法律上の規定です。民法491条では、「債務者が利息と元本を支払う場合において、弁済する金額が債務の全額に満たないときは、まず利息に充当する」と規定されていますが、過払い金の引き直し計算では特別な取り扱いがなされます。
また、利息制限法では、元金(元本)の額に応じて上限金利が定められています(10万円未満:年20%、10万円以上100万円未満:年18%、100万円以上:年15%)。この上限を超える金利契約は無効とされ、過払い金が発生する可能性があります。
元金(元本)の返済方法
借入金の返済方法には、主に「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。どちらの方法を選択するかによって、返済計画や総返済額に違いが生じます。
| 元利均等返済 | 毎回の返済額(元金+利息)が一定になる方法 当初は利息の割合が多く、次第に元金の割合が増えていく |
|---|---|
| 元金均等返済 | 毎回の元金返済額が一定になる方法 返済額全体(元金+利息)は当初が最も多く、徐々に減少していく |
| リボルビング払い | 最低返済額のみ決められている方法 元金返済が少額になりがちで、長期化すると利息負担が大きくなる |
上記の表は主な元金(元本)の返済方法の特徴をまとめたものです。住宅ローンなどの長期ローンでは元利均等返済が一般的ですが、元金均等返済の方が総返済額は少なくなる傾向があります。
クレジットカードのリボルビング払いは、毎月の返済額が少額で済む反面、元金(元本)の返済が進みにくく、結果的に多額の利息を支払うことになる可能性があるため注意が必要です。債務整理を検討する方の中には、このリボ払いが原因で借入が膨らんだケースも少なくありません。
債務整理における元金(元本)の扱い
債務整理では、元金(元本)と利息・遅延損害金が区別して扱われることが一般的です。各債務整理方法における元金(元本)の扱いは以下の通りです。
| 任意整理 | 将来利息のカットが一般的で、元金(元本)は原則として全額返済する ただし、状況によっては元金(元本)の一部減額も交渉可能 |
|---|---|
| 特定調停 | 基本的に元金(元本)は全額返済するが、分割返済の条件緩和を行う 将来利息のカットや遅延損害金の減免が一般的 |
| 個人再生 | 元金(元本)を法定の割合(最大で約90%)まで減額できる 住宅ローン特則を利用する場合は住宅ローンの元金は減額されない |
| 自己破産 | 原則として元金(元本)を含むすべての債務が免責される 一部の債務(税金、養育費など)は免責されない |
上記の表は債務整理における元金(元本)の扱いをまとめたものです。債務整理の方法によって元金(元本)の扱いが大きく異なるため、自分の状況に合った方法を選択することが重要です。
また、債務整理を行う前に、過払い金がないかを確認することも重要です。過払い金があれば、債務の元金(元本)に充当したり、返還を受けたりすることで、債務整理の負担を軽減できる可能性があります。
過払い金計算における元金(元本)の重要性
過払い金請求において、元金(元本)と利息の区別は極めて重要です。過払い金の計算では、「引き直し計算」と呼ばれる特殊な計算方法が用いられます。
引き直し計算では、これまでの取引をすべて利息制限法の上限金利で再計算し、支払った金額をまず元金(元本)に充当し、その後に法定利息に充当するという形で計算を行います。このとき、法定金利を超えて支払った部分が過払い金となります。
- 取引履歴を時系列で整理する
- 各取引時点での借入残高を確認する
- 利息制限法の上限金利(元金に応じて15%〜20%)を適用して利息を再計算する
- 支払った金額をまず元金(元本)に充当し、残りを利息に充当する
- 全取引を再計算した結果、過払いが発生していれば過払い金となる
上記のリストは過払い金計算における「引き直し計算」の基本的な流れを示しています。この計算は複雑であるため、専門家に依頼することが一般的です。
過払い金請求では、元金(元本)の返済と利息の支払いの区別が明確になり、法定金利を超える利息は元金(元本)の返済に充当されることになります。これにより、想定よりも早く完済になったり、過払い金が発生したりする可能性があります。
よくある質問
元金(元本)と利息はどのように区別されるのですか?
元金(元本)は借り入れた当初の金額であり、利息は元金(元本)を借りている対価として支払う金額です。返済の際には、通常、支払金額の中から一部が元金(元本)の返済に、残りが利息の支払いに充てられます。
返済明細書などでは、毎回の返済額がどのように元金(元本)と利息に分かれているかが記載されていることが一般的です。この区別は債務整理や過払い金請求において重要な意味を持ちます。
リボ払いは元金(元本)の返済にどのような影響がありますか?
リボルビング払い(リボ払い)は、最低返済額が設定されており、その中で元金(元本)返済分が少額になりがちです。そのため、返済期間が長期化し、結果的に多額の利息を支払うことになる可能性があります。
例えば、10万円の借入に対して毎月の返済額が5,000円で、そのうち3,000円が利息、2,000円が元金(元本)返済だとすると、完済までに非常に長い期間がかかります。債務問題を抱える方の中には、このリボ払いが原因で借入が膨らんだケースも少なくありません。
過払い金請求をすると元金(元本)はどうなりますか?
過払い金請求では、過去の取引を利息制限法の上限金利で再計算(引き直し計算)します。この計算では、支払った金額はまず元金(元本)に充当され、その後に法定利息に充当されます。
その結果、法定金利を超えて支払った分が過払い金となります。現在も借入が残っている場合は、過払い金をまず残債務に充当し、残りがあれば返還を受けることになります。完済している場合は、過払い金全額の返還を求めることができます。
まとめ
元金・元本とは、借入や融資において最初に借りた金額のことを指し、利息計算の基礎となる重要な概念です。元金(元本)と利息は密接に関連しており、返済においてはこの区別が重要になります。
法律上では、民法や利息制限法、貸金業法などにおいて元金(元本)に関する重要な規定が設けられています。特に利息制限法では、元金(元本)の額に応じた上限金利が定められており、これが過払い金請求の根拠となっています。
元金(元本)の返済方法には、主に元利均等返済と元金均等返済があり、また、クレジットカードなどではリボルビング払いも一般的です。リボ払いは毎月の負担は小さいものの、返済期間が長期化し、総返済額が増加する可能性があるため注意が必要です。
債務整理においては、方法によって元金(元本)の扱いが異なります。任意整理や特定調停では原則として元金(元本)は全額返済し、個人再生では法定の割合まで減額、自己破産では原則として免責されます。
過払い金請求では、引き直し計算によって支払った金額をまず元金(元本)に充当し、その後に法定利息に充当するという形で計算を行います。これにより、法定金利を超えて支払った部分が過払い金として返還の対象となります。
元金(元本)と利息の区別を理解することは、借入・返済計画を立てる上でも、債務整理や過払い金請求を検討する上でも非常に重要です。借入に関するトラブルを防ぐためにも、これらの概念をしっかりと理解しておくことをおすすめします。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



